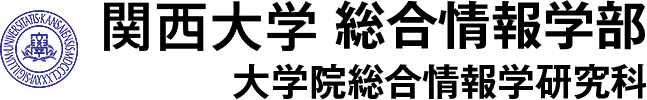総合情報学専攻(博士課程後期課程)
博士課程後期課程は1専攻(総合情報学専攻)としています。
博士課程後期課程で履修・修得できる授業科目は、講義と演習があります。
講義と演習の要項(シラバス)は、シラバスシステムから科目名・教員名で検索・閲覧することができます。
研究領域
総合情報学専攻では、科目(研究領域)の中から1つを選択し研究を進めていきます。
2025年度に開講される研究領域は以下の通りです。
| 専攻 | 研究領域 |
|---|---|
| 総合情報学専攻 | 高度情報システム |
| 応用ソフトコンピューティング | |
| 認知情報処理 | |
| 意思決定システム | |
| マルチモーダルコミュニケーション |
以下、【 】内は研究領域名を表します。
【高度情報システム】
| 指導教員 | 堀井 康史, 桑門 秀典, 田頭 茂明, 笹部 昌弘 |
|---|---|
| 概要 | 高度情報化社会を支える重要な技術的基盤の1つは高度情報システムである。この分野の教育研究を遂行し有為の人材を育成することは極めて重要である。高度情報システムは、高性能な情報処理技術、有線・無線情報ネットワーク技術、情報ベースやその情報内容の知識表現法、情報セキュリティ技術など、その実現構築に関わる技術的基盤は多岐にわたる。ここでは、情報システムの根底を支えるコンピュータ科学や情報科学、ならびに数理科学などの基礎科学を踏まえて理論と実践の両面より教育研究を行う。 具体的には、まず、情報システムの高度化に必要不可欠となる情報やデータの処理の高性能化に関わる「高速コンピューティング」について教育や研究指導を行う。さらに、技術的視点とともに、進化するサイバー社会における実用性の視点も加えながら、次世代を支える「高速無線通信のための先端デバイス技術」、「暗号技術」や「情報セキュリティ技術」などを取り上げて教育や研究指導を行う。 これらにより、次世代の高度情報システムや情報メディアの技術的基盤の確立に貢献する。 |
| 授業科目 |
|
【応用ソフトコンピューティング】
| 指導教員 | 林 勲, 田中 成典, 浅野 晃, 広兼 道幸,伊藤 俊秀, 友枝 明保, 竹中 要一, 井上 真二, 奈良 光紀, 堀口 由貴男 |
|---|---|
| 概要 | 現在の高度に発達した社会、人間生活を維持するにはコンピュータが不可欠である。ところが、人間生活を快適なものとするには、人間の主観、嗜好をコンピュータに理解させることが必要である。最近、人間とコンピュータを扱うための技術としてソフトコンピューティング技術が注目されている。 ソフトコンピューティングには二つの側面がある。一つは前述のように、人間の主観、論理等をコンピューティングに理解させることであり、もう一つは人間のもつ能力を利用してコンピュータをよりインテリジェントなものにしようというものである。すなわち、確実さを犠牲にして計算効率をあげることなどである。この二つの面に注目して、理工学への応用に重点を置いて、人工知能、ファジィ理論、ニューラルネットワーク、遺伝的アルゴリズム、人工生命、カオス理論等のソフトコンピューティングの基礎理論および技術の習得、ならびに開発を行い、この方面の先駆的役割を担える専門技術者および研究者の養成を行う。 |
| 授業科目 |
|
【認知情報処理】
| 指導教員 | 堀 雅洋, 林 武文, 松下 光範, 研谷 紀夫, 林 貴宏, 米澤 朋子, 山西 良典 |
|---|---|
| 概要 | 情報技術の急速な進歩は、高度な情報機能を備えた様々な人工物を人間に提供してきた。人間がこうした複雑な人工物と知的かつ快適に共生するには、人工物のヒューマンインタフェースが人間との親和性に優れたものでなければならない。とりわけ、コンピュータに代表される情報処理システムの場合には、人間の認知情報処理特性との親和性が強く求められる。そのようなヒューマンインタフェースの実現には、人間の認知情報処理特性に関する具体的な知見が必要となる。また、コンピュータシステムによって人間の営みを広く効果的に支援するためには、コンピュータシステム自身の知的情報処理能力がますます高度化され洗練化されなければならない。 本研究領域では、人間の優れた知的情報処理の基盤である認知情報処理機能について探究するとともに、新規性に優れた工学的応用をめざす。 |
| 授業科目 |
|
【意思決定システム】
意思決定支援
| 指導教員 | 今野 一宏, 古賀 広志, 松本 渉, 施 學昌 |
|---|---|
| 概要 | 社会や企業における活動においては、何らかの最適化を求められる局面が少なくない。近年の情報技術の発達は、個々の活動の部分最適化から複数の活動にまたがる全体最適化に向かっている。たとえば、ある企業では全体最適化を可能とする情報システムを持つことで、経営の活性化を成し遂げ、高い業績につながっていると言われている。また、小売業者は、商品管理システムを利用して店舗あるいは会社全体の商品の最適化をはかることが、避けて通れない課題となっている。 このような最適化に関連した問題を実際および理論の両面から検討し、意思決定支援システムの応用と問題解決をめざす。また、離散数学、アルゴリズム、統計学、数理計画法等の「数理的意思決定」の基礎理論および解法技術を研究・教授する。 |
| 授業科目 |
|
社会的意思決定
| 指導教員 | 伊佐田 文彦, 齋藤 雅子, 地主 敏樹, 大堀 秀一, 名取 良太, 泉 克幸 |
|---|---|
| 概要 | 社会的意思決定の研究は、組織の構造や制度、あるいは組織成員の行動、社会条件などが組織決定にどのような影響を与えるかを解明しようとするものである。本研究科では、私的組織については経営学、公的組織については政治学・行政学・公法学・経済学の理論的な成果を踏まえ、実際の政策・法や経営の事例について実証的かつ学際的な研究を指導する。 |
| 授業科目 |
|
【マルチモーダルコミュニケーション】
学習環境デザイン
| 指導教員 | 黒上 晴夫, 小柳 和喜雄 |
|---|---|
| 概要 | インターネットや携帯電話などのさまざまな情報通信技術(ICT)が多機能化し、インタラクティブな道具として生活のなかに入り込んできた。本研究領域のテーマは、ICTツールを含んだ望ましい環境をデザインすることである。そのために、ICTを活かした学びとコミュニケーションの方法に関する調査研究を行う一方で、ICTツールそのものとは一見関係ないように見える学習空間、教材、学習方法、学習組織など学習者を取り巻くすべての資源をデザインに組み入れる方法を模索する。この領域の学生は、これからの教育においてどのような環境が必要か、さまざまな角度から実際の社会にアプローチしながらこのテーマに迫ることが求められる。研究の対象は学校教育だけでなく、教師教育、生涯教育なども視野に入れる。また日本だけでなく、近隣のアジア諸国を始め諸外国の教育状況も分析の対象とする。 |
| 授業科目 |
|
コミュニケーション環境学
| 指導教員 | 森尾 博昭, 谷本 奈穂, 岡田 朋之 |
|---|---|
| 概要 | 以下の三つの観点から研究・指導を行なう。 まず基礎理論として、マルチモーダルなメディア環境におけるメッセージの意味作用について、とくに意味論や語用論の観点から取り上げる。 次に社会心理学的な観点から、人それぞれが生活している環境の中でいかなる情報を求め、受け止めた情報の解釈を通じてどのような感情を喚起し、行動にいかなる影響を受けるのかといった問題を扱う。 さらに社会学的な観点から対面的にコミュニケーションの状況依存性と構造性に注目し、それが現代のコミュニケーション環境の解明にあたってどのような意味を持つかを考える。 |
| 授業科目 |
|