教員紹介
日本史・文化遺産学専修
-
井上 主税教授 Chikara Inoue
-
教育内容

考古学とは、過去の人類が残したさまざまな遺構や遺物の研究によって、人類の歴史や文化を復元する学問です。その研究範囲は、先史時代や古代に限らず、近世や近現代までも対象とします。研究の対象となる遺構や遺物は発掘調査によって得られるため、フィールドワークと出土した資料の整理・分析を基礎とした教育を重視しています。
-
研究テーマ、概要説明
韓国・朝鮮考古学、日本考古学を研究しています。とくに弥生時代から古墳時代の日韓・日朝の交流関係を、両国で出土する考古資料から復元しています。また、関西大学がこれまで積み重ねてきた飛鳥の研究に東アジアの視点から取り組んでいます。著書に『朝鮮半島の倭系遺物からみた日朝関係』(2014年)など。
-
ひとこと
考古学研究室(大学博物館1階)で一緒に研究の面白さを体験しませんか。
-
-
小倉 宗教授 Takashi Ogura
-
教育内容

古文書などを読み解きながら、近世の政治・経済・社会・文化のあり方やその特徴をとらえる方法を学ぶとともに、歴史的な背景をふまえて現代の日本をより深く理解することを目指します。
-
研究テーマ、概要説明
日本近世の政治史や法制史、地域史を研究しています。これまでは、関東とならぶ拠点であった上方(かみがた。現在の関西地域)を主なフィールドに、江戸幕府の支配(政治・法・軍事)とその機構について検討してきました。近年は、上方のみならず日本全体をフィールドとして、幕府や藩の政治と法、地域の社会や文化などに関する実証的な分析を進めています。著書に『江戸幕府上方支配機構の研究』(2011年)など。
-
ひとこと
みなさんが日本の歴史や文化の魅力を知るお手伝いをしたいと考えています。
-
-
官田 光史教授 Akifumi Kanda
-
教育内容

近現代日本について、多様な史料から自分なりの言葉で説明できるようになることが目標です。歴史が私たちにとって身近な問題とつながっていることを感じてもらうため、大阪を中心とする関西の地域史も積極的に取り上げます。
-
研究テーマ、概要説明
日本近現代史、とくに日中戦争・太平洋戦争期の政治史を研究しています。戦時期の政党は、政策過程にどのようにコミットしようとしていたのか。この問いから、戦前・戦後も視野に入れて政党と地域社会・業界団体の関係を調べています。また、議員の召集や戦死、つまり国民が自分たちの代表を失うという出来事をとおして、議会・選挙制度の根源的な意味も考えています。著書に『戦時期日本の翼賛政治』(2016年)など。
-
ひとこと
さまざまな史料を読んで、歴史の面白さを語り合いましょう。
-
-
黒田 一充教授 Kazumitsu Kuroda
-
教育内容
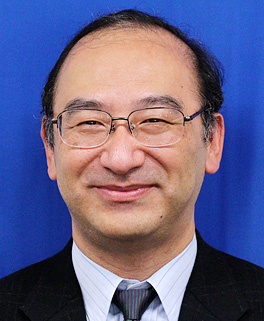
歴史の研究は、昔の人が書き残した文書や記録を読み解いていくのが基本ですが、生活文化や祭りと信仰、民俗芸能などの分野では、文字ではなく人から人へ直接伝えることで受け継がれているものがあります。そういった伝承資料の調査や分析方法の修得を目指します。
-
研究テーマ、概要説明
日本民俗学の分野で、各地の祭りや民俗行事・民俗芸能などの調査や記録、分析をおこなっています。現在は、大阪市の住吉大社の祭りを記録した文献資料と絵画資料を集める作業や、境内に立てられている石燈籠をゼミ生たちとともに調査し、日本各地に広がった住吉信仰の様子を探る研究をしています。著書は、『祭祀空間の伝統と機能』(清文堂出版、2004)など。
-
ひとこと
日本各地で古くから伝わる生活文化を調べてみませんか。
-
-
髙久 智広教授 Takaku Tomohiro
-
教育内容

人類の文化的営みにより生み出された有形・無形の所産が文化遺産であり、文化遺産学では、それらについて幅広い視野から考えていきます。また、多角的な視野を養うために、博物館や史跡のフィールドワークなども行います。
-
研究テーマ、概要説明
絵図や絵画資料、古写真、古文書などの歴史資料や史跡、建造物など多様な文化遺産を研究対象とし、それらの分析を通じて、地域の歴史を追究しています。また、研究成果を社会へ還元していくことも、文化遺産学の目指すべき課題の一つと考えています。最近は幕末期の海岸防備と関連遺産を主な研究テーマとしています。研究成果として、『幕末の大阪湾と台場』(共編著、2018年)、図録『大阪湾の防備と台場』(2021年)など。
-
ひとこと
日本各地の文化遺産について、いかに守り、活用していくか。一緒に考えてみませんか。
-
-
原田 正俊教授 Masatoshi Harada
-
教育内容

鎌倉時代から戦国・織豊時代までの歴史について、講義・演習を行います。中世史を中心に現代につながる日本社会・文化の形成と展開を考えていきます。論文・史料の読解能力を培い、史料批判を通じて、現代社会を考えるための歴史的思考能力を身につけます。
-
研究テーマ、概要説明
日本中世史を研究しています。特に仏教と国家・社会との関係を研究し、中世社会の特質を解明しようとしています。日本の中世は、武士のみならず公家、寺社の勢力も大きく、たいへん興味深い時代です。この他、中世の妖怪の政治的文化的意味、女性と仏教、対外交流史なども研究しています。
-
ひとこと
日本の歴史はおもしろい。中世史研究会(月6)に参加して下さい。
-
-
村元 健一教授 Muramoto Ken’ichi
-
教育内容

文化遺産とは有形・無形にかかわらず、人々が生み出し、現代に残されたものです。その研究のためには実際にモノを見、現地に立つことが大切です。そのため、モノにふれる機会、博物館見学、史跡見学を重視します。
-
研究テーマ、概要説明
日本各地に残された文化遺産の中で、私は古代の都、「都城」を研究テーマとしています。都城研究には、歴史学、考古学、建築学など様々な分野の専門家との共同研究が必要です。学際的研究、モノに即した研究は、文化遺産研究の重要な手法です。私は、都城研究を通じて他分野との協働の意義と楽しさを実感しました。こうした研究の面白さを伝えるだけでなく、文化遺産を理解し、次世代に伝える人材の育成に努めます。主な著書に『日本古代宮都と中国都城』(2022年)。
-
ひとこと
本学が所在する関西一円は文化遺産の宝庫です。実際に歩き、その意義をともに考えましょう。
-
-
櫻木 潤准教授 Jun Sakuragi
-
教育内容

日本古代史は、今から1000年以上前の人々の営みや社会のありようを探求する学問です。当時を知るための数少ない史料を手がかりに、先行研究を批判的に検討し、柔軟に発想することで、現代へのヒントも発見できます。
-
研究テーマ、概要説明
日本古代史を研究しています。奈良・平安時代を中心に、仏教の受容と展開過程を通して、文献史料を読みながら、政治・社会・文化のありようについて解明しようとしています。最近は、「海のシルクロード」を通じた交流にも視野を広げ、インドネシアなどに調査に出かけ、日本古代の宗教や文化との関わりについて探求しています。大学や図書館での屋内での活動はもちろんのこと、実際に現地に出かけ、古代史のナゾを一緒に解き明かしませんか?
-
ひとこと
木曜6限に古代史研究会もやってます。
-