
メディア専攻 media ゼミ・卒業研究テーマ
卒業研究テーマの一例
- 見るだけで運気が上昇する動画は、なぜ人々を惹きつけるのか
- 人は常に演技している?−甲子園球場ビール売り子から見る印象操作−
- ふくまる通り57から見るwalkableな街づくりの現状と展望
- 現代社会とひとり空間:公共トイレが持つ機能とイメージ
- 魔法の絆−ディズニー映画における母娘関係の変遷と社会的影響−
- タブーからの女性解放−広告が伝える月経観の変化−
- 漫画におけるホロコーストの表象−『マウス』から『進撃の巨人』へと至る表現手法の変遷−
- SNS時代のノスタルジア表象−令和からみた「昭和レトロ」「平成レトロ」−
- 能登半島地震から半年−初めての震災ボランティア−
- テレビドラマで描く聴覚障がいに関する考察−「愛していると言ってくれ」の日本オリジナル版と韓国リメイク版の比較−
- 奥田民生と旅の親和性−男らしさの観点から−
- 生成AI の比較研究−どのAI が「恋人」として適役か−
- メタバース×エンターテインメントの可能性
- 外から見た「尼崎」と内から見た「尼崎」−つくられたアマの“悪”伝説−
- さよなら大学−フルコロナ禍世代 2年間の記録−
メディア専攻 学生研究レポート
※年次は取材当時のものです。
「昆虫館」のメディアとしての力は人々にどのような影響を与えられるのか、その可能性を探る。
3年次生 ファネス 倫留ステファニー

コミュニケーションを媒介するものは、すべて「メディア」ととらえることができます。例えば昆虫館は、博物館として昆虫の知識を得られるだけでなく、蝶の放し飼いや体験イベントなどによって、あらゆる人に生物の多様性を伝える力があります。しかし現在、昆虫館の多くは子ども向けのメディアとしてしか機能していません。そこで、今後はフィールドワークなどを通して、昆虫館の社会的な意義を多角的に掘り下げたいと思っています。
教員からのアドバイス

理論と実践の双方からメディアにアプローチしてください。
「メディアとしての昆虫館」というテーマはおもしろいですね。昆虫を扱う図鑑や博物館の成り立ち、館の発するメッセージ、訪れる人のコミュニケーションなどを併せてみていくと、社会の中の位置がみえてきます。新しい提案にもつなげられますね。
村田 麻里子 教授
仮想空間でアバターとなって行う交流が、現実とどう異なり何をどう規制するべきかを考える。
4年次生 牧野 悠輝

VRアバター・コミュニケーションによる社会の変化と規制論を研究中です。メタバースなど仮想空間で、私たちは特殊なディスプレイを介してアバターとなり、表情や身振りでの高品質なコミュニケーションを行えます。この活動が現実とどう異なり何に生かすべきかの研究は少なく、規制への議論もこれから。私は所属する法人で、不登校学生に対しメタバースでのコミュニケーション支援をしているため、教育や心理面への影響、法的な課題も分析し、事業にも生かしています。
教員からのアドバイス

メディアのルールをどう作り、環境を良くするかを考える機会にしてほしい。
既存の法に、メタバース空間に適したルールは存在しません。環境をどうデザインすれば楽しいメディアになるのかは、牧野さんたちの世代が先駆者となって整えていくもの。この研究を、メディア環境づくりを考える機会にしてもらいたいと思います。
水谷 瑛嗣郎 准教授
人と人、人とモノをつなぐ広告を通したコミュニケーションの在り方を考える。
3年次生 西村 悠里

広告主の意図を的確に表現しながらも、人を傷つけず、受け手との間にある壁を柔らかくする広告を通したコミュニケーションについて研究しています。授業の一環としてあるキャンペーンのキャッチコピーの公募に参加し、採用されたことがありましたが、制作過程では自分の視野の狭さを痛感しました。「コミュニケーションは受け手が全てを決める」という原則を意識しながら自分を客観視する力を養い、誰にとっても心地良い環境を作れる人になることが目標です。
Interview メディア専攻を選んだ理由は?
身近なところから私たちに影響を与える広告について学びたいと思ったから。
高校時代に見たあるテレビCMがきっかけで広告に興味をもちました。短い映像やシンプルなキャッチコピーを通して商品・サービスの魅力を伝え、受け手である消費者の意思や選択に変化を与える広告について学べるメディア専攻を選びました。
Interview どんな毎日を過ごしている?
【3年次】学びのテーマを自ら発見し、探究する日々。
1日のスケジュール
- 10:40 「メディア企画演習(広告)」受講
- 自分たちで広告の企画を立案し、より伝わりやすくするための実践的な技術も学んでいます。
- 14:30 ゼミの打ち合わせ
- ゼミ生と課題について打ち合わせます。何気ない会話から、新しい発見が得られることもあります。
- 16:20 ゼミ
- 山本先生の「広告クリエイティブ」ゼミに所属。ゼミ生の興味・関心に従ってテーマを設定し、調査や議論を通して理解を深めています。
- 18:30 よさこいサークル
- 週に3~4回は練習しています。「吹田まつり」をはじめ全国のお祭り会場で踊りを披露したこともあります。
教員からのアドバイス

多様な価値観に触れながら疑問を発見し、探究してほしい。
受け手の多様な解釈によって成立する広告を学ぶには、積極的に多様な価値観に触れることが必要です。西村さんには「ヒト/モノ/コト」に興味を持ち、その中に疑問を発見し、考え続けることによって自分を大きく成長させて欲しいと思っています。
山本 高史 教授
人はなぜ「リアリティーショー」を観るのか。メディア研究を通じて自分と社会をみつめなおす。
4年次生 鈴木 仁志

台本がないという設定で出演者の行動や反応を楽しむリアリティーショーは、SNSと組み合わさることで、視聴者が出演者を攻撃したり、番組から落としたりする現象を生み出しました。私は「人は出演者が成功する姿よりも、失敗したり傷ついたりするところを見たいのではないか」と考えているのですが、この後ろめたい気持ちは自分の中にも存在すると感じます。今後研究を深めることで、自分自身の理解にもつながればと思います。
Interview メディア専攻を選んだ理由は?
日常的に親しんでいるコンテンツをより深く知りたいと思ったから。
テレビや映画を観たり、YouTubeで動画を投稿したりと、幼いころからさまざまなコンテンツを楽しんできました。そして進路選択にあたって、自分の好きなものについて深く学びたいと考えた結果、メディア専攻を選びました。
Interview どんな毎日を過ごしている?
1日のスケジュール
- 14:30 登校
- 大学では自分で時間割を決められるので、工夫すれば午後から授業を受ける日を作ることもできます。
- 16:20 「メディア・リテラシー論」を受講
- メディアの仕組みや、メディアで描かれることの意味について考える授業です。
- 18:00 ラーニングコモンズで自習
- 教室以外にも自由に利用できる自習スペースがあるので、友人と時間を合わせて資格取得のための勉強に取り組むことも。
- 20:30 友人と関大前で晩ごはん
- キャンパスの正門から駅まで続く学生街には飲食店がいっぱい!ラーメン店や唐揚げ屋さんなど、気分に合わせて選べます。
教員からのアドバイス
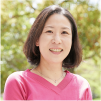
人間がもつ普遍的な問題を、現代のメディアから考える面白い研究です。
鈴木さんが自分の中に感じる「暴力」は、昔から多くの人が感じ、悩んできた普遍的なもので、社会学やメディア研究の重要なテーマでもあります。この問題意識の歴史を遡ると同時に、番組やSNSの分析を通じて現代の問題として捉えなおしていきましょう。
村田 麻里子 教授
テレビCMの次の可能性「字幕」を、広告の送り手、受け手の双方から考える。
4年次生 秋原 帆乃夏

より多くの人に商品やサービスを知ってもらうための広告が、なぜ見た人すべてに伝わるように作られていないのでしょうか。例えばテレビCMの「音声」です。聴覚に障がいをお持ちの方や聴き取りにくくなっている高齢者の方がいらっしゃいます。社会参加や高齢化という社会のトレンドを考えるときに「字幕」というものがきっかけになっていくという仮説を立てました。現状、字幕付きのテレビCMを製作している企業の事例から、変化に対応する広告の姿を明らかにしようと考えています。
Interview メディア専攻を選んだ理由は?
広告を専門に学べる環境に魅力を感じたから。
高校生の時にオープンキャンパスに参加して、メディア専攻では広告を専門に学べると聞いて興味をもちました。当時からCMに興味があり、テレビの歴史や広告について知識を深めようと考えました。
Interview メディア専攻のオススメ講義は?
グループで広告制作に取り組み、作品を完成させた。
広告の実制作に取り組む「メディア企画演習(広告)」です。「献血」をテーマにグループでアイデアを出し合い、絵コンテの作成から撮影地やキャストの選定、撮影、編集までを約1カ月間で行いました。
Interview メディア専攻の魅力は?
多彩な授業が興味の幅を広げてくれる。
個性豊かな先生方の授業を通して、テレビCMに限らず、新聞やラジオ、音楽などに対する興味が広がりました。広告以外の知識を身に付けたことが、広告制作にも活きていることを実感しています。
教員からのアドバイス

広告を学ぶことは社会を学ぶこと、人間観を作り出すことです。
広告を作るためには、子どもから高齢者までさまざまな人が何を求めているかを考える必要があります。秋原さんはメディアや社会について幅広く学び、そこで得た知識や物事の見方を広告制作に活かしている点がいいですね。
山本 高史 教授
 社会学部・
社会学部・