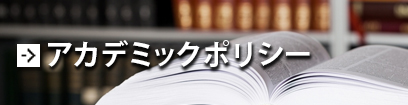第53回経営学と危機、想像力
商学部教授 原 拓志(マネジメント専修)
2020年4月、新型コロナウイルスのパンデミックが世の中に強烈な不安感をもたらしているなかで、私は、経営組織論担当として関西大学商学部に着任いたしました。その年の春学期はすべてが遠隔授業となり、キャンパスに行っても人影はほぼ無く、何か異なるゾーンに入り込んだかのような気分でした。それから3年が過ぎ、この5月8日には、新型コロナウイルス感染症も5類となって、いわば普通の感染症となりました。キャンパスの活気も戻りました。これを「日常を取り戻した」と表現する人もいます。
しかし、今回の経験で改めて思ったのですが、「日常」とは何でしょうか。このパンデミックの前には東日本大震災や福島原発事故がありました。その前には、リーマン・ショックがありました。日本を揺るがす危機が10年も空けずにやってきています。昨年にはロシアのウクライナ侵攻が勃発しました。世界を見渡すと、地域的な紛争は毎年各地で起こっていますし、甚大な自然災害も同様です。
これまで経営学は、経営環境の変化を強調してきました。しかしそれは、技術の変化であったり市場の変化であったりと、震災や恐慌、戦争、パンデミックという危機的な状況とは質が違います。グローバル化が進んだ現代において、企業がこれらの危機的状況の影響を受けることは珍しいことではなくなりました。そのため最近は、経営学でも危機管理やレジリエンスが論じられるようになりました。
ただ危機と言っても多様です。これに備えるには、情報収集と分析に加えて豊かな想像力が必要です。想像力を養うには、歴史やフィクションから多くのストーリーを獲得することが大切だと思います。学生にもストーリーの学習機会を意識的に増やしてほしいと思っています。
『葦 2023.№185 夏号』
2023年7月28日更新
※役職表記は、掲載当時のものです。