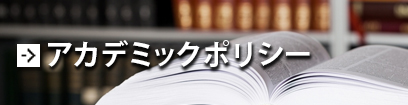第49回計画性と偶発性
商学部准教授 細見 正樹(マネジメント専修)

夏休みの宿題を計画的にこなせていないと、子どもについ注意したくなります。振り返ると私も、計画的というよりお盆過ぎてからようやく真剣になるタイプでしたが。
卒業論文でも、当初の計画通りに進む学生はあまり多くありません。3年の時からテーマを決め、既存研究を収集する学生もいます。一方、4年の秋に突然興味を持ったテーマに変更し、何とか書き切る学生もいます。計画性も大事ですが、方向転換を行う大胆さも時に重要です。
学生自身が楽しく、興味が持続するテーマを見つけることが理想です。ゼミのテーマはヒトの心理とマネジメントです。働きやすさ、リーダーシップ、就活に関心を持つ学生が多いです。オンラインゲームの勝者の条件、アニメやアイドルグループを題材としたマネジメント、お笑いコンテストのコミュニケーションといったユニークなテーマの学生も結構います。好きなことを探求できるチャンスはそれほど多くないと思うので、卒業論文の執筆は学生にとって貴重な体験です。
計画的偶発性理論というキャリア理論があります。将来が不確かな時代において、偶然の出会いでキャリアの多くが決まり、偶然の出会いを活かしキャリア成功に結びつけることもできるというものです。私は、地方公務員から社会人大学院生を経て、現在は商学部で教えています。キャリアの転換点は、職場で追求したいテーマと出会ったことでした。
計画的偶発性理論において、偶然の出会いを活かす特性の一つに、好奇心の強さが挙げられます。出会いには、人だけでなく、本、映画、テレビ番組、趣味など様々なものが含まれます。学生は卒業後も広くアンテナを張り巡らし続けて、キャリアの満足度を高めてほしいです。
『葦 2022.№181 春号』
2022年4月20日更新
※役職表記は、掲載当時のものです。