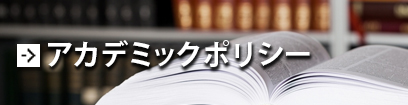第48回ビック・ブラザーは見ている
商学部准教授 馬場 一(流通専修)

私はインターネットやSNSやスマホに囚われている。恐ろしいことである。自分ではプレイせずに、YouTubeのゲーム配信をたれ流している。二郎系ラーメンを食べる理由の一部は、インスタへのアップだ。ネットで欲しい商品に出会っても、閲覧していると物欲が満たされてしまう。これらは単なるコロナ禍の制約にだけ起因する訳ではなかろう。
私は商学部で国際マーケティング論を担当している。少なくとも十年前は、海外でマーケティングが行われる場としての「現地」に興味があった。足で稼いだ情報にこそ価値があると思っていた。だから、海外で調査を行い、英語で論文を書き、英語でプレゼンするという七面倒臭いゼミ活動を行っている。
ところが、過去三年間のゼミ生の研究テーマはバーチャルである。SNSアディクション...SNSへの依存が消費行動に与える影響。フォトジェニック...若者の旅行動機は、SNSでの映え(ばえ)と経験の共有。スラクティビズム...「いいね」するだけで、実際の行動(例えば、寄付、集会への参加、商品の購入)を起こさない。学生が選んだテーマと冒頭に挙げた私の行動は見事にかぶっている。
では、何が恐ろしいのか。私が依存症であったり、引きこもりであったりは個人的な問題である。真に恐ろしいのは、ビック・ブラザーの存在である。ジョージ・オーウェルは小説『1984』のなかで、ビック・ブラザーを、テレスクリーンを通じて民衆を支配する独裁者として描いている。本当の正体は誰も知らない。実在するかも定かではない。だが、ビック・ブラザーは知っている。私が好きなのは何かを、私が考えなくなっていることを、そして、私が行動しなくなっていることを。いまこそデジタル・デトックスが必要ではなかろうか! おっと、LINEだ。こんな夜遅くに、誰だ─
『葦 2021.№179 夏号』
2021年8月19日更新
※役職表記は、掲載当時のものです。