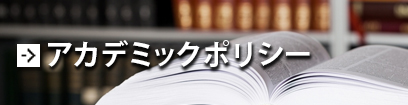第46回カブトムシ
商学部教授 田中 孝憲(ファイナンス専修)

今年の夏、我が家にカブトムシがやってきた。保育園に通う息子が友達から譲り受けたものである。私も幼少の頃カブトムシを家で飼っていたが、繁殖に成功できなかった苦い思い出がある。そこで、過去の自分へのリベンジと思い、幼少期に戻った気持ちで世話をすることにした。
カブトムシの飼育方法は昔とかなり異なっている。今は、カブトムシにスイカを与えない方がいいらしい。その代わりに、(カブトムシにとって)栄養価の高いゼリーをあげるのが一般的になっている。その他にも、成長段階に合わせて飼育土壌を交換するのがいいようである。成虫・幼虫それぞれを育てるのに適した土壌が販売されている。
現在、私は日が昇る前の早朝に起きるのが習慣になっている。早朝の時間帯は(私にとっては)一日の中で頭が最も冴えているため、研究する時間に充てている。夜行性であるカブトムシは私が仕事を始める前から既に活発に動いている。カブトムシが虫かごの中で動いている様子を傍で感じながら論文を書くのは面白い。早朝の時間をカブトムシと過ごすことにより新しい発見をした。カブトムシの鳴き声のようなものを初めて聞くことができた。どうやら求愛行動の時に鳴くようである。カブトムシ以外にも、早朝の時間帯は様々な音に触れることができる。始発電車が駅に到着する音、鳥の鳴き声、新聞を届けてくれるバイクの音。静寂の中から聞こえてくるこれらの音は、一日の始まりを感じさせてくれる。
夏が終わる頃カブトムシは死んでしまったが、世話の甲斐もあり多くの卵を産んでくれた。卵は孵化し、日々幼虫が大きくなっている。来年の夏もカブトムシと早朝の時間を過ごすのが今から楽しみである。
『葦 2020.№177 秋冬号』
2020年12月18日更新
※役職表記は、掲載当時のものです。