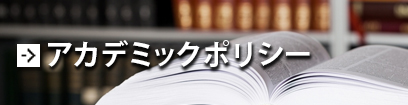第10回フィールドワークで学ぶ
商学部准教授 三谷 真(流通専修)
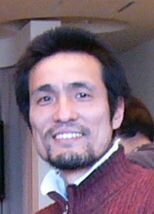
駅前など市街地の商店街の衰退はますます進んでいます。商店街に未来はあるのか、をテーマにゼミではここ数年商店街のフィールドワークを行っています。調査だけではなく、実際にイベントの企画・実行まで商店主らと共に汗を流しています。
実は、その学生達には商店街経験はほとんどありません。生まれた時にはすでに大型ショッピングセンターが跋扈していて、商店街で買い物をしたことがないのです。商店街を歩いた後の最初の感想が「欲しい物がない」です。つまり、学生達にとっては買い物をしたことがないし、買う物がないというのが今の商店街なのです。
でも、そんな彼・彼女らは何度も通っている内に、商店街のおもしろさに気付きます。それは、「人がいる」ということです。単にモノを売るだけの「機械」になってしまった売り子さんや店員さんではなく、個性たっぷりの店主がお客と掛け合いをしながらモノと心意気を売っている姿を目にするのです。商売(=ビジネス)とはモノを相手にするのではなく、人を相手にしていることを学ぶのです。(そんな商店主ばかりだと商店街の未来は明るいのですが...)座学では学ぶことのできないことを経験できるのがフィールドワークの良さです。
さらに商店街ではもっといろんなことが学べます。店頭のモノは誰がどこで作ってどのように流れてくるのか。お客は何を見てどのように買い物しているのか。人が入る店と入らない店の違いは何か。売れるモノと売れないモノの差は何か、などなど。商店街はフィールドワークの宝庫なのです。
もちろん、そこには興味と好奇心と問題意識がなければ何も見えません。人と触れあうのは楽しいです。その楽しさを血や肉に換えることが肝腎なのです。
『葦 №136号』より
2008年10月28日更新
※役職表記は、掲載当時のものです。