動物園へ出かけてみよう―溝井裕一先生と巡る、歴史と文化へのアクセスポイント「天王寺動物園」
文化・スポーツ

かわいい動物に会える身近なスポットとして、幅広い世代に人気の動物園。
しかし、主役となる動物たちにとどまらず、展示・飼育のための施設や方法、園内にある碑や像などにも注目すると、動物園のあらたな側面が見えてくる...。著書『動物園・その歴史と冒険』を出版したばかりの文学部・溝井裕一教授とともに、大阪市・天王寺動物園を巡りながら、「文化的な動物園の楽しみ方」を味わった。

溝井裕一先生は2014年、古代の動物コレクションから近代動物園まで、動物園をめぐる人々の思想的営みの歴史を描いた『動物園の文化史』を出版。2018年には水族館を考察した『水族館の文化史』でサントリー学芸賞を受賞している。そして最近、主に19世紀以降の近現代動物園のデザインの変遷を辿った『動物園・その歴史と冒険』を出版したばかりの文学部・溝井裕一教授とともに、大阪市・天王寺動物園を巡りながら、「文化的な動物園の楽しみ方」を味わった。
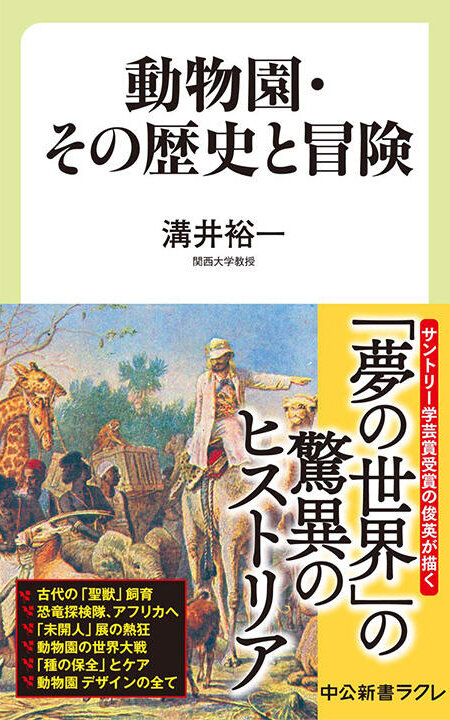
その溝井先生に天王寺動物園を案内してもらえるとは、またとない機会である。待ち合わせたのは天王寺動物園の新世界ゲート。入場する前に、動物園のどんなポイントに注目して見るとおもしろいのかを伺ってみた。
「動物園はただ動物がいる場所、ではありません。"歴史に触れるアクセスポイント"としての魅力があります」
といいますと?
「動物園は人間/動物、文化/自然などの関係をめぐってさまざまな営みが繰り広げられ、姿を変えてきた場所です。政治とも無縁ではない。というより、かなり政治的な場です。例えばヨーロッパの動物園に行くと、現代的な動物園の中に、近代動物園の祖先となる近世メナジェリーの痕跡が残っていることもあります。メナジェリーとはヨーロッパの王様たちが自分たちの力をアピールするために動物を集めて作った飼育舎です」
今回見て回る大阪市・天王寺動物園もまた歴史の痕跡が残っているということですね?
「天王寺動物園は1915(大正4)年、上野、京都に続いて日本で3番目に長い歴史をもつ動物園です。現在にいたるまで、展示を何度か作り変え、存続の危機も乗り越えてきました。もちろん第二次世界大戦も経験しています。
興味深いのは、いろいろな時代の動物園の姿がミックスされた状態になっていること、そして歴史的な記録を意識的に保存している部分があるということです。過去のことは必ずしも肯定すべきものばかりではありませんが、そのあたりのこともきちんと今に語り継いでいるのも、天王寺動物園の素晴らしいところでしょう」
なるほど、具体的なことは巡りながら伺うとして、今の話だけでもかなり貴重な動物園であることがわかる。
「まさに、日本でもっともすぐれた動物園の一つだと言って間違いないです。これから見ていくように、展示の仕方も日本では先駆的な試みをおこなってきました」
日本屈指の動物園だという天王寺動物園。今回は、溝井先生が特におすすめする4つのポイント――アフリカサバンナ、アジアの熱帯雨林、リタとロイドの像、アイファー(爬虫類生態館)――を中心に園内を見ていくことになった。
ということで、近代的なシンメトリー構造とゆるやかな現代イラストのミックスが印象的な新世界ゲートから、園内に入場した。


最初に向かうは、新世界ゲートを入って左、アフリカサバンナゾーンである。
「ここは、アフリカの野生動物保護区などでの現地調査も経て、サバンナの環境を取り入れた展示が行われているゾーンです。例えば岩山群を置いて東アフリカのサバンナの地形を再現したり。ゲートや案内板も無味乾燥なものではなく、雰囲気のあるものになっていますね」
確かに、「ンザビ国立公園」と名づけられたこのゾーンの入り口には、木で作った大きな門が建ち、その奥には植物が茂っている。何か別の世界に入り込んでいくような感覚になる。
「動物園は長らく、権威を示すために動物を囲っておくショーウィンドウでした。19世紀の帝国主義の時代や20世紀の大戦期、そして冷戦期にもそのように使われた側面があります。そこでは人間が中心ですから、動物たちにとっての快適さなどはあまり考慮されていませんでした。
ところが1960、70年代ごろから、動物園のあり方への批判が巻き起こります。狭い檻に動物を押し込めて劣悪な環境で飼育しているのは、おかしいんじゃないかと。主に動物園関係者たちが声を挙げました。同時代の環境保護運動や人種解放運動、女性解放運動などともリンクしていました。
こうした反省を経て、近年は動物たちが生息する環境を可能な限り再現した展示に変わってきています。そして人間たちはその環境に没入していく。私が『テーマ・ズー』と呼ぶ、テーマパーク的な動物園展示が増えてきました。
これは20世紀初頭にドイツのハーゲンベック氏が先駆的に取り組んでいたのですが、その後シアトルのウッドランド・パーク動物園がより没入感を高めた展示を作って衝撃を与えました。天王寺動物園のサバンナゾーンもこの流れに位置づけられます」
取材で訪れたのは晩秋だったので、草木が少し葉を落としていたが、温かい季節にはもっと草木が生い茂り、園外の都市景観も目に入りにくくなるという。まさにテーマパーク的だ。
さて、ンザビ国立公園(※ンザビ国立公園は天王寺動物園だけにある架空の国立公園です。念の為)の門をくぐって最初に登場するのはカバ、そしてサイである。展示施設の壁には壁画が描かれ、アフリカの伝統的な仮面もかけてある。こうした装飾も雰囲気作りに一役買っている。


カバ舎とサイ舎を過ぎると、キリンやエランド(オオカモシカ)などの草食動物たちが暮らす草原のような展示場につながる。

「ここは目線の高さが動物よりも少し低くなります。動物を上から見下ろすのではなく、見上げる。こういう展示も増えてきています。さて、もう少し先に今回特に注目したいポイントがありますので、行ってみましょう」
先に進むと肉食動物がいる。狩りをするブチハイエナや、動物園の人気者ライオンが暮らしている。
「このライオンたちのいる場所の奥に広がっているのは、さきほど見たキリンなどの草食動物の暮らすエリアです。タイミングによっては肉食動物と草食動物が同じ場所で生活する、サバンナのような景観が広がります」
以前ここで、キリンはライオンに食べられてしまわないのか?と気に懸けている来園者を見かけたことがある。実際には、あいだに深い堀があって隔離されているのだが、どうも心配になってしまう。そのくらい巧妙な展示なのだ。溝井先生の本で動物園展示のデザインの意味を知ってから行くと楽しい場所である。
アフリカサバンナを抜け、続いての目的地へ向かう。
次は動物園の南側のエリアにある、アジアの熱帯雨林ゾーン。先に言っておくと、かつてこのゾーンにはゾウがいたものの、今は不在。ですよね?
「ええ、動物園の人気者、ゾウがいないのは残念です...が、そう言っても仕方がないので、ゾウがいたらどう見えるのか想像しつつ、遊歩道や看板、建築物に注目して欲しいと思います」
周囲に目をやると、ゴツゴツとした岩や、たくさんの植物。うねうねと曲がりくねった道が続いている。
「アフリカサバンナゾーンと同様、あるいはそれ以上に没入感を誘うゾーンです。看板もタイ語。雰囲気がありますよね。この道をどんどん進んでいくんですが...」



「ドーンと、ここで一気に視界がひらけてゾウが出てくる、という展示だったわけです」
なるほど!これはすごい。ゾウがいたらさらに圧倒されていただろうが、展示方法を見ているだけでも興味深い場所である。

「しかも、現地の生活を再現したものもあります。たとえば、ゾウの見張り台を再現したものが見えますね」

そんなところまでとは、かなり気合いが入っている。
「このゾーンは、アジアの熱帯雨林やその周辺の動物が暮らす環境、そして動物と人間との関係まで含めて再現しています。例えば畑を荒らすゾウについての警告看板からは、人々がゾウをどう捉え、どのように共存しているのかまで伝わってくる。非常に素晴らしいゾーンだと思います」


動物園がただ動物を見るだけの場所ではないことがかなり実感できてきた。そして次に辿り着いたのが「リタとロイドの像」。チンパンジーの像である。溝井先生がこの像に注目した理由とは?
「この像は天王寺動物園における代表的な歴史スポットと言えます。リタは昭和初期にやってきたメスのチンパンジーです。自転車や竹馬、ナイフとフォークを使った食事などの芸に長け、オスのロイドとともにアイドル的な人気がありました。でも野生のチンパンジーは自転車なんて乗りませんよね?明らかに不自然です。動物に不自然な芸を教えこむというのも、人間による動物の支配の一環だった。さらにリタは軍服を着せられ、戦意高揚の道具にも使われました」
最初に溝井先生が話していた、動物園は政治的な場である、ということがはっきりとわかるエピソードだ。
「天王寺動物園では、こうした反省を踏まえて現在では動物には芸を教えこんでいません。そして、しっかりこうした像を作って今の来園者にもその過去を伝えている。この動物園の優れたところだと思います」
リタとロイドの像を後にし、最後の目的地へ向かう前に、ホッキョクグマ舎の前で立ち止まる溝井先生。
「このホッキョクグマ舎はなかなか古いですね。ハーゲンベック式の展示施設です。昔の写真と見比べても同じです」
細かいところは変わっているようだが、写真を見る限り確かに基本は同じである。

「これから動物園も施設を新しくし、より動物にとって自然な環境に変わっていくでしょう。私もそれには賛成です。しかし実際に動物をそこで展示しなくなってからも、古い施設を史蹟として後世に伝えておいてほしいなと思っています。完全に取り壊してしまうと、動物園がかつてどういう場所だったのかがわからなくなってしまいます」

そして最後、爬虫類生態館「アイファー」に行くことに。アイファー(IFAR)とは無脊椎動物/魚類/両生類/爬虫類の英語の頭文字をとって名づけられたもので、1995年にオープンした。その見どころとは?
「ここは生態を再現するという試みが早い段階で行われました。特に良いのが、地下にある日本の自然コーナーです」

動物園というと普段なかなか見られない海外の動物に目が行きがちですが。
「これまで動物園展示の中心は、他の土地からやってきた生き物でした。別の言い方をすると、動物園に行っても自分たちが生活する土地本来の生き物のことを知ることはあまりできなかったということです。さらに、異国から動物を連れてくることは、辿っていけば植民地主義的な思想とも無縁ではない。そういったこともあって、自分たちの暮らす場所の動植物を知る展示というのが注目されています。天王寺動物園のアイファーの地下展示はその先鞭をつけた展示だったと言えます」
今の、そしてこれからの動物園における展示のあり方を、先頭を切って示したのが天王寺動物園ということか。
「これからもどんどん変化していくと思いますよ。だとすれば、今の姿は今しか見られないとも言えますね」
天王寺動物園はさまざまな時代にアクセスできる場所。溝井先生のこの言葉の意味がよくわかった。近代動物園の初期スタイル、過渡期のスタイル、新しいスタイル。あらゆる時代の展示デザインが同居し、時代時代の思想や世相の異種混交といった風情がある。さらに像のようなモニュメントを通して、過去の動物園で何があったのかを伝えている。
園内を新世界ゲートへ向かっていくと通天閣が見える。振り返ると反対側のゲートのほうには大阪市立美術館が見える。天王寺動物園は「モダン大阪」を象徴するエリアの一画をしめている。動物園を訪れた後、周辺を散策するのもよさそうである。
歴史や文化に関心のある人こそ、天王寺動物園は楽しめる。そして他の動物園にはどんな展示や特長があるのか、比べてみるのも面白い。