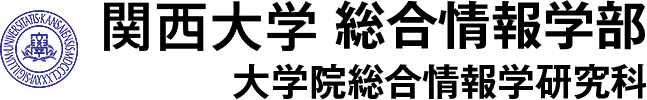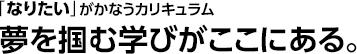メディア情報系

インターネットをはじめ多様化が進む情報メディアとコミュニケーションに関する専門分野を中心に学びます。 心理・言語・文化・社会・教育など多角的視点から情報学に関する知識・理論を身に付けると共に、最新のマルチメディア機器を利用した制作実習などによって知識と技能をバランスよく養います。
メディア情報系から広がる将来のフィールド
- 情報技術(IT)に強いジャーナリストや編集者に
- 雑誌や映像の編集・撮影スキルを生かして、クリエーターに
- 広告戦略を学び、広告関連企業や一般企業の広報担当に
- メディア教育の専門知識を生かして、教育産業へ

エンターテインメント業界をめざす学生の履修例
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
|---|---|---|---|
|
|
|
卒業研究 |
制作実習(映像基礎)
多メディア時代における基礎的能力としてメディアリテラシーの基本を身に付ける。
近年のメディア・テクノロジーの革新のもとで、映像作品発表の場が従来のテレビ局やビデオ作品、映画等のメディアに限らず、インターネット上にも求められるようになってきた。この実習では、そうした時代背景のもとで普及してきた小型化した映像撮影機材と、パソコンを利用した映像編集ソフトを活用した映像作品の制作をおこなう。
映像作品制作の基礎を学ぶことにより、多メディア時代における基礎的表現能力を身に付けることをめざす。

ヒューマンエージェントインタラクション
既存システムの擬人化技術とインタフェースについて知見を深め、自らの問題にその手法を導入するチャンスを発見する能力を磨く。
ヒューマンエージェントインタラクションとは、擬人化された人工的な存在と人間とのやりとりやコミュニケーションを示す言葉である。ペットロボットやPC 画面内の案内エージェントなど、様々な擬人化システムと触れ合う世の中になりつつある。本講義では、世の中のシステムの擬人化技術とインタフェース設計について知見を深め、設計手法や必要技術の知見を深め、自らの問題意識に擬人化の手法を導入するチャンスを発見する能力を磨く。グループワークや個人課題に取り組み、擬人化システムのアイディアを出すトレーニングを行う。

メディアイベント論
巨大メディアイベントから、情報メディアと私たちの日常生活との深い関わりを考察する。
今年は夏季五輪のパリ大会が予定され、さらに来年2025年には大阪での万博の開催が予定されている。今日、こうした巨大メディアイベントが日常生活にもたらす影響力は、いかなる形でどのような局面におよぶのであろうか。また、その受け手としての一般の人びとはどのようにそれらのイベントを受け止め、参加していくのだろうか。
本講義は巨大メディアイベントの形成過程と現状について、多面的に検討することを通じ、情報メディアと私たちの日常生活や意識との深い関わりを考察していく。具体的な流れとしては、まず万博を中心に五輪やサッカーW杯といったメガイベントのこれまでの歴史的な経緯をたどる。そして21世紀以降に開催されたそれぞれの大会で見られた新たな状況を参照しつつ、私たち多くの市民より広く巻きこむに至っているこれらのイベントの今後のあるべき姿を展望する。

メディア情報系に関連する卒業研究テーマ(例)
- TPP参加によって、日本の二次創作文化は衰退していくのか
- 60年代から現代におけるまでのテレビメディアからみた男性アイドルの職業的変化
- ゆるキャラからみる人々に愛されやすいキャラクターの特徴
- 口コミサイトで支持される化粧品
- 若者の伝統的な書式の手紙への関心
- 友人集団内における自己開示とアイデンティティの関係とその性差について
- 対人魅力を規定する要因について—どのような人が好まれるのか—
- 対面コミュニケーション、非対面コミュニケーションにおける会話の違い—両方から考えるコミュニケーションの注意点—
- 初等の理科教育における映像教材の課題についての考察~映像教材制作活動を事例として~
- 高等学校情報科における高校生の学習の有効性認知と学習意欲の関連
- 音楽イメージと同調した実験的映像制作
- CMが与える購買意欲への影響
- 政治家のソーシャルメディア利用と若者~「政治情報」に若者に関心を持たせる方法
- デジタルサイネージにおけるステンドグラス風のグラフィックデザインの提案
- ストップモーションムービー制作における技術的手法と構成について
- Webデザインとユーザビリティの原則調査
- 洪水ハザードマップにおける所在地からの避難方向指示による避難所選択支援の提案