2019.03.13COILについてCOIL Course Example
関西大学×東呉大学(台湾)2018年秋学期
COIL コース 実践例 1
本コースは、通常のCOILコースよりも期間が短いミニCOILプロジェクトで、COILを初めて導入する方向けです。また、COILの要素を取り入れてみたいけれどもツールの経験が不足している場合や、パートナーとの関係を構築して双方のコースの特徴となるようなCOILコースを開発できるようにしたい場合などにも参考にしていただけるかと思います。実践例として、2018年秋・冬学期にかけて、関西大学(日本)が国際情勢の中の日本についての授業を提供し、東呉大学(台湾)が社会問題の授業を提供した取り組みを紹介します。
本コースは、関西大学・東呉大学での授業期間開始後にスタートしました。当初は2週間のバーチャル交流として始まり、最終的に4週間のミニCOILに発展し、交流は主に非リアルタイムで行いました。担当教員にとっては初めてのCOIL実践だったため、将来的に通常のCOILコースを行うための最初のステップとしてミニCOILプロジェクトの形を取りました。本コース実施期間は、関西大学の2018年から2019年にかけての年末年始休業期間(東呉大学は学期中)に一部重なっています。
参加者は関西大学の学生24名と東呉大学の学生30名でした。また、参加学生の中には1学期または2学期の交換留学プログラムで留学中の学生も含まれます。
このCOIL実践の目的は、参加学生が留学生と交流し、協働で小さいプロジェクトを完成させることです。 原則として、社会問題のトピックが双方のコースの中核をなすこと、そして学生が台湾と日本の共通の社会問題を取り上げたプロジェクトに協働で取り組んだり、他の留学生の国や文化との比較によって学びを得ることを目指しました。関西大学・東呉大学における2つの授業のシラバスの間には、社会問題に取り組むという点、そしてCOILが社会問題を探求する効果的な方法を提供するという点で共通点を持たせました。
| アイスブレーキング 1週間 |
(個人またはグループ単位で)padletとflipgridを使って短い自己紹介自己紹介動画を作成し交換 |
|---|

| 協動学習 2週間 |
台湾と日本(場合によっては他国)に共通する社会問題についての発表資料作成 |
|---|

| アウトプット | 台湾の学生が作成した資料を使って授業内で発表 日本の学生はpadlet上にディスカッション用の資料を作成 |
|---|
図:COILプロジェクト全体図
アイスブレーキング

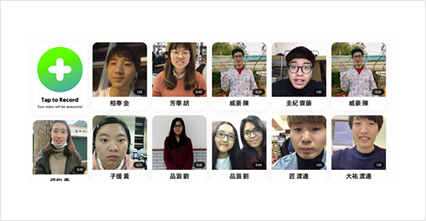
写真:flipgridを使った紹介動画の例
1週目に学生たちはflipgridやpadletを使った簡単な紹介動画の作り方を学びました。Padletは、グループやコースに関する情報の送受信や、最終発表のためのツールとして活用しました。
学生は10グループ(各グループは台湾人学生3名程度、日本人学生2名程度で構成)に分かれて、個人またはグループで紹介動画を作るための準備をしました。flipgridは基本的な編集機能しかないものの、一部の学生グループは様々な動画編集アプリを使用してより巧妙な動画を作成していました。
グループリストはpadletのほか、電子メールで全参加学生に共有しました。学生たちは、各々メールアドレスやSNSの連絡先(主にLINE)を交換していました。プロジェクトに必要な事項は授業時間中に説明し、学生自身が台湾と日本に関するテーマを自ら定め、協働で社会問題に関する発表のための資料準備に取り組むことを求めました。
通常のCOILでは、学生がグループごとに協働でプロジェクトに取り組み、共通の方法でアウトプットすることが求められます。しかし本COIL実践では、(台湾での授業がすでに始まっていたこともあり)協働で作成した資料を使って台湾の学生は授業の中で最終発表を行い、その発表を成績評価対象としました。日本の学生は、padletに最終発表資料を投稿し、クラス内でディスカッションをしました。通常授業と連動したCOILに参加した日本の学生には、コースの最低合格点が与えられました。
協働学習

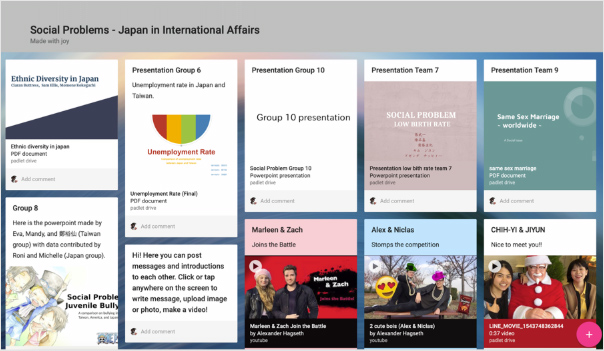
写真:紹介動画と最終グループ発表の見本を掲載したpadlet
アイスブレーキングに続いて、学生たちはグループごとに台湾と日本の共通の社会問題に関するトピックを選択し発表スライドを協働で制作しました。パワーポイントなどのプレゼンテーションソフトを使って作業をし、完成スライドはCOILコース終了時にすべての参加者と共有しました。コース運営、情報の共有は主としてpadletを使って行いました。
アウトプット
台湾の学生は、最終発表スライドを使って、協働作業によって気づいた事を授業の中でグループごとに発表しました。日本の学生はpadlet上で最終発表スライドを共有し、グループディスカッションで活用しました。本来のCOILプロジェクトでは、学生たちがそれぞれの気づきをビデオ会議で発表し合ったり、グループで最終発表用動画を制作したりして、協働プロジェクト全体を総括する形の最終発表が理想です。今回のミニCOILでは時間と予算が限られていたため実現が叶いませんでしたが、そうした最終発表へ向けての協働学習が今後のCOILコースの中心となっていくでしょう。
要点のまとめ
| コース | Japan in International Affairs (関西大学, 日本) Social Problems (東呉大学, 台湾) |
|---|---|
| COIL タイプ | ミニCOIL (2~4週間) |
| COILの目的 | 通常のCOILの前段階的な取り組みとしての実践。地域関連性のある国際問題、異文化間コミュニケーション |
| 学生 | 学部生54人(社会科学/人文科学/社会福祉専攻) |
| 協働学習の課題 | グループ発表資料 |
| 主なツール |
|