 未来の経済大国インドの成長から考える、
未来の経済大国インドの成長から考える、
いま、アジアを学ぶ意味
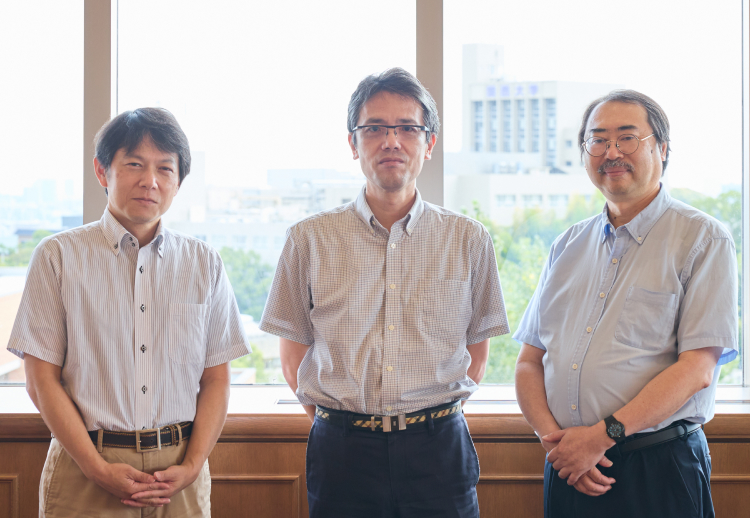
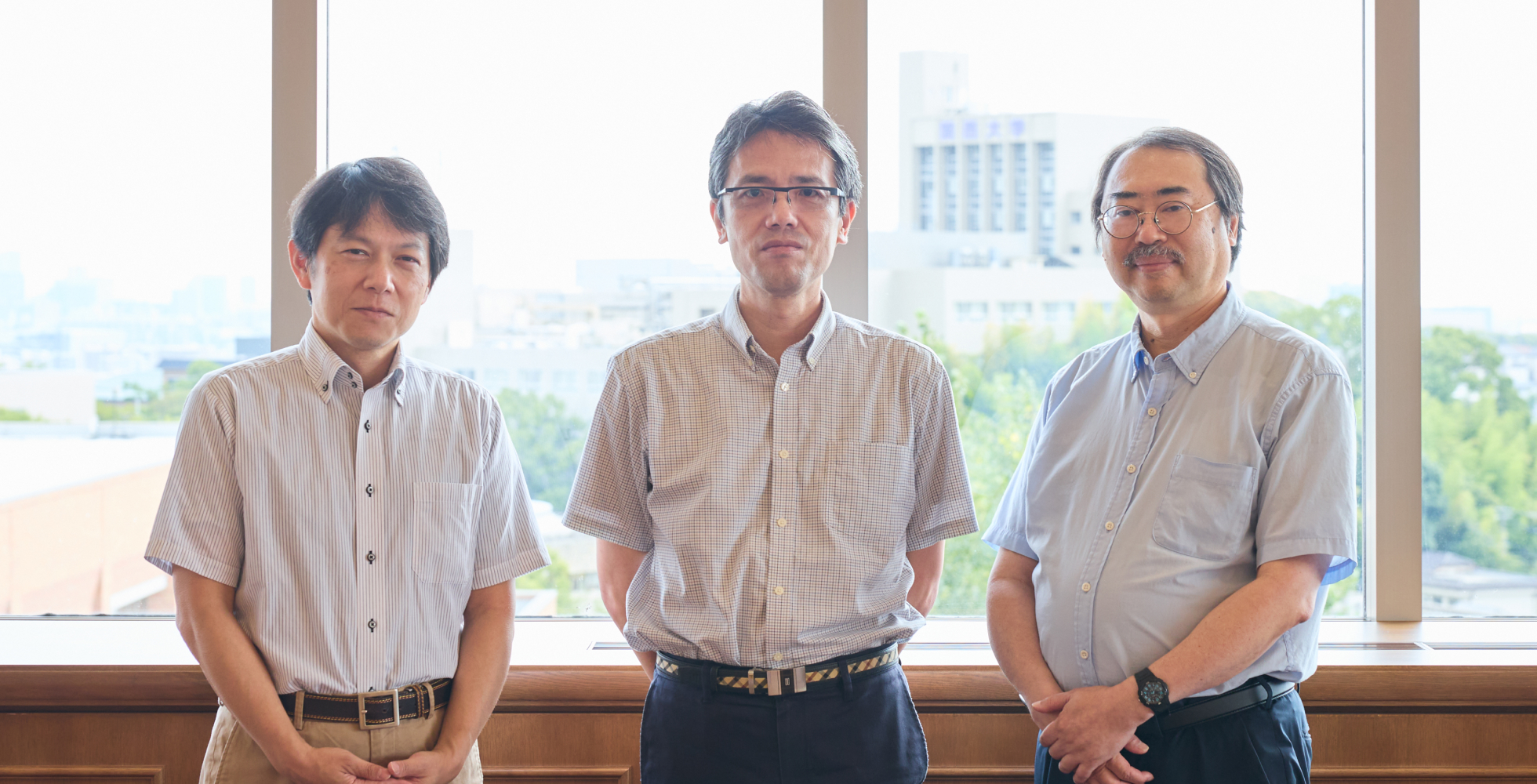
インドはIT大国として著しく経済成長し、
数年後にはGDP(国内総生産)で
日本を抜いて世界第3位になると
予測されています。
その実態はどうなのでしょうか。
また、インドをはじめ、
アジアについて学ぶ意義とは何なのか。
政策創造学部の教授3名が語り合います。
登壇者
-

西澤 希久男 学部長 国際アジア学科 教授
(専門分野:タイ法、比較法) -

浅野 宜之 副学部長 国際アジア学科 教授
(専門分野:比較憲法、南アジア法) -

福味 敦 政策学科 教授
(専門分野:インド経済論)
中世と21世紀が
混在しているかのような
インドには、
発展途上の魅力がある
西澤
近年躍進してきた中国よりもさらに人口の多いインドが、GDPをどんどん伸ばしているのは、ある意味、自然な流れにも感じられます。実際のところ、インド経済は本当に順調なのでしょうか。
福味
1990年代に経済改革をし、2007年頃からはITが成長のドライバーとなって経済成長率が高まっています。ただ大前提として、インドはまだ発展途上国です。実際にはスラムがあってインフラも整っておらず、昔のインド的な景色はまだまだ残っています。
浅野
走っている車の種類は増え、きれいになったものの、まだまだ道路は昔のままですよね。とくに歩道の整備が遅れているように思います。
一方でスマートフォンの普及は著しく、2000年代に入ってからは農村でも使われるようになり、キャッシュレス決済も当たり前のように行われるようになっています。
福味
インドの農村では、水牛を使った耕作がいまだに行われているところもありますが、農民はスマートフォンで話していますもんね。中世と21世紀が混在しているかのようです。
浅野
先日、訪れたときは、道端でココナッツを売っている人の手押し車に、キャッシュレス決済のQRコードが掲げてありました。とはいえキャッシュレス決済はインドの口座を持っていないと使えないので、外国人には不便でもあるんです。

西澤
エネルギー供給の問題はどうなのでしょう。経済発展には欠かせない部分ですが、今では停電は起きないのでしょうか。
福味
とにかく地域差が激しいです。かなり改善はされましたが、日系企業などは自前の発電所を持っています。急に電気が遮断されて困るケースも多いですからね。そういう面ではコストもかかり、楽に商売ができる国ではありません。
西澤
となると、日本人や日本企業にとって、インド経済の魅力というのは…。
福味
魅力はすごくあると思うのですが、期待先行になっているのが実情ではないでしょうか。
市場として見ても、中国や韓国のメーカーが安くてそれなりの品質のものを売るのに対し、日本の製品は素晴らしいものの価格が高く、苦戦しているところが多いと聞きます。ただ、14億もの人がいて、今後さらに消費パワーが広がっていくでしょうから、チャレンジしない手はありません。
生産基地としても、人件費がそこまで上がっていないうえ、欧州、中東、東南アジアに近く地理的にもアドバンテージがあるので、大きなポテンシャルを秘めています。
アジア諸国を
比較対象にすることで、
日本がより
クリアに見えてくる
西澤
良い面も悪い面も含め、日本の学生がインド、それにアジアを学ぶ意義はどこにあると思われますか。
浅野
やはり自分の国を知るための手法として、他の国を知るというのは大きな意味があると思います。
とくにインドは、総選挙を前に野党の指導者が逮捕されたり、同性婚を認めるかの裁判が行われたり、公益訴訟という枠組みが設けられたりと、トピックが多岐にわたります。これらトピックについて、日本と比較しながら考えるだけでも、日本を知るうえでかなりのヒントとなるはずです。
福味
確かにそうですよね。以前はインドについて、ただ知りたいという思いが中心でしたが、日本の先行きが心配になるに連れ、状況の違うインドの研究を通じて日本をもっと知っておきたいという思いが強まっています。
日本は一時期、栄華を誇った時代があるゆえに、下がってくると必要以上に意気消沈してしまっているようにも感じられ、そこもまた気になるところです。
西澤
そうなんですよ。日本人は一度世界のトップになったら、ずっとそれが維持できるものだと思っていた気がします。でも実際は、さまざまな国が栄枯盛衰を繰り返しているわけです。これも海外の国々について知り、世界を俯瞰できてこそわかることです。
では、学生時代にアジアを深く知ることには、どんな価値があるのでしょうか。
浅野
日本もその一員であるアジア諸国は、比較対象としての距離がちょうどよく、見えてくるものが多い。西欧社会まで離れてしまうと、比較対象にするにはちょっと遠いような気がします。
とはいえ、アジアであっても、その他の国々であっても、学生のうちから日本と違う社会があることを知り、体感しておくのとしないのでは、自身の幅を広げるうえで全然違うように思います。
西澤
確かに。それに日本と違うからこそ、コミュニケーションが重要だということも意識できますね。何も言わなくてもわかりあえる、なんていうのはありえない話です。自分を知ってもらうためにも、相手を知るためにも、対話を重視するようになりますよね。

アジア諸国と
フラットな関係に
なりつつある現在、
さらなる相互理解が必要
西澤
コロナ禍では海外の大学ともオンラインで交流していましたが、やはり現地に行かなければ得られない経験もありますよね。舗装されていないガタガタ道を歩いたり、道端に捨てられているゴミのにおいを嗅いだり、日本との違いを感じられます。
福味
人生が変わるような経験もありますからね。海外へ行く準備をするところから勉強になりますし。
西澤
私のゼミでは、ゼミ生たちが自分たちで計画を立て、タイへゼミ旅行に行くことがあるのですが、ちゃんと準備ができれば、私が現地の大学の先生に依頼を出し、特別講義を開いてもらうようにしています。
以前、このゼミ旅行を率先して取りまとめてくれた学生が、4年次春学期が終了した際、もう単位が取れたからゼミをやめると言いだしました。なぜかと訊ねたら、ヨーロッパを横断したいからだと。それはもう行ってこいと背中を押しました(笑)。

浅野
それは素晴らしいですね。何が得られるかわからなくても、何かを得たいという気持ちがあれば、どこでもいいので行ってみて、サバイブしてくる経験をされるのがいい。なかでもインドはハードルが高いですけど(笑)。
福味
インドは、どこかで慣れてから行ったほうがいいかもしれませんね。とはいえ、実際に現地を見てくると、熱も入りやすくなる。論文を書くにしても、見て経験しているのとそうでないのでは、全然内容が違ってきますから。
浅野
経験することが自信にもなるでしょうし。本学部でもさまざまな国際教育プログラムを用意しています。個人で海外に行くことが不安なら、まずは「語学を学ぶため」といった目的で、大学のプログラムを利用してみてもいいかもしれません。
西澤
政策創造学部では、1年次から参加可能な「海外英語研修」と、2年次以上を対象とした「在外社会科学研究」という2種類の海外研修プログラムを開講しています。いずれも政策創造学部生のためのプログラムで、興味関心を深める手助けになるはずです。
浅野
これらプログラムは学生たちにとって、いい刺激になっていますね。
西澤
そう思います。私がかかわるタイでの研修プログラムで、向こうの学生さんと交流し、自分たちがいかに不勉強かを痛感して帰ってくる学生も多いです。

浅野
私のゼミでは今、日本語に訳されたことのない国々の憲法を翻訳していますが、ほかでやられていないことを探してやってみるのも面白いです。お金を使わなくてもできる体験はいくらでもあるので、いろいろ探してやっていただければと思いますね。
福味
大学への進学を考えていて、少しでもアジアに関心のある人たちには、政策創造学部へ学びに来てほしいですね。
昔は日本がアジアでは一強のような感じで、今でもそういうマインドの人は多いのですが、時代が変わり、アジア諸国ともフラットな関係になってきています。アジアの国々と対等に付き合っていくための知識やマインドをもつ学生たちを育てていければと考えています。
浅野
相手方のことを知っていれば、付き合いもより円滑になりますからね。
西澤
フラットな関係になりつつあるのは明らかですからね。相手側を理解し、自分たちも理解してもらうためには、日本のこともしっかりと知った上で対等なコミュニケーションを取っていくことが重要です。
日本と海外、両方に関心を持っている人は、政策創造学部にぜひ来てもらえるとうれしいですね。
Profile

西澤 希久男
政策創造学部 学部長 国際アジア学科 教授
植民地になることなく、西欧近代法による法制度整備を求められたタイと日本を比較し研究。法の適用のあり方、法に対する意識が、どのような歴史的、社会的背景に基づき形成され、変容するのかについて追究している。
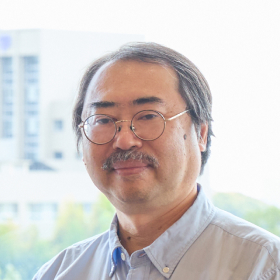
浅野 宜之
政策創造学部 副学部長 国際アジア学科 教授
アジアにおける立憲主義について、比較憲法学的視点から考察。司法に焦点を当て、制度的・機能的側面から考えるとともに考えるとともに、障害者法など個別の分野についても検討。主にイギリスの植民地統治を受けた国々における法制度の発展についても研究。
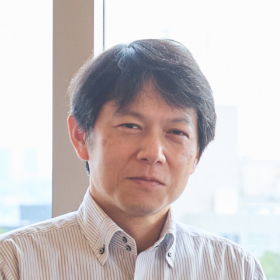
福味 敦
政策創造学部 政策学科 教授
インドの宗教やカースト、所得格差といった社会的な要因が政策決定、公共財の蓄積、民間投資、長期的な経済発展に及ぼす影響を研究。経済理論と経済・社会・政治統計を分析の軸としつつ、インドでのフィールドワークを重視している。




