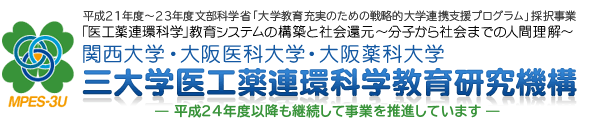活動報告
小学校への出張講義報告(高槻市立如是小)(10.11.26)
2010年11月26日
平成22年11月26日(金)に高槻市立如是小学校の6年生2クラスを対象に出張講義を実施しました。
如是小学校は女瀬川の近くある小学校です。
出張講義では一学期にも6年生対象に「顕微鏡で生物を観察しよう!」の実験講義で訪れており、今回が二回目の訪問となります。
今回は2クラス合同2限連続でランチルームにて、関西大学 倉田先生の「腕の動きと筋肉の働き」についての授業を行いました。
「力こぶのできる人、手を挙げてください」との問いかけから始まり、「筋肉ってどうやればつくのか、答えは決して一つだけではないから」とつぎつぎと生徒たちが思い思いの答えを返していきます。
また、倉田先生の研究室のティーチングアシスタントの学生の方がモデルとなり、上腕二頭筋(力こぶ)と上腕三頭筋(二の腕)に筋電計をつけ、曲げ伸ばしした時にどちらの筋肉が使われているか、筋電位の変化を大画面のモニタ画面に映しだすと「すげー!」と歓声が沸き上がりました。
倉田先生と力を入れて踏ん張っている学生のやりとりを生徒たちは好奇心一杯で見入っていました。
次に人工模擬筋肉を使って筋肉が力を入れたときどうなっているのかをティーチングアシスタントの学生が生徒のひとりひとりに実際に触ってもらって感触を確かめてもらい、理解を深めてもらいました。
また休み時間には生徒たちにも腕に筋電計をつけて、体験してもらう時間も設け、多くの生徒が自分の筋肉で実感を深めました。
授業後半では、テコ実験器を使い、テコの種類の説明をしたり、力をかける場所によって必要な力が異なるというテコの原理を実際に体験してもらったり、「どちらのほうが小さな力で持ち上げられるのか」の問いかけに対して、それぞれの答えを予想した生徒たちの代表に自ら実際で確かめてもらいました。
普段は使わない「二の腕」の使い方や、子どものうちから筋肉を均等に鍛えることによって老後も腰の曲がらない健康な体を維持できるなどの話で締めくくられました。
小学校への出張講義報告(高槻市立上牧小)(10.11.25)
2010年11月25日
2010年11月25日(木)、高槻市立上牧小学校の5年生2クラスを対象に出張講義を実施しました。
実験講義のテーマは「顕微鏡で生物を観察しよう!」(関西大学 河原先生)でした。
上牧小学校は田畑に囲まれたのどかなところにあり、校門から直ぐのところには庭石サイズの大きな岩石標本が並んでいて目を引きました。
実験講義では生徒のみなさんに自分でプレパラートを作ってもらうため、植物の葉を持ってくるよう、事前に連絡を入れています。
紅葉の季節なので銀杏や楓の紅葉が目立っていました。
なかにはアロエの葉を持ち込んでいる生徒さんもいました。
河原先生から顕微鏡の歴史や、身近な食べ物、納豆に含まれる納豆菌が一つの細胞で出来ていることや、人間を含めたすべての生物は細胞でできていることについて話されました。
また初めて微生物を発見したオランダの商人、レーウェンフックが自作していた単式顕微鏡と同じ原理のものを厚紙、ビニールテープ、ガラスビー ズを材料に押しピンを使って小学生のみんなに自作してもらいました
さらに摘んできてもらった葉っぱを使ってプレパラートも作成してもらいました。
また、大学でも使用される高性能の光学顕微鏡も用いてさまざまな微生物、植物、解剖組織のプレパラートの自由観察をおこないました。
植物や、プランクトン以外にも豚の肝臓など動物のプレパラートにも夢中になっていました。
短い限られた時間のなかの実験講義なので「もっとやってみたかった」などの生徒の声が聞かれました。
中村桂子先生(JT生命誌研究館館長、関西大学客員教授)講演会開催(於:関西大/医科大・薬科大にはTV会議システムにより配信)(10.11.17)
2010年11月17日
三大学医工薬連環科学教育研究機構は関西大学大学院理工学研究科と共催し、JT生命誌研究館館長の中村桂子客員教授による講演会を関西大学千里山キャンパスで開催しました。
 講演会の模様はテレビ会議システムで大阪医科大学、大阪薬科大学にも配信され、
講演会の模様はテレビ会議システムで大阪医科大学、大阪薬科大学にも配信され、
三大学の学生ら合わせて150名が聴講しました。
「生命を基本に置く社会をつくる」をテーマに、「人間は本来自然の一部であったのですが、いまや多くの人工のものが私たちのまわりにあふれています」
「20世紀は機械と火の時代であったが、21世紀は生命と水の時代といえるでしょう」
「言い換えれば世界観が機械的なものから生命論的なものに移っているともいえます」
「無から始まった宇宙の中で誕生した地球にあって、38億年もの間の悠久のときを経た生命の歴史があり、生まれてきた生きものたちは互いにかかわりあいながら、
また大きな絶滅も経験しながら多様に進化してきました」
「それらの多くの生きものたちが織りなす生命誌をひもといてこれからの時代を考えるとき、生きものとしての生き方を大切にし、自然を愛づる想いをもつことが必要なのではないでしょうか」と、学生らに語りかける中村先生の講演に聴講者は熱心に聞き入っていました。
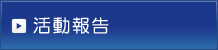
-
教育課程の構築
- 更新日:2017年12月09日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(17.12.9)
- 更新日:2017年12月02日「機能形態学1」実習報告(於:大阪薬科大学)(17.12.02)
- 更新日:2017年07月11日「基礎漢方薬学」実習報告(於:大阪薬科大学)(17.07.11)
- 更新日:2016年12月16日「お屠蘇で新年をお祝いしましょう!」報告(於:関西大学)(16.12.16)
教育支援システムの構築と教育環境の整備
- 更新日:2018年12月15日「機能形態学1」実習報告(於:大阪薬科大学)(18.12.15)
- 更新日:2018年12月08日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(18.12.8)
- 更新日:2016年06月25日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(16.06.25)
- 更新日:2010年02月17日戦略的大学連携支援プログラムに係る打合せ(教育サポート部門)(於:薬科大)(10.02.17)
社会還元
- 更新日:2018年12月06日小学校への出張講義報告(高槻市立土室小学校)(18.12.06)
- 更新日:2018年11月29日小学校への出張講義報告(高槻市立樫田小学校)(18.11.29)
- 更新日:2018年11月27日小学校への出張講義報告(高槻市立松原小学校)(18.11.27)
- 更新日:2018年11月26日小学校への出張講義報告(高槻市立阿武山小学校)(18.11.26)