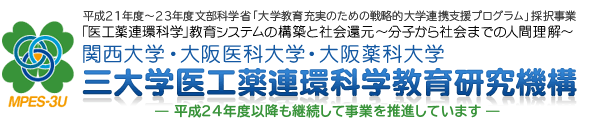活動報告
高槻家族講座(第4回)(於:薬科大)(10.10.16)
2010年10月16日
平成22年10月9日(土)と16日(土)に、高槻家族講座(通算4回目)シリーズ『食の楽しみ』
第2回「おいしさのタイムカプセル、冷凍食品」を開催いたしました。
9日はこども体験コーナーを株式会社ニチレイフーズ関西工場において実施し、
16日は講演を大阪薬科大学において実施しました。
招待講演「もっと知ってほしい、冷凍食品」
株式会社ニチレイフーズ 関西工場長 大畑 健一氏
 大畑氏は、まずはじめに、ニチレイフーズの設立史と企業グループの全国事業を説明した後、同社が生産する主だった家庭用と業務用の商品を紹介し、そして高槻市にある関西第一工場で生産される冷凍商品やキッズツアーの取組みについて説明されました。
大畑氏は、まずはじめに、ニチレイフーズの設立史と企業グループの全国事業を説明した後、同社が生産する主だった家庭用と業務用の商品を紹介し、そして高槻市にある関西第一工場で生産される冷凍商品やキッズツアーの取組みについて説明されました。
講演に先立ち行われたこども体験コーナーでの冷凍庫体験と冷凍ピラフ作りのようすを動画で紹介しました。次に、冷凍食品の歴史では、80年前に同社が初めて冷凍設備を作ったことや、冷凍コロッケができて爆発的に冷凍食品が普及したことなどを説明されました。
さらに、前処理をした素材を急速凍結して温度変化に注意して低温保管し、素材に合わせて良い解凍をすると本当に美味しい冷凍食品が食べられることを説明され、急速凍結には凍結段階ごとのマグロの顕微鏡写真を使って詳しく説明されました。
最後に、10人の聴講者に冷凍のほうれん草と生鮮のほうれん草のおひたしをその場で食べ比べていただき、生鮮ほうれん草を当てるクイズをしました。冷凍野菜は貯蔵12ヶ月後もビタミンCがほとんど逃げず、美味しく食べられることを説明と共に実証されました。
講演「冷凍保存技術の現状と未来 ~冷凍保存の仕方でおいしい食事を~」
関西大学化学生命工学部 准教授 河原 秀久氏
 河原准教授は、世界各地において異なる冷凍食品の基準を説明されたあと、コロッケ・うどん・ピラフなど日本での冷凍食品流通上位3位がすべてデンプン加工食品であり、デンプンの老化防止の関係から急速冷凍が理にかなっていることや、逆にイチゴの冷凍保存など冷凍の研究の課題などを紹介されました。
河原准教授は、世界各地において異なる冷凍食品の基準を説明されたあと、コロッケ・うどん・ピラフなど日本での冷凍食品流通上位3位がすべてデンプン加工食品であり、デンプンの老化防止の関係から急速冷凍が理にかなっていることや、逆にイチゴの冷凍保存など冷凍の研究の課題などを紹介されました。
また、冷凍保存のコツや解凍調理のコツなど聴講者にとって身近な話題ですぐに実践できることをお話され、役立つ知識を得ることができました。その後、先生が研究されている不凍タンパク質の機能について説明し、それが応用された食品がメーカーから商品化されるなど冷凍について幅広くご講演されました。
高槻家族講座(こども体験コーナー)(於:株式会社ニチレイフーズ関西工場)(10.10.09)
2010年10月 9日
平成22年10月9日(土)と16日(土)に、高槻家族講座(通算4回目)シリーズ『食の楽しみ』
第2回「おいしさのタイムカプセル、冷凍食品」を開催いたしました。
9日はこども体験コーナーを株式会社ニチレイフーズ関西工場において実施し、
16日は講演を大阪薬科大学において実施しました。
こども体験コーナーには、小学生23名とその保護者17名が、第1部、第2部の講演には191名が参加されました。
★こども体験コーナー★「my冷凍ピラフを作って食べよう!」
瞬間凍結で、myピラフのおいしさを閉じ込めよう!
ご協力:株式会社ニチレイフーズ関西工場
 小学生を対象としたこども体験コーナーは、株式会社ニチレイフーズ関西工場の荒木氏、有森氏をはじめとしたニチレイフーズ関西工場の方々により、工場見学と冷凍庫体験、さらに「凍る」しくみの講座や工場スタッフの指導のもと、冷凍ピラフ作りの体験が行われました。
小学生を対象としたこども体験コーナーは、株式会社ニチレイフーズ関西工場の荒木氏、有森氏をはじめとしたニチレイフーズ関西工場の方々により、工場見学と冷凍庫体験、さらに「凍る」しくみの講座や工場スタッフの指導のもと、冷凍ピラフ作りの体験が行われました。
今回は高槻市東上牧に立地し、優れた加工技術と生産能力を持つ冷凍食品専門のニチレイフーズ関西工場が会場になりました。まず参加者全員は見学用白衣を着用し、2組に分かれて工場見学と冷凍庫体験を順に行いました。
工場見学では一日68万個作られるミニハンバーグが大きな鉄板で片面焼かれ、
落差を利用してハンバーグを反転しもう片面を焼くようすや、各工程で入る金属異物チェックや味のチェック、見た目の目視検品など14回ものチェックが入るようすを見学しました。

また、ロボットが箱詰め用段ボールを一瞬で組み立てる様は面白く、子どもたちの関心を引いていました。
冷凍庫体験では、約マイナス25度の倉庫に入り、ぬらしたタオルを広げ1分ほどよく振り、タオルについた水分が凍り固まってタオルが板のようにピンと立つようすを体験しました。
子どもたちは、ふだん体験できない温度に、震えながらも驚き興奮していました。
その後、「凍る」しくみの講座で、急速凍結と緩慢凍結の違いを学びました。
いよいよ冷凍ピラフ作りです。プラスチックカップにトッピング(チャーシュー、白ネギ、コーン、まぐろフレークなど)で好みの味を3分目まで入れたあと、チャーハンベースを8分目まで入れ、それらを透明袋に移しマイナス40度の粉末ドライアイスを加え、袋の中が上下に踊るようにしっかり振ります。

煙がたくさん出てドライアイスがなくなった(瞬間凍結された)ところでレンジ用容器に移し、
レンジアップして試食します。工場で生産しているチャーハンとの食べ比べを行いました。
子どもたちは自分でトッピングしたチャーハンがやはり気に入ったようです。また、工場で
生産しているミニハンバーグやからあげチキンなども試食させていただきました。
最後に今回受講した小学生の皆さんは「冷凍博士」の称号の賞状を受け取りました。
三大学医工薬連環科学シンポジウム(第4回)報告(於:医科大)(10.10.02)
2010年10月 2日
平成22年10月2日(土)、当機構は大阪医科大学 別館(歴史資料館)3階多目的講義室において第4回シンポジウムを行った。
本シンポジウムは、三大学医工薬連環科学教育研究機構副機構長 出口 寛文教授の司会進行により、冒頭、大阪医科大学 竹中 洋学長から開会挨拶があり、その後、プログラムに従って進められた。
第1部では、大阪医科大学医学部教育機構 田中孝生准教授から、「医学からみた医工薬連携への展開『PARP-1 阻害薬の医療への期待』」について、大阪医科大学看護学部 佐々木 くみ子准教授から、「看護学からみた医工連携への展開『医工薬連携と看護学』について、そして、関西大学化学生命工学部化学・物質工学科 池田 勝彦教授からは「工学からみた医工薬連携への展開『医療材料としての金属』」について講演があり、それぞれの講演後に質疑応答を行い、活発な討論が行われた。
第2部では、招待講演として、新潟大学工学研究科機械システム工学科 超域研究機構 原 利昭教授から、「新潟発イノベーション創出を目指して-医工連携プロジェクトの現状と成果」について、続いて、特別発言として新潟大学超域研究機構 大森 豪教授から、「新潟大学における医工連携の意義-整形外科医の立場から」について講演され、変わる医療の現場、医工薬連携の必然性、人材の育成等、幅広くお話いただいた。
また、それぞれの講演後に質疑応答を行い、新潟大学超域研究機構の活動内容における問題点等をもとに活発な討論が行われた。
最後に、三大学医工薬連環科学教育研究機構 機構長 土戸 哲明教授から、当機構が目指す目標と課題等について述べ、また、本事業の遂行に賛同、協力いただいている行政、企業等に対して謝辞が述べられ、シンポジウムは盛会のもと終了した。



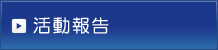
-
教育課程の構築
- 更新日:2017年12月09日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(17.12.9)
- 更新日:2017年12月02日「機能形態学1」実習報告(於:大阪薬科大学)(17.12.02)
- 更新日:2017年07月11日「基礎漢方薬学」実習報告(於:大阪薬科大学)(17.07.11)
- 更新日:2016年12月16日「お屠蘇で新年をお祝いしましょう!」報告(於:関西大学)(16.12.16)
教育支援システムの構築と教育環境の整備
- 更新日:2018年12月15日「機能形態学1」実習報告(於:大阪薬科大学)(18.12.15)
- 更新日:2018年12月08日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(18.12.8)
- 更新日:2016年06月25日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(16.06.25)
- 更新日:2010年02月17日戦略的大学連携支援プログラムに係る打合せ(教育サポート部門)(於:薬科大)(10.02.17)
社会還元
- 更新日:2018年12月06日小学校への出張講義報告(高槻市立土室小学校)(18.12.06)
- 更新日:2018年11月29日小学校への出張講義報告(高槻市立樫田小学校)(18.11.29)
- 更新日:2018年11月27日小学校への出張講義報告(高槻市立松原小学校)(18.11.27)
- 更新日:2018年11月26日小学校への出張講義報告(高槻市立阿武山小学校)(18.11.26)