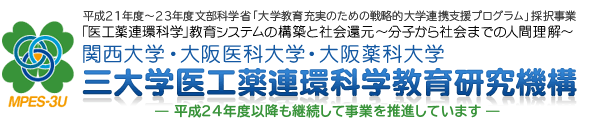活動報告
小学校への出張講義報告(高槻市立土室小)(10.07.12)
2010年7月12日
平成22年7月12日(月)に高槻市立土室小学校の6年生4クラス145人を対象に出張講義を実施しました。
土室小学校には平成21年度にも訪れ、6年生対象に講義を行なっています。
今回は2クラス合同2限連続で、関西大学 倉田先生の「腕の動きと筋肉の働き」についての授業を行いました。
「力こぶができますか?またどこにできますか?」との問いかけから始まり、力こぶを作って筋肉の動きを触ってみたり、骨のどのあたりに筋肉が付いているのかを触ってみたりします。
その後、腕・筋肉模型実験装置を見て、肘関節を曲げるときには上腕二頭筋が縮むことを確認してもらいました。
こどもたちは筋肉が縮んで太くなると長さは短くなること、その時に関節が曲がることを目で見てしっかりと納得できたようです。
また、大学の研究室に所属するティーチング・アシスタントの学生の上腕二頭筋と上腕三頭筋に筋電計をつけ、曲げ伸ばしした時にどちらの筋肉が使われているか、筋電位の変化という目に見える形で示しました。
希望者にはティーチング・アシスタントの学生と同じように腕に筋電計をつけて、体験してもらう時間も設けました。
授業後半では、大型のテコ実験器を使い、テコの種類の説明をしたり、力をかける場所によって必要な力が異なるというテコの原理を実際に体験してもらったりと、ちょうど学習したばかりのテコの分野についてタイムリーな授業を提供することができたようです。
こどもたちも腕の動きとテコの働きとの結びつきに目を輝かせていました。
2限連続としたことで、より詳しく踏み込んだ講義を行うことができたのではないでしょうか。
普段はあまり意識していない筋肉の存在を改めて認識し、筋肉を成長させるためには「栄養・運動・睡眠」が大切であることを最後にお話しして、終了時刻となりました。



小学校への出張講義報告(高槻市立冠小)(10.07.07)
2010年7月 7日
2010年7月7日(水) 、高槻市立冠小学校の5年生2クラスを対象に出張講義を実施しました。
テーマは「顕微鏡で生物を観察しよう!」(関西大学 河原先生)です。
この日は七夕だったので小学校内のあちらこちらが七夕飾りで彩られていました。
今回の出張講義はいつもの理科室でなく、最上階のランチルームだったので機材の運び上げがいつもより大変でした。
河原先生から単細胞生物や多細胞生物の違いなどが身近な例を出しながら分かりやすく解説されました。
そして「微生物学の父」レーウェンフックの単式顕微鏡を厚紙とガラスビーズと身近な材料でみんなに自作してもらいました。
また、摘んできてもらった葉っぱをサフラン染色し、表皮剥離法のプレパラートも作成してもらいました。
手作り顕微鏡と大学でも使用される高性能の光学顕微鏡を用いて自作プレパラートだけでなく、さまざまな微生物、植物、解剖組織のプレパラートを見比べたりもしました。
アンケートでは「いろんなものが見られて楽しかった」、「大学生がわかりやすく教えてくれた」、「理科が楽しくなってきた!」などの多くの感想を頂きました。



小学校への出張講義報告(高槻市立阿武野小)(10.07.07)
2010年7月 7日
2010年7月7日(水)、高槻市立阿武野小学校の6年生3クラスを対象に出張講義を実施しました。
テーマは「腕の動きと筋肉の働き」(関西大学 倉田先生)でした。
阿武野小学校はJR摂津富田駅からバスで北側に向かった所にあり、校庭側の門から入ると、低学年が遠足に向かうところで注意事項の説明を先生から受けていました。
昨年度とは異なり、小学校のカリキュラム改正の影響で、出張講義までにテコの原理を習っているクラスと習っていないクラスがあったため、倉田先生から教室のみんなに問いかけて答えてもらうというふうに授業は進みました。
こども達は、自分たちの腕を曲げて実際の筋肉の様子を観察したり、模擬筋肉や筋肉模型を手にして、「うわっー」「何、これ?」と筋肉の働きに興味津津の様子でした。
また、大学の研究室に所属する筋肉隆々の学生にモデルになってもらい、筋電計を使って筋肉には伸筋や屈筋があることを目で見て実感してもらいました。
阿武野小学校の理科担当の先生が、こども達が答えを言うたびに「いいねー」とはきはきと声を掛けられ、こども達も積極的に実験に参加していました。
アンケートでは「筋肉の動きがよくわかった」、「クイズみたいで楽しみながらできた」、「筋肉の働きってスゲー!!」など、たくさんの感想をいただきました。
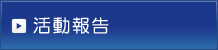
-
教育課程の構築
- 更新日:2017年12月09日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(17.12.9)
- 更新日:2017年12月02日「機能形態学1」実習報告(於:大阪薬科大学)(17.12.02)
- 更新日:2017年07月11日「基礎漢方薬学」実習報告(於:大阪薬科大学)(17.07.11)
- 更新日:2016年12月16日「お屠蘇で新年をお祝いしましょう!」報告(於:関西大学)(16.12.16)
教育支援システムの構築と教育環境の整備
- 更新日:2018年12月15日「機能形態学1」実習報告(於:大阪薬科大学)(18.12.15)
- 更新日:2018年12月08日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(18.12.8)
- 更新日:2016年06月25日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(16.06.25)
- 更新日:2010年02月17日戦略的大学連携支援プログラムに係る打合せ(教育サポート部門)(於:薬科大)(10.02.17)
社会還元
- 更新日:2018年12月06日小学校への出張講義報告(高槻市立土室小学校)(18.12.06)
- 更新日:2018年11月29日小学校への出張講義報告(高槻市立樫田小学校)(18.11.29)
- 更新日:2018年11月27日小学校への出張講義報告(高槻市立松原小学校)(18.11.27)
- 更新日:2018年11月26日小学校への出張講義報告(高槻市立阿武山小学校)(18.11.26)