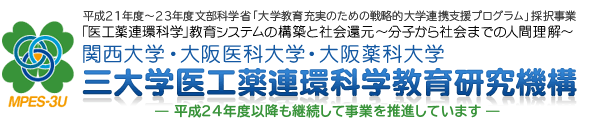活動報告
市民講座報告(於:薬科大)(10.5.22)
2010年5月22日
平成22年5月22日(土)、大阪薬科大学において、3大学(関西大学・大阪医科大学・大阪薬科大学)連携事業
-thumb-160x106-289.jpg) 第29回大阪薬科大学市民講座を開催し、215名に参加いただきました。
第29回大阪薬科大学市民講座を開催し、215名に参加いただきました。
1講目「人にやさしい技術」
-thumb-160x106-292.jpg) 関西大学システム理工学部機械工学科 准教授 倉田 純一 氏
関西大学システム理工学部機械工学科 准教授 倉田 純一 氏
倉田准教授は、大学での講義及びに医工薬連環科学教育システムの構築と社会還元の概要について説明の後、「人にやさしい技術」に関連する福祉工学等の用語について、また、評価、判断基準及び開発機器について、車イスを例に挙げ、工学的な側面及び経済的な側面から企業に対する期待、さらに、利用者の視点に立った技術の必要性等について説明されました。
2講目「介護・看護の現場は、今どのようになっているか」
・すこやかな皮膚を保つコツ-床ずれ予防-
大阪医科大学附属病院看護部主任 皮膚・排泄ケア認定看護師 池 智代 氏
・健康維持のために-口腔ケアを見直そう-
大阪医科大学附属病院看護部主任 摂食・嚥下障害看護認定看護師 檀上 明美 氏
池看護師は、要介護・看護状態の方がなりやすい床ずれについて、実際の業務での経験を基に、予防洗浄方法及び保湿方法について、予防製品の使用方法を交えて説明されました。続いて、檀上看護師は、口腔ケアと誤嚥性肺炎の関係について説明の後、実際の業務での経験を基に、口腔ケアについて必要な口腔ケアグッズについて、歯ブラシ、スポンジブラシ及び入れ歯等の選択並びに使用方法を具体的に説明されました。
-thumb-160x106-299.jpg)
-thumb-160x106-302.jpg)
3講目「お薬を安心してのんでいただくための「くすりの話」」
-thumb-160x106-306.jpg) 大阪薬科大学臨床実践薬学教育研究室 教授(特任) 鈴木 芳郎氏
大阪薬科大学臨床実践薬学教育研究室 教授(特任) 鈴木 芳郎氏
鈴木教授は、高齢者とくすりの関係について、身体的及び社会的な観点から、ジェネリック医薬品等のお話を踏まえて説明の後、様々なくすりの安全な使用方法について説明されました。さらに、安全なくすりの使用方法と関連して、薬剤師及び薬局並びにおくすり手帳の活用についても説明されました。
-thumb-160x106-310.jpg) 講演後には参加者からの質疑を基に、講演者全員による、
講演後には参加者からの質疑を基に、講演者全員による、
「3大学によるパネルディスカッション」を行いました。
参加者からは今回の講演で感じた様々な疑問等について活発な質問がありました。
また、従前からの「くすりの相談室」「薬用植物園の見学」も併せて開催し、「くすりの相談室」では大阪医科大学附属病院等の近隣病院及び薬局からの協力も受け、第一線で活躍中の薬剤師の先生方に、くすりに関する様々な相談に応じていただきました。
最後になりましたが、本講座の開講にあたり、ご共催いただきました高槻市、(社)日本薬学会近畿支部、(社)大阪府薬剤師会、(社)大阪府病院薬剤師会及び大阪薬科大学同窓会、並びにご後援いただきました大阪府、高槻市教育委員会及び高槻市薬剤師会に厚く御礼申し上げます。
高槻家族講座(第2回)報告(於:薬科大)(10.02.27)
2010年2月27日
平成22年2月27日(土)、大阪薬科大学において、高槻家族講座 シリーズ「食と健康」第2回「お口 スッキリ 健康家族」を開催いたしました。
サンスター㈱ オーラルケア研究開発部 高塚 勉 氏
高塚氏は、まず初めに、現在のサンスター株式会社の概要の説明の後、サンスター株式会社の創業期からの話をされました。
サンスターが何故、ハミガキなどのオーラルケア以外の部門があり、製造販売しているかを説明されました。
次に、歯磨きの歴史から、歯磨きの重要性について話をされました。歯を磨くことによって、歯周病などの予防になることを再度認識しました。
さらに、新製品の歯みがきチューブが、何故きれいにストライブが入って、出てくるのかを説明するために、歯磨きチューブを液体窒素の中で冷凍し、冷凍後にカッターを用いて、外側のチューブを切り開き、中にどのように歯みがきがパッケージされているかの説明がありました。
聴講の方々は、その説明はわかりやすく、理解することができたようです。
大阪医科大学 教授 島原政司 氏
島原教授は、歯みがきをすることが病気と関係していることを紹介し、インフルエンザへの罹患率と歯みがきと関係があることを説明されました。
また、例として、学生に夜と朝に歯磨きをせずに来るように指導され、翌日、歯のねばねばした部分(歯こうやバイオフィルム状態部分)を採取し調べた所、非常に多くの細菌が検出されたことが判明したことを紹介されました。
これらの細菌は、嫌気性(空気のないところでしか生育できない)であり、寝ている間にどんどん生育していくことを説明されました。
歯周病になってしまうとその細菌群が他の体内部分に移動して、病気の引き金になることも紹介され、歯みがきの必要性を実感しました。
第2部 こども体験コーナー 「ハミガキを作って、味や匂いを感じてみよう!」
いちご・メロンのハミガキをもとに、オリジナル・ハミガキを作ろう
ご協力: サンスター株式会社
第2部として小学生を対象としたこども体験コーナーではサンスター株式会社のオーラルケア研究開発部の高塚 勉氏をはじめとしたサンスターの方々の指導のもと、オリジナル歯磨き粉作りの講習が行われました。
今回は東西面がガラス壁で中庭や高槻市街が見渡せる大阪薬科大学の学生ラウンジD棟が会場になりました。
最初に赤色と緑色のついた香料の匂い当てクイズが行われました。
赤色がイチゴの匂いとメロンの匂いの場合と、緑色がメロンの匂いとイチゴの匂いの場合の組合せで、人間の嗅覚が視覚からの情報による思い込みで簡単にだまされてしまうなどの体験が盛り込まれていました。
次は匂いも味も色も付いていない白い歯磨き粉のペーストをもとに、色づけのコーナー、匂い付けのコーナー、味付けのコーナーに分かれて好みの歯磨き粉になるようエッセンスを添加してもらいました。
後から複数の色素や匂いや味を添加してもらったりするこどもたちも現れ、どんな色や匂いや味になるのか予測のつかない遊び心に溢れていました。
このオリジナル歯磨きペーストをよく練り混ぜ合わせてビニール袋に入れた後、この先端に穴をあけ、ケーキのクリームの飾りつけの時の要領で空の歯磨きチューブの口とは反対方向の開放部からオリジナル歯磨き粉を充填しました。
これをサンスターのお兄さんに渡してシーリングの機械で開放部を密閉してもらいました。
このオリジナル歯磨き粉の入った白いチューブにこどもたちはカラーマジックで絵や文字でデザインを加えていました。
用意された歯ブラシでさっそくオリジナル歯磨き粉の味見?をするこどもたちも現れました。
自分で作った歯磨き粉だと毎日の歯磨きも楽しくなるのかもしれません。
最後に今回の受講した小学生の皆さんは「ハミガキ博士」の称号の賞状を受け取りました。
小学校への出張講義報告(10.01.25)
2010年1月25日
2010年1月25日(水)に高槻市立五百住(よすみ)小学校の6年生2クラスを対象に、今年度最後の出張講義を実施しました。
「人間の体の中の消化反応を体の外で観てみよう!」(関西大学 河原先生)と「腕の動きと筋肉の働き」(関西大学 倉田先生)の異なった授業を1時限ずつ体験してもらいました。
「人間の体の中の消化反応を体の外で観てみよう!」は、マイクロチューブの中に詰められた消化酵素を使い、体の中で行われている消化反応を体の外である試験管の中で、カツオブシや豆腐などの身近な食材を使って観察しました。
消化に関わる器官によって消化酵素や消化液の酸性やアルカリ性の度合いが違うことを体験してもらいました。こどもたちは酸性・アルカリ性を調べるのにリトマス試験紙を使ったことがありますが、今回は中性付近の細かい範囲を調べることのできるBTBや、広範囲用のWR試験紙を用いました。
また、酵素なしと酵素ありの比較や胃腸薬には何が含まれているかをネガティブコントロール(陰性の対照)とポジティブコントロール(陽性の対照)を使って比較調査を体験してもらいました。これは適切なコントロールを踏まえることが実証実験の本質であるからです。
 「腕の動きと筋肉の働き」ではスライドを交えて解説しながら、関節と筋肉のシステムについてこどもたちと質疑応答を行ってから、骨格と筋肉の模型に触ってもらい、その後再度考えてもらうなど、自分で考えを深めていけるように誘導していくことを配慮した内容になっています。
「腕の動きと筋肉の働き」ではスライドを交えて解説しながら、関節と筋肉のシステムについてこどもたちと質疑応答を行ってから、骨格と筋肉の模型に触ってもらい、その後再度考えてもらうなど、自分で考えを深めていけるように誘導していくことを配慮した内容になっています。
また倉田先生と学生アシスタントとの力比べの実演と、筋電計の計測結果を比較して屈筋や伸筋の違いやその制御機構について理解を深めてもらいました。
このような体験型の授業を通して理科や科学への興味が芽生え、将来的に医工薬の分野に進もうと考えるこどもたちが少しでも増加すれば幸いです。
4月からの新年度には刷新された内容の出張講義を計画中です。ご期待下さい。
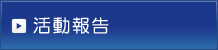
-
教育課程の構築
- 更新日:2017年12月09日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(17.12.9)
- 更新日:2017年12月02日「機能形態学1」実習報告(於:大阪薬科大学)(17.12.02)
- 更新日:2017年07月11日「基礎漢方薬学」実習報告(於:大阪薬科大学)(17.07.11)
- 更新日:2016年12月16日「お屠蘇で新年をお祝いしましょう!」報告(於:関西大学)(16.12.16)
教育支援システムの構築と教育環境の整備
- 更新日:2018年12月15日「機能形態学1」実習報告(於:大阪薬科大学)(18.12.15)
- 更新日:2018年12月08日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(18.12.8)
- 更新日:2016年06月25日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(16.06.25)
- 更新日:2010年02月17日戦略的大学連携支援プログラムに係る打合せ(教育サポート部門)(於:薬科大)(10.02.17)
社会還元
- 更新日:2018年12月06日小学校への出張講義報告(高槻市立土室小学校)(18.12.06)
- 更新日:2018年11月29日小学校への出張講義報告(高槻市立樫田小学校)(18.11.29)
- 更新日:2018年11月27日小学校への出張講義報告(高槻市立松原小学校)(18.11.27)
- 更新日:2018年11月26日小学校への出張講義報告(高槻市立阿武山小学校)(18.11.26)