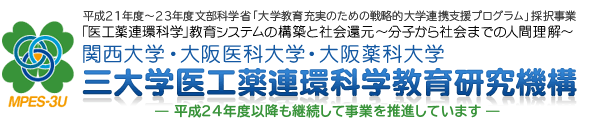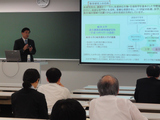活動報告
小学校への出張講義報告(高槻市立高槻小)(10.07.06)
2010年7月 6日
2010年7月6日(火)、高槻市立高槻小学校の6年生2クラスを対象に出張講義を実施しました。
テーマは「聴こえない音:超音波を見よう」(関西大学 山本先生)です。
山本先生からは、イルカやコウモリなどの超音波を使う動物の話から、お母さんのお腹の中の赤ちゃんの超音波診断や、ガンの治療などの医療と超音波の話、そして聴こえない音である超音波の周波数には個人差があることなどがクイズを通してわかりやすく解説されました。
その次は各テーブルに移り、「超音波による物体を浮遊」、「指向性超音波スピーカー」、「超音波による霧化装置」、「超音波洗浄機」などのバラエティー豊かな実験を大学の研究室に所属するティーチング・アシスタントの学生たちが担当しました。
子ども達は加湿器などにも使用されている人工の霧のなかに手を突っ込んだり、超音波でアルミホイルに穴を開けたり、何個の浮遊物体を超音波で浮かせることができるのか等々、活発にチャレンジしていました。
アンケートでは「学生さんや先生の説明がうまかった」、「超音波はまっすぐに進むことを知れた」、「楽しく勉強が出来た」などの多くの感想を頂きました。
三大学医工薬連環科学シンポジウム(第3回)報告(於:薬科大)(10.07.03)
2010年7月 3日
平成22年7月3日(土)、大阪薬科大学において、三大学医工薬連環科学シンポジウム(第3回)を開催しました。
 シンポジウムには、三大学を中心に教員23名、学生33名、その他10名計66名が参加されました。
シンポジウムには、三大学を中心に教員23名、学生33名、その他10名計66名が参加されました。
梶本哲也大阪薬科大学特任教授の司会により、三大学医工薬連環科学教育研究機構長の土戸哲明関西大学教授から三大学医工薬連環科学教育研究機構の取り組みについての紹介と開会の挨拶が行われ、続いて、千熊正彦大阪薬科大学学長から挨拶が行われました。



最初の講演は、関西大学社会連携部産学官連携センター長の西山豊教授より「関西大学における産学官連携の取り組み-大学連携を中心に-」の演題で行われました。
まず、関西大学が他大学との間で行っている大学間連携について、2大学間又は3大学間で学長が正式に協定を締結して行っている6つの取り組みについて紹介されました。
次に、連携事業としての大学連携として、文科省の戦略的大学連携支援事業に採択されている2つの取り組みの紹介があり、最後に、西山教授が所属されている社会連携部産学官連携センターとしての大学間連携の取り組みについて、社会連携部の組織と活動目標と合わせて説明されました。
二番目の講演は、大阪医科大学の中野隆史准教授より「新しい医療廃液処理法の開発と評価」の演題で行われました。まず、医工薬の3つの連携がないと実現できない研究テーマに取り組んでいるとの前置きの後、「飲用水に医薬品残留」とのショッキングな新聞記事の紹介から始まりました。
現行の医療廃液の処理方法は、環境への悪影響が懸念される。そこで、環境への負荷が小さい医療廃液の処理方法について研究していたところ、電気分解による処理が環境への負荷が小さいことがわかり、その実用化に取り組んでいるとして、その共同研究について紹介されました。
三番目の講演は、岐阜大学連合創薬医療情報研究科長 先端創薬研究センター長の北出幸夫教授より「岐阜地域における創薬をキーワードとする取組と将来展望」の演題で招待講演が行われました。
国立大学法人である岐阜大学と公立大学法人である岐阜薬科大学との連携の取り組みについて、先端創薬研究センターの設立から連合大学院である連合創薬医療情報研究科の設立に至る経緯について紹介されました。
さらに平成21年10月に岐阜大学のキャンパス内に岐阜薬科大学の校舎が完成し、岐阜薬科大学の先端創薬研究センターおよび連合創薬医療情報研究科を同校舎に移転したことにより医工薬の連携が強化されたとして、連合大学院の特色ある教育課程等について紹介され、その将来展望について述べられました。
最後の講演は、早稲田大学先端生命医科学センター長の梅津光生教授より「TWInsにおける真の医理工連携の実践」の演題で招待講演が行われました。
早稲田大学と東京女子医科大学の連携により女子医大の隣接地に誕生した先端生命医科学センター(TWIns)の創設には、
1)40年の医工連携の歴史 2)キーパーソンの存在 3)両大学のトップの理解と強力なリーダーシップが必要不可欠であったとの設立時の経緯から現在の運営状況について、また、TWInsで行われている医理工連携による研究成果について紹介されました。さらに、平成22年4月に開設された共同大学院である共同先端生命医科学専攻について紹介され、今後の医療産業の普及、グローバル化につながる人材育成について述べられました。
最後に、三大学医工薬連環科学教育研究機構副機構長の辻坊裕大阪薬科大学教授より、本シンポジウムの4名の講師への謝辞と三大学医工薬連携の取り組みへの協力・支援の要請があり、閉会の挨拶とされました。
小学校への出張講義報告(高槻市立奥坂小)(10.06.28)
2010年6月28日
2010年6月28日(月)、高槻市立奥坂小学校の6年生3クラスを対象に出張講義を実施しました。
テーマは「顕微鏡で生物を観察しよう!」(関西大学 河原先生)です。
奥坂小学校は名前の通り見晴らしの良い坂の上に建っていました。
河原先生からは「微生物学の父」と呼ばれるレーウェンフックが日本とサッカーのワールドカップで闘ったオランダの商人であることなど身近な話題と合わせて易しく解説されました。
レーウェンフックの単式顕微鏡とプレパラートの自作を、各班に一名ずつ大学の研究室に所属するティーチング・アシスタントの学生らの指導を受けて完成させました。
大学の研究室でも使用されている高性能の光学顕微鏡や手作り顕微鏡を用いてさまざまな微生物、植物、解剖組織のプレパラートを見比べてもらい、目を輝かせて覗き込んでいる姿がとても印象的でした。
後半にはこども達の自信作のプレパラートをCCDカメラ付き顕微鏡からの画像を大きなスクリーンを通して教室のみんなに披露してもらいました。
アンケートでは「顕微鏡を作るのも見るのも楽しかった」、「いろんな生物や細胞を見ることができて良かった」、「とてもわかりやすくお姉さんたちや先生たちが説明してくれた」など好評を得ました。
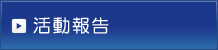
-
教育課程の構築
- 更新日:2017年12月09日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(17.12.9)
- 更新日:2017年12月02日「機能形態学1」実習報告(於:大阪薬科大学)(17.12.02)
- 更新日:2017年07月11日「基礎漢方薬学」実習報告(於:大阪薬科大学)(17.07.11)
- 更新日:2016年12月16日「お屠蘇で新年をお祝いしましょう!」報告(於:関西大学)(16.12.16)
教育支援システムの構築と教育環境の整備
- 更新日:2018年12月15日「機能形態学1」実習報告(於:大阪薬科大学)(18.12.15)
- 更新日:2018年12月08日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(18.12.8)
- 更新日:2016年06月25日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(16.06.25)
- 更新日:2010年02月17日戦略的大学連携支援プログラムに係る打合せ(教育サポート部門)(於:薬科大)(10.02.17)
社会還元
- 更新日:2018年12月06日小学校への出張講義報告(高槻市立土室小学校)(18.12.06)
- 更新日:2018年11月29日小学校への出張講義報告(高槻市立樫田小学校)(18.11.29)
- 更新日:2018年11月27日小学校への出張講義報告(高槻市立松原小学校)(18.11.27)
- 更新日:2018年11月26日小学校への出張講義報告(高槻市立阿武山小学校)(18.11.26)