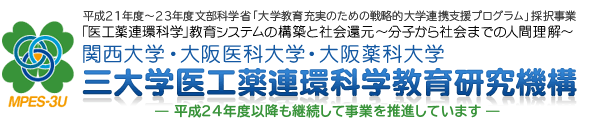活動報告
小学校への出張講義報告(高槻市立奥坂小)(10.12.02)
2010年12月 2日
平成22年12月2日(木)に高槻市立奥坂小学校の5年生2クラスを対象に出張講義を実施しました。
奥坂小学校は名前の通り坂の上にある小学校です。
出張講義では昨年度も含めて今回が3回目の訪問となります。
今回は関西大学 河原先生の「顕微鏡で生物を観察しよう!」の実験テーマで授業を行いました。
河原先生の「身近な微生物って何かな、いつもみんなが食べているかもしれないものの中にもいますよ」の呼びかけに、考え込む子どもたちは「ヨーグルトの中にいる乳酸菌って聞いたことがあるかな、じゃあ納豆菌は?細菌は一つの細胞で生きているけれど、みなさんも実はたくさん細胞が集まって人間になっていますよ!」と言う先生のお話に生徒たちは聞き入っていました。
理科室には颯爽とした白衣姿の研究室に所属する理系女子の学生たちがティーチングアシスタントとして実験の進行を班ごとにサポートします。
最初は植物の葉を染色してプレパラートを作ります。
その次はレーヴェンフックの顕微鏡を自作しました。
レンズ用のガラスビーズを転げ落としたり、穴を上手く開けられなくて、初めての顕微鏡の工作に悪戦苦闘する生徒たち。
自分の顕微鏡でプレパラートを見た後は、高性能の光学顕微鏡でも見てもらいました。
解剖した組織の細胞の染色プレパラートもいろいろあり、「えーもう時間がなくなっちゃった。」と言う声も聞こえる程、あっという間に実験講義の時間は過ぎてしまいました。
「けんび鏡をつくれて楽しかった」、「説明がわかりやすかった」、「先生の話や実験をして、わかったことがたくさんあったのでいいけいけんになったと思った」などの感想をたくさん頂きました。
小学校への出張講義報告(高槻市立三箇牧小)(10.12.01)
2010年12月 1日
平成22年12月1日(水)に高槻市立三箇牧小学校の6年生2クラスを対象に出張講義を実施しました。
三箇牧小学校は刈り入れの終わった田園と堤防の近くにある小学校です。
出張講義では一学期にも6年生対象に「顕微鏡で生物を観察しよう!」の実験講義で訪れており、今回が二回目の訪問となります。
今回は2クラス合同2限連続で関西大学 倉田先生の「腕の動きと筋肉の働き」についての授業を行いました。
理科室での大人数の講義に生徒たちもいつもより興奮気味のようでした。
倉田先生が「力こぶのできる人、手を挙げてください、えー誰もいないのかなー、ついてないように見えてもみんなには必ず筋肉が付いています」の呼びかけに、生徒たちも自分の力こぶの辺りを触りながら筋肉を確かめていました。
倉田先生の研究室の筋肉隆々のティーチングアシスタントの学生の方が実験のモデルとなり、筋肉から発生する微小な電気を検出する装置である筋電計の電極を上腕二頭筋(力こぶ)と上腕三頭筋(二の腕)を装着しました。
力こぶができると大きな青いパルスが電子黒板に映しだされ、生徒たちの歓声が上がります。
筋電計では二の腕の動きは黄色いパルスで示され、力こぶの筋肉とは別々に働いていることが映しだされました。
「そうか、腕を曲げる筋肉と伸ばす筋肉は違うのか!」と生徒たちも興味津々の様子でした。
次に倉田先生が、人工骨に曲げる筋肉と伸ばす筋肉の2種類の人工筋肉が付いた模型筋を使って筋電計での実験での腕の中身の筋肉の動きについて解説を加えました。
今度はティーチングアシスタントの学生たちが人工筋肉の模型を持って生徒たちに次々とさわってもらいました。
「筋肉に力を入れるどうなるのかな?」休み時間は生徒たちの筋電位計の体験コーナーになりました。
大勢の生徒たちは自分の筋電位のパルスを見て大喜びでした。
授業後半からはテコの実験器を使い、骨と筋肉の関係について考えを深めました。
テコには力点、支点、作用点の位置関係で三種類あり、力点と支点の長さでどちらの方が小さな力で重いものを持ち上げられるのかを問いかけられました。
「これを腕の筋肉の動きで見ればどうなるかな?腕の筋肉は骨の付け根、テコでいえば非常に効率の悪い位置に筋肉が付いています、これはなぜなのかな?筋肉は腕の動きを邪魔しないため、骨の付け根で大きな力を出してがんばっています。みんなも今のうちから曲げる筋肉と伸ばす筋肉のバランスに気をつけて鍛えていれば老後も腰が曲がらない元気なおじいさん、おばあさんになれるよ。」と実験講義は締めくくられました。
自由研究コンテスト2010 発表会(於:高槻ミューズキャンパス)(10.11.28)
2010年11月28日
「自由研究コンテスト2010」第二次審査会、表彰式を開催しました。
 三大学医工薬連環科学教育研究機構では、今年から、高槻市内の小・中学校に通う児童・生徒を対象に「自由研究コンテスト2010」を開催。
三大学医工薬連環科学教育研究機構では、今年から、高槻市内の小・中学校に通う児童・生徒を対象に「自由研究コンテスト2010」を開催。
高槻市内の公私立小・中学校から寄せられた総数230作品の中から、第一次審査で選出した22作品について、28日、関西大学高槻ミューズキャンパスミューズホールにて第二次審査会、表彰式を行いました。
 第二次審査では、小学校低学年9名が作文
第二次審査では、小学校低学年9名が作文
(「未来の生活について」)を朗読し、小学校高学年・中学生13名がそれぞれの自由研究の内容を発表しました。
発表者はスクリーンに大きく投影された研究成果を前に、
レーザー・ポインターを駆使して、すばらしいプレゼンテーションを
繰り広げていました。
 会場には発表者の家族や学校の校長先生、担任の先生、友人たち118名が来場し、それぞれの発表に熱心に耳を傾けていました。
会場には発表者の家族や学校の校長先生、担任の先生、友人たち118名が来場し、それぞれの発表に熱心に耳を傾けていました。
また、第二次審査に進んだ小学校高学年・中学校部門の作品はポスターとして掲出され、来場者はこどもたちの力作に見入っていました。
審査会の後、審査員のお1人 寺戸 真 先生による実験とお話では、家族揃って工作と実験に取り組んでいました。
 審査の結果、最優秀賞2名、優秀賞3名、関西大学賞1名、大阪医科大学賞1名、
審査の結果、最優秀賞2名、優秀賞3名、関西大学賞1名、大阪医科大学賞1名、
大阪薬科大学賞1名、審査員特別賞2名が入賞し、発表者全員が入選として表彰されました。
身近にある「なぜ?」をこどもたちが調べ、研究し、発表することが未来の科学の発展につながっていくということを知ってもらういい機会になったのではないかと私たちは考えています。
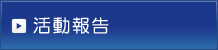
-
教育課程の構築
- 更新日:2017年12月09日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(17.12.9)
- 更新日:2017年12月02日「機能形態学1」実習報告(於:大阪薬科大学)(17.12.02)
- 更新日:2017年07月11日「基礎漢方薬学」実習報告(於:大阪薬科大学)(17.07.11)
- 更新日:2016年12月16日「お屠蘇で新年をお祝いしましょう!」報告(於:関西大学)(16.12.16)
教育支援システムの構築と教育環境の整備
- 更新日:2018年12月15日「機能形態学1」実習報告(於:大阪薬科大学)(18.12.15)
- 更新日:2018年12月08日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(18.12.8)
- 更新日:2016年06月25日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(16.06.25)
- 更新日:2010年02月17日戦略的大学連携支援プログラムに係る打合せ(教育サポート部門)(於:薬科大)(10.02.17)
社会還元
- 更新日:2018年12月06日小学校への出張講義報告(高槻市立土室小学校)(18.12.06)
- 更新日:2018年11月29日小学校への出張講義報告(高槻市立樫田小学校)(18.11.29)
- 更新日:2018年11月27日小学校への出張講義報告(高槻市立松原小学校)(18.11.27)
- 更新日:2018年11月26日小学校への出張講義報告(高槻市立阿武山小学校)(18.11.26)