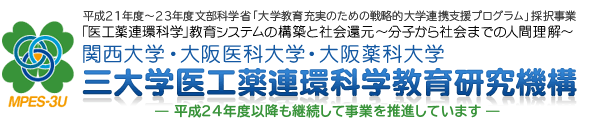活動報告
市民講座報告(於:薬科大)(11.05.21)
2011年5月21日
 平成23年5月21日(土)、大阪薬科大学において、3大学(関西大学・大阪医科大学・大阪薬科大学連携事業)
平成23年5月21日(土)、大阪薬科大学において、3大学(関西大学・大阪医科大学・大阪薬科大学連携事業)
第31回大阪薬科大学市民講座『快適で健やかな老後のために』を開催し、363名に参加いただきました。
 1講目 高齢化社会と食の関係 ~今まで何を食べ、これから何を食べていくべきか~
1講目 高齢化社会と食の関係 ~今まで何を食べ、これから何を食べていくべきか~
関西大学化学生命工学部生命・生物工学科 教授 福永 健治 氏
福永教授は、食生活の欧米化が進行した背景、欧米型食生活の進行による功罪、具体的な食料消費構造の変化について説明の後、生活習慣と生活習慣病との関係、食生活と高齢者とガンの関係を踏まえて、高齢者の食生活に求められる要点についてわかりやすく説明されました。
 2講目 高齢者に多い神経の病気~知っておきましょう病気と薬~
2講目 高齢者に多い神経の病気~知っておきましょう病気と薬~
大阪薬科大学薬品作用解析学研究室 教授 大野 行弘 氏
大野教授は、脳の構造と機能、神経伝達物質とその異常に伴う神経の病気について説明の後、高齢者に多い神経の病気であるアルツハイマー病について、具体的な症状と病態、最新の治療薬と治療法について薬物治療の観点からわかりやすく説明されました。
 3講目 神経内科の立場から
3講目 神経内科の立場から
大阪医科大学内科学Ⅰ教室 准教授(神経内科 科長) 木村 文治 氏
木村准教授は、神経内科及び神経再生医療の概要、脳卒中の種類とその特徴、本邦で初めての試みとなる高槻市医師会地域連携クリティカルパスについて説明の後、高齢者の主な神経の病気であるパーキンソン病やアルツハイマー病の症状及び特徴、地震発生後の生活環境等からも懸念されるエコノミークラス症候群の症状や予防策等について、医師の視点から説明されました。
 講演後には、参加者のからの質疑を基に、講演者全員による、「3大学によるパネルディスカッション」を行いました。
講演後には、参加者のからの質疑を基に、講演者全員による、「3大学によるパネルディスカッション」を行いました。
参加者からは今回の講演で感じた様々な疑問等について活発な質問がありました。
また、従前からの「くすりの相談室」「薬用植物園の見学」も併せて開催し、「くすりの相談室」では大阪医科大学附属病院等の近隣病院及び薬局からの協力も受け、第一線で活躍中の薬剤師の先生方に、くすりに関する様々な相談に応じていただきました。
本講座の開講にあたり、ご共催いただきました高槻市、ご協賛いただきました(社)日本薬学会近畿支部、(社)大阪府薬剤師会、(社)大阪府病院薬剤師会及び大阪薬科大学同窓会、並びにご後援いただきました大阪府、高槻市教育委員会及び高槻市薬剤師会に厚く御礼申し上げます。
三大学医工薬連環科学シンポジウム(第6回)報告(於:高槻ミューズキャンパス)(11.02.26)
2011年2月26日
三大学医工薬連環科学教育研究機構では、地域・家庭での理科教育振興のため、「これからの理科教育を考える」をテーマに、教育関係者、保護者など理科教育にご関心をお持ちの方を対象にシンポジウムを開催しました。
当日は175名の方が来場し、たいへん賑やかなシンポジウムとなりました。
開会には土戸哲明機構長からの挨拶に続き、楠見晴重関西大学学長が挨拶をいたしました。


 講演「理科教育の関わり」
講演「理科教育の関わり」
(三大学医工薬連環科学教育研究機構 教育開発部門長 倉田純一)
当機構が社会還元事業として主に高槻市内での実施した取組みから、特に児童・生徒の方を対象にした各種事業をご紹介しました。
 講演「教科書や黒板が変わると授業ってこんなにおもしろい!
講演「教科書や黒板が変わると授業ってこんなにおもしろい!
~情報通信技術(ICT)でもっと楽しい授業を~」
(関西大学初等部 教諭 田邊則彦 先生)
電子黒板やコンピュータを使用した教材等、情報通信技術を活かした学習についてご講演されました。
約15年前に作成された未来の授業風景の映像では、すでに導入され、活用されているものもあり、来場者は興味深く耳を傾けていました。
 講演「夢とロマンの冒険あふれる理科教育~ワクワクどきどきの世界~」
講演「夢とロマンの冒険あふれる理科教育~ワクワクどきどきの世界~」
(オンライン自然科学教育ネットワーク(ONSEN)
世話人、科学教育ボランティア研究大会 実行委員長 山田善春 先生)
簡単な実験を通して、身近にある疑問や不思議に焦点を当て、「慣性」や「中和反応」等を体感し、会場内からは驚きや歓声が上がっていました。
講演後も、こども達が山田先生を囲み、実験を楽しんでいました。
 講演「自由研究の取組み方」
講演「自由研究の取組み方」
(三大学医工薬連環科学教育研究機構 教育サポート部門長 河原秀久)
当機構の「自由研究コンテスト2010」を振り返り、自由研究のテーマの選び方や研究のまとめ方、さらには審査のポイント等を具体的にご紹介しました。
 パネルディスカッション
パネルディスカッション
「理科嫌いにしないための大人の努力とコツ~ずっと理科好きでいるために~」
(司会:倉田純一、パネリスト:山田善春 先生、
高槻市教育センター 松村 尚 先生、
広島県立広島観音高等学校 教諭 岩屋道子 先生、
三大学医工薬連環科学教育研究機構 梶本哲也)
事前に来場者に対し、理科嫌いについてのアンケートを行い、集計した結果を踏まえながら、各パネリストがそれぞれの経験、立場から、理科好きを増やすためのアイデアや工夫について意見を述べ、議論を重ねました。
 理科実験体験コーナー
理科実験体験コーナー
「聞こえない音:超音波を感じよう!」、「いろんな生物を顕微鏡で見てみよう!」、「レインボーメタルを作ろう!」、「腕の動きと筋肉の動き」の4つのテーマでコーナーを設置。
シンポジウム開会から閉会間際まで、多くの保護者、児童・生徒が各コーナーにつめかけました。参加者は、大学教員と大学生の指導のもと、本格的な機材を用いて、理科実験を楽しんでいました。
講演や実験のほか、「自由研究コンテスト2010」入選作品展示コーナーなど、内容が盛りだくさんの今回のシンポジウムは、児童・生徒から保護者、教育関係者まであらゆる方々に理科の魅力に触れていただく楽しいひとときとなりました。
このシンポジウムを通して、理科好きが少しでも増えることを期待しています.。
小学校への出張講義報告(高槻市立西大冠小)(11.01.20)
2011年1月20日
平成23年1月20日(木)に高槻市立西大冠小学校の6年生2クラスを対象に出張講義を実施しました。
西大冠小学校は城北公園のさらに南にある小学校です。
出張講義では昨年も含めて今回が2回目の訪問となります。
今回は関西大学 河原先生の「顕微鏡で生物を観察しよう!」の実験テーマで授業を行いました。
河原先生の医工薬の紹介や、身近な目には見えないヨーグルトなど発酵食品に含まれている微生物の話からはじまりました。
オランダの商人レーヴェンフックのアマチュアの趣味の研究によって生まれた小さな手作り顕微鏡のこと、レーヴェンフックは雨粒の中、口の中から動きまわる微生物を初めて発見されたことを話されました。
「みんなは実はたくさんの細胞が集まって体ができています。細胞は皮膚の細胞、髪の毛の細胞、目の細胞、一つ一つがみんな違います。今日はみんなにレーヴェンフックと同じ原理の顕微鏡を作ってもらいます。それだけではつまらないので今日持ってきてもらった植物の葉でプレパラートも作ってもらいます!」と話されました。
各実験台に一人ひとり、白衣姿の研究室所属のティーチングアシスタントがついて実験の指導を行いました。
「みんな、手を刺さないように気をつけてブラックボードにピンで穴を開けましょう!」と恐る恐る初めての顕微鏡の工作がはじまりました。
「黒テープ側とレンズの光の通り道が上手く開けられるかな?自分の顕微鏡でプレパラートを見た後は、大学でも使っている光学顕微鏡でも見てみようね!」と問いかけがあり、そのあとも、「複数の染色液で染めた気孔のプレパラートもあるから見てみる?」との問いかけに「ヨウ素で染めたデンプンの結晶が滅茶苦茶綺麗やった!」と生徒たちも喜んでいました。
デジタル実体顕微鏡では小さなダンゴムシも見てもらい、触角や動かしてる口を見て生徒たちも夢中で観察していました。
今回もたくさんのプレパラートを顕微鏡で観察しているうちに時間は過ぎてしまいました。
アンケートでは「けんびきょうで、見たことのないものがみえてびっくりした。」「ダンゴムシやクモを顕微鏡で見れたし、自分でつくれたから楽しかった」「いろいろな細ぼうをけんび鏡をつかって見たので楽しかったです。」「話が長かったりしたけど分かりやすく言ってくれた」「実際にやったから分かりやすかった。」などの感想をたくさん頂きました。



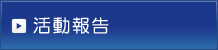
-
教育課程の構築
- 更新日:2017年12月09日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(17.12.9)
- 更新日:2017年12月02日「機能形態学1」実習報告(於:大阪薬科大学)(17.12.02)
- 更新日:2017年07月11日「基礎漢方薬学」実習報告(於:大阪薬科大学)(17.07.11)
- 更新日:2016年12月16日「お屠蘇で新年をお祝いしましょう!」報告(於:関西大学)(16.12.16)
教育支援システムの構築と教育環境の整備
- 更新日:2018年12月15日「機能形態学1」実習報告(於:大阪薬科大学)(18.12.15)
- 更新日:2018年12月08日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(18.12.8)
- 更新日:2016年06月25日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(16.06.25)
- 更新日:2010年02月17日戦略的大学連携支援プログラムに係る打合せ(教育サポート部門)(於:薬科大)(10.02.17)
社会還元
- 更新日:2018年12月06日小学校への出張講義報告(高槻市立土室小学校)(18.12.06)
- 更新日:2018年11月29日小学校への出張講義報告(高槻市立樫田小学校)(18.11.29)
- 更新日:2018年11月27日小学校への出張講義報告(高槻市立松原小学校)(18.11.27)
- 更新日:2018年11月26日小学校への出張講義報告(高槻市立阿武山小学校)(18.11.26)