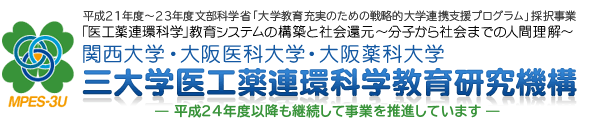活動報告
小学校への出張講義報告(高槻市立北日吉台小)(11.06.07)
2011年6月 7日
2011年06月7日(火)、高槻市立北日吉台小学校の5年生3クラスを対象に出張講義を実施しました。
実験講義のテーマは「顕微鏡で生物を観察してみよう!」(関西大学 河原先生)でした。
河原先生の実験講義が始まり、納豆菌のお話しや、はじめて顕微鏡で微生物を発見したオランダの商人、レーヴェンフックと同じ顕微鏡で植物の葉のプレパラートを作ってもらいました。
ティーチングアシスタントの学生も交えて実験がはじまり、大きな葉っぱを持ち込んでいる生徒もいました。
短時間の濃密な実験講義の時間は瞬く間に過ぎ去り、生徒たちから「かんたんにおもしろいけんびきょうがつくれると思わなかった。」「葉っぱのつぶつぶがみれた!」「先生の話しがおもしろかった。」「大学生が優しくおしえてくれた」などのたくさんの感想をいただきました。


小学校への出張講義報告(高槻市立芥川小)(11.06.06)
2011年6月 6日
今回はTA(ティーチングアシスタント)として参加した、関西大学大学院理工学研究科の大垣内龍也(おおがいとりゅうや)さんから報告です。
平成23年6月6日(月)に高槻市立芥川小学校の6年生3クラスを対象に出張講義を実施しました。
テーマは、「腕の動きと筋肉の働き」(関西大学 倉田先生)でした。
私は、大学院生の大垣内龍也と言います。
将来の夢は、教師です。今回、倉田先生のティーチングアシスタントという形で出張講義に参加させていただきました。
講義での一番人気は、やはり筋電計です。
私たちTAが、実験モデルとして腕に筋電計をセットし、力を入れて力こぶを出します。
するとセンサが反応し、スクリーン上にその時入れている力を波形として表すことができるものです。
力の強弱によって、スクリーン上に映しだされる波形の大きさも変わり、その時の子ども達の声の大きさが波形の大きさに比例しているように感じられ、ものすごく面白かったです。
また、その瞬間教室内の空間が一つになったようにも感じられました。
それと、やはり眼に見えない物を形にして、伝えることの重要性ということが子ども達の声の大きさからわかるような気がしました。
次に、筋肉の中身がどのようになっているのかを知るために、人工筋肉の模型筋を使用しました。
その模型を見てスケッチしてもらったり、子ども達が感じたことを書いてもらいました。
ゆっくりと触りにくる子もいれば、おもいっきり触りに来る子もいたりしました。
みんな様々な表情をしていましたが、ただ目の前のモノに対して一生懸命になっていたことが印象的です。
アンケートの回答にも多く記載されていましたが、実験を通して実際に触れたことに関しての喜びが多く寄せられていました。
講義中に関しても子ども達の反応は私たちの予想を上回る反応で嬉しく思いました。
講義を通じて改めて学ぶ事に関しての興味の重要性に気付かされました。
しかし、すべての内容が全員に伝わっているわけでもないということを知る機会もあり、また、子ども一人ひとりをきちんとみることができていたか不安であることも反省点として挙げられています。
講義に参加してくれたすべての人に対して面白いと思える授業を展開出来るように今後、ティーチングアシスタントの立場からできることをより一層考えていき、今後、もっと視野を広めていき即座に気づくことができるようにしていきたいです。
そして、子ども達と同じで日々成長できることができる教師になりたいです。
今回、講義に参加させていただいて良かったと感じたことは、子ども達の様々な声でした。
その声一つひとつを聞くことができ、より一層教師になりたいと強く思うようになりました。
来年から、教師生活を全力で送れるように頑張っていきたいと思います。
ありがとうございました。



小学校への出張講義報告(高槻市立阿武野小)(11.05.30)
2011年5月30日
2011年5月30日(月) 、高槻市立阿武野小学校の6年生3クラスを対象に出張講義を実施しました。
テーマは「顕微鏡で生物を観察してみよう!」(関西大学 河原先生)です。
河原先生から単細胞生物や多細胞生物の違いなどが身近な例を出しながら分かりやすく解説があり、単式顕微鏡を厚紙とガラスビーズと身近な材料でみんなに自作してもらいました。
また、摘んできてもらった葉っぱをサフラン染色し、表皮剥離法のプレパラートも作成してもらいました。
ティーチングアシスタントの学生と一緒に、さまざまな微生物、植物、解剖組織のプレパラートを見比べたりもしました。
アンケートでは「自分でけんびきょうをつくれて楽しかった」、「大学生がわかりやすく教えてくれた」、「理科に興味をもった!」などの多くの感想を頂きました。
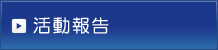
-
教育課程の構築
- 更新日:2017年12月09日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(17.12.9)
- 更新日:2017年12月02日「機能形態学1」実習報告(於:大阪薬科大学)(17.12.02)
- 更新日:2017年07月11日「基礎漢方薬学」実習報告(於:大阪薬科大学)(17.07.11)
- 更新日:2016年12月16日「お屠蘇で新年をお祝いしましょう!」報告(於:関西大学)(16.12.16)
教育支援システムの構築と教育環境の整備
- 更新日:2018年12月15日「機能形態学1」実習報告(於:大阪薬科大学)(18.12.15)
- 更新日:2018年12月08日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(18.12.8)
- 更新日:2016年06月25日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(16.06.25)
- 更新日:2010年02月17日戦略的大学連携支援プログラムに係る打合せ(教育サポート部門)(於:薬科大)(10.02.17)
社会還元
- 更新日:2018年12月06日小学校への出張講義報告(高槻市立土室小学校)(18.12.06)
- 更新日:2018年11月29日小学校への出張講義報告(高槻市立樫田小学校)(18.11.29)
- 更新日:2018年11月27日小学校への出張講義報告(高槻市立松原小学校)(18.11.27)
- 更新日:2018年11月26日小学校への出張講義報告(高槻市立阿武山小学校)(18.11.26)