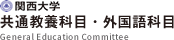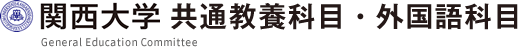Chinese 中国語
1.さあ、始めよう!外国語学習を。

外国語を学ぶ目的や意義は何でしょうか。
人は言語で考え、思考は言語に影響されます。人は各々の属する社会の言語を用いて、現実世界の森羅万象を切り取り、それを理解します。母語以外の言語を知ることは、その言語を用いて思考している人々の世界の切り取り方と把握の仕方を追体験することにほかなりません。それだけでも新たな発見を得るでしょうし、知的好奇心が満たされるはずです。もし、そのこと自体が「教養」という名にふさわしいとすれば、我々が外国語を学ぶ意味は、この点にあるでしょう。
もちろん、言語の最も大切な機能の一つは、これを手段としてその言語の担い手と交流することです。つまり、外国語学習は、教養のためでもあり、実用のためでもあるのです。
2.十数億人と友達に!
どの言語を学ぶのか。
これまで英語を通してみてきた英語圏の世界とは異なる価値観や文化背景を知りたいと思うならば、アジアの言語に取り組んでみるのも、また新たな世界認識のきっかけになるでしょう。なかでも中国語は、東アジアにおける漢字文化圏の中心的言語として、巨大な文化的影響力と悠久の歴史を有することは、みなさんご存知の通りです。また、中国語は世界で最も多くの人々に使用されている言語であり、国連公用語の一つでもあります。中国や台湾はもとより、東南アジアをはじめ、世界各地の華僑や華人社会の間で使用されています。このことは、中国語が話せれば地球上で十数億の友人ができる可能性があることを意味します。現に、関西大学で学ぶ留学生で最も多いのが、中国語を母語とする人たちであり、キャンパス内を歩くと常に中国語が聞こえてきます。
中国は日本の26倍もある広大な国であり、56もの民族がいる多民族国家です。よって、そこで話されている言語も多種多様であり、人口の90数パーセントを占める漢民族の言語である「漢語」(≒中国語)のほか、55もの各民族が使用する言語(モンゴル語、チベット語、朝鮮語など)があります。「漢語」も1種のみならず、10もの方言(広東語、福建語、上海語など)が存在し、またそれぞれの方言間の差異も大きいため、異なる方言を話す者同士では、中国人でも意思疎通ができません。そこでみなが理解できる共通語が必要となります。中国語の共通語は、「普く通じる話」すなわち“普通話”(プートンホア)といいます。普通話は北方の方言を基礎にして成立したもので、公の席はもとより、学校や公共放送、文学作品、映画、演劇などの芸術やマスコミで日常的に用いられており、私たちが第二外国語で学ぶのもこの普通話です。以下で使用する「中国語」は、この普通話を指します。
3.言葉は音!
では、これから学んでゆく科目の内容を学部ごとにごく簡単に紹介しておきましょう。
(1)法、文、経済、商、社会、政策創造、システム理工、環境都市工、化学生命工学部
原則として1年次で学ぶ中国語Ⅰa・Ⅰbと中国語Ⅱa・Ⅱbは、2つ併せて「入門篇」です。この2科目の目標は、大きく区分すれば次のように位置づけられます。
| 中国語Ⅰa,b | 音声言語を中心にして、基礎語彙と表現文型を習得する。 |
|---|---|
| 中国語Ⅱa,b | 単文を中心に、基礎文法、主として構文を習得する(書面語を含む)。 |
1年次はまずなにより発音の習得が第一です。
中国語の発音は難しいと言われることがありますが、4つの声調(トーン)の違いがわかり、それを発音し分けることができれば、それほど恐れる必要はありません。中国語は(もちろん例外はありますが)基本的に一文字一音節(つまり、漢字1文字に一つの読み方)なので、一度ある漢字の読み方を習得してしまえば、どんなときでも発音できるようになります。一つの漢字にいくつもの読み方がある日本語と比べれば、より容易に習得可能です。1年次は発音の仕組みを理解しある程度発音できるようになったら、発音練習と並行して、中国語の構造や骨組みを理解し、応用できるように心がけましょう。また頭で理解するだけではなく、反射的に中国語を発信したり運用するようになるには、ひたすら模倣、繰り返し、暗記といった単純なインプット作用も欠かせません。なお、1年次の学習到達レベルとしては、習得語彙数は800前後で、中国語検定試験準4級合格程度とします。
次に、2年次で履修する中国語Ⅲa・Ⅲbと中国語Ⅳa・Ⅳbの2科目について紹介します。原則として1年次開講の中国語Ⅰabと中国語Ⅱabの内容を理解し、応用力をつけるという目的で配置されている科目です。
| 中国語Ⅲa,b | 音声言語あるいは口語的な文体に親しみ、運用力を増強する。 |
|---|---|
| 中国語Ⅳa,b | 書面語の読解力を養成し、文法力と語彙力を養成する。 |
これらの科目は「基礎篇」と位置づけられています。これらを学び終えれば、中国語の基礎力を備えたといえます。基礎力があるということは、一人で応用ができるようになることを意味します。学習到達レベルは、1年次と併せて習得語彙数1,400~1,600で、中国語検定試験3級合格程度とします。
中国語では運用面の強化をはかり、1年次、2年次ともコミュニケーションクラスを開設しています。次にコミュニケーションクラスの概要を紹介しますので、希望する場合は、忘れないように登録をしてください。
□コミュニケーションクラス
これは希望者が選択して登録するクラスです。
1年次開講の中国語Ⅰab、Ⅱabのコミュニケーションクラスは、週2回、2人の教員が、同一の教科書を用いてリレー式に授業を進める形式をとります。
コミュニケーションクラスの特徴は、基本的な語彙や文法の学習と同時進行で、口頭でのコミュニケーションを行う訓練を重点的に行うことです。よって、このクラスは、通常クラスよりも、やや小規模なクラス編成になっています。どれだけ積極的に授業に参加し、どれだけコミュニケーションスキルを身につけたかが評価の対象となります。このクラスに参加すると、ことばの学習とは教室に座ってただおとなしく聞いているだけではだめだということ、自分で積極的に口を開いて何かを発信しなければ、コミュニケーションの能力が身につかないことが理解できると思います。
2年次に開講するⅢab、Ⅳabのコミュニケーションクラスも、1年次に引き続き小規模クラスで、中国語音声言語の能動的な運用能力をつける訓練の場として位置づけられています。ただし、1年次とは異なり、2名の教員がリレー方式で進める方式ではなく、それぞれの教員が、別々の教科書を使用します。
※このクラスを希望する人は、年度ごとに登録する必要があります。
さらに上級をめざす人には、中国語Ⅴa, bと中国語Ⅵa, bがあります。これらの科目は、学習レベルを考慮した教科書の中の中国語から飛び出し、書面語であれ音声言語であれ、「生」の中国語に挑戦する訓練の場です。さらに高く飛翔したい人、中国語をものにしたい人のための「応用篇」といえます。学習到達レベルとしては、習得語彙数は2,000前後で、多くの人が中国語検定試験3級に合格し、その上の2級をめざす程度とします。
以上の履修方法をチャートで示すと、次のようになります。
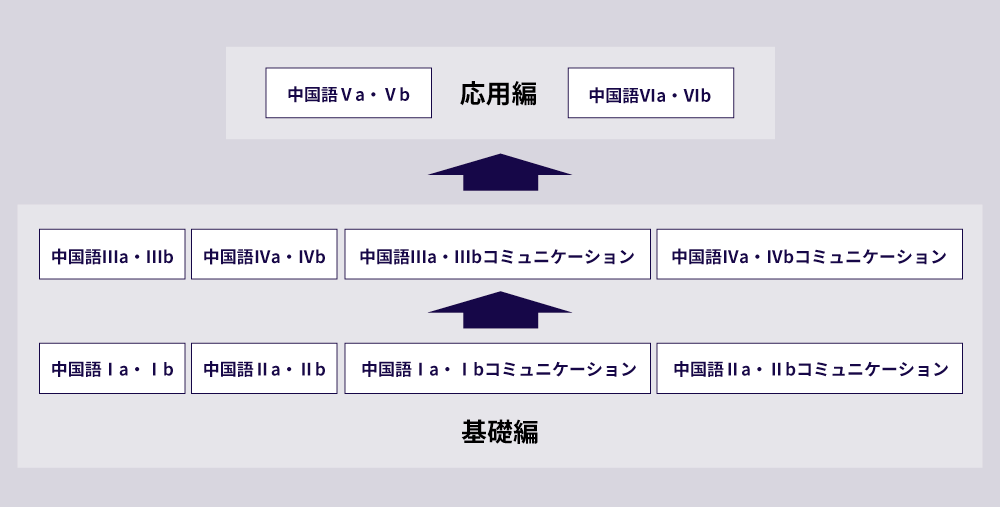
(2)外国語学部
1年次で学ぶプラスワン外国語(中国語)Ⅰa・Ⅰbとプラスワン外国語(中国語)Ⅱa・Ⅱbは、中国語の発音を一から学習したのち、日常的な基本語彙と簡単な文のパターンを使って、初歩的なコミュニケーションを行う練習をします。この2つの科目は、同じ教材を用いてリレー式に授業を行います。
次に、スタディー・アブロードから帰国後の3年次に、選択科目として履修できるプラスワン外国語(中国語)Ⅲa・Ⅲbとプラスワン外国語(中国語)Ⅳa・Ⅳbは、基礎を復習したうえで、語彙を増やし応用力を身に付け、中級レベルの読解力と会話力を養うことを目指します。
以上の履修方法をチャートで示すと、次のようになります。
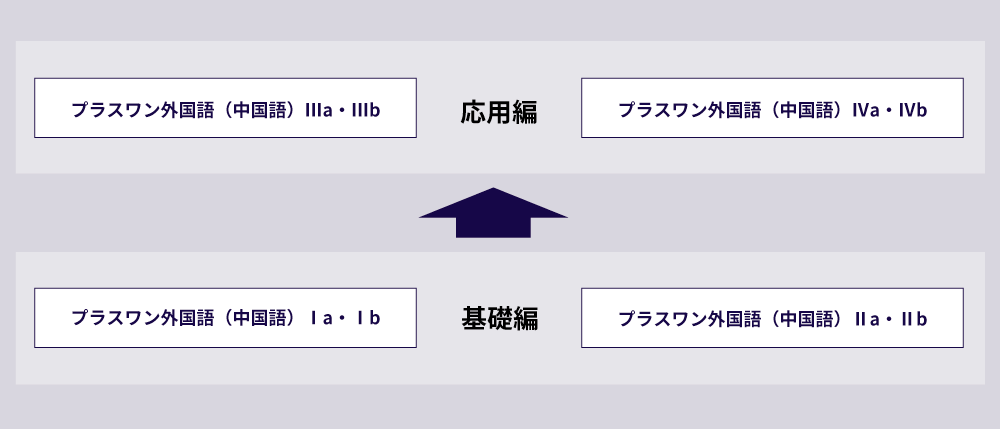
(3)総合情報学部
| 【1年次】中国語Ⅰa,b | 音声言語を中心に、基礎的な力を身につける。 |
|---|---|
| 【2年次】中国語Ⅱa,b | 1年次で学んだ中国語Ⅰa, bを基礎に、応用力を養成する。 |
| 【3年次】中国語Ⅲa,b(選択科目) | 中国語Ⅰa, b~Ⅱa, bで学んだ事項をもとに、更なる応用力を養成する。 |
以上をチャートで示せば、次のようになります。
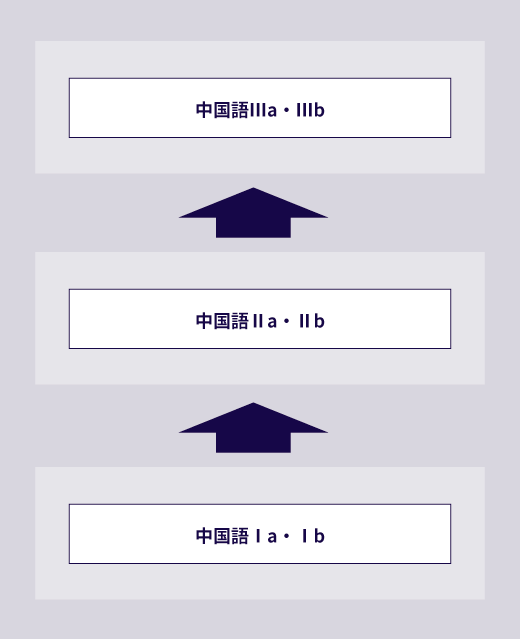
(4)社会安全、人間健康、ビジネスデータサイエンス学部
中国語Ⅰa・Ⅰbと中国語Ⅱa・Ⅱbはどちらも選択科目として受講することができます。
中国語Ⅰと中国語Ⅱはリンクさせながら授業を行うことにより、中国語の基礎を着実に身につけることをめざします。中国語検定試験4級合格が、学習到達目標の目安です。
4.やるのは君!

教室にただ座っているだけでは、どんな天才でも外国語をマスターすることは不可能です。外国語をマスターする秘訣と言って、特別な方法があるわけではありません。結局、どの言語でも、その言語の習得に積極的になれるか、そして学習を継続できるか、にかかっています。
授業だけではなく、様々な機会を利用して中国語を耳にし、声に出すようにしましょう。以下思いつくままに。
- NHKラジオ・テレビ中国語講座:ずいぶん工夫がこらされており、信頼できますから、積極的に利用しましょう。
- 関西大学の協定大学である北京大学、復旦大学(上海)、静宜大学(台湾)等への交換留学に参加:情報を収集するには、国際部に足を向けてください。
- 暗唱大会・弁論大会に参加:上位入賞者は中国や台湾旅行に招待されたり、1年間留学させてくれるものもあります。これまで多くの先輩たちが、いろいろな大会に参加し、毎年のように上位入賞をはたしています。
5.辞書─自分だけの1冊を
外国語学習に欠かせないのが辞書です。辞書は、紙媒体のもの、電子辞書、ネット上のもの、スマホなどにアプリとして入れるもの、があります。紙の辞書では、中型辞典で学習辞典としても使えるのは、以下のようなものが挙げられます。
- 『中日辞典』 小学館(第3版)
- 『白水社 中国語辞典』 白水社
- 『講談社 中日辞典』 講談社(第3版)
- 『東方中 国語辞典』 東方書店
ちょっと値が張りますが、紙の辞書は引いた項目だけではなく、その周辺にある語も目に入り、長い目で見れば語彙力を増やすことになるかもしれません。電子辞書を使う場合は、上記の辞書が収録されていることを条件に選んでください。
最近では、スマホやiPADなどに有料の辞書アプリを入れて活用する人も増えてきました。この利点は、スマホさえあれば、いつでもどこでも中国語が引けることです。また、最近では、インターネット上に公開され無料で利用できる辞書もあります。詳しくは、担当の先生に聞いてみて下さい。
とにかく、辞書はこれ1冊で足りるというものではありません。辞書の不足をあげつらうのは容易ですが、このような世上の俗論に耳を傾ける必要はありません。それぞれに苦心の成果であり、互いに補い合うものですから、本格的にやろうとする人には、辞書は多いほどいいに決まっています。ただ、入門や基礎の段階で一番大切なことは、自分自身が使いこなすことのできる自分だけの辞書を、早く持つようにすることです。
6.参考書

世の中には数多くの中国語参考書がありますが、お勧めできるほんの一部のみあげておきます。
以下は、初級の文法書として読みやすく、また解説も充実しています。 授業で習った文法項目をより深く理解するために活用してもよいでしょう。また、最近ではウェブ上でも様々に工夫された教材があります。自分に合ったものを見つけてください。
文法書(初級用):
- 相原茂、石田知子、戸沼市子『Why?にこたえるはじめての中国語の文法書』(同学社)新版 2016年
- 守屋宏則『やさしくくわしい 中国語文法の基礎』(東方書店)改訂新版 2019年
文法書(中級以上):
- 杉村博文『中国語文法教室』(大修館書店)1994年
- 丸尾誠・李軼倫『中国語解体新書』(駿河台出版社)2017年
以下は、初級の人だけでなく、さらに上をめざす人が読んでも面白く、中国語の仕組みや奥深さを理解する助けになる書籍です。
- 中川正之『はじめての人の中国語』(くろしお出版)1996年
- 佐藤晴彦他『中国語表現のポイント99』(好文出版)1997年
- 木村英樹『中国語はじめの一歩』新版(ちくま学芸文庫)2017年
7.検定試験
中国語の検定試験には、年に3回(3月、6月、11月)開催される日本中国語検定協会による「中国語検定試験」や、中国の教育部が認定する「漢語水平考試」(通称HSK)などがあります。このような試験によって、自分の中国語の力を客観的に測ってみるのも良いでしょう。