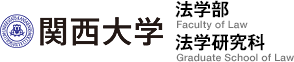令和6年度司法試験に本学部4回生の秋本 峻佑さんが合格されました。
秋本さんは、高校生の時に法曹の仕事に憧れ、大学進学後本格的に勉強を開始し、見事司法試験に合格されました。
秋本さんにインタビューさせていただきました。
【法学部でつかんだ将来】
・関西大学法学部を選んだ理由はなんですか。
関西の私大の中でもキャンパスライフが楽しそうで、受験生である自分が頑張って努力すれば手が届く大学であり、法曹コースが設置されていたということが関西大学法学部を選んだ理由です。
・司法試験までどのように勉強されていましたか。1年~4年の学びについておしえてください。
◆1年次
1年次春学期前半は大学生活に慣れること、法律学の大枠を掴むことを意識して勉強しました。当時は新型コロナウイルスの影響で授業のほとんどがオンデマンド授業でしたが、学部の授業を利用して法律学の基本的な部分を勉強しました。もともとは2年次から本格的に勉強を始める予定でしたが、ほとんどの授業がオンデマンド授業ということもありかなり時間に余裕があったため、1年次の6月から予備校のオンライン講座を利用して本格的に司法試験予備試験(以下、「予備試験」とします。)・司法試験に向けた勉強を開始しました。それからは、ひとまずは来年(2年次、令和4年)の予備試験でそれなりに戦える実力を身に付けることを目標に勉強をすることにしました。ここから自習の時間が増え始めました。
◆2年次
2年次に初めて予備試験を受験し、5月の短答式試験(1次)はなんとか合格することができましたが、対策が間に合わず7月の論文式試験(2次)は特に惜しいということもなく不合格となりました。しかし、不合格ではあったものの、成績通知を見ると想定していたより良い成績を取れていたため、「もう1年、時間があれば合格できるのではないか。」と感じ、モチベーションが上がりました。論文式試験の直後に免許合宿や長期間の旅行に行っていたことを除けば、試験前・試験後ともに1年次よりも勉強していたと思います。
◆3年次
短答式試験は一度合格した経験があるため、2年次後半から3年次前半にかけては、短答式試験の対策の割合を減らし、予備試験の天王山である論文式試験の対策を重点的に行いました。7月の短答式試験の合格後は、本気で論文式試験の合格を目指して勉強し、想定していたレベルには程遠い完成度でしたが、なんとか9月の論文式試験にも合格することができました。この年の論文式試験の直前期は夏休みで、基本的には試験対策に専念することができたとともに、モチベーションも高かったため、かなり勉強していたと思います。論文式試験の合格発表後はすぐに1月の口述式試験(3次、最終)の対策に取り掛かりました。口述式試験は多くの受験生が合格できるものの、不合格となった場合には来年また1から受験しなければならない点で大変大きなプレッシャーがあり、直前期はかなり勉強をしました。勉強の甲斐あって、口述式試験も無事合格し、これによって令和5年予備試験に最終合格することができました。口述式試験直前の1か月間はこれまでの人生で1番勉強したと思います。
◆4年次
予備試験の合格発表から7月の司法試験までは約5か月間しかありませんでしたが、予備試験合格によって燃え尽きてしまい、どうしても司法試験へのモチベーションが上がりませんでした(これは予備試験合格者あるあるらしいです。)。これに加えて就職活動(インターン)が重なり、3年次の3月が終わるまではほとんど勉強することができませんでした。そこで、同い年の他大学の令和5年予備試験合格者数人と自主ゼミを組み、この自主ゼミと学部で所属しているゼミをペースメーカーに司法試験の対策を行いました。この自主ゼミにより大変レベルの高い勉強をすることができたとともに、モチベーションが上がらない中でもなんとか最低限の勉強時間を確保することができました。学部ゼミでの毎週の問題演習・検討も、勉強時間を確保する上で助けとなりました。こうしてモチベーションが上がらない中でもなんとか最低限の対策を行うことができ、無事令和6年司法試験に合格することができました。正直なところ、司法試験直前期は予備試験直前期に比べれば勉強量は明らかに少なかったと思います。
・法学部で学んだ知識や経験で、司法試験の受験、就職活動でどのように生かされましたか。
1年次前半は、法律学の大枠を掴むこと、また上三法(憲法・民法・刑法)の基本的な部分を理解することを目標に法学部の授業を受けました。その後は、予備校のオンライン講座を利用した自習により予備試験・司法試験で出題される科目については授業よりも先に一通りの勉強を済ませていたため、法学部の授業は、主に自習で理解することができなかった箇所を理解すること、自習によって得た知識を深めることを目的として授業を受けました。この点で、法学部での学びが予備試験・司法試験の対策に役立ちました。
2年次からは法曹コースに所属した(司法試験に合格したため同コースを修了する予定はありません。)ため、法曹コースに所属する学生のみが受けることができる授業も履修していました。その中には予備試験・司法試験に直結する内容の事例演習を行う授業があり、特に受験生の間でも有名な基本書を執筆されている関西大学法科大学院の先生による「事例講義憲法(法曹)」という授業は、予備試験・司法試験の対策に大変役立ちました。
3年次からは、毎週、旧司法試験・予備試験・法科大学院入試等の過去問の答案作成・検討を行う民事訴訟法のゼミに所属しました。それまでは民事訴訟法は苦手科目でしたが、毎週のゼミによってレベルの高い民事訴訟法の問題に触れることができ、少なくとも司法試験受験時には比較的得意な科目といえるレベルにまで実力を上げることができました。ゼミを選ぶ際、あえて当時苦手科目であった民事訴訟法のゼミを選びましたが、これは今振り返っても良い選択だったと思います。
・司法試験を目指した理由およびモチベーションの保ち方についておしえてください。
高校の文理選択の時期に検察官という職業に憧れを抱き、法曹を目指しました。それまでは理系に進むつもりでしたが、これをきっかけに文系(法学部)に進学して司法試験を目指すことを決意しました。大学に進学後、法律の勉強をする中で弁護士という職業にも憧れを抱くようになりました。
予備試験合格までは、試験直後を除きモチベーションが下がったことはあまりありませんでしたが、予備試験の論文式試験に合格するまでは基本的に勉強仲間を作らず1人で勉強をしていたため、SNSを利用し他の受験生・合格者の方の投稿を見ることにより、情報収集・モチベーション維持を行っていました。予備試験合格後は、燃え尽きたことにより司法試験へのモチベーションがかなり下がってしまいましたが、学部ゼミや同い年の他大学の予備試験合格者との自主ゼミにより、なんとか最低限のモチベーションを維持していました。
・卒業の目標はなんですか。
ひとまずは、司法修習をやり遂げ司法修習の最後に行われる二回試験に合格して、法曹になることが今の目標です。
(指導教員 吉田 直弘教授からのコメント)
「中高校生時代に検察官など法曹に憧れを抱き法学部へ進学する学生は、いつの時代にも一定数存在します。しかし、その憧れを実現できた人は、ほんの一握りに過ぎません。憧れを現実のものへと手繰り寄せるために、秋本くんが本学に入学後、どのような努力を積み重ねられてきたのか、その詳細な過程がこのインタビューで明らかにされました。法曹を目指している学生諸君には、彼と同じ様にはできなくても、まずは日々の暮らし方を見直すきっかけにはなるでしょう。1人でも多くの法曹志望者が憧れを実現されることを願ってやみません。」
この度は合格まことにおめでとうございます。
今後の活躍を期待しております。