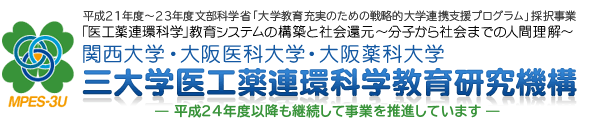活動報告
小学校への出張講義報告(高槻市立松原小学校)(13.06.11)
2013年6月11日
平成25年6月11日(火)、高槻市立松原小学校の5年生2クラスを対象に出張講義を実施しました。
実験講義のテーマは「顕微鏡で生物を観察してみよう」(関西大学 河原先生)でした。
顕微鏡を作ったり、自分達で積んできた葉っぱを観察してもらったりしました。いつもとは違う理科の授業を楽しんでもらえたようです。
小学校への出張講義報告(高槻市立津之江小学校)(13.06.06)
2013年6月 6日
平成25年6月6日(木)、高槻市立津之江小学校の6年生3クラスを対象に出張講義を実施しました。
実験講義のテーマは「顕微鏡で生物を観察してみよう」(関西大学 坂元先生)でした。
手作りの顕微鏡作成に学生アシスタントと一緒に取り組み、とても喜んでもらえたようです。
高槻家族講座報告(於:薬科大)(13.01.26)
2013年1月26日
平成25年1月26日(土)に、高槻家族講座(通算7回目)シリーズ『食と夢』第1回「おいしいくすり、チョコレート」を開催いたしました。
講演には234名が、こども体験コーナーには、小学生34名が参加されました。
第1講目「知っていそうで知らない?『チョコレート』大解剖 ~チョコレートができるまでを体感しよう~」
株式会社 明治 大阪工場技術部技術室 室長 井上 雅之 氏
井上氏は、まずJR京都線沿いにある明治大阪工場のチョコレート型パネルが世界最大級のプラスチック看板としてギネスブックに載っていること、パネル1枚が明治のミルクチョコレート38万枚分に相当し、季節にもよるが、大阪工場のほぼ1日のチョコレート生産量であることを紹介されました。次に原料であるカカオ豆は今から約4,000年前の紀元前2,000年頃から栽培されていたが、王侯貴族の不老長寿の薬や貨幣としても使われていたほど貴重で高価なものであったこと、昔は飲み物であったが現在のような食感のチョコレートが出来たのは1,890年頃であり、そこにたどり着くまでに多くの歴史があったこと、チョコレートの年間消費量、カカオの栽培に適する気象条件が赤道付近に限られること、収穫後には発酵の必要があることをカカオ豆の模型や農園の写真を交えて話されました。また、含まれる油脂には結晶多形が存在するため、安定型の結晶を得るためには、テンパリング操作という温度コントロールが必要であることを図解でわかりやすく説明されました。最後に工場でのチョコレートの製造工程を紹介されましたが、参加者は配布された工程ごとのサンプルを試食しながら説明を聞き、おいしいチョコレートができるまでを文字通り"体感"することができました。
第2講目「カカオと薬学~カカオの成分と効能について~」
大阪薬科大学 生薬科学研究室 教授 馬場 きみ江 氏
馬場教授は、最初にカカオの木についてラテン語の学名(Theobroma cacao L.)の成り立ち、植物としての形態的な特徴を説明されたあと、含まれる成分が「食用」と「薬用・化粧品」として利用されてきたことを紹介されました。カカオバターを構成する脂肪は柔軟効果に優れ、クリームや乳液に配合され現在も使われていること、薬用としては坐剤の油脂性基剤として用いられていたが現在は他の基剤が使われていることを説明されました。また、「2種類の坐薬を使用する場合、少なくとも30分以上はあけること」、「坐薬を挿入して1~2時間経っても効かないからといって、すぐにもう一つ使わずに5~6時間様子を見ること」、「飲み薬との違いは何か」といった坐剤の特徴や使い方についての注意点を解説されました。次にカカオの薬効成分であるポリフェノールは総称であり、お茶や柿のタンニンもその仲間に含まれること、活性酸素の抑制作用により細胞の突然変異やがん化から身を守っているという効能を教えて下さいました。また、カカオに含まれるテオブロミンやカフェインは喘息の治療薬であるテオフィリンと良く似た化学構造を有することや、交感神経興奮作用のあるチラミンや金属のニッケルが含まれるため食べすぎないよう注意が必要とお話しになり、最後は"高カロリーで栄養価が高いお菓子なので楽しんで食べましょう。"と締めくくられました。
こども体験コーナー「みんな大好き!あのチョコレート菓子に挑戦!」
小学生を対象としたこども体験コーナーは、株式会社 明治 大阪工場のスタッフのみなさんにより、大阪薬科大学食堂にて「チョコレート菓子『きのこの山』」の手作り体験が行われました。今回は20組の募集に対し、応募が殺到したため、明治さんのご厚意で定員を26組に増やしての実施となりました。
製作にとりかかる前に、まず「チョコレートの歴史」、「カカオ豆の生産」や「テンパリング」についてスクリーンに映し出された画像を見ながら学習しました。次に、パティシエのお兄さん、お姉さんがそれぞれ設置されたテーブルで実演。まず、ボールで溶かされたチョコレートをゴムべらでかき混ぜながら徐々に冷やし、31℃になったところで安定型の結晶核となるココアパウダーを投入、素早くかきまぜたあとは絞り袋に移し、チョコレートをきのこの型に流し込む。トントンとテーブルに叩きつけ平らになったところで、きのこの柄となるビスケットを差しこむ。後は冷蔵庫で冷やして固まれば出来上がり。
こどもたちは二手に分かれて目の前で、保護者の方々は実況映像を見ながらしっかりお手本を目に焼き付けました。その後はこどもたちと保護者が協力し合って、「きのこの山」を手作りしました。さらに、チョコレートが固まるまでの時間を利用して、抹茶、イチゴ、バナナなどの「オリジナルきのこ」や、バレンタインレシピの大人編として「ラムボム」、「チョコレートブラウニー」の作り方が実演混じりで紹介されました。
今回受講された小学生の皆さんには「チョコレート博士」の称号の修了書が授与されました。
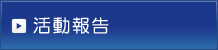
-
教育課程の構築
- 更新日:2017年12月09日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(17.12.9)
- 更新日:2017年12月02日「機能形態学1」実習報告(於:大阪薬科大学)(17.12.02)
- 更新日:2017年07月11日「基礎漢方薬学」実習報告(於:大阪薬科大学)(17.07.11)
- 更新日:2016年12月16日「お屠蘇で新年をお祝いしましょう!」報告(於:関西大学)(16.12.16)
教育支援システムの構築と教育環境の整備
- 更新日:2018年12月15日「機能形態学1」実習報告(於:大阪薬科大学)(18.12.15)
- 更新日:2018年12月08日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(18.12.8)
- 更新日:2016年06月25日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(16.06.25)
- 更新日:2010年02月17日戦略的大学連携支援プログラムに係る打合せ(教育サポート部門)(於:薬科大)(10.02.17)
社会還元
- 更新日:2018年12月06日小学校への出張講義報告(高槻市立土室小学校)(18.12.06)
- 更新日:2018年11月29日小学校への出張講義報告(高槻市立樫田小学校)(18.11.29)
- 更新日:2018年11月27日小学校への出張講義報告(高槻市立松原小学校)(18.11.27)
- 更新日:2018年11月26日小学校への出張講義報告(高槻市立阿武山小学校)(18.11.26)