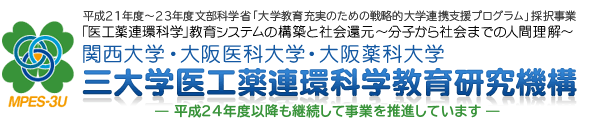活動報告
自由研究コンテスト2013 第二次審査会報告(於:関西大学高槻ミューズキャンパス)(13.11.10)
2013年11月10日
11月10日(日)関西大学高槻ミューズキャンパスに於いて「自由研究コンテスト2013」第二次審査会・表彰式を開催しました。今年度は高槻市内の小学校10校から総数412作品の応募があり、その中から第一次審査を通過した32作品の発表が行われました。 高学年(4~6年生)の部では、レポートをスクリーンに投影し、ひとりあたり3分間の持ち時間内で上手に内容をまとめ、堂々と発表をしていました。
高学年(4~6年生)の部では、レポートをスクリーンに投影し、ひとりあたり3分間の持ち時間内で上手に内容をまとめ、堂々と発表をしていました。
 低学年(1~3年生)の部では「未来の生活」をテーマに、それぞれが思い描く感性豊かな未来の絵をバックに、作文を朗読しました。
低学年(1~3年生)の部では「未来の生活」をテーマに、それぞれが思い描く感性豊かな未来の絵をバックに、作文を朗読しました。
 当日は、保護者の方以外にも学校の先生やお友達と、総数161名と多数のご参加をいただきました。また会場では、当日発表者のレポートをまとめたポスターを展示し、来場者は力作に見入っていました。
当日は、保護者の方以外にも学校の先生やお友達と、総数161名と多数のご参加をいただきました。また会場では、当日発表者のレポートをまとめたポスターを展示し、来場者は力作に見入っていました。
 発表終了後、審査員のおひとり平野雅親先生(科学ボランティア集団夢LOBO副会長)による講演会「北摂の虫~生活の不思議~」が行われました。普段何気なく目にする虫たちも、その生態については知らないことが多く、たいへん興味深いお話しとなりました。
発表終了後、審査員のおひとり平野雅親先生(科学ボランティア集団夢LOBO副会長)による講演会「北摂の虫~生活の不思議~」が行われました。普段何気なく目にする虫たちも、その生態については知らないことが多く、たいへん興味深いお話しとなりました。
 表彰式では、入賞の9名に加え、審査会に参加の入選者全員に表彰状が授与され、最後は全員での記念撮影を行いました。
表彰式では、入賞の9名に加え、審査会に参加の入選者全員に表彰状が授与され、最後は全員での記念撮影を行いました。
今回のコンテストを通じて、子どもたちが自身の発表だけでなく、たくさんの発表に触れ、理科研究の面白さに気づいてくれたのではないでしょうか。
このような取組みが未来の科学の発展につながっていくと私たちは考えています。
二次審査の結果は以下のとおりです。
※個人情報保護の為、氏名は省かせていただいております。
| 賞 | 学校名 | 作品名 |
| 小学校高学年の部 最優秀賞 |
関西大学初等部 | カスミサンショウウオを守れ! &ナガレホトケドジョウの採集記録 |
| 小学校低学年の部 最優秀賞 |
関西大学初等部 | 未来の生活について |
| 優秀賞 | 関西大学初等部 | 虹は一度に二つ出るって本当? |
| 優秀賞 | 土室小学校 | イースト菌で糖分を調べる |
| 関西大学賞 | 阿武野小学校 | 植物とでんぷん |
| 大阪医科大学賞 | 関西大学初等部 | わたしのかんがえたみらいのいえ |
| 大阪薬科大学賞 | 奥坂小学校 | 尿素の結晶作り |
| 高槻ロータリークラブ賞 | 阿武山小学校 | おいしい温泉たまごの作り方 |
| 審査員特別賞 | 阿武山小学校 | 火や電気を使わない調理実験 |
なお、上記入賞作品について、12/5~13の間、高槻市役所1階にポスターを展示いたしますのでぜひご覧ください。
小学校への出張講義報告(高槻市立寿栄小学校)(13.11.8)
2013年11月 8日
JSTサイエンスキャンプ報告(高校生対象)(於:薬科大、医科大)(13.08.20-23)
2013年8月23日
2013年度サマーサイエンスキャンプDX
"くすりを「知る」・「創る」・「活かす」"
実施日:2013年8月20日(火)~23日(金)
場所:大阪薬科大学、大阪医科大学、たかつき京都ホテル
対象:高校生(20名)
"くすりを「知る」・「創る」・「活かす」"をテーマに初日から3日目は大阪薬科大学、たかつき京都ホテル、最終日は大阪医科大学にて、全国から集った高校生を対象に講義、施設見学、実験実習を実施しました。
・1日目 (会場:大阪薬科大学)
「医薬品の働きを知る-ヒトの消化と消化薬の働き-」
北は北海道、南は鹿児島から集った参加者たちは、担当の先生方の紹介を受けた後、カビから消化酵素を抽出し、実際に医薬品に含まれる消化酵素と比較する実験を行いました。4人ずつ5班のグループに別れ、はじめて握る実験器具の取り扱いを実習補助(TA)の大学生・大学院生から指導を受けながら実験をすすめました。戸惑うことも多かったようですが、時間内に実験を終えることができました。
「医薬品を創り出す-薬のシードの発見から製品まで-」
夕食後、たかつき京都ホテルにて創薬についての講義がありました。新薬の開発は数万の化合物の中から非常に低い確率でしか医薬品にはならないことや、研究開発から商品化までには短くても10年はかかるなど大変な世界であることが語られ、医薬品の開発から製造までには医学・薬学だけではなく、獣医、工学、バイオ関連や、精製・製造プロセスの工業化研究などあらゆる分野の人材が関わる業種であることも説明されました。
・2日目 (会場:大阪薬科大学)
「薬用植物の観察」・「薬用植物の成分をクロマトグラフィーで分離してみよう」
まず最初に、日本の民間薬や漢方薬などに使われる生薬の講義を受けた後、朝の涼しいうちに構内の薬用植物園にて薬用植物の観察を行いました。甘味料の原材料のステビアを味見したり、身近な植物からも薬が作られていることを体感しました。また、刻み状態の生薬と生きた植物の実物との比較を体験しました。観察後は薬用植物の薬効成分を抽出し、成分を分析する実験を行いました。
「ミクロの世界を覗いてみよう」
午後からは薬が吸収される消化管を中心に、光学顕微鏡観察や電子顕微鏡を用いた動物の組織の観察を行いました。一人ひとりに光学顕微鏡が用意され、じっくりと標本を観察することができました。
「身近なくすりを創ってみよう」
冒頭でなぜ医薬品にとって剤形が重要なのかの説明があった後、打錠機を使って錠剤を作成したり、カプセル剤の充填を体験しました。最終的なカプセルのフタのロックは参加者の手で行い、これを小瓶に移し、実習の記念品としました。また、「製剤試験」についても体験し、薬がいかに厳しい基準を超えて製品になるかを学びました。実習室内の壁周りには様々なタイプの医薬品の実物と解説ボードがあり、待ち時間に先生方が詳しく説明してくれました。
「交流会」
実験後には夕食を兼ねた交流会がありました。参加者たちは先生方と将来の進路の話や、全国から集まった参加者同士の高校生活についての話題で盛り上がっていました。
・3日目 (会場:大阪薬科大学)
「カビ・胃腸薬に含まれるデンプン分解酵素の活性染色による検出」・「カビ・バクテリアの細胞形態の観察」・「分子模型を用いたデンプン構造のモデリング」
初日に抽出した消化酵素の活性を、電気泳動法を用いて調べました。また、実体顕微鏡や光学顕微鏡を用いてカビをはじめとした様々な試料の観察をする班と、分子模型でグルコースを組み立てる班に分かれて実験を行いました。
「ポスター作成・プレゼンテーション準備」
各班ごとに研究テーマが決定され、午後から発表用のポスター作成が始まりました。先生方のアドバイスを受け、次第にポスターの概要が決まり、それぞれの役割を担いながらポスター作りを進めて行きました。夕刻にはホテルに戻り、夕食後もポスター作成が続きました。参加者たちは夜遅くまでプレゼンテーションの構想を練っていました。
・4日目 (会場:大阪医科大学)
「発表」・「講評」
最終日は、参加者たちによるポスターのプレゼンテーションが行われました。班ごとの二交代制でポスター発表も行い、先生方や実験補助(TA)の学生からも質問を受け、活発な質疑応答が行われました。最後に各先生方やTAからの講評・感想が伝えられました。
「医薬品の効果的な使い方-医療現場で薬を扱う立場から-」
大阪医科大学付属病院薬剤部の先生より、医薬品全般についての話や、医療従事者の立場から薬剤師の仕事内容についての講義がありました。講義の後は実際の薬やデモ用の投薬器具などの扱い方の説明がありました。
「閉校式」
伝統と格式が漂う講堂内にて、大阪医科大学の竹中洋学長より参加者一人ひとりにサマーサイエンスキャンプの修了証が手渡されました。最後は全員で集合写真を撮り、記念として各自のポスターのコピーを手渡されました。参加者たちは4日間の日程を終え、元気にそれぞれの帰路につきました。
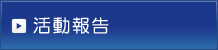
-
教育課程の構築
- 更新日:2017年12月09日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(17.12.9)
- 更新日:2017年12月02日「機能形態学1」実習報告(於:大阪薬科大学)(17.12.02)
- 更新日:2017年07月11日「基礎漢方薬学」実習報告(於:大阪薬科大学)(17.07.11)
- 更新日:2016年12月16日「お屠蘇で新年をお祝いしましょう!」報告(於:関西大学)(16.12.16)
教育支援システムの構築と教育環境の整備
- 更新日:2018年12月15日「機能形態学1」実習報告(於:大阪薬科大学)(18.12.15)
- 更新日:2018年12月08日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(18.12.8)
- 更新日:2016年06月25日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(16.06.25)
- 更新日:2010年02月17日戦略的大学連携支援プログラムに係る打合せ(教育サポート部門)(於:薬科大)(10.02.17)
社会還元
- 更新日:2018年12月06日小学校への出張講義報告(高槻市立土室小学校)(18.12.06)
- 更新日:2018年11月29日小学校への出張講義報告(高槻市立樫田小学校)(18.11.29)
- 更新日:2018年11月27日小学校への出張講義報告(高槻市立松原小学校)(18.11.27)
- 更新日:2018年11月26日小学校への出張講義報告(高槻市立阿武山小学校)(18.11.26)