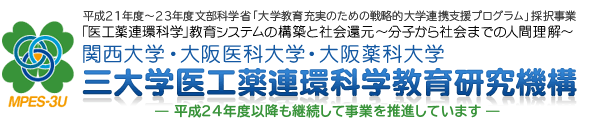活動報告
小学校への出張講義報告(高槻市立真上小学校)(14.5.30)
2014年5月30日
2014年5月30日(金)、高槻市立真上小学校の6年生3クラスを対象に出張講義を実施しました。
テーマは「腕の動きと筋肉の動き」(関西大学 倉田先生)でした。
普段学校で使わない筋電計や筋肉模型で見る筋肉の力の伝わり方に興味津々でした。
また、TA(学生アシスタント)の留学生などと、楽しく給食の時間を過ごしました。
三大学医工薬連環科学シンポジウム(第9回)報告(於:関西大千里山キャンパス)(14.01.23)
2014年1月23日
日時: 2014年1月23日(木)13:20-17:15
場所: 関西大学100周年記念会館 第3会議室
 三大学医工薬連環科学教育研究機構では、関西大学先端科学技術シンポジウムとの併催
三大学医工薬連環科学教育研究機構では、関西大学先端科学技術シンポジウムとの併催
近年、経済産業省での医療機器開発プロジェクトや、新学会である看護理工学会が設立され、昨年2013年10月5日に東京大学で第1回 看護理工学会学術集会が開催されるなど「看工連携」の動きが活発化しています。看工連携にご感心のある方々に向けて工学、看護学、薬学のそれぞれの専門家の立場から、これまでの経験を踏まえ、事例紹介、問題提起を交えて講演し、今後への期待を交えた活発な議論が行われました。
当日は36名の方が来場し、講演終了後は活発な質疑応答が行われました。最初に関西大学 倉田純一 機構長より、10年計画の文部科学省の大学連携事業よりはじまった医工薬連環科学教育研究機構の活動が5年の中間地点に差し掛かったこと、連携校である大阪医科大学看護学部が完成年度に達したことを交え、開会挨拶が行われました。
「看工連携の現状と今後」
(大阪大学大学院医学系研究科 特任教授 山田 憲嗣 氏)

また看工連携の問題では、病院での転倒転落防止のビジョンセンサーの開発が凍結した経緯を踏まえ、工学の人たちは「最先端」や「サイエンス」がなければ動かないこと、企業からの洗髪ロボットの評価の依頼では、性能評価のみで自分たちの作ったものの評価でなければ研究としての面白みがないこと、看護学の研究は調査研究が多いこと、研究期間が2ヶ月程度と短いこと、研究の多くがニーズ、市場調査、ビジネスモデルまで考慮しているのだろうか、などの問題提起がありました。
研究室での看工連携の話題では、看護学出身の学生が病院内の人の行き来の動線の画像解析をC言語でプログラミングしたこと、3Dプリンターを使い20代の斬新な発想でモノ作りが行われていること、文系の知財関係出身の学生もいて良い影響を及ぼしていることなどが話されました。また、フィリピン語なども含めた17言語に対応した多言語問診票MultiQは文系の語学関係者の協力も受けて開発された事例なども紹介されました。病院での夜間眩しくない巡視ライトは、ペットボトルを使って開発できる現場では求められる製品であっても技術そのものはローテクであり、大阪大学としては最先端を求められること、現場のニーズと最先端をどう両立させるのかなどの苦悩も話されました。また科研費では新たに「看護工学」の項目ができ、この分野の推進に繋がるであろうとのことでした。
「看護を中心とする連携期待に対して」
(大阪医科大学 看護学部長 教授 林 優子 氏)
 三大学医工薬連環の中での看護学の位置づけと、どのように連携していくことができる
三大学医工薬連環の中での看護学の位置づけと、どのように連携していくことができる
「薬学分野から看護と連携に期待するもの」
(大阪薬科大学薬学部 特任准教授 銭田 晃一)
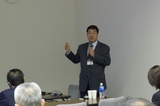
「継続的な看工連携実施に対する問題提起」
(関西大学システム理工学部 准教授 倉田 純一)
 機械工学の専門の立場から倉田純一先生より、ご講演いただきました。機械屋の思い込
機械工学の専門の立場から倉田純一先生より、ご講演いただきました。機械屋の思い込
ワークショップ
看工連携の継続的実施へ向けて-医療機器の具体的改善案を例に考える-
倉田先生の司会のもと3名の講演者を前にワークショップが行われました。会場からの質問も多く、看工連携における大学院教育や学部教育についても紹介されました。サイエンスということが取り上げられ、医工連携の研究では自然科学に焦点化した研究になるが、看護学はヒューマンサイエンスが基盤であり、看護学ではサイエンスといっても自然科学のみをさすのではないという立ち位置が話されました。また、大学の看護学部教員と臨床の看護実践者が協働連携してケアに関する研究を行うことの重要性など、臨床との協力関係の構築への課題などが指摘されました。


小学校への出張講義報告(高槻市立玉川小学校)(13.12.12)
2013年12月12日
平成25年12月12日(木)、高槻市立玉川小学校の6年生2クラスを対象に出張講義を実施しました。
実験講義のテーマは「聴こえない音:超音波を見よう」(関西大学 山本先生)でした。
超音波を目で見ることができる装置を使っての実験では、理科の面白さを感じてくれたようです。
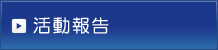
-
教育課程の構築
- 更新日:2017年12月09日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(17.12.9)
- 更新日:2017年12月02日「機能形態学1」実習報告(於:大阪薬科大学)(17.12.02)
- 更新日:2017年07月11日「基礎漢方薬学」実習報告(於:大阪薬科大学)(17.07.11)
- 更新日:2016年12月16日「お屠蘇で新年をお祝いしましょう!」報告(於:関西大学)(16.12.16)
教育支援システムの構築と教育環境の整備
- 更新日:2018年12月15日「機能形態学1」実習報告(於:大阪薬科大学)(18.12.15)
- 更新日:2018年12月08日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(18.12.8)
- 更新日:2016年06月25日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(16.06.25)
- 更新日:2010年02月17日戦略的大学連携支援プログラムに係る打合せ(教育サポート部門)(於:薬科大)(10.02.17)
社会還元
- 更新日:2018年12月06日小学校への出張講義報告(高槻市立土室小学校)(18.12.06)
- 更新日:2018年11月29日小学校への出張講義報告(高槻市立樫田小学校)(18.11.29)
- 更新日:2018年11月27日小学校への出張講義報告(高槻市立松原小学校)(18.11.27)
- 更新日:2018年11月26日小学校への出張講義報告(高槻市立阿武山小学校)(18.11.26)