« July 2007 | メイン | January 2013 »
December 25, 2007
コラム第8号【時代の空気】をアップしました!
コラム第8号【時代の空気】をアップしました。
こちらからご覧下さい。
投稿者 Fc_policy : 03:25 PM | コメント (0)
December 20, 2007
【フィールドワーク最前線Vol.2】 まちづくりの「現場」を学ぶ
<三枝「専門導入ゼミⅠ」 ゼミ生からのリポート>
|
私たちのゼミでは、「まちづくり」をテーマに近畿一帯の地域復興を調査しました。現在、”地域”の希薄化が進んでいる一方で、もう一度従来の”地域”を取り戻していこうとする動きに密着しました。 私たちの班では、「池田の祭り」をトピックとし「まちづくり」の様子を見ていきました。今回、池田市渋谷地区の渋生会、会長の小川剛さん、副会長の乾文雄さん、稲原孝さんにお話を伺いました。 この渋谷地区では毎年、”盆踊り”、”夏祭り”、”秋祭り”、”もちつき”、”大とんと”といった、たくさんの行事が行われています。特に”秋祭り”の起源は江戸初期、約300年の歴史があり、ずっと伝え続けられています。これらの行事を通して、町を活性化させ、従来の良き日本の姿を取り戻そうとしています。得るものも多く、300年の伝統を残していきたいという思いが、”大人と子供を繋ぐ”そして、それが”地域の繋がり”へと発展し、住みやすい町となる。祭りを通して、子供を含めた町内の人を知ることができ、大人は子供たちが良いことをしていたら褒め、時に叱ることができる。つまり、町全体で子供の健全育成ができるのです。これは地域が1つになっていなければできないことだと思います。 |

政策創造学部1年次生 菊田 菜摘 |
|
また、池田の祭りは岸和田のだんじり祭りのように、地元魂の強い祭りではなく、他の地域から住み移ってきた人たちも、その年から祭りに参加するなど、とても溶け込みやすい「まちづくり」も展開しています。近年は交換留学生として関西大学に来ている様々な国々の学生も、日本の文化を知る目的で、池田の祭りに参加しています。このように歴史ある日本の文化を伝える役割も果たしています。 渋谷地区では、商店街のような場所が存在しているわけではなく、祭りを通して「まちづくり」を展開していて、町内のみなさんはそれぞれに仕事を持っています。だが、「伝統を受け継いでいきたい」、「良い町にしていきたい」という意志から、時間を割き、負担がかかるけれども、”誇り”を持って地域の「まちづくり」に力を注いでいます。 今回、”祭り”という視点からの「まちづくり」を見ていったけれど、とても興味深く、いろんな発見ができたと思います。現在の世の中に一番大事なことが、この「まちづくり」ではないかと考えさせられるほどでした。これから、もっといろんな「まちづくり」を勉強していき、その知識を活用していきたいです。 |
|
|
|
|
|
|
|
【ゼミ担当者からの一言コメント】 「コモンズ」を共通テーマにすえた秋学期の専門導入ゼミでは、地域住民が共同で一つの「資産」を管理したり守ったりしている事例について学んできた。学生たちには、まず6週間にわたって24本の関連論文と格闘してもらった後、5つの班に分かれて身近な事例を調査してもらった。調査地の選定から実施、結果の報告までをすべて学生たちの自主性に任せて行っている。政策創造学部では、文献から得た知識を絶えず現実の社会と結びつけるかたちで理解してもらいたいと考えているが、このゼミもそうした試みの一つである。 |
投稿者 Fc_policy : 10:06 AM | コメント (0)
December 17, 2007
【第1期生の熱き日々!Vol.6】
<交換派遣留学>
|
平成20年度交換派遣留学に内定をいただき、来年の8月からアメリカのアリゾナ大学(UA)に行くことになりました。(※) アリゾナ大学で1年間勉強する目的に英語能力の向上はもちろんですが、今年の4月から大学で勉強を始めてから最も興味のある経済学をアメリカで学ぶことが大きな目的になります。同じ学問を学ぶにしても、国が違うと教授の教え方や生徒の考え方が異なるので、自分の知識を豊かにすることができます。また全世界規模で取り組まなければならない環境問題や食糧危機についても学んでみたいです。 日本にいると気付かないこと、アメリカに行って初めてわかること、あるいはアメリカから見た日本など今までわからなかったことを発見または再確認できることが留学のすごく貴重な点であり、とても楽しみにしていることです。友達も国籍など関係なくたくさん作りたいです。生活環境が全く異なり慣れるのには時間がかかるかもしれないですが、自分のペースで順応していきたいです。何より大事にしたいのは、常に誰にでもオープンに接することです。 貴重な機会をあたえていただいたことに感謝し、何事にもチャレンジしたいです。 |

政策創造学部1年次生 有間 友祐 |
|
|
私はベルギーにあるルーヴェン・カトリック大学への交換派遣留学生として内定をもらいました。(※) 私が留学へ応募した理由は自分を変えたいと思ったからです。今の生活ではついつい自分を甘やかしてしまうことが多く、大学入試での頑張りを無にしてしまう、そんな気がしました。だからベルギーという英語圏ではない異国の地で、自分がどれだけのことが出来るかを試したいと思います。さらに、日本人の苦手とする自己主張のできる人間になりたいです。グローバル化が進み、日本もそのような人材が求められるようになってはいるものの、実際にそのような人材を育成する環境はとても少ないです。だから私はよりアグレッシブな環境に身を置きたいと思います。アグレッシブな人々と環境の中で自分の意見を主張することの自信や大切さ、喜びを学び、ハングリー精神を養いたいです。 |

政策創造学部1年次生 楠 佳奈枝 |
|
|
もちろん不安は山ほどあります。言葉の問題や生活・文化の変化、そして何よりも一人の生活が始まることなど、他にもたくさんあります。だけどこの経験は私の人生を変えるものになるかもしれない。この人生の正念場で少しでも良い結果を出せるように今はがむしゃらにがんばるしかないと思っています。 最後に、このチャンスを与えてくれた関西大学に感謝します。 ※交換派遣留学とは、関西大学と学生交換協定を結んでいる外国の大学に選考を経て、1年間 留学する制度です。 上記2名は派遣留学内定者として各協定大学へ推薦され、その受入許可があった時点で、派 遣留学生として決定します。 |
||
投稿者 Fc_policy : 01:31 PM | コメント (0)
December 14, 2007
政策創造学部 主催講演会
「エネルギー産業の情勢と都市ガス業界の取組み」が
開催されました!
去る2007年12月12日(水)に、関西大学第1学舎5号館E503教室にて学部主催
講演会が実施されました。今年度最後を迎えた今回は、大阪ガス株式会社取締役社
長である芝野博文氏(本学部客員教授)をお招きして、「エネルギー産業の情勢と都市
ガス業界の取組み」を論題に、講演していただきました。
講演では、まず、世界的なエネルギー市場における危険性の高まりが指摘されまし
た。特に、アジア諸国の急成長と二酸化炭素排出問題、そして国連気候変動枠組み条
約の現状・問題点などを丁寧に説明され、国家を超えた温暖化対策の必要性を強調さ
れました。このような課題を受けて、天然ガスへの期待が高まっています。エネルギー
市場自由化が進んでいくなかで、大阪ガスは、天然ガス安定供給システムの構築に向
けて、国際的舞台でのより一層の活躍を目指しているそうです。
最後に芝野氏は、学生達に、①文系理系問わず広く学習すること、②学生時代に様々
な経験をすること、そして③地球環境問題を肌で感じることの大切さを力説されました。
そのメッセージは、講演を聴いた200名を超える学生達を大いに勇気づけました。講演
後、学生との質問応答が行われるなど、熱気溢れる講演会となりました。
本学政策創造学部は、これからも政策創造の最前線で活躍する方々をお招きして、こ
れからの社会を考える機会を提供していきます。


投稿者 Fc_policy : 03:50 PM | コメント (0)
政策創造学部 主催講演会
「エネルギー産業の情勢と都市ガス業界の取組み」が開催されました



投稿者 Fc_policy : 02:44 PM | コメント (0)
December 13, 2007
【第1期生の熱き日々!Vol.5】
<国際交流>
|
~学部外国人留学生第1期生~ 政策創造学部での一年目の大学生活はこれからの三年間学習の基礎知識をしっかり身につける時間だと思います。導入科目の中から、興味を持っている科目を選び、勉強しています。その中にはいくつかの科目は聞いたこともありませんでしたが、担当先生のイントロダクションを聞き、最初の緊張感がなくなり、代わりに知識を求める気持ちが湧いてきました。本学部では、一年目からゼミが始まり、25人程のクラスで、アカデミックな論文の書き方から課題の調べ方まで、根本的なものはこの一年できちんとマスターできます。一年生のはじめは緊張感がたくさんでしたが、今は政策創造学部の一年生になりましてよかったと思います。私は企業や団体などの組織のネットワークにかかわるプロセスに興味を持っています。これからの三年はその方面について研究したいです。 卒業したら、成長期の企業に入り、キャリアを磨いていこうと思っています。現在就職ますます難しくなっている中国では、私の世代は厳しい就職現状で悩んでいます。ですから、私は日本に留学し、中国では得られない知識と能力を身につけようと考えます。将来は大学で得た知識を生かし、日中のビジネスをつなぐ仕事で活躍したいと考えます。 |

政策創造学部1年次生 孫 岸易 |
|
|
~学部派遣留学生第1期生~ 私がこの静宜大学特別留学プログラム(※)に応募した動機は、将来自分が進む道について、航空会社に就職するという目標をすでに決めていたからです。そのためには、基本的にまず英語を話せることが大前提となりますので、目標に近づくため第一段階として、TOEICの得点を現時点よりさらに上げなければなりません。ですからこの秋、関西大学のエクステンションリードセンターで英語講座などに一生懸命取り組みました。第二段階としては、この留学が終わった後に英語圏・中国語圏のどちらかに長期留学をしたいと考えています。交換留学か、認定留学か、私費留学か、どちらの圏に行くかなどはまだ検討中ですが、おそらくこの留学プログラムの成果によって大きく変わってくると思います。 留学は私の夢でした。しかし、夢が現実になるにつれて思うことは、ただ単に他国に行ったからといって必ずしもその言語を話せるようになるとは限らないということです。話すということは他者と会話するということであり、相手に何を伝えたいのかは自分の本当に持っている教養というものが試されるのではないかと思います。私が、台湾に行く目的は語学の習得だけではなく、いろいろなことを学び、自分自身の価値観を変え、教養を増やしたいから、そして、将来自分の体験したこの経験を英語ないし中国語で語りたいからです。 |

政策創造学部1年次生 籠瀬 亜里沙 |
|
|
正直、今の段階での中国語の運用能力を考えると不安な面もありますが、「何のために留学するのか」という目的意識をもつことに大きく意味があると思います。私の場合、「航空会社に入るため」、がそれにあたります。このことを決して忘れずにいればどんなことでも乗り越えられます。「困難は分割せよ」、という言葉があります。夢を叶えるにはすこしずつ前進していけば叶えることができるというこの言葉を胸に、向こうでもコツコツ頑張ってきます。 ※協定大学の静宜大学(台湾)において、1学期間(2月から6月まで)留学するプログラムで、留学期間 は、在学年数への算入や単位認定などの教学上の措置が講じられる。 |
||
投稿者 Fc_policy : 12:35 PM | コメント (0)
December 11, 2007
政策創造学部 主催講演会
「“ものづくり”が日本の求心力-その中心に ICTがある」が
開催されました!
去る2007年12月7日(金)に、関西大学第1学舎5号館E501教室にて、学部主催
講演会が実施されました。秋学期を迎えて2回目の本講演では、「“ものづくり”が日
本の求心力-その中心にICTがある」と題して、秋草直之氏(富士通代表取締役会
長 本学客員教授)にご講演頂きました。
21世紀を迎えた現代においても、日本は製造業に高い競争力を有しており、その
強化にエレクトロニクスが果たす役割は益々高まっています。それを踏まえて秋草氏
は、エレクトロニクスが、運輸・医療・家電・自動車産業などへの産業連関効果を生み
出し、製品の付加価値を大いに高めうることを、詳細なデータに基づいて紹介されまし
た。
これからのものづくりには、ICT(Information and Communication Technology )
が必要とされます。それは、情報技術の発展だけを指すのではありません。つまり、
異業種間のコラボレーションや暗黙知の共有、そしてチームワークの重要性が高まっ
ているのです。インフォーマルな情報の共有を可能にする、いわば「長屋経営」的な
環境作りこそが、新しい商品を生み出す土壌なのです。
最後に秋草氏は、グローバル社会のなかで、強い信念と自信をもつことの必要性
を強く主張されました。このことで、会場を埋め尽くした200名を超える学生達は、
自身の将来像をはっきりと思い描けたことでしょう。
今後も、本学政策創造学部は、政治・経済分野を広く学ぶ機会を提供していきます。


投稿者 Fc_policy : 10:15 AM | コメント (0)
December 10, 2007
【第1期生の熱き日々!Vol.4】
<2007 学園祭>
|
~関西大学統一学園祭を経験して~ 私は、政策創造学部1期生として、また事務局長として今回の学園祭に携われたことをとても嬉しく思っています。政策創造学部1期生ということで、学園祭実行委員会もゼロからのスタート。何も無いところから何か新しいモノを創り上げるということは、日々みんなで悩み・ぶつかり合い…と、決して容易なものではありませんでした。しかし、その分とてもやりがいがあり、全員で同じ目標に向かって努力する喜び・支えてくれる人たちのありがたさを感じることができました。 そして、学園祭当日。私たち政策創造学部生の企画は関大生にも学外から訪れた方々にも予想以上に好評で、後夜祭では涙が自然と溢れました。様々な場面で支えてくれたみなさん、本当にありがとう。 私はぜひ来年も学園祭実行委員として政策創造学部を、そして、関西大学をさらに盛り上げていきたいです。また、その時は新しく入学される2期生のみなさんと共に、政策創造学部の新たな歴史を “創造”していけたらと、今から楽しみにしています。 |

政策創造学部 祭典実行委員会 事務局長 山縣 昂亮 |
|
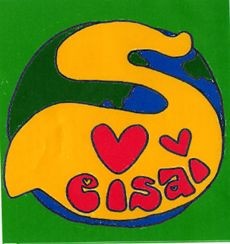
|
←政策創造学部祭典実行委員会 「Seisai」 ロゴマークです。 |

|
|
私が所属する企画局は実行委員の中でも最も大変で忙しい局であり、同時にやりがいのある局です。 当日の4日間のため、舞台に至ってはたった1時間強のために、何ヶ月も前から会議を繰り返し、試行錯誤しながら準備します。実家から2時間かけて通う私にとって、朝早くから夜遅くまでという作業は本当に体力的に辛いものがありました。上手くいかなかったり失敗したりして泣いてしまう場面も。それでも毎日BOXに行けば、大好きな26人の仲間がいたので、最後までやり切ることができました。 もちろん来年はさらにパワーアップした政祭を、関西大学中、大阪中に見せつけてやります!!合い言葉はENJOY!!みんなで政策創造学部を盛り上げて行きましょう!! |

政策創造学部 祭典実行委員会 川瀬 彩子 |
|

|
|
|
投稿者 Fc_policy : 06:47 PM | コメント (0)
December 07, 2007
【第1期生の熱き日々!Vol.3】
<プロフェッショナル英語>
|
現在、高校では複雑な構文を日本語に訳す練習や、高度な文法や単語を使った英語作文を中心に学習していると思います。もちろん、英語を学習する上でその学習は絶対にやらなければならない方法です。 しかし、将来仕事で必要になる英語は瞬発力のある英語です。つまり、英語を語順どおりに理解し、それに対する意見をすぐに発言できる能力です。 プロフェッショナル英語は、1クラス30人の少人数で、外国人教師による授業と、英語を専門とする日本人講師の2つの授業で構成されていて、実践に直結する学習方法を使った授業を、様々な角度から総合的に行っています。 |

政策創造学部1年次生 久保田 ちひろ |
|
|
|
授業では英語でコミュニケーションがとれるようになることを目的としているので、基本的に自分の意見を英語で言う練習をしています。そのために、専門教育の入門となるような大学生が学ぶべきものをテキストとしたリーディングの練習や、リアルタイムなニュースを使ったリスニングの学習をしています。 今後、英語を使う仕事は増える一方で、もはや不可避なスキルであると言えます。このプロフェッショナル英語ではそのニーズに応えられる授業を受けることができます。 |
|
|
私は、英語が苦手で実力もありませんでした。しかし、「英語をもっと学びたい・英語の能力を上げたい」と強く思っていました。そんなとき、プロフェッショナル英語クラスを「チャンスだ!」と思い選択することにしました。 授業のはじめには単語・リスニングテストがあるので、覚える量は多くて大変な面もあります。テストが終わると、先生手作りの教材を使って、長文をリスニングします。その時に、Question&Answer・キーワードの聞き取り・発音・シャドウィングしながら、英文を理解し、何度も口に出しながら、英文を覚え1人ずつSpeakingしていきます。 最後には、同じ内容のレベルアップした長文をリスニングしながら、英文を書いて完成です。その週の日本の時事問題に関する英文記事を、先生が用意してくれているので、クラスのみんなは、興味深く取り組んでいます。 |

政策創造学部1年次生 田中 宗子 |
|
|
|
ネイティブの先生のクラスでは、クラスで「特定の話題について」話し合い、自分の言いたいことを相手にすぐさま伝えられることを目指して勉強しています。 最初は、授業についていけるかどうか不安でした。しかし、クラスは、テスト結果に基づいて分かれています。だから、「ついて行くのがやっと」「授業でわからないところが、たくさんありすぎる」などと感じることはありません。しかも、少人数制クラスで授業が実施されるので、疑問点はすぐに先生に質問できます。授業は2コマ連続で開講され、頭を英語に切り替えることもできますし、先生とも仲良くなることができ、毎週クラスで楽しく勉強することができています。 |
|
投稿者 Fc_policy : 09:00 AM | コメント (0)
December 05, 2007
【第1期生の熱き日々!Vol.2】
<新入生合宿>
|
私は、政策創造学部で第2回目に実施された飛鳥文化研究所への新入生合宿に参加しました。まず、行きのバスでは、学部祭典実行委員の人たちが企画したゲームのおかげで、バスガイドの方とも仲良くなり、学生間の交流が深まりました。飛鳥文化研究所では、関西大学文学部の米田文孝教授の講演が実施され、飛鳥の土地や歴史、文化について理解を深めることができました。 合宿では、食事や入浴時間を共有して、友情を深める機会が多く得られました。そして、食後には卓球大会が企画され、多くの学生や先生方とチーム戦を行う中で交流の輪が広がり、とても良い体験となりました。それからは友人同士で話し合い、トランプなどを通じて夜通しで楽しむことができました。 |

政策創造学部1年次生 石川 裕二 |
|
|
|
二日目は、飛鳥でのフィールドワークが実施されました。米田教授や大学院生が、飛鳥地域の案内や遺跡の説明をしてくれ、飛鳥独特ののどかな雰囲気や風情を味わいながら友達と自然の中を散策し、教科書で見るような有名な遺跡も見て、理解を深めることができました。 この2日間の合宿を通じて、飛鳥の色々な歴史や遺跡のおもしろいエピソードを学習して、知的好奇心を高めただけでなく、友達や先生方と楽しく語り遊ぶことができたことは、大学生活の大切な思い出となりました。 |
|
|
私は、第2回目の政策創造学部新入生合宿(奈良県明日香村)に参加しました。 今回の合宿では、様々な催しを通して、たくさんの友達ができました。例えば、合宿所に向かうバスでは、学園祭実行委員がさまざまなゲームを企画してくれました。そして飛鳥文化研究所では、関西大学文学部の米田文孝教授のキトラ古墳についての講演を聞くことが出来ました。その後、夜は卓球大会、翌日早朝にはテニスを楽しみました。 私は、大学に入学して、学習方法や友人関係に大きな不安を抱いていました。しかし、この合宿でたくさんの学生や先生たちと交流することで、お互いの考えを知ることができ、これからの科目選択やクラブ・サークル活動など大学生活についての情報交換をする良い機会となりました。そのおかげで、私の不安が少しずつなくなっていきました。それだけでなく、自分の将来について真剣に考えている学生から刺激を受けて、自分の将来像を具体的にイメージするきっかけになりました。 |

政策創造学部1年次生 山田 真由 |
|
|
|
私は、これまで開発途上国での開発活動に関わりたいと考えていました。しかし、そういった国際機関でなくても民間企業が地域社会への貢献活動や国際協力に関わっていることを知り、企業の社会貢献に興味を持つようになりました。 これからも私はたくさんの学生達とのコミュニケーションを通じて、自分の将来について考えてみたいと思います。今後も、このような学生が交流できるような企画があれば、是非参加したいです。 |
|
投稿者 Fc_policy : 09:00 AM | コメント (0)
December 03, 2007
【第1期生の熱き日々!Vol.1】
<アデレード大学英語研修>
【新シリーズ登場】政策創造学部生のキャンパスライフを「第1期生の熱き日々!」と題してシリーズで紹介します。
第1回目はこの夏に実施されたオーストラリア・アデレード大学での海外英語研修参加者の声です。
|
このセミナーを終了して得たものは大きいと思います。英語の能力が、ぐっと伸びたというわけではないですが、このセミナーが勉強への良い意欲を生んでくれたし、何といってもこの経験自体が本当に大きな収穫でした。 僕には大きすぎる夢があります。将来自分の足で世界のいろいろな国々を回って、自分の目で様々なもの、例えば、その国々の文化、ヒト、あるいは、起きている事(問題)を見て、また肌で感じ、それを何らかの形で世の中の人に伝えたい。そう思っています。そして今回、セミナーのクラスに、サウジアラビア、韓国、台湾といった、いろいろな国々の人がいて、英語で会話し、一緒に勉強し、時には思いっきり笑ったりと、とても貴重で自分の夢につながる経験ができたことが本当に嬉しかった。他国の人と会話していると、あっと驚かされるようなことがたくさんあります。それがとても新鮮で、「こんな考え方もできるんだ」と視野が広がり、自分にプラスになる発見がたくさんできました。 |
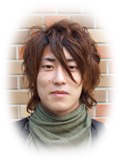
政策創造学部1年次生 景岡 佑太 |
|
|
|
このセミナーに参加したのは、夢への実現に近づくためで、英語能力の向上はもちろん、たくさんの人と接することで、夢への良い足掛けとなる経験をするのが目的でした。なので、ここで終わりではなく、ここからが自分の夢への挑戦だと思っています。 最後に、今回のセミナーは親や親戚の人、僕に関わる全ての人たちのサポートがあってこそのものだったので感謝しています。とりわけ両親にはとても感謝しています。その恩を、今勉強意欲が高まっているので、“勉強”で返したいと思います。 |
|
|
私のもうひとつの家族――それがホストからの最後のプレゼントでした。別れの日、そのあまりのつらさに溢れ出した涙は、今でも忘れることができません。帰りたい、そう思える家族に出会いました。 見知らぬ街、見知らぬ家で過ごしたアデレードでの一ヶ月。ホームステイはある意味とても強烈な体験でした。日本とは違う初めての空間に、ひとりぽつんとやって来る。周りの環境が一気に変わり、新たな生活がスタートする。それがどれほど強烈で影響力の大きいことなのかを、留学に行って初めて味わいました。「私」が剥き出しになった瞬間、まず初めに向き合うべきものは、自分自身だということに気付きました。 |

政策創造学部1年次生 合田 ゆさ |
|
|
|
我が家のような温もり。ホストファミリーとの毎日は想像以上に親密で、日本人であることを一瞬忘れてしまうほど、会話に花が咲きました。話が弾み、一緒に思いっきり笑った瞬間、「あぁ、私はこのために英語を勉強していたんだ」という気持ちと、「もっと、もっと話したい、伝えたい」という気持ちが一気に込み上げ、胸が熱くなりました。英語が、人と人とをつなぐ手段であるいうことを肌身に感じた瞬間でした。 ホストファミリーの家に帰る日へと向かって、これからも英語を通して視野を広げてゆく充実した大学生活を歩みたいと思います。 |
|
投稿者 Fc_policy : 09:00 AM | コメント (0)
December 01, 2007
政策創造学部専任教員による
FD(Faculty Development)研究会の概要を紹介します!
政策創造学部では、学部の教育理念・目的をたえず再確認しつつ、その具体化を専任教員全員で考えて
いくための研究会としてFD(Faculty Development) 研究会を継続的に開催しています。今回はその研究会
での論議の概要を以下簡単に情報発信します。
|
政策創造学部は、国際社会に活躍しうる豊かな知識と行動力を持った人材育成を目指しています。そのためには、高度な学術的知識を身につけるだけでなく、「自ら情報を分析し実践する能力」が必要とされます。そのために本学部では、初年次から卒業にいたるまで、政治経済分野の諸問題について広く学ぶことを目標として、「スパイラルアップ型の少人数教育制度」を導入しています。 本学部は、独自の試みとして、FD研究会を定期的に実施し活発な論議を続けています。これは、専任スタッフが教育方法や実践例を題材にして議論することを通じて、学部教育システムのさらなる充実を図ろうとするものです。 |
第Ⅰセメスター配当「導入ゼミ」授業風景 |
|
第1期生を迎えた本年4月に実施した研究会では、導入ゼミの教育目標である「読み・書き・話す」という自己表現能力の向上を実現するためのガイドラインを確認しました。それに続くFD研究会で、各教員が指導実践例を報告し、教育方法を提案しあうことで、学生のニーズや学習到達度に応じた教育方法を模索しています。 また、本学部では、独自の教育システムとしてGPA(Grade Point Average)制度を導入しています。このシステムは、学生の成績をできるだけ客観的に評価しようとするだけではありません。学生自身が、自分の学習到達度や今後の課題を見つける確かな道しるべともなりうるものです。それに加えて本学部では、オフィスアワーを設けて、アカデミックアドバイザーが学生への学習アドバイスを定期的に実施しています。このことで、GPA制度のよりいっそうの充実を図っているのです。 今後、FD研究会では、「導入ゼミ」、それに続く「専門導入ゼミⅠ・Ⅱ」、「専門演習Ⅰ・Ⅱ」を通じて、学生への教学指導をさらに充実させるべく議論を進めていきます。それは、各担当教員が、学生個人へのコミュニケーションを深めていくことで、各学生が充実したキャンパスライフを送れるようサポートしようとするものなのです。 「スパイラルアップ型のゼミナール教育体系概念図」 |
|