
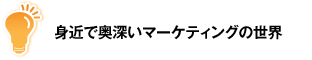
1年次には、総情を知るきっかけにもなったメディア系の授業はもちろんのこと、系の区分にこだわらず少しでも興味を感じた授業は、なるべく履修するようにしていました。
特に印象に残っているのは『経済学』です。この授業を受けるまでは、"経済"と聞いてもどこか自分とは縁遠い世界のことのように感じていました。でも本来は、消費をしない人などいないのと同様に、誰もが"経済"の当事者のはずです。そんな身近で奥深い分野に可能性を感じ、興味の軸が社会情報システム系に映り始めた頃出会ったのが、今ゼミで取り組んでいる"マーケティング"でした。当初は「お金に関する計算が難しそう」という印象が強く、文系だった私には苦手意識もありました。しかし、やみくもに数字だけを追いかけるのではなく、実際の消費の現場で得た、さまざまな情報を考慮・分析し、"売れる仕組み"を考えていく。なんてクリエイティブでおもしろいんだ!とマーケティングの虜になりました。本格的に自分の学びを掘り下げる3年次からは、今まで座学で学んできたことを実践したいと思い、実際の商品開発にチャレンジできる今のゼミに決めました。
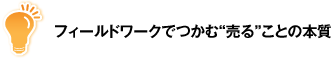
ゼミでは、マーケティングの基礎を学ぶケーススタディとして、毎年取り組んでいる2つの有名コーヒーチェーンの違いについて考察する課題があります。まず両店舗を訪れ、食器やインテリアなどのハード面から、商品ラインナップ、客層や価格帯の違いなど…etc。フィールドワークで調査します。普段何気なく利用しているコーヒーショップにも、"一杯のコーヒーを売る"ための工夫と緻密な戦略があふれていることに気がつきます。その後は、先輩にも参加していただきながら、調査結果を発表し合い意見を交わします。ディスカッションでは、自分では思ってもみなかった意見が出たり、まったく異なる視点で分析を試みるメンバーがいたりと、マーケティングの難しさとおもしろさ、その両方を実感することができました。このゼミは自分の意見をしっかりと発言できるメンバーが集まっているので、議論が白熱しすぎることもあります(笑)。ですが大切なのは、それぞれの意見に耳を傾け、空中分解させること無くひとつの目標に向かって前向きな議論にしていくこと。この課題を通じてマーケティングのフローだけでなく、分析の仕方やディスカッションの際の役割分担など、グループワークのポイントも学ぶことができました。
.