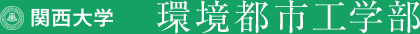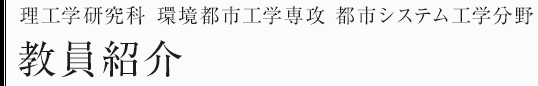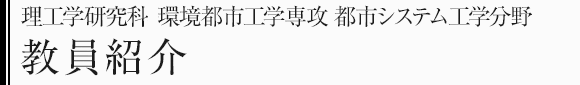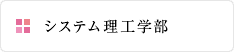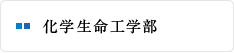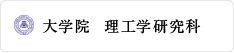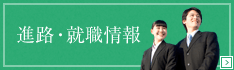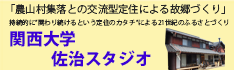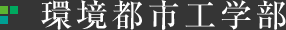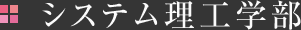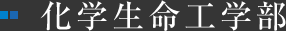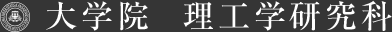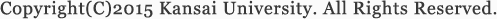-
環境マネジメント
尾崎 平 教授
-
地盤防災工学
飛田 哲男 教授
-
海岸工学
安田 誠宏 教授
-
リアルタイム洪水氾濫解析
橋本 雅和 准教授
-
地盤環境工学
宮﨑 祐輔 准教授
-
構造工学、鋼構造、維持管理
石川 敏之 教授
-
コンクリート構造学、維持管理
上田 尚史 教授
-
コンクリート工学、維持管理
鶴田 浩章 教授
-
プロジェクトマネジメント
北岡 貴文 准教授
-
交通システム
井ノ口 弘昭 教授
-
社会資本計画
北詰 恵一 教授
-
社会システム工学
尹 禮分 教授
-
景観学・土木史学
林 倫子 准教授
-
システムモデリング・リスク工学
兼清 泰明 教授
-
社会基盤情報学
窪田 諭 教授
-
ネットワーク工学
滝沢 泰久 教授
-
情報システム工学
安室 喜弘 教授
-
情報通信工学
安達 直世 准教授
-
建築環境デザイン・地域再生デザイン
井ノ口 弘昭 教授
岡 絵理子 教授
北詰 恵一 教授
木下 光 教授
- 2023年度に開講する博士課程前期課程の研究領域および研究指導教員を掲載しています。
地球環境系
環境インフラのリ・デザインに関する研究では、上下水道、廃棄物処理インフラを中心に、高付加型のサービス供給拠点・ネットワークの構築を目的に、施設更新のシナリオ、政策立案・評価に関する研究を行う。気候変動に対する適応策のデザインに関する研究では、都市の持つ脆弱性の改善による気候変動と折り合える適応社会の実現を目的に、水災害、水資源、自然生態系分野の適応策に関する研究を行う。
地盤防災工学とは、関連するさまざまな工学・理学分野と協力し、地盤工学の視点で自然災害による被害を軽減すること、合理的に構造物を設計することを目的とする工学分野である。現在、世界規模で地震、豪雨、土砂災害などの自然災害が頻発している。わが国においても、2011年東北地方太平洋沖地震後の津波で多くの土木・建築施設が壊滅的な被害を受けた。また、今度数十年以内に発生することが確実と見られる南海トラフ巨大地震に対し、特に大阪平野の地盤増幅特性を適切に評価し、公共構造物等の耐震性を確保しておくことは極めて重要である。本研究室では、解決が強く求められている社会的問題に挑戦するため、地盤工学および地震工学の観点から研究を行う。このような研究を通じて、研究を進める上での知識や道具を身につけるとともに、問題発見・解決能力の育成を図る。
テーマは「津波、高潮、高波による沿岸災害の軽減と気候変動への適応」です。安全・安心な海岸防護を目指して、津波や高潮などの沿岸災害からいかに人的・資産被害を軽減するかについて研究しています。さらに、顕在化しつつある地球温暖化による海面上昇や気象の極端化と、それに伴う水災害の激甚化に対して、効果的な適応策を提唱するための研究に取り組んでいます。
河川監視カメラの情報を用いて、リアルタイムかつ不確実性の少ない浸水予測手法を確立する研究。
地盤環境工学
宮﨑 祐輔 准教授
本研究室では,原位置計測や模型実験で得られる計測データと数値シミュレーションの融合により,地盤工学上の問題の可能性を高め,土中の水理に関わる地盤災害の発生メカニズムや,諸問題に対して有効な対策工,設計法の提案へつなげる研究を幅広く展開する。
設計建設系
社会基盤構造物は、長く安全に利用されなければならないため、強度や耐久性に優れた設計、施工を行い、適切な維持管理が必要です。当研究室では、鋼橋を中心とした社会基盤構造物を対象に、長く安心して利用するための技術の開発を行っています。また、社会基盤構造物への新材料の適用に関する研究も行っています。
コンクリート構造物の設計、施工、維持管理に係わる全ての事象を対象として、実験と解析を駆使することにより、その本質に迫ることを目指している。材料工学、構造工学の他、物理化学の知識を活用し、ミクロ、メゾ、マクロのそれぞれのスケールにおける現象を明らかにするとともに、それら数値モデルを構築することでコンクリート構造物のライフサイクルシミュレーションを行う。
コンクリートは橋梁、トンネル、ダム、港湾施設など重要な社会基盤施設の建設に欠かせない建設材料である。コンクリート用材料の選定、配合、施工、品質管理などの材料施工と、安全性、第三者影響度、使用性、外観、復旧性、修復性および耐久性などのコンクリート構造物の性能に関して、環境負荷や生物共生・カーボンニュートラルなども考慮し総合的に研究する。その際、既設構造物の維持管理や新設時の高機能化・高強度化・長寿命化などのライフサイクルの検討も行う。
プロジェクトマネジメント
北岡 貴文 准教授
kitaoka![]()
当研究室では、防災・維持管理の高度化を目的とした「プロジェクトマネジメント」に関する研究に取り組む。建設プロジェクトにおける人工知能AIを用いた地質リスク評価手法立案に関する研究、斜面災害リスク軽減を目的とした土砂災害早期警戒体制立案に関する研究などをテーマとし、原位置計測や数値解析、人工知能に関する内容を指導して研究する。
計画マネジメント系
効率的かつ安全・環境負荷の少ない都市交通システムの構築のため、実証的な研究を中心に行っている。脱炭素社会構築のための都市交通分野での政策の検討、交通量配分モデル・交通シミュレーションモデルを用いた環境負荷量の定量的検討などを中心に研究する。また、健康まちづくりのための交通分野の検討を行う。
社会資本は、関係する主体が多数かつ多様で、その影響も大きく長期に渡る。従って、それらを計画する者は、高い見識と豊富な知識を持って取り組まなければならない。多くの異なる意見を取りまとめ、公正な評価と変化への柔軟な対応をリアルタイムに行う英断が求められる。透明性の高い計画手法を選び、それらを実践する能力が必要である。このため、計画理論の基礎から応用を学び、その実証を行うことで、その能力の取得をめざす。
工学・社会システムにおける諸問題を、人間とコンピュータの協調によって解決するためのシステムの知能化と最適化に関する研究を行っている。実際に使う立場から物事を考え、社会基盤システムの維持管理計画問題、防災システム開発などへの応用研究にも取り組んでいる。
これまでにどのような風景が形作られ、それが人々によってどのように解釈されてきたのかという、場所の履歴と風景形成のメカニズムを明らかにすること、そして、現代の風景の魅力や価値を発見・実証していくことにより、今後の地域づくり・国土づくりに役立つ知見を得ることを目標としています。
情報システム系
複雑化した都市システムに存在する様々なリスクに対処するには、工学的技術の適用だけでなく、経済的手法の援用などを考慮に入れた総合的視点からの考察が必要となる。こういった背景の下、確率システム理論を活用し、都市システム、構造システムの信頼性・リスク評価を行う能力の習得を目標とする。
社会基盤施設を運営するための情報技術の領域は、情報システムの開発と利用のみならず、人や組織に係わる社会システムを含むより幅広い領域に発展している。社会基盤工学と情報学を融合した社会基盤情報学に立脚し、社会基盤施設のライフサイクルに係わる様々な課題を情報通信技術と情報システムによって解決し、新たなサービスを創出する研究に取り組む。特に、道路の情報マネジメントシステム、3次元空間データを用いた維持管理業務支援システム、都市空間のBIM/CIMモデルの構築と可視化の研究を行っている。
本研究室の研究目標は、多様な都市環境において人間の活動を支援する情報処理サービス空間を動的に構成可能とすることである。すなわち、常に変化する人間個々の社会活動において、その活動空間内に偏在する情報処理アプライアンスを有線・無線ネットワークを用いて動的に組合せ、適時、人間活動環境の状況をセンシング・認知し、人間が必要とするサービスをリアルタイムに提供する情報処理技術およびネットワーク技術を研究する。
人間に有用な情報を、用途や目的に応じて、適したメディアとして伝えるためのシステム構築の方法論を習得する。特に人間の行動や振舞いに注目し、視覚的な計測・情報処理を行うシステムを扱い、アプリケーションを見据えた研究を展開する。さらには、生活環境や社会生活を含む、より大規模な枠組みで、人間を中心に捉えた情報システムの在り方や機能設計について取組む。
情報通信工学
安達 直世 准教授
n-adachi![]()
今日,社会基盤システムの構成・運営において,情報処理技術とくに通信システムは重要な役割を担っている。今後も,社会基盤システムと情報通信技術との融合は,都市空間の至る所で今まで以上に進められていく事が予想される。本研究室では,将来の社会基盤を支える新しい通信技術の開発・研究に取り組む。
地域再生学
建築環境デザイン・地域再生デザイン
井ノ口 弘昭 教授
hiroaki@kansai-u.ac.jp
岡 絵理子 教授
okaeri![]()
北詰 恵一 教授
kitazume![]()
木下 光 教授
kinosita![]()
地域コミュニティの持続と再生を集住環境の持続性という視点から捉え直し、ソフトな仕組みを内在するものとしてのハード、つまり持続的な集住環境のあり様として、様々な工学的専門領域を基軸に研究し提案する。「再生」とは、歴史的連続性を意識しつつ、持続力のあるコミュニティを再形成する取組みをイメージするものである。