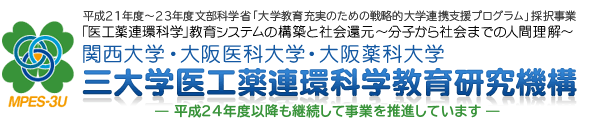活動報告
自由研究コンテスト2011 第二次審査会(於:高槻ミューズキャンパス)(11.11.23)
2011年11月23日
三大学医工薬連環科学教育研究機構が「自由研究コンテスト2011」第二次審査会、表彰式を開催しました。
 三大学医工薬連環科学教育研究機構では、昨年から高槻市内の小・中学校に通う児童・生徒を対象に自由研究コンテストを開催。
三大学医工薬連環科学教育研究機構では、昨年から高槻市内の小・中学校に通う児童・生徒を対象に自由研究コンテストを開催。
今回は、高槻市内の公私立小・中学校から寄せられた総数360作品の中から、第一次審査で選出した32作品について、23日、関西大学高槻ミューズキャンパスミューズホールにて第二次審査会、表彰式を行いました。
 第二次審査では、小学校高学年22名(1名欠席)が自由研究の内容を発表し、小学校低学年9名が作文(「未来の生活について」)をそれぞれ郎読しました。
第二次審査では、小学校高学年22名(1名欠席)が自由研究の内容を発表し、小学校低学年9名が作文(「未来の生活について」)をそれぞれ郎読しました。

発表者はスクリーンに大きく投影された研究成果を前に、レーザー・ポインターを駆使して、
すばらしいプレゼンテーションを繰り広げていました。
会場には発表者の家族や学校の校長先生、担任の先生、友だちら182名が来場し、それぞれの発表に熱心に耳を傾けていました。
また、第二次審査に進んだ作品はポスターとして掲出され、来場者はこどもたちの力作に見入っていました。
 審査会の後、審査員のお1人 山田 善春先生による実験では、食パンを水だけでおいしくする方法や、風船につまようじを刺す実験では驚きと喜びの声が上がっていました。
審査会の後、審査員のお1人 山田 善春先生による実験では、食パンを水だけでおいしくする方法や、風船につまようじを刺す実験では驚きと喜びの声が上がっていました。
審査の結果、最優秀賞2名、優秀賞3名、関西大学賞1名、大阪医科大学1名、大阪薬科大学1名、審査員特別賞3名が入賞し、発表者全員が入選として表彰されました。
身近にある「なぜ?」をこどもたちが調べ、研究し、発表することが未来の科学の発展につながっていくということを知ってもらういい機会になったのではないかと私たちは考えています。

小学校への出張講義報告(高槻市立芥川小)(11.11.22)
2011年11月22日
芥川小学校の5年生3クラスを対象に顕微鏡の実験講義を実施しました。
この日は、少し風が吹いていて、教室は寒かったのですが、中には、半そで半ズボンのこどももいて、ビックリしました。
授業が始まるチャイムが鳴ると、みんなすぐに席に座り、静かに先生の話を聞いていました。
顕微鏡の作成時には、上手くできないこどもや作り方がわからないこどもを同じ班のこどもが手伝うなど、班のみんなが協力してくれたので、すごく助かりました。
みんな自分の顕微鏡ができると、友達と見せ合いっこしたりしてすごく楽しそうでした。
光学顕微鏡での観察では、解剖標本をみたり、なかには自分の指紋をセロテープにつけて観察したり、砂やアリを顕微鏡で見ようとしていたこどももいて、おもしろかったです。
今回の実験講義を終えて感じたことは、実際に体験することで得られる感動や興味、発見、疑問がたくさんあることです。
今日感じたことを忘れないで、私たちも研究に取り組んでいきたいです。



小学校への出張講義報告(高槻市立南大冠小)(11.11.21)
2011年11月21日
平成23年11月21日(月曜日)に高槻市立南大冠小学校の6年生3クラスを対象に出張講義を実施しました。
今回は1クラスずつ1限のみの講義を3回連続で行いました。
テーマは関西大学 倉田先生の「筋肉の動きと筋肉の働き」です。
倉田先生がこども達に対して最初に「力こぶができる人」という質問をしたところ、みんな恥かしかったようで、力こぶを前で披露してくれる子は少なかったのですが、次に「筋肉をつけるにはどうしたらいいか?」という問いには思い思いの回答をしてくれました。
次に筋肉の活動を筋電位計を通して観察しました。
倉田先生の研究室のティーチングアシスタント(TA)が、Tシャツ姿となって力こぶの筋肉をむき出しにして測定される人(被験者)となり、こども達はスクリーンに映し出される波形を見ました。
TAが力を入れると筋電位は大きくなり、力を入れていないと小さくなります。
筋電位が大きくなったときは歓声がありました。
休み時間には、こども達にも被験者になってもらいました。
大勢のこども達が筋肉の働きを肌で感じてくれたように思います。



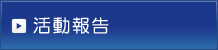
-
教育課程の構築
- 更新日:2017年12月09日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(17.12.9)
- 更新日:2017年12月02日「機能形態学1」実習報告(於:大阪薬科大学)(17.12.02)
- 更新日:2017年07月11日「基礎漢方薬学」実習報告(於:大阪薬科大学)(17.07.11)
- 更新日:2016年12月16日「お屠蘇で新年をお祝いしましょう!」報告(於:関西大学)(16.12.16)
教育支援システムの構築と教育環境の整備
- 更新日:2018年12月15日「機能形態学1」実習報告(於:大阪薬科大学)(18.12.15)
- 更新日:2018年12月08日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(18.12.8)
- 更新日:2016年06月25日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(16.06.25)
- 更新日:2010年02月17日戦略的大学連携支援プログラムに係る打合せ(教育サポート部門)(於:薬科大)(10.02.17)
社会還元
- 更新日:2018年12月06日小学校への出張講義報告(高槻市立土室小学校)(18.12.06)
- 更新日:2018年11月29日小学校への出張講義報告(高槻市立樫田小学校)(18.11.29)
- 更新日:2018年11月27日小学校への出張講義報告(高槻市立松原小学校)(18.11.27)
- 更新日:2018年11月26日小学校への出張講義報告(高槻市立阿武山小学校)(18.11.26)