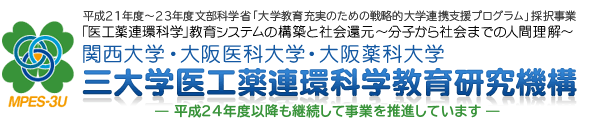活動報告
高槻家族講座(第6回)報告(於:薬科大)(11.12.03)
2011年12月 3日
 平成23年12月3日(土)に、高槻家族講座(通算6回目)
平成23年12月3日(土)に、高槻家族講座(通算6回目)
シリーズ『食と育み』第2回「体に良いもの、いただきます」を開催いたしました。
講演には172名が、こども体験コーナーには、小学生32名とその保護者22名が参加されました。
第1講目「地球は大きな薬箱・地球を食べて健康に」 崇城大学薬学部 薬用植物園 教授 村上 光太郎 氏
 村上教授は、まず、健康は朝起きてがんばろうという気持ちから始まることで、病気の概念とは病名が付いたからではなく、今日はすこしセーブしようと考えている時点で既に病気に入っていることを強調されました。
村上教授は、まず、健康は朝起きてがんばろうという気持ちから始まることで、病気の概念とは病名が付いたからではなく、今日はすこしセーブしようと考えている時点で既に病気に入っていることを強調されました。
そして、野の植物が薬草効果を持ち、摂取することでいかに健康になれるかを数々の例を挙げてご紹介されました。
ヨモギは摘んだ芽を一日5、6個食すと、6カ月後には骨密度が上がり、骨粗しょう症が治るというお話、また、紫に蘇ると書くシソ(紫蘇)は倒れた旅人がこれを食すと生き返ったという由来があるほど、体の疲れがとれるというお話、小児ぜんそくを治すフキや、乾燥させたカキの種を食すと認知症が治ること、肝臓の働きを良くするクズ等々、驚きのお話を次々とされ、会場の皆さんを引きこみました。
さらに、植物にはアクがありますが、ミネラルの多いアクがこれらの効果をもたらすため、アク抜きは良くなく、アクの感じない調理法も植物ごとにご紹介されました。
1時間弱の講演ではご紹介仕切れないほど数々の薬草があるそうで、村上教授はこれらのことをまとめた著書『食べる薬草辞典』も出版されています。
第2講目「食べ物を選ぶ力を身につけよう!」 丸大食品株式会社 中央研究所 砂田 智子 氏
 丸大食品でメニュー提案をご担当され、ウインナーやハムを使ったメニューを日々考案する砂田氏は、まず食育という言葉の語源から現代の食事へ警鐘を鳴らし、食育を構成する3つの柱である選食・しつけ・食糧問題について触れられました。
丸大食品でメニュー提案をご担当され、ウインナーやハムを使ったメニューを日々考案する砂田氏は、まず食育という言葉の語源から現代の食事へ警鐘を鳴らし、食育を構成する3つの柱である選食・しつけ・食糧問題について触れられました。
次に、生活習慣病予防になる「バランスの良い食事」とは、実は定義がないため漠然と捉えがちなところを、より具体化し、野菜は両手に盛るくらいであるとか、主菜は片手に盛るくらい、果物は握りこぶし一つ分など1食の摂取目安量を非常にわかりやすく覚えやすい言葉で説明されました。
また、もうひとつのバランスの良い食事として、良い器を使って心を満たすことや大好きな方と一緒に食べる楽しさなど心で感じるゆとりも大切であることを述べられました。
後半では、私たちがスーパーなどで目にする食品表示、食品添加物、3つのJASマークの意味など有用な情報を説明されたり、世界の食料自給率を比較した日本の低さをグラフで表したり、幅広い話題についてクイズ形式で会場の皆さんが参加できるような講演をされました。
こども体験コーナー「手作りウインナーに挑戦しよう!」
毎回好評の小学生対象こども体験コーナーは、丸大食品株式会社の中根氏をはじめ丸大食品のスタッフのみなさんにより、ウインナーの手作り体験が大阪薬科大学食堂にて行われました。エプロンと手袋をきちんと着用し、まずは味付け済みの1本の長いソーセージを使って、ひねる練習から始めました。
好きな長さを決めたら、両手の親指と人差し指でソーセージの端を軽く潰し、両指でくるくると前方に転がします。さらに前回りを数回繰り返すとしっかりひねられ、ソーセージがしっかり張ります。練習でひねり方を覚えたら、いよいよ肉の味付けから自分たちで行います。
白こしょう・黒こしょう・ナツメグ・ガーリック・バジル・パセリと6種類の香辛料が用意されました。
好きな香辛料をミンチ肉(豚100%)に10g加え、よく手で混ぜ合わせます。
子どもたちはこねるのが楽しいようで、みな夢中でした。
これを充填機でケーシングと言われる皮(ウインナーは羊の腸)に絞りだします。絞り口に皮全体を繰り寄せ、お肉が出始めると面白いように皮に詰められていきます。
これらを同じようにひねり、ひもでバナナの房状に束ねたら、鍋に入れ10~15分じっくりと茹であげます。これで出来上がりです。
熱々出来たてのウインナーをパンに挟んでケチャップやマスタードをかけていただきました。
自分たちで調合した香辛料はどんな味のウインナーになったのでしょうか。
今回受講した小学生の皆さんは「ウインナー博士」の称号の修了書を受け取りました。



小学校への出張講義報告(高槻市立安岡寺小)(11.11.29)
2011年11月29日
安岡寺小学校の6年生2クラスを対象に顕微鏡の実験講座を実施しました。
授業が始まる前から、先生やTAの学生に、自分が持ってきた葉っぱを見せてくれたりと、人懐っこいこどもが多かったです。
今日の実験講座を楽しみにしていたこどもが多かったようで、みんな先生の話にも興味をもって聞いていました。
実験講座が始まると、みんな一生懸命取り組んでいましたし、ガビョウで黒いボードに穴をあける作業では、怖がりながらもみんな上手にできていました。
完成した顕微鏡で、自分の作製したサンプルを見たり、友達と交換して見せ合いをしたりして、すごくはしゃいでいました。
光学顕微鏡での観察では、標本をみて、感動していました。
本日の小学校での講座もすごく楽しかったですし、とても有意義な時間を過ごす事ができました。
小学校への出張講義報告(高槻市立清水小)(11.11.28)
2011年11月28日
平成23年11月28日(月)、高槻市立清水小学校の6年生3クラスを対象に出張講義を実施しました。
今回は3クラス合同2限連続で、関西大学 倉田先生の「腕の動きと筋肉の働き」というテーマで授業を行いました。
倉田先生の「力こぶができる人」と言う質問には、こども達が元気良く手を挙げ、前に出てみんなの前で力こぶを披露してくれました。
次の「筋肉をつけるにはどうしたらよいか」という質問にも、みんな思い思いの回答を出してくれました。
また、筋電位計という装置を使い、筋肉の強さを目で見て理解するといった実験が行われました。
ティーチングアシスタントが力を入れると筋電位が大きくなり、力を入れていないときは筋電位が小さくなります。
こども達は筋電位が大きくなったら「おおー」、小さくなったら「ああー」というような楽しい反応を見せてくれました。
休憩時間を使って筋電位計を測る事ができる時間を設けると、大勢のこども達が列になって集まりました。
実際に自分で体験することで、筋肉の動きをより理解してくれたようでした。
次に人工筋肉や模型を使って、筋肉の動きを説明しました。
人工筋肉に力が入ると模型の腕が上がり、こども達は興味深そうにその様子を見ていました。
「筋肉の長さや太さ、ついている位置はどう変わっているでしょう」と課題が出され、人工筋肉に触ったり模型を見に行ったりしながら、楽しく観察していました。
最後に今習っているてこの原理で筋肉が腕を動かしていることを説明し、筋肉が体にとってすごく大事であることを話し、「今のうちからよく食べて、よく寝て、よく運動して、(そして勉強もきちんとやって)丈夫で健康な体づくりを心がけよう」とのお話で締めくくられました。



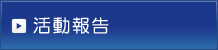
-
教育課程の構築
- 更新日:2017年12月09日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(17.12.9)
- 更新日:2017年12月02日「機能形態学1」実習報告(於:大阪薬科大学)(17.12.02)
- 更新日:2017年07月11日「基礎漢方薬学」実習報告(於:大阪薬科大学)(17.07.11)
- 更新日:2016年12月16日「お屠蘇で新年をお祝いしましょう!」報告(於:関西大学)(16.12.16)
教育支援システムの構築と教育環境の整備
- 更新日:2018年12月15日「機能形態学1」実習報告(於:大阪薬科大学)(18.12.15)
- 更新日:2018年12月08日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(18.12.8)
- 更新日:2016年06月25日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(16.06.25)
- 更新日:2010年02月17日戦略的大学連携支援プログラムに係る打合せ(教育サポート部門)(於:薬科大)(10.02.17)
社会還元
- 更新日:2018年12月06日小学校への出張講義報告(高槻市立土室小学校)(18.12.06)
- 更新日:2018年11月29日小学校への出張講義報告(高槻市立樫田小学校)(18.11.29)
- 更新日:2018年11月27日小学校への出張講義報告(高槻市立松原小学校)(18.11.27)
- 更新日:2018年11月26日小学校への出張講義報告(高槻市立阿武山小学校)(18.11.26)