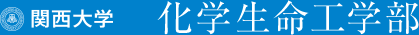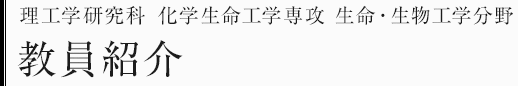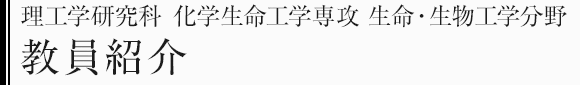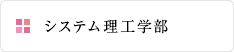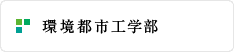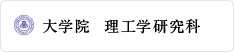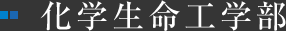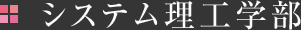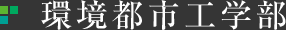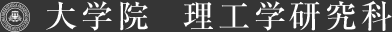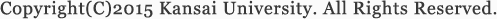-
環境微生物工学
岩木 宏明 教授
-
酵素工学
老川 典夫 教授
-
生物化学工学
片倉 啓雄 教授
-
神経再生工学
下家 浩二 教授
-
医薬品工学
住吉 孝明 教授
-
医薬品工学
長岡 康夫 教授
-
食品栄養化学
福永 健治 教授
-
食品栄養化学
細見 亮太 教授
-
微生物制御工学
松村 吉信 教授
-
生物化学工学
山崎 思乃 教授
-
酵素工学
山中 一也 教授
-
環境微生物工学
岡野 憲司 准教授
-
発生工学
日下部 りえ 准教授
-
微生物制御工学
佐々木 美穂 准教授
-
植物細胞生物学
安原 裕紀 准教授
-
生命機能工学
山口 賀章 准教授
- 2023年度に開講する博士課程前期課程の研究領域および研究指導教員を掲載しています。
生命・医薬
生命活動の根幹を担う生体分子、特に物質代謝、エネルギー代謝を支える酵素の機能、構造、触媒機能や応用について酵素科学および酵素工学的手法を用いて研究する。アミノ酸代謝関連酵素および補講素含有型酵素などを主な対象とし、多機能性生体触媒の基質認識並びに触媒機能を支える立体構造と、これらの情報に基づくタンパク質工学的研究を行う。また、工業的に有用な反応を触媒する新規酵素の探索とその応用研究や食品中のD-アミノ酸などの機能性物質の探索とその生合成機構の解明や応用研究を行う。
高次神経機能を司る神経細胞に関わるタンパク質を研究対象とする。神経細胞における細胞内情報伝達機構を生化学、分子生物学、細胞生物学的に探究する。特に、神経細胞の分化誘導や生存維持(アポトーシス防御)に働く神経成長因子(NGF)などの作用機構を、酵母two-hybrid systemによるタンパク質-タンパク質間相互作用解析や、培養動物細胞を使った細胞工学的手法を用いて分子レベルで解明する。さらに、小胞体ストレス誘導によるアポトーシスとその防御の細胞内情報伝達機構、環境汚染化学物質の神経細胞に対する影響とその防御機構、神経細胞の分化(突起伸長)に関わるエピジェネティックな遺伝子発現調節機構等の研究を行う。
微生物は我々の社会生活に貢献する各種有用物質、抗生物質や抗がん剤をはじめとする医薬品及びそれらのリード化合物の生産者として産業上重要な役割を果たしている。当研究室では、遺伝子工学的手法を用いた産業上重要な微生物の改良研究や、次世代DNAシークエンス技術によってもたらされる膨大な環境微生物遺伝資源から、新規な有用生理活性物質の生産に関与する遺伝子群を探し出し、最新の遺伝子工学技術を駆使して、これら未開拓の遺伝資源を効率的かつ直接的に物質生産すなわち産業応用に結び付けることを目指した研究を行う。また、酵素学的、遺伝子工学的手法を用いた各種有用生理活性物質の生合成研究を通して得られる知見を応用し、天然には存在しない新しい生理活性物質の創生にも挑戦する。これらの研究活動を通して、当該分野の多様な技術の習得だけでなく課題解決能力も養う。
医薬品や化粧品原料となることが期待される生理活性物質の探索や薬剤の創生を目指した研究を行っている。薬理学や分子生物学的な手法と有機化学や天然物化学の手法を駆使して、分子標的抗がん剤、遺伝子治療用製剤、美白剤を含むメラニン産生制御剤そして脳神経疾患の改善を期待した薬剤の開発を行っている。
医薬品や化粧品原料となることが期待される生理活性物質の探索や薬剤の創製を目指した研究を行っている。薬理学や分子生物学的な手法と有機化学や天然物化学の手法を駆使して、医薬品、化粧品、機能性食品などのシーズの開発を行っている。
生命機能工学
山口 賀章 准教授
yama![]()
様々な疫学研究から、シフトワークは生活習慣病の高リスクになることが示されてきたが、実践的な対処法は見出されていない。当研究室では、このような24時間社会の弊害に対処するため、概日リズムの中枢部位である視交叉上核をターゲットとして、概日リズムの分子神経機構の解明や、概日リズムの周期の長さや明暗等の外部環境への同期能を調節する化合物の開発や生理活性物質の同定に取り組んでいる。
高等植物の形態形成機構すなわち、どのようにして植物の形が決まるのかを明らかにし、これを作物の増産に結びつけることを目標に研究を行っている。植物細胞は動物細胞と異なり、細胞が堅い細胞壁に覆われている。そのため、隣接する細胞との位置関係は基本的にこの細胞壁によって固定されており、動物の胚発生過程で見られるような細胞同士の位置関係のダイナミックな変化は起こらない。したがって、植物の形ができ上がって行くとき、どのように細胞が分裂するのかと、新たにできた細胞がどのような形になるのか(細胞形態形成)が非常に重要である。微小管やアクチン繊維に代表される細胞骨格は、細胞分裂と細胞形態形成にきわめて重要な働きをしている。そこで、それらの働きを制御する多様な細胞骨格関連タンパク質の機能に注目して研究を行っている。
発生工学
日下部 りえ 准教授
kusakabe![]()
受精卵からさまざまな臓器を備えた個体ができあがるプロセスに注目し、メダカなどの魚類を使って研究する。魚の初期発生における遺伝子の発現調節機構を明らかにし、疾患メカニズムの解明やドラッグディスカバリー、新たな疾患マーカーの検索を目指す。また食料としての魚類の系統作成や資源枯渇問題にもアプローチする。
環境
地球上には多くの微生物が生息しており、これらはさまざまな能力を持つ。その能力は、環境浄化、食品、医薬品、化成品など、幅広い分野で活用可能である。本研究室では、土壌・海洋・河川などの多様な環境から有用微生物を探索・分離し、分離した微生物の遺伝情報を解析している。さらに、得られた遺伝情報を基に、環境浄化や物質生産を目的とした微生物育種を進めている。加えて、環境微生物の機能を詳細に解明するための解析ツール開発にも取り組み、微生物の潜在能力を最大限に引き出す技術の確立を目指している。
微生物の機能を理解し、有用手物質を効率的に生産させる以下の研究を行っている。(1) プロバイオティクスとしても有用な乳酸菌を従来よりも一桁高い濃度まで培養する研究。(2) 乳酸菌に免疫賦活効果をもつ多糖を高効率に生産させる研究。(3) セルロースからのバイオエタノール生産において律速となる酵素糖化を効率化する研究。
生態系の分解者である微生物は、様々な酵素を利用して地球環境の浄化に寄与している。我々の研究室では、微生物がもつ未知なる環境浄化能を見出すと共にその効率的活用法の開発を目指している。その中で、(1)環境汚染物質分解菌の単離やその分解に関与する酵素群の取得、さらにそれら遺伝情報の解析を行っている。また、(2)このような微生物の機能は不安定で、遺伝情報の伝播も観察されるため、遺伝情報の変化の仕組みについても解析している。(3)環境中の微生物の中にはヒトの健康を脅かすものも知られているため、微生物の生長をコントロールする手法(微生物制御技術)の開発も行っている。この研究は環境分野のみならず、医療や食品製造分野にも活用できる技術である。さらに、(4)微細藻類や真菌類を活用したバイオエネルギー生産やバイオマス利用に関する研究も始めている。
私たちの腸内には多種多様な腸内細菌が腸内細菌叢を形成して共生している。腸内細菌叢は宿主の健康に大きく影響するため、腸内細菌と宿主との相互作用の理解や有用細菌による腸内環境のコントロールは重要な課題である。そこで(1)腸内細菌や有用細菌、その生産物の膜小胞がもつ生理活性の発見と理解、(2)機能性食品や医薬品に応用可能な膜小胞の開発を通して、ヒトの健康の維持・増進に貢献する研究を進めている。
抗菌・殺菌技術は様々な分野で利用されているが、対象となる有害微生物の種類や適用範囲は異なる。メタゲノム解析手法を活用した評価系を用いて、新規化合物・素材の効果を検証していくとともに、微生物の薬剤耐性獲得やバイオフィルム形成などのメカニズムを解明し、それらを適切に制御するための新たな抗菌・殺菌技術の開発をめざしている。また、有用微生物を物質生産や環境浄化に応用するための研究も行っている。
お酒造り(エタノール発酵)やアミノ酸発酵に代表されるように、微生物が産生する化合物は人類の豊かな生活に欠かせない。これらの化合物は「代謝」と呼ばれる微生物細胞内の一連の化学反応によって生産される。この「代謝」反応を遺伝子工学の技術を用いて人為的に改変することで、代謝物の増産や、微生物が元来生産しない化成品や燃料、医薬品原料の生産を目指す。また、微生物の集合体である微生物菌叢は単一の微生物では成し得ないような高度な機能を発揮することがある。微生物菌叢の構成員や機能を自在に改変する技術を開発することで、腸内細菌叢の健康促進機能や、土壌細菌叢の作物成長促進機能の強化に貢献する。
食品
研究分野としての食品・栄養化学は微生物やDNAに代表される「バイオ」とは一線を画している。論文指導では、食と健康に関連したテーマを選択させており、特に必須微量ミネラルのセレンや亜鉛等の食品中含有量や存在形態、脂質の機能解析と酸化の防止、水産廃棄物の有効利用に焦点をあて、ミネラルと脂質の機能解析と栄養有効性について学ばせている。講義・ゼミナールにおいても、食と健康の関連を採り上げており、周辺科学である疫学、統計学、動物栄養試験、食文化についても解説している。
私達の日々の生活に欠かせない「食品」を研究対象としている。論文指導では、食と健康に関連したテーマを選択させており、食品を構成する成分であるタンパク質、脂質、ミネラルを研究対象とし、これらの健康機能の解析、機能発現機序解明、栄養有効性の評価について学ばせている。また、食品の低温での熟成・貯蔵中の風味やテクスチャーの変化に関する研究も行っている。講義では、食品の保存時に起こる栄養成分の化学構造の変化を中心に解説している。