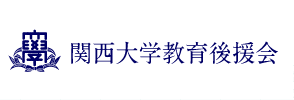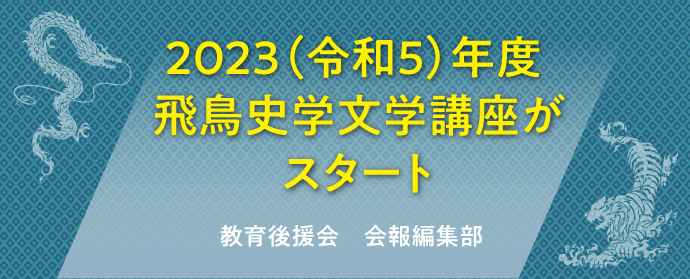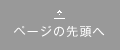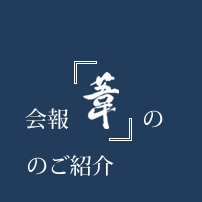関西大学飛鳥文化研究所と奈良県明日香村との共催で1975(昭和50)年から開催している「飛鳥史学文学講座」が、今年度も4月より始まりました。故網干善教名誉教授らによる高松塚古墳の世紀の発見を記念して創設された本講座は、今年で49年目を迎え、今や日本で有数の歴史文化講座となっています。今回は、第1講から第4講までの様子をお伝えいたします。
飛鳥史学文学講座に関する情報は、こちらでご案内しています。
4/16(日) 開講式・記念植樹


49年目を迎えた公開講座の開講式を実施
2023(令和5)年4月16日(日)、奈良県・明日香村の中央公民館にて「飛鳥史学文学講座開講式」が行われ、明日香村村長森川裕一氏、芝井敬司理事長、前田裕学長らが挨拶をしました。「飛鳥史学文学講座」は関西大学教育後援会が主催する公開講座で、今年で49年目を迎えました。シニア層を中心に根強い人気を誇り、これまでに延べ約11万人が受講しています。
明日香村に記念樹を寄贈
つながりはより強固に
開講式の前には「明日香村役場新庁舎竣工記念植樹式」が執り行われ、関西大学千寿会(関西大学教育後援会役員OB・OGの会)と関西大学飛鳥史学文学講座振興会から「ヤマザクラ」と「クロマツ」を明日香村へ寄贈しました。
関西大学と明日香村は、1972(昭和47)年、考古学史上最大の発見とされる高松塚古墳壁画の発見からつながりを深めており、2006(平成18)年に「地域連携に関する協定」、2020(令和2)年には「学術・文化交流に関する覚書」を締結しています。今回の式典を通じて、明日香村と関西大学の関係はより緊密なものとなりました。
4/16(日) 第1講 陵墓にみる律令国家のすがた
─藤原不比等の描いたこの国のかたち─ 関西大学文学部 教授 米田文孝
陵墓に残された情報から、治世者の志を考える
今回の講義で米田教授は、国号が倭国から日本へ、大王から天皇へと変わった時代における陵墓(皇室関係の墓所)に焦点を当てて講演しました。隣国・唐王朝との関係が日本史に何をもたらしたのか、現代にどのようにつながっているのかなどについて検証していきました。
飛鳥時代後期から聖武天皇の即位に至るまでの6世紀後半から7世紀前半、特に藤原京から平城京へ遷都する予定の時代を中心に講演されました。
まず日本のお墓の話として、明日香村の天武・持統天皇陵などの測量図、現況などを例示しながら、そこに込められた意味、政治的な背景、唐王朝の影響などについて、一般的な解釈と米田教授の見解とを交えて紹介されました。
さらに女帝・元明天皇に至る急激な変化の中で、藤原不比等に代表される政治家はこの国の未来をどのように描いていたのかを検証していきました。
米田教授は、藤原不比等が活躍した30年間は決して順風満帆なものではなく、現代の政治家と同じように悩み苦しみ、歴史の螺旋階段は地続きであったことが感じられると締めくくりました。

5/14(日) 第2講 歌物語としての『古事記』下巻
─歌物語最終章 清寧・顕宗条─ 関西大学文学部 教授・なにわ大阪研究センター長 乾善彦
ウタの用法の特異性から、編者の意図に思いを馳せる
今回の講義は、2021(令和3)年度から続く「歌物語としての『古事記』下巻」シリーズの最終回となりました。2021(令和3)年度の「雄略天皇条」、2022(令和4)年度の「仁徳天皇条」、そして今回の「清寧・顕宗条」をもって『古事記』のウタの引用がなくなります。
乾教授は、雄略天皇条からのあらすじを振り返り、雄略に父親(市辺之忍歯別王)を殺害された二人の皇子(顕宗、仁賢)が、皇位を継承していく物語を解説しました。そして、ここで使われているウタが、他の歌謡の表記に用いられる「一字一音」でもなく、「漢文的」でもなく、万葉集に見られるような「音訓交用」に近いものであり、『古事記』のなかでは極めて異例の表記になっていることに注目しました。この特徴は、同じ場面が描かれている『日本書紀』と『播磨国風土記』にも見られ「二王子の出現」の伝承に対する何らかの共通意識があったことがうかがえることを解説しました。
また、雄略の「悪」と二王子の「善」を対比させる歌物語としての魅力にも触れ、講義を締めくくりました。
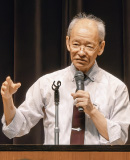
6/11(日) 第3講 万葉人と大海原Ⅱ
─大和から海のかなたへ─ 作家・関西大学客員教授 玉岡かおる
海洋国家・日本の航海術、海の文化を紐解く
第3講は、2021(令和3)年に上梓した『帆神─北前船を馳せた男・工楽松右衛門─』で第41回新田次郎文学賞と第16回舟橋聖一文学賞を受賞した玉岡かおる客員教授が登壇。「帆」を改良し江戸中期に画期的な航海術を生み出した工楽松右衛門の物語を描くにあたり、日本の航海文化を調べた経験には多くの発見があったといいます。
日本では、弥生時代には木を組み合わせた「準構造船」が生まれていたことが銅鐸に描かれた絵によってわかります。時代が下ると、遣隋使は奈良から難波津へ、大和川を使って小舟で荷物を運び、瀬戸内海から関門海峡を越えて隋をめざしました。瀬戸内海は島が多く、かつ鳴門や来島など潮の流れが急な海峡があり操船に苦労したはず。それは壇ノ浦の戦いの顛末や豊臣秀吉が関門海峡で難破した史実などからも垣間見えます。従って『古事記』に描かれた神武天皇の東征も海のルートは苦難に満ちたものだったのでは、との推理が働きます。ほかにも、住吉大社と航海の文化、シルクロードの海のルートなど、小説家としての想像力を駆使して自在に語る講義となりました。

7/9(日) 第4講 飛鳥で最後の王墓群
─持統天皇と中尾山古墳・高松塚古墳─ 関西大学文学部 非常勤講師 今尾文昭
王墓の形や立地の違いから、浮かび上がる歴史
明日香村の中尾山古墳と高松塚古墳は200メートルほどの距離にあり、規模や時期も近しいものです。しかし、墳形や立地が異なります。なぜでしょうか?
中尾山古墳と高松塚古墳は、藤原宮跡から真南に列なる王墓群にあり、該当エリアに点在する古墳は二つに大別できます。ひとつは、丘陵尾根の頂上の選地。次に、尾根の斜面を成形して谷に向かう選地です。中尾山古墳は前者で丘陵の天辺にあり、高松塚古墳は後者で斜面にあります。この違いは「天皇と臣下の格差」と考えられます。中尾山古墳を天武天皇の直系の孫である文部天皇陵としたとき、高松塚古墳に葬られたのは文武天皇の治世で「知太政官事」として王権を分掌した刑部親王が最有力でしょう。忍壁皇子とも呼ばれる刑部親王は、天武天皇の子であり、文武天皇の叔父にあたります。
685(天武14)年の皇親冠位制により、皇族に位階が授けられて序列がつくられたことや、天武天皇の皇后である持統天皇が実子の草壁皇子の子である文武天皇を天皇に推した経緯などにも触れながら、王墓の謎に迫りました。