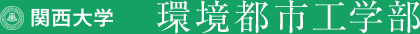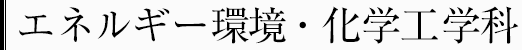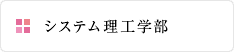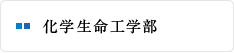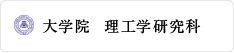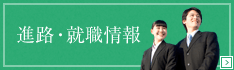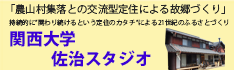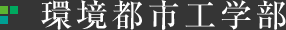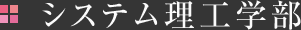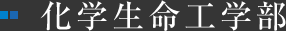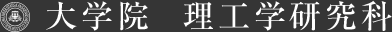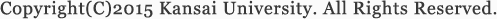やがて石油の供給不足が現実になるといわれ、地球環境の悪化も進行しています。これ以上の環境破壊を食い止め人類の持続的発展を維持するためには、今とは異なる新しいエネルギー体系を構築することが求められています。深刻化する地球温暖化問題に対しては、二酸化炭素の排出を最小化して、低炭素社会を構築する必要があります。そのためには省エネルギーの推進と既存エネルギーの変換効率の飛躍的向上に加えて、太陽光、風力、バイオマス、廃棄物や水素などの新エネルギーを利用する技術開発を進めていくことが重要です。本学科では、省エネルギーや新エネルギー、環境修復、環境汚染防止など、エネルギーと環境を見据えた科目を配置。1年次から多くの実験・演習を課し、身に付けた実践的な知識・技術を生かして環境負荷の少ない新システムを構築できる人材を育成します。
学びのスタイル


分離システム工学研究室
博士課程前期課程 1年次生
⽚⼭ 元貴
研究テーマ
CO2分離回収技術の開発




火力発電所や工場から排出されるガスから、地球温暖化の主な原因となる二酸化炭素を分離する技術の効率化に取り組んでおり、metal-organic framework(MOF)と呼ばれる多孔質材料を研究しています。MOFは既存の多孔質材料には見られない機構に基づくガス吸着挙動を示し、二酸化炭素を選択的に分離できる可能性を秘めています。MOFは比較的新しい素材で、社会に流通させるには合成コスト面などの課題があり、現在はより低コストで合成できる方法を探っています。また、MOFはそのままだと粉状の物質のため、最終的には膜状に加工し、分子をふるい分ける「膜分離」と呼ばれる分離技術に応用することが目標です。研究は常にトライアンドエラーの連続です。この研究を通じて、失敗を恐れず、常に新たな可能性を探りながらチャレンジする精神力が身に付いたと感じています。
この学科を選んだ理由
高校生のころ、地球温暖化による気候変動、生態系の破壊などの問題に触れて、「このままじゃダメだ」と危機感を覚えたことがきっかけです。解決に貢献する力を身に付けたいと思い、環境問題とその解決方法をエネルギーという観点も含めて学べる点にひかれ、本学科を志望しました。
将来の目標
大学院で研究を継続して取り組み、MOFによる膜分離を確立させたいと考えています。また、学会発表や共同研究などの意見交流を通じて、さらに専門知識を深めながら、視野を広げていきたいです。
「答えが見つかっていない問い」へのアプローチを通して、社会に新たな価値を創出する
分離技術は、化学産業やエネルギー産業を支える極めて重要な基盤技術です。さらなる技術革新のため、日々議論しながら研究に取り組んでいます。「予想通りにいかない」結果の中にこそ、これまでの常識を覆す考え方が存在し、新たな価値を生み出すきっかけになります。ぜひ共に、研究を通してより良い未来づくりに取り組みましょう!


エネルギー環境・化学工学科
⽥中 俊輔 教授
- ※この学びのスタイルは2023年度のものです。
学びのキーワード
【新エネルギー】
【リサイクル】
【環境保全】
取得できる資格
所定単位を修得すると資格を取得できるもの
中学校教諭一種免許状〔理科〕
高等学校教諭一種免許状〔理科・工業〕
司書、司書教諭、学芸員、毒物劇物取扱責任者
所定単位を修得すると在学時から受験資格が得られるもの
甲種危険物取扱者
卒業時に受験資格が得られるもの
甲種消防設備士
受験できる資格
公害防止管理者
高圧ガス製造保安責任者
放射線取扱主任者
環境計量士