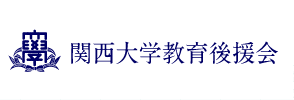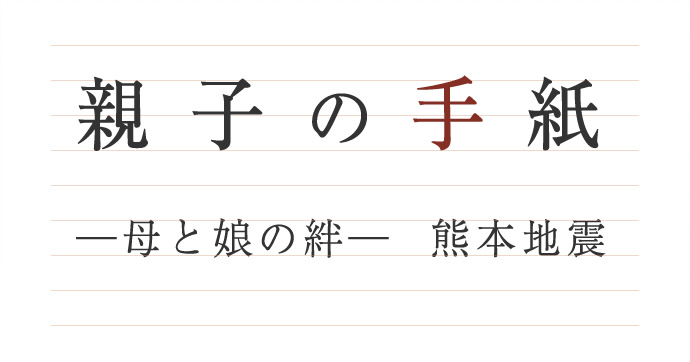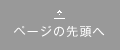教育後援会では、このたびの熊本地震で、震度5以上の地域にお住まいの会員の方々全員にお見舞いの手紙を送りました。そのやりとりの中で一通の手紙が寄せられました。熊本に住む母親から本学3年次生の娘に宛てた手紙で、後援会の総会で紹介され、会場に詰めた6千人近い保護者の心に大きく響いたようです。今号ではその手紙の全文を紹介するとともに、娘が地震発生後帰郷した際に記録したルポを合わせて紹介します。母と娘の絆がうかがえる「親子の手紙」です。

私を力づけた母の4文字
![]()

平成26年4月、私は大学進学を機に熊本市を離れ大阪で生活を始めた。それから約2年後、平成28年4月14日。その日から、私の家族は「被災者」、そして私の育った大好きなその場所は「被災地」と呼ばれるようになった。
4月14日、午後9時30分。母から電話がかかっていたが、タイミングが悪く出ることができなかった。こちらから何度かけなおしても、電話はつながらない。時間をおいてかけなおそう、と何気なく開いたYahoo!ニュースのトップを見て鳥肌が立った。「熊本で震度7の強い揺れ」。
母は、あの強い揺れの中、震源地が熊本とはまだ知らないまま、自分たちのことより大阪に住む私の安否を気づかって連絡してくれたのだった。5分後、ようやく返信が。「大丈夫だよ。」その文字を見て私は安堵のあまり、道路の端にしゃがみこんで泣いた。
その晩母と祖父母は、近くの中学校で夜を過ごした。「なんかー、こんな、現実、やっぱり、ありだった」スマホの液晶越しの母の言葉と、テレビに映る崩れた熊本城。これが現実なのだと受け止められず、何もできない自分は無力だった。
何から手をつけたら…
夜が明けた15日の昼、家族は片付けにとりかかった。「何から手を付けたらいいのかわからない」と母のメール。余震も続くので、怖くて寝室では眠れないので廊下で寝る、と電話があり、それから1時間もしない間に本震が襲った。
4月16日、午前1時25分。しばらくの間電話が全くつながらず、私は最悪の事態を予想した。父は後で「本震の揺れの中で、人ってこんな風に死んでいくんだなあと思った」と、死を意識したことを教えてくれた。避難所へ向かう途中、再び強い揺れに襲われ、電線はバチバチと火花をあげ、近所の家の瓦はごろごろと落ちてきたそうだ。
避難所ではパニック状態で、声を荒げる人もいたという。揺れの恐怖に加え、そのように怒鳴り散らす人がいたことも怖かった、と母はいう。しかしながら、中学校の校長先生のしっかりとした陣頭指揮で少しは不安が和らいだ。
メールで「わかった」
午前4時28分。私はメッセージを送った。「なにがあっても絶対生き抜く約束だよ」。短いメールが返ってきた。「わかった」。わずか4文字がどんなに私を力づけてくれたことか。
自宅はヒビや穴こそ開いていたが、倒壊は免れた。寝室の家具はほとんど倒れており、尚且つ押入れの扉も外れて倒れた。母がもし廊下ではなく寝室で寝ていたら、とぞっとした。食器棚の突っ張り棒は天井を突き抜けた。
ガス、水は止まったが、幸い自宅は停電を免れ、前震の際にお風呂に水をためていたこと、非常用の水を用意していたこと、食料が少しあったこともあり家族は一切配給を受けなかった。避難所では、水が一人80㏄とお年寄りや子供優先でおにぎり、もしくはパンが二人で一つという状況だったという。
被害の大きかった益城や阿蘇のほうに物資が優先され、ほかの地域には物資の到着が遅れていたのである。人口に対しての物資の量が少なすぎていた。後日、阿蘇に住む祖父の姉から聞いた話だと、比較的被害が少なかった地域であることもあってか、阿蘇のほうは水も食料もあまり困らなかったそうだ。

早く安心
19日の午後、私は大阪を発った。自分にできることを少しでもしたかったから、と言いながらも傷ついた家族のことが心配でたまらなかった。早く顔を見て、自分が安心したいという気持ちのほうが強かった。「帰ってくるなら、自分たちの食料は自分たちで用意して来い」と、父に言われ、帰る覚悟を決めた。そして20日の午後1時過ぎ、熊本に着いた。電車の景色が、熊本市内に近付くにつれて痛々しくなる。倒れてしまったビニールハウス。半壊の民家。変わり果てた故郷の姿に目を覆いたくなった。「本当に被災地、なんだね」。妹が隣でそう呟いた。それまでどこか心の奥でこんなの現実なんかじゃない、そんなわけないと拒み続けた現実がそこにはあった。
「こぎゃん危なかとこに」
「ああ、本当に帰ってきたとね、なんで…」自宅に着くと、祖母はそう言って私と妹を出迎えた。「なんでこぎゃん危なかとこに」と言いながらもどこか安堵の表情を浮かべていた。
避難所ではコミュニティができ、夜寝るために教室へ戻ると「おかえりなさい」朝、自宅へ戻るときは「いってらっしゃい」という挨拶が生まれた。避難所の教室には、倒壊したマンションに住んでいた人もいたそうだ。命からがら逃げてきた、という話を聞いた。立ち入りができないので、荷物を取りに帰ることもできないという。
21日、余震も落ち着いてきたので自宅で眠ることになり、教室に置いていた毛布を取りに行った際、おじいさんに声をかけられた。「住むところが見つかったとですか?」と。自宅で過ごすということを伝えると、どこかさみしそうな表情で「また、何かあったらいつでもどうぞ」と言ってくれた。わずかな期間ではあったが、同じ恐怖を乗り越えた人々の間で絆が生まれていた。
恵みの雨

中学校も断水状態であり、飲み水だけでなく生活用水も足りない状態であった。一番困ったのはトイレ。本震後の豪雨で仮設トイレが吹き飛ばされたのである。校舎のトイレは流れないので、使うことができない。17日の夜も大雨が降った。夜中、祖母がトイレに行ったきりなかなか帰らない。母が心配して様子を見に行くと、そこには大雨の中バケツや水が溜まる容器を外に運び出す祖母の姿があった。後から祖母に話を聞くと、雨が降らなかったらもっと早く水が底をついていたかもしれなかった、と話してくれた。土砂災害や河川の増水を危惧された雨は、ある意味で恵みの雨でもあった。
授業のため大阪に戻る日、気分転換に散歩に行こう、と母と外に出た。散歩といえば熊本城が定番であった。自宅から熊本城まで徒歩約10分。熊本城へ向かういつもの道は封鎖されていた。当たり前にそこに立っていた熊本城や熊本大神宮が、今は痛々しい姿をさらしていた。言葉が出なかった。今も心の奥でこれは何かの間違いではないかと思うことがあるそうだ。
しかし、悲しいことに熊本で地震が起きたことは事実であり、多くの人が苦しんでいる。起きてしまった事実を受け入れなければ前に進むことはできない。がんばろう熊本、と多くの人が励ましてくれているのは知っている。でも、何を頑張ればいいのかわからない。生きるだけで精いっぱい。「ほんなこつ、サバイバルたい」、と母はおどけて言ったが、その目は悲しみと不安に溢れていた。
ツバメとイチゴ
自宅に戻る途中、ツバメが空を旋回していた。隣のマンションの軒下を除くと、例年と同じ場所に巣を作る親ツバメの姿があった。玄関に置いていたイチゴの鉢植えは、真っ赤な実をつけている。庭のサクランボの木も小ぶりながら赤い実を実らせていた。変わらないものもそこにはあった。
熊本城の再建には10年以上の歳月がかかるそうだ。家族を亡くした人、家を失った人、仕事を失った人…失ったものはどれも大きい。何年、何十年かかってでも熊本が元の姿を取り戻すまで、私は自分ができること少しずつでも行っていきたい。
私は1年前、神戸市長田区の靴メーカーや大丸百貨店と共同で、はきやすい婦人靴を製作し大丸の全国9店舗で売り出すというゼミ活動に参加した。この時、靴の街と呼ばれた長田区は阪神淡路大震災で大きな被害を受け、20年たった今でも、震災前の生産量には戻れていないことを知った。復興には実に長い時間とたくさんのお金がかかるのだ。
私は関西大学で学び続ける。大好きな熊本に寄り添い貢献するためだ。必ず復興の日は来る、と信じているからだ。
(政策創造学部3年次生)