- トップ
- 教員が語る専門領域の魅力
- 教員が語る専門領域の魅力 vol.4
高橋 秀彰 教授
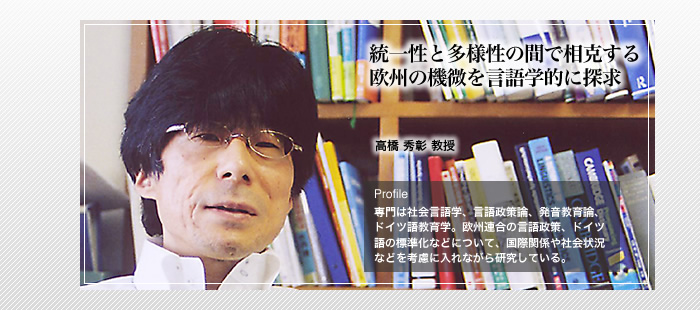
欧州連合(European Union, EU)
EUは27の加盟国(2009年2月現在)を擁する巨大な共同体で、地理的に見ると東部は旧ソ連邦に接しています。多様性を旨とするEUは、加盟国の平等を根本原則にしており、EU公用語は23言語にもなります。

ゲーテとシーラの像(ワイマール)
ドイツ語

大聖堂(ケルン)

木組みの家(フランクフルト)
欧州でも英語を使用する人が増えていますが、「母語+2言語」の計3言語を習得しようという運動が展開されています。誰もが英語しか学ばないようなことになると、多様な言語・文化から成り立っているEUの存立基盤が揺らいでしまうからです。また、英語以外の言語を軽んじたりすれば、EU内で不平等が生じ、社会的な結束が脅かされることにもなりかねません。さらに、外国語を学ぶ機会に恵まれないことで不利益を蒙らないように、外国語を学ぶことは大切な権利とも考えられています。これは「複言語主義」(plurilingualism)により保障され、誰もが必要に応じて、生涯にわたって多くの言語でコミュニケーション能力を発展させる権利があるされています。
功利主義的な物の見方が幅を利かせている今日のグローバル化世界では、人の人生には経済的損得以外にも大切なことがあるということを忘れてはなりません。言語は単なる道具ではなく、人間性の本質に根ざしたものです。他者と情報や気持ちなどを共有すると言う意味でのコミュニケーションは、人間として最も大切な活動であり、そこでは言語がとても大きな役割を果たしています。もちろん英語が大切な言語であることは言うまでもありません。しかし、英語以外の言語圏の文化や社会にも目を向けないと、英語圏諸国ですら相対的な視野で理解することが難しくなってしまいます。欧州に関心がある人は、ドイツ語を学んで自分の中に新しい窓を作ってみませんか。
学生のみなさんへのメッセージ
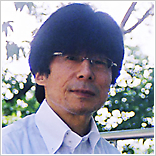
あなたは大学での生活を通じて何を学びたいですか。世の中の仕組み、人の心、愛、学問など、学びたいことはたくさんありますね。いろんなことを学ぶ上で、自分がどんな能力を持っていて、どこまでその能力を伸ばすことができるのか、知りたいと思いませんか。今の時点で、自分が得意なことと不得意なことを、自分なりにある程度はわかっているかもしれません。でも、どんな領域であっても、その活動を精一杯がんばって、とことん深めなければ、あなたの潜在力が芽生えることはありませんし、本当に向いているのかはわからないものです。多くのことを幅広く見ることはもちろん大切ですが、何か没頭できるものも必ず持ってほしいと思います。忍耐を持ってどこまで深めることができるか試し、新しい自分が見つけられると素晴らしいですね。あなたのそんな取り組みをサポートするのが大学です。
沈 国威 教授
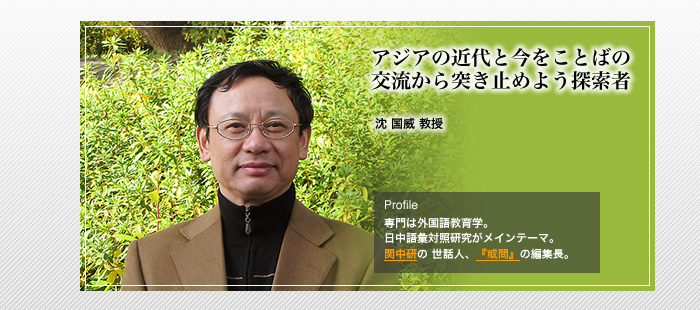
なぜ中国語か

言葉ほど人間社会を根底から特徴づけるものはないと言われています。だから1つの外国語をマスターすることは、日常と異なる風景を眺める窓を開けたことに等しいわけです。その言葉を使う人間社会のあらゆる面−政治、経済、社会、芸術、文学、歴史は言うに及ばず、風俗習慣、衣食住の日常まで知ることができるのです。これこそ外国語を習う醍醐味だぞ、といったら、それは教養としての外国語の時代の話で、このサバイバルの世の中ではまず実用だ、と反論されるかもしれません。就職に強いという理由で中国語を選ぶ人が多いかも知れません。確かに世界の工場としての中国は今後も世界の市場として期待され、日本の経済活動とますます関係を強めていくことでしょう。しかし大学で専門として勉強する以上、プロの目で中国社会を観察できる能力をぜひ身につけて欲しいのです。そのための徹底的なツールとしての中国語の習得をいっしょに目指しましょう。
中国語:漢字を使う外国語
中国語は漢字を使う言葉です。日常的によく用いられる漢字の数は2500字前後と統計的に出ています。日本の新常用漢字表にも2200字近くが収録されているので、楽に勉強できるというわけですが、同じ漢字を使っても、それぞれの風土、そして長い歴史の中で漢字の発音・意味・用法が大きく変容してきました。また文の構造などが日本語と全く違うことは言うまでもありません。中国語は外国語だという意識を強く持って、勉学に臨んで欲しいのです。


学生のみなさんへのメッセージ

熊谷 明泰 教授
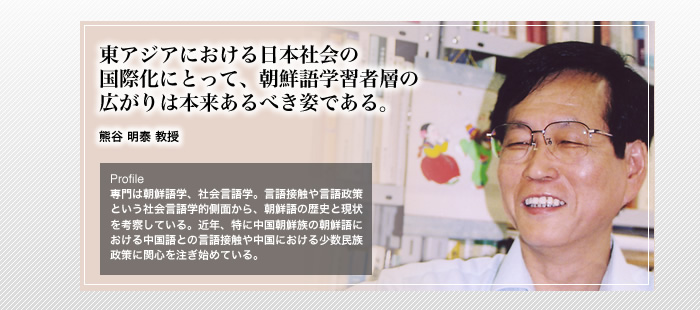
自分の肌に合った外国語との出会い

21世紀に生きる人間として、「国際語」を身に付けるメリットの大きさは自明のことのように思われます。
しかし、高い社会的ステータスを得て、国際的に活躍するための「ツール(道具)」を獲得しようという功利的な発想だけでは、どこか物寂しくはありませんか。最近、中国人として始めて芥川賞を授賞した楊逸(ヤン イー)さんは、対談の中で「私の場合、日本語がわかるようになったことで頭の中に窓が開いた感じで、新しい風景が見えてきた」と語っています。外国語を身につける過程で、自分が生まれ育った文化的環境の枠を乗り越え、「新しい風景」を自由に羽ばたく精神世界を得ることは、功利的な発想を遥かに凌駕する喜びだろうと思います。そして、こうした喜びをもたらす外国語学習は、言語の国際的な強弱を決定付ける経済力や話者数の多寡とは別次元のものです。自分の肌に合った外国語との出会いこそが、人生を楽しく豊かなものにしてくれることでしょう。
これまで芥川賞を受賞した在日朝鮮人作家には、李恢成、李良枝、柳美里、玄月の4人がいますが、受賞は逃したとはいえ、1939年の第10回芥川賞候補になった金史良(キム サリャン)という作家は朝鮮語でも日本語でも創作活動を行いました。
金史良はピョンヤンの学校で反日学生運動に加わり退学処分を受けた1931年に渡日し、旧制佐賀高校、東京帝国大学文学部を卒業したエリートでした。金史良のように日本で学んだ人に限らず、植民地時代(1910年‐1945年)に生きた朝鮮の知識人の大多数は、高度な日本語能力を身に付けていました。それは、朝鮮の人々は日本による植民地統治下で「日本国民」とされ、「国語」として日本語を身に付けざるを得ない状況にあったためです。金史良は解放直前の 1945年春、日本の支配下から脱出し、亡命先の中国で朝鮮義勇軍に加わって抗日独立闘争を戦いました。日本語で文学作品をまとめ上げ、また、多くの学友もいた日本に対して民族解放のための刃を向けねばならなかった引きちぎられた人生を思うと、とても複雑な思いになります。1950年秋、金史良は朝鮮戦争のとき朝鮮人民軍の従軍作家として活動しましたが、米軍からの反攻を受けて退却する道筋で行方不明となりました。
日本語は朝鮮民族一人一人の人生に光と影を残してきました。私は、「国語」や「公用語」なる言語政策がもたらす功罪について、かつて朝鮮総督府が朝鮮で行った「国語」政策、朝鮮語と中国語とのバイリンガルである中国朝鮮族の言語生活、中国における少数民族政策、および朝鮮民主主義人民共和国における言語政策などに関心を持って研究を行っています。
なお、学部専門教育では「基礎演習」、「総合朝鮮語」などを、大学院では「言語政策論」、「地域言語文化論(朝鮮)」などを担当しながら、学生の皆さんと共に東アジアにおける言語と文化の諸問題についての考察を進めています。
伝え合いたい思いがあってこそ、外国語を学ぶ喜びも高まる

かつて、岩国基地の米兵と恋に落ちた日本人女性の悲しい思いを描いた「エド&ユキコ」という詩を読んだことがあります。ベトナムで戦死した恋人を偲びつつ、“でも英語など覚えなければよかった。言葉をよく知らなかったときのほうが、かえって気持が通じ合いました”と回想する一節が記憶に残っています。お互い言葉がよくわからないだけに、なんとしても心を通わせたい切なさゆえ、よりよく相手を感じ取れることがあるのでしょう。外国語を学ぶとき、自分の思いを伝えたい対象があればこそ、単語の一つ一つ、会話文の一つ一つに、日々、心ときめく思いで接していけるに違いありません。その一方で、外国語が流暢になればなるほど、肌身で相手を理解しようとする繊細な感覚を失っていくこともあるという悲しい事実にも気付かざるを得ません。


「冬ソナ」でピークに達した「韓流」ブームは、愛を伝える言葉が朝鮮語に乗って日本社会に流れ込んだ点において、画期的でした。しとやかな日本的愛情表現ではなく、かなり押しが強いともいえる韓国人社会の愛情表現が新鮮に映り、日本女性を魅了したのかもしれません。昨今、日本と韓国や中国との間では人的交流がとても幅広く行われるようになりました。日本で朝鮮語学習者や中国語学習者の裾野が広がりつつある今日、東アジア社会で日本が国際化を進める上で、本来あるべき姿を実現しつつあるともいえます。
学生のみなさんへのメッセージ
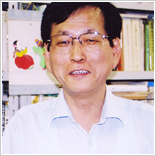
日本に対して、良くも悪しくも最も強い関心を抱いているのは、なんといっても隣国の韓国と中国の人々です。しかし、韓国や中国のような隣国との間では、接触が多いだけにさまざまな歴史的葛藤も抱え持っています。自分は過去の不幸な歴史の時代に生きていないから関係がないという考えは説得力に欠けます。そして、韓国や中国の人々と付き合うとき、過去の歴史がいかに捉えられているかといった事実を理解していない限り、深い信頼関係を築くことは容易ではないでしょう。外国語の学習ではスキルばかりに目を奪われることなく、幅広く相手国の歴史や文化に関心を抱き続けることが大切です。






