Interview no. 18
有権者の限定合理的な行動を踏まえた実用的な投票ルールをデザインする
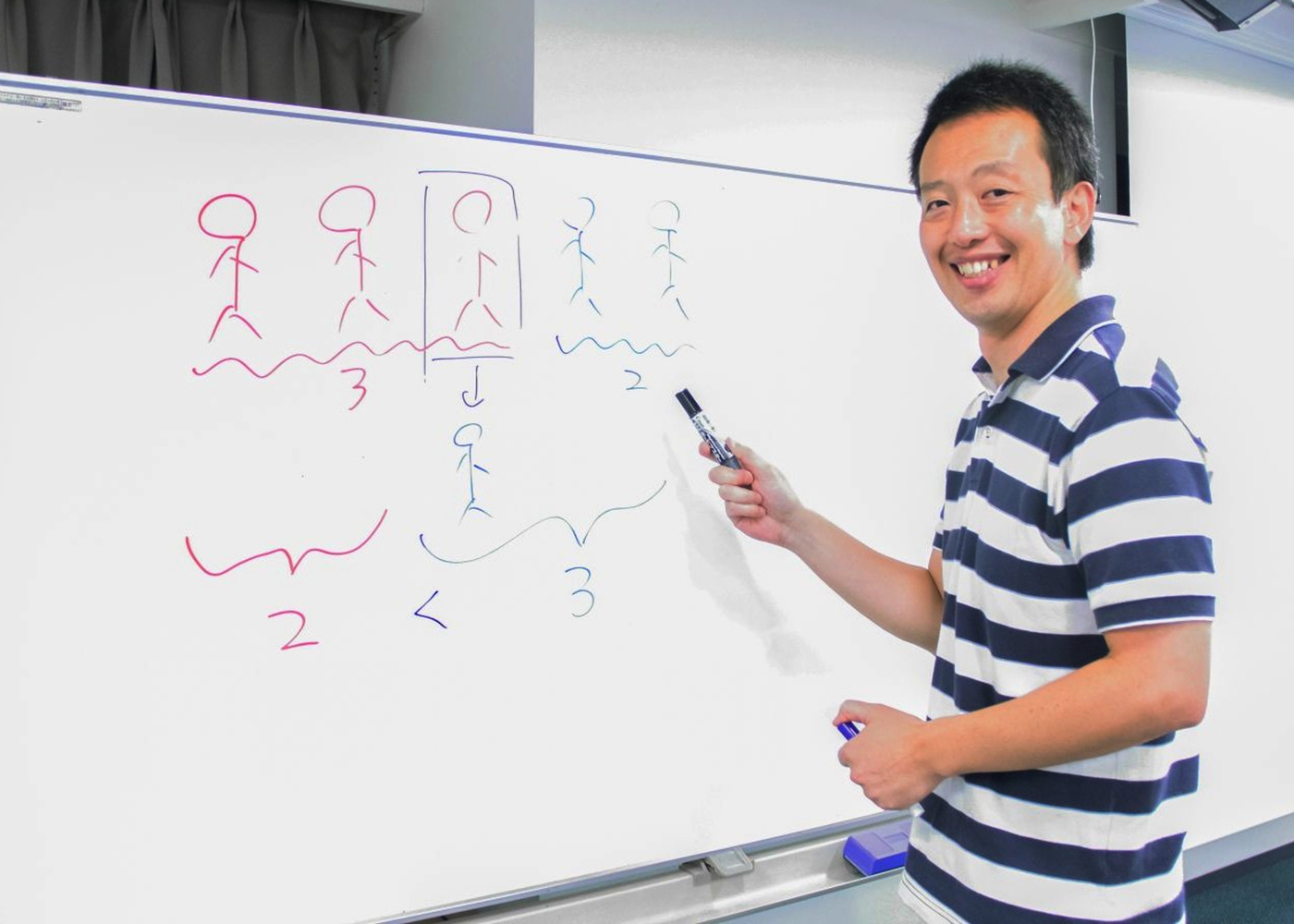
- 西﨑 勝彦
- Nishizaki Katsuhiko
- 桃山学院大学 経済学部 准教授
Chapter 01
常に最適な選択ができるとは限らない有権者を前提として
経済学において、企業や個人の「戦略的な」意思決定を分析する学問といえば「ゲーム理論」です。意思決定すべき場面において「自分の行動が相手にどう影響し、相手の行動が自分にどう影響するか」を考えて、それぞれがいちばん良い選択をした結果、どのような状況が実現するのかをゲーム理論では分析します。
私の専門である「メカニズム・デザイン理論」はゲーム理論の応用分野ですが、ゲーム理論とは逆のアプローチをとります。つまり、ゲーム理論が「すでにあるルールの中で人々がどう行動するか」を分析するのに対し、メカニズム・デザイン理論では、実現したい状況を目標とし、人々がどのようなルールに従えば(メカニズムを設計すれば)皆がバラバラに動いてもその目標を実現できるのかを考えます。例えば選挙において、有権者全体で見ると野党を支持している人たちの方が多いのに、野党の各党が候補者をそれぞれに立てて票が割れた結果、与党の候補者が選ばれてしまうことがあります。では、多くの有権者が支持する野党の候補者を選ぶにはどのような投票ルールで候補者を選べば良いでしょうか。こうしたルールを分析・設計するのがメカニズム・デザイン理論です。
メカニズム・デザイン理論では、基本的に有権者は合理的に判断する(自分が支持する候補者が選ばれるように投票する)ことを前提としていますが、そうとも限らないような事案が発生しました。2016年のアメリカ大統領選挙では、ヒラリー氏が有力視される中、トランプ氏が選ばれる結果になりました。有権者が合理的に判断するならばヒラリー氏が選ばれるはずですが、中には有力視されているヒラリー氏が選ばれることを前提に、現状への不満を表明するべくトランプ氏に投票した有権者が少なからず存在して、そうした“変な”(合理的でない)行動の結果、トランプ氏が選ばれてしまったと指摘する声もありました。それが事実なら、そのように多数派の一部の人たちが変な行動をしたとしてもヒラリー氏が選出されるルールを理論的に導き出せないか、と思い至りました。私がRISSで行った実験では、多数派の人たちは比較的自分の考えに忠実に動き、合理的でない行動を避ける傾向にあることが分かってきました(この実験結果を踏まえると、2016年のアメリカ大統領選挙では、投票前の世論調査で出て来なかった「隠れトランプ支持者」がポイントだったようです)。ならば、多数決という意思決定の仕組みは、概ね問題ないのかもしれません。しかしながら現実には多数決が望ましい結果を生まないことも多いです。ここに、現実と実験結果での齟齬があります。現在は、この齟齬に着目しながら、合理的でない行動の要因を探りつつ、実用的なルールの設計可能性を明らかにすることに取り組んでいます。
Chapter 02
ルールを構築する学問に惹かれて
世の中には、時として社会を大きく動かす「うねり」が見られます。学部生時代にニュースなどを見聞きする中で、社会のうねりを生み出すものに関心をもつようになり、うねりの要因を考えて行くうちに「ルール」が変わることで世の中も変わるのではないか(ルールが社会のうねりを形作る大きな要因ではないか)と考えるようになりました。経済学部で経済学を学んでいた私は、経済学史の授業で制度学派という社会の「制度」に着目して経済活動を分析する一派が存在していたことを知り、これまでの経済学に関する学びを活かしつつ、ルールについてより深く探求できないか文献を漁っていたら、経済学の中に「比較制度分析」という制度を研究対象とする学問分野があることを知りました。比較制度分析は、メカニズム・デザイン理論と同じくゲーム理論の応用分野で、今現在成立している制度をゲーム理論における「均衡」と捉え、なぜそのような制度が成立するに至ったのかを分析します。比較制度分析について学び始めた私は、比較制度分析では「今あるものがなぜそう成り立っているか」をつかむことはできても、そこから先の政策的視点、すなわち「目指したい状況に対し、どのようなルール(制度)を作ればそこに到達できるか」という分析に至らないと感じました。そうした折、大学4年生の夏頃に、「どのような制度を設計するか」を問題意識とするメカニズム・デザイン理論の存在を知り、「私が求めていたのはこれだ」と得心しました。
近代経済学に大きな影響を与えたアルフレッド・マーシャルの有名な言葉に「冷静な頭脳と温かい心」があります。学部生時代にこの言葉に出会い、常に頭の片隅にあったことが、メカニズム・デザイン理論に惹かれた理由のひとつかもしれません。理論的な分析だけでなく、人々の生活に寄り添う心を持ち、現代社会の問題解決に何か役立つことができればと、研究を続けています。

Chapter 03
RISSでのデータ分析の知見を生かす
RISSは本格的な行動実験ができ、また学術的なデータ分析にも定評がある日本では数少ない研究機関です。
日本では社会保障費の負担が問題になっていますが、その負担の在り方については、社会保障費を上げる/消費税を上げる/子育て世帯に関しては助成金を支給しつつ社会保障費を上げる(いわゆる給付とセットにする)など、いくつかのパターンが考えられます。そこで、日本人の特性を活かした受け入れられやすい政策を提案するため、RISSでは関西大学の学生をはじめとした実験参加者に協力してもらい、様々な政策のアイデアを行動実験を通して検証することができます。
加えて、実験参加者にアンケート調査を実施し、その結果とRISSが持つデータアーカイブに結び付けるなどして、行動実験の結果を国レベルにまで一般化できる余地があります。RISSが持つデータ分析の強みを活かし、より実用的なルールの設計に取り組んで行けたらと思っています。

Nishizaki Katsuhiko
Profile
2006年、和歌山大学経済学部卒業。2013年、大阪大学大学院経済学研究科博士後期課程修了。関西大学社会的信頼システム創生センターポストドクトラル・フェロー、桃山学院大学経済学部講師を経て、2020年から桃山学院大学経済学部准教授。博士(経済学)。専攻は「メカニズム・デザイン理論」「社会的選択理論」「実験経済学」。理論的には使えても(望ましくても)現実的には使えない(理論どおり機能しない)メカニズム(制度)の存在が指摘されているが、その使えない原因を行動実験を通して分析している。さらには、その原因も踏まえた新たなメカニズムを模索することで、より実用的なメカニズムの設計可能性を明らかにすることにも取り組んでいる。