Interview no. 17
一人ひとりが納得のいく選択をするために
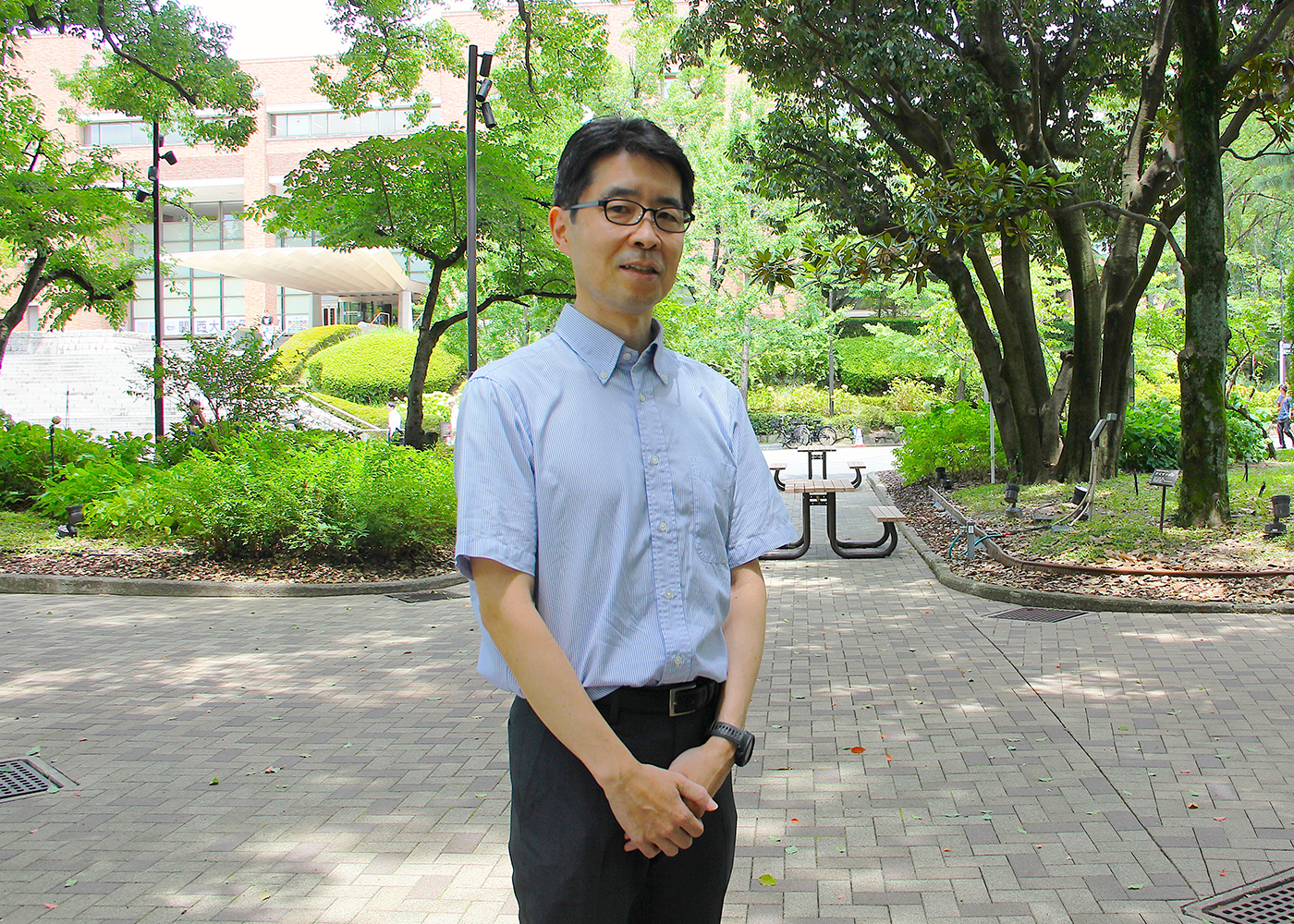
- 本西 泰三
- Motonishi Taizo
- 関西大学経済学部 教授
Chapter 01
一筋縄ではいかない金融教育
私は、効果的な金融教育の実現を目指し、人々の金融行動について分析を行っています。金融行動とは、貯金や投資、貸し借りといったお金に関する意思決定のことです。近年、金融商品の多様化や政府による税制優遇制度の導入に伴い、社会全体で投資に対する意識が高まっており、金融教育は重要性を増しています。
では、どのようにすれば正しい金融知識を身につけられるのでしょうか。企業が開くセミナーに参加したり、金融商品の専門家に相談したりすることも有効かもしれません。でも、彼らは自分たちの商品を売って利益を出したい立場であるかもしれないということも忘れてはいけません。相手の言葉を全面的に信用するのではなく、自分に必要な情報を取捨選択する必要がありますが、これは簡単なことではありません。勉強を始めたばかりの方にお伝えしたいのは、ただ金融知識を身につけるだけでは不十分であるということです。
2021年にRISSの研究者と共同で発表した論文"Is Financial Literacy Dangerous?(金融リテラシーは危険なのか?)"では、一般の方を対象にアンケート調査を行い、金融知識やスキル、好みや信念が金融行動に与える影響を分析したところ、高い金融リテラシーが慎重さを欠く行動を誘発する場合があることがわかりました。金融知識が身につくことによって自信が先走り、自分にとって不利な選択をしてしまう場合もあります。正しい金融行動のためには、投資に関連した多少の専門的な知識が必要な場合もあります。でもそれよりも、取引相手や助言者の思惑を良く見極めたうえで、知識におぼれず冷静に行動することのほうがはるかに大切です。
Chapter 02
心理学と実験が、経済学の可能性を広げる鍵
私自身、高校生の時にアルバイトをはじめ、初めて株式を買いました。現代社会の授業が好きで、新聞をよく読んでいたこともあり、社会の動向を反映する株式に興味を持ちました。大学・大学院では経済学を専攻、当時の研究テーマはマクロ経済学や金融論で、植田和男先生や吉川洋先生のご指導を受けることができ、現実の経済に即した内容に魅了されました。林文夫先生が計量経済学の教科書を書きながら行ってくださった丁寧な授業も大変印象深いものでした。
でも研究者として独立して論文を書くようになると、「合理的な判断を下す人間」をモデルとすることが主流であった当時の経済学界と、自分がイメージする経済との乖離に悩まされました。研究を離れ学内行政に力を入れていた時期もあります。そこには想像とは全く異なる世界が広がっており、人の必ずしも合理的ではない行動に対する関心はさらに強くなりました。それまでの自分の研究の限界を自覚していたものの、心理学を取り入れたり、実際に人間からデータを得る実験を行ったりするようなことには、手が届きませんでした。
変化が生じたのは、RISSとの関わり合いがきっかけでした。心理学の知見を応用した実験が当たり前のように日々行われるRISSの環境に驚いたことを今でも覚えています。ここで様々な分野の研究者から知識やノウハウを学ぶうちに、これまで見過ごしていた「個人の金融行動」がとても興味深く、新たな分析対象となりました。従来の合理的な人間モデルでは、人は自分で正しい答えを選択できるため、人の行動の失敗を詳しく分析する方法がありませんでした。しかし、心理学的な要素を加えることで多様な行動を分析する枠組みが手に入り、新たな政策介入の余地も生まれます。個人の性格や環境が要因となって生まれる様々な行動が分析対象となり、現実に即した納得感のある議論を展開できることに魅力を感じ、次第に研究の主軸がマクロ分野から、個人に焦点を当てるミクロ分野へ移りました。

Chapter 03
一般の人々が適切に判断できる環境
学内行政に携わっていた時期に、大学の地域連携活動を担当していた経験から、RISSでの金融行動の研究を生かして消費者の正しい選択を手助けできないかと考えるようになり、数年前から大阪府堺市の協力を得て、小中学校・高等学校で金融リテラシーに関する出前授業を始めました。現代の子どもたちは、キャッシュレス決済やゲームへの課金などで、インターネットを介して簡単に多額のお金を扱える環境にあります。身近に潜む危険から身を守るために、正しい金融知識を身につけてほしいと考えています。出前授業は、こちらから教えるだけでなく、子どもたちから学ぶ良い機会でもあります。時代の先を行く子どもたちの新鮮な意見は研究にも役立っています。
これまで金融教育に関する研究を中心に行っていますが、「消費者・生活者の選択」をキーワードに、研究を広げています。具体的には、特定保健指導の結果が、人々の行動に与える影響に関する研究などです。さらに、私たちが人生で直面する他の重要な判断にも、これまでの分析手法を応用していければと思います。インターネットには情報があふれ、売り手はSNSなどを通じて、AIも駆使しながら巧みに私たちを誘導してきます。多様な選択肢から自分に合ったものを1つ選ぶだけでも難しい現代で、私たちは情報に対してあまりにも無力です。このような状況でも一人ひとりが適切な判断を下せる環境を作るため、RISSで得た知見をもとに、幅広い研究に取り組んでいきます。
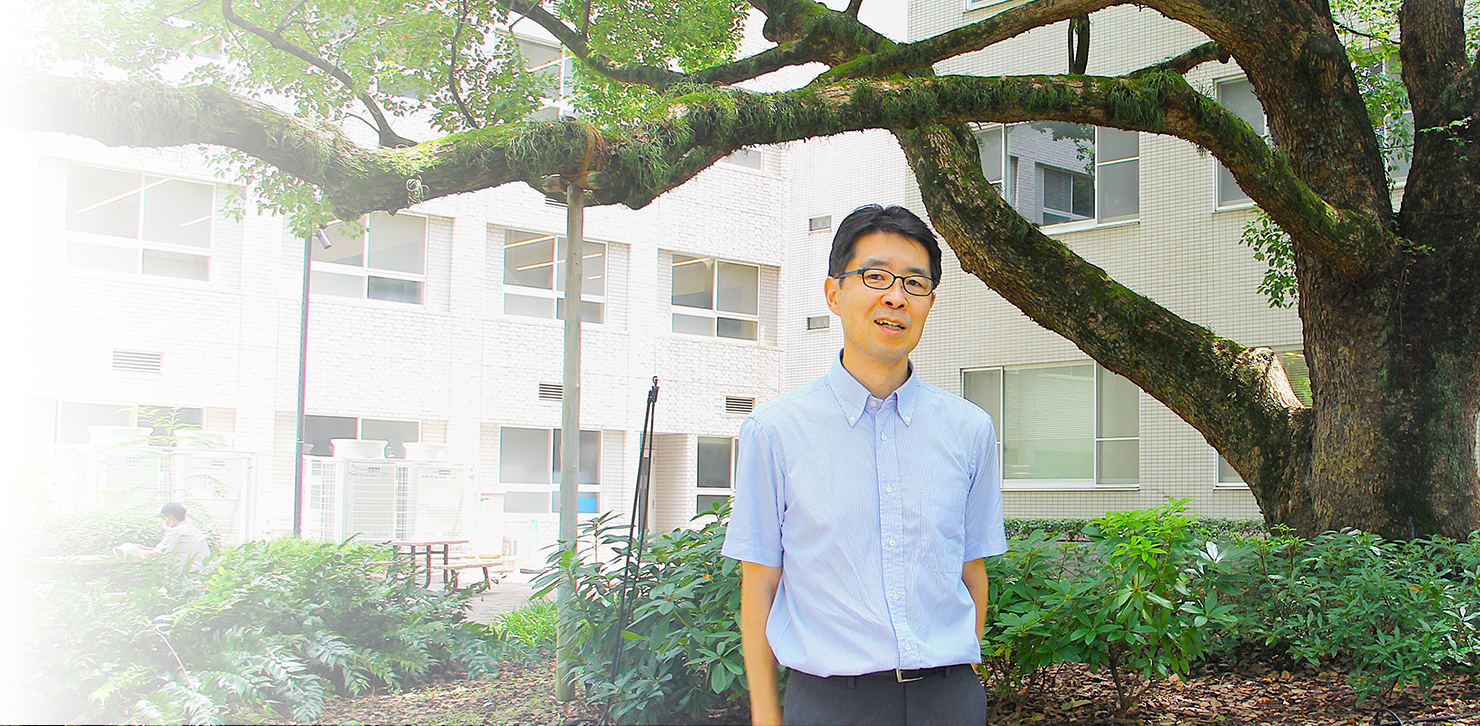
Motonishi Taizo
Profile
博士論文は”Macroeconomic Aspects of Imperfect Financial Markets”(不完全な金融市場のマクロ的側面)。長崎大学経済学部に5年間勤務したのち、2004年に関西大学経済学部に着任。その間アジア開発銀行・北京大学・韓国対外経済政策研究院・豪ラトローブ大学などで為替レート・所得分配などについて研究。2017-2023年 RISS機構長。現在の研究テーマは、消費者の金融行動・保健行動。とりわけ高齢者や若者の行動に関心を持っている。大阪府労働委員会公益委員を務める。