Interview no. 16
さまざまな切り口から集団の意思決定を分析する

- 岡野 芳隆
- Okano Yoshitaka
- 関西大学経済学部 教授
Chapter 01
理論通りの⼈間⾏動を⽬の当たりにした実験
社会⽣活の様々な場⾯で、私たちは他者と話し合い、物事を決めています。皆さんも集団内で⾃分の意思とは異なる選択をした経験があるのではないでしょうか。私は、こうした集団の意思決定に焦点を当て、個⼈の意思決定との違いを明らかにする研究を⾏っています。
経済実験の⼿法を認識したのは⼤学院⽣のときでした。当時、指導教員が⾏う授業で「混合戦略均衡」を調べる実験を⾏うことになり、TA(ティーチング・アシスタント)として準備を任されました。混合戦略とは、各プレイヤーが相⼿に戦略を読まれないよう、都度ランダムに⾏動を選択する戦略です。例えば、じゃんけんでは、グー、チョキ、パーを1/3の確率で均等に出すことが、相⼿に読まれにくい最適な戦略となります。
授業で実施したのは「OʼNeillゲーム」と呼ばれる実験です。このゲームは、2名のプレイヤーが4枚のトランプカードから1枚を同時に出し、そのカードに応じて勝敗が決まるというシンプルなルールに基づいています。しかし、このゲームの混合戦略均衡を導き出すには、複雑な連⽴⽅程式を解く必要があり、現実のプレイヤーがそのような計算を⾏う時間はありません。それにもかかわらず、受講⽣たちは混合戦略均衡に近い⾏動を取っていたことが実験結果から明らかになりました。これまで勉強してきた理論で現実の⼈間⾏動を適切に説明でき、さらに簡単な実験で確認できることに、驚きと強い関⼼を抱いた瞬間でした。
博⼠課程に進んだ頃、OʼNeillゲームに関する興味深い論⽂が発表されました。プロのサッカー選⼿がOʼNeillゲームを⾏うと、⼀般⼈と⽐べてより混合戦略均衡に近い⾏動を取るという内容でした。その論⽂を読み、プロと素⼈の差に注⽬した私は「百戦錬磨のプロは、チームメイトと状況を分析して相⼿に読まれない戦略性を⾝につけてきたのではないか」と推測しました。そこで「素⼈であっても、みんなで⼒を合わせれば混合戦略均衡に近づけるのではないか」という仮説を⽴て、実験を⾏いました。その結果は、おおよそ仮説通りでした。チームで取り組んだほうが混合戦略均衡により近い⾏動をとることが明らかになりました。個⼈と集団で選択の結果が異なることは、他者とのコミュニケーションを通じて個⼈の判断が変化していると⾔えるでしょう。他者の存在が集団としての選択に及ぼす影響をさらに追究するため、様々な条件下で個⼈と集団を⽐較する実験研究を⾏うようになりました。
Chapter 02
不正⾏動に⾒られる集団の意外な特徴
前出の結果からも⾔えることですが、⼀般的に集団は、個⼈よりも合理的であり利⼰的になりやすいと⾔われています。しかし、必ずしもその傾向に当てはまるとは限りません。以前実施した不正⾏動に関する実験では、嘘をついて⾃分だけが得をしようとする⼼理に陥りやすい環境を⽤意し、個⼈と集団で実験参加者の⾏動にどのような違いが⾒られるかを明らかにしました。この実験では、私たち研究者の監視がなく、誰もいない部屋で、実験参加者にサイコロを振ってもらいます。事前にサイコロの⽬の数によって受け取ることのできる報酬額が変わることを伝えたうえで、⽬の数を報告してもらいます。報酬は、5が最も⾼く、4、3、2、1と続いて、6が最も低くなるように設定します。本来、出る⽬の確率は均等なので、実験参加者がサイコロの⽬を正直に報告するならば、1〜6までの⽬が1/6(16.6%)ずつになるはずです。ところが、報告された結果は、報酬が最も⾼くなる5が38%、次に⾼い4が24%という偏りのある結果になりました。このことから、嘘をついて多くの利益を得ようとした⼈が⼀定数いることがわかります。集団になるとこの傾向が強まると予想していましたが、ペアで同じ実験を⾏ったところ、5の報告は⼀気に減り、4や3を報告する割合が増える結果となりました。基準値以上の4や3を申告する理由は、部分的虚偽という「控えめな嘘」であり、嘘の申告をしたペアの多くが5を避けたのは、嘘がばれたときに⾃⾝のソーシャルイメージが悪化することを恐れたためだと考えられます。不正⾏動に関する先⾏研究からも、ソーシャルイメージが不正⾏動に影響を及ぼすことが理論的に検証されています。
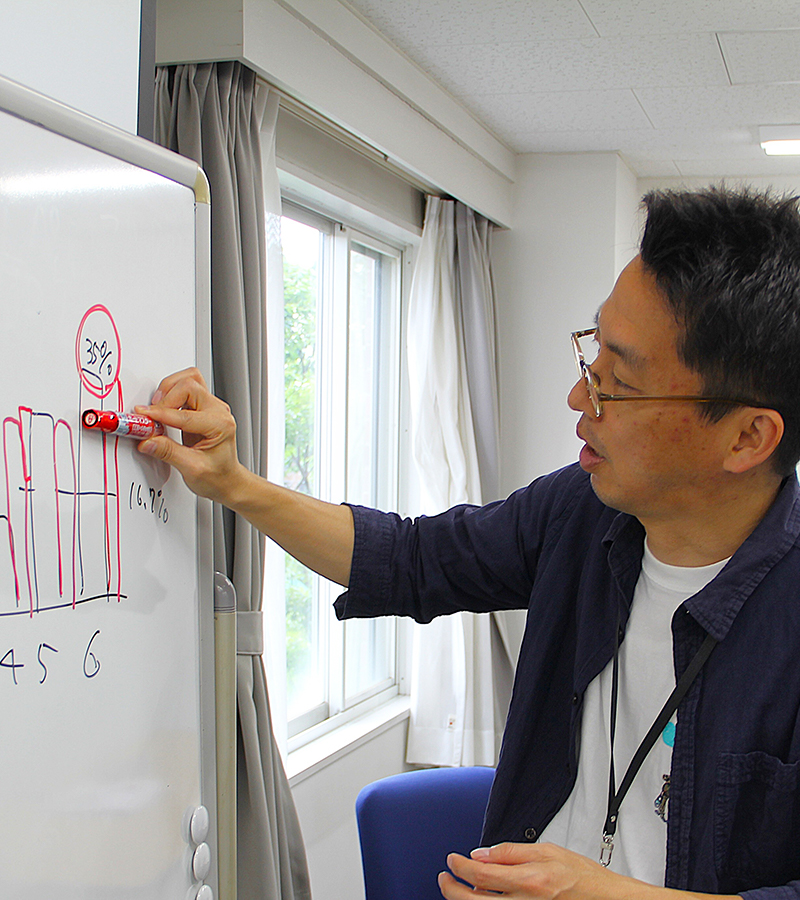
Chapter 03
⼼理学的要素を加味した、
より現実に近い意思決定モデル
現在、公共財供給ゲーム実験での⽐較を⾏っています。協⼒⾏動を⾒る公共財実験では、⾃⼰の利益と社会の利益、どちらを優先するかという選択がポイントとなるため、個⼈の考え⽅が意思決定に⼤きな影響を与えます。そこで、社会⼼理学分野で開発されたアンケートを⽤いて、実験参加者を「向社会的(社会全体や他⼈の利益を優先する)」と「向⾃⼰的(⾃⼰の利益を優先する)」のタイプに分類した後、ランダムにペアを組み合わせます。実験の結果、個⼈と⽐べてペアのほうが協⼒率が下がりました。その理由は、向社会的な⼈と向⾃⼰的な⼈がペアになると、向社会的な⼈は向⾃⼰的な⼈の意⾒に影響され、ペアとしては向⾃⼰的な⾏動をとる傾向が強くなるためでした。さらに、相⼿とコミュニケーションをとる過程で実験ルールへの理解が深まり、あいまいな判断が減ったことも要因の⼀つであることがわかりました。
以上のように、個⼈の⼼理が絡み合う集団の意思決定プロセスは、⾮常に複雑であることがわかります。個⼈と集団の違いを明らかにするだけにとどまらず、その理由を説明・検証することが不可⽋です。⼼理学をはじめとする異分野の知⾒を積極的に取り⼊れながら、今後も⼈間の集団⽣活に関する理解を⼀つずつ積み重ねていきます。

Okano Yoshitaka
Profile
2001年、神⼾⼤学経済学部卒業。2007年、東京⼤学⼤学院経済学研究科博⼠課程修了。東京⼤学⼤学院経済学研究科特任研究員、⼤阪⼤学社会経済研究所特任研究員、⾼知⼯科⼤学経済・マネジメント学群講師、関⻄⼤学経済学部准教授を経て、2024年から関⻄⼤学経済学部教授。博⼠(経済学)。専攻は「実験経済学」「⾏動経済学」。集団の意思決定、集団に属する個⼈の意思決定が、どのような経済学的特徴を持っているかについて、経済実験を通じて検証している。