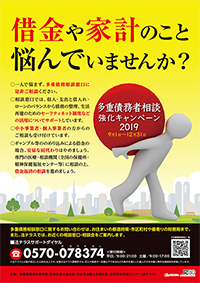IRの大阪誘致に伴う社会問題に対する規制方法の考察
| 研究代表者 | 座主 祥伸 経済学部・准教授 |
|---|---|
| 研究概要 |
|
| 研究分担者 |
多治川 卓朗 法務研究科・教授 三島 徹也 会計研究科・教授 |
| 研究期間 | 2020年度~2021年度(2年間) |
研究成果概要
研究期間全体を通じた研究体制は、次の通りである。本研究班は、大阪IRに関する問題として消費者金融を例に、合理性に欠ける消費者への規制方法を考察した。多治川は民法学からの考察を、三島は商法・会社法による考察を、座主は法と経済学による考察を行った。なお、正式なメンバーではないが、井上(関西大学校医)は研究班に実質的に参画し、依存症についての考察を行った。
研究会では、各自が報告するとともに、それぞれの分野の視点からコメントし、学際的な議論が行われた。研究成果は、各メンバーによってなにわ大阪研究に発表予定である。加えて、この研究班での成果を関西大学の学生に還元すべく、共通教育科目のチャレンジ科目に21年度末に申請し、22年度23年度の秋学期に「ここなにわ大阪で消費者金融を学際的に考える」という科目名で開講する。多治川、三島、井上、座主が、なにわ大阪研究に投稿予定の具体的テーマは下記の通りである。
多治川:契約自由の原則は「人は合理的な判断をする」ことを当然の前提とする(民5条・9条等を参照)。しかし、メンタルヘルスに関する近時の研究では、「人は合理的な判断をするとは限らない」ことが明らかにされている。多治川の研究では、合理的な判断がなされたとは言いがたい契約につき、私法上の取扱いの検討を行った。
三島:大阪で予定しているIR誘致に関して、特にその収益の中核をなすカジノ事業者およびカジノ行為に対する法規制について考察するとともに、大阪のIR事業を手掛けるMGM・オリックスのコンソーシアムである「大阪IR株式会社」について、そのガバナンスのあり方に関して、地域の活性化や治安等、ステイクホルダーの利害の観点も含めて検討を行った。
井上:ギャンブル障害は依存症の範疇に含まれる。アルコール、ニコチン、違法薬物等と関連する物質依存に対して、ギャンブル障害のような行動への依存は行為(プロセス)依存と呼ばれている。井上の研究では,依存症、特にギャンブル障害について医学的知見を整理したうえで、法的な規制を含む予防方法について検討した。
座主:消費者が消費者金融を利用する際に、合法的な市場と非合法市場の二つの市場にアクセスできる状況を考察した。合法市場と非合法市場をそれぞれ現実に合わせて特徴付け、合法市場における金利規制が消費者に与える影響を考えるとともに、非合法市場への派生効果も考察した。加えて、ギャンブルなどの依存症の消費者を前提とした場合の考察も行った。