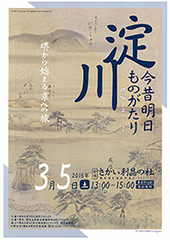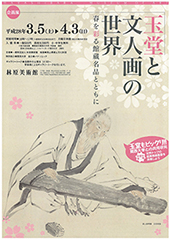文・社・情連携による地域文化資源の発掘、デジタル化および地域活性資源化-DCH構築による地域研究ハブ形成の実践-
| 研究代表者 | 林直保子 社会学部・教授 |
|---|---|
| 研究概要 |  なにわ大阪研究センターに期待されているハブ形成機能を、地域内部の内向きのネットワーク形成(= 結束型ネットワーキング)にとどめるのではなく、大阪周辺地域までを含めたネットワーク形成(結節型ネットワーキング)へと
展開できるかどうかを、実践的に検討するというのが本プロジェクトの課題である。今回の研究でフィールドとして設定したのは、文人画をめぐって、江戸時代中期に大阪との文化交流が歴史的に確認されている岡山県である。そのなかで、岡山市・林原美術館には大阪と深いつな
がりをもつ浦上玉堂の作品など、文人画が多数収蔵されている。今回は、技術的なチャレンジの視点と、文人画以外での大阪の物語の掘り起しの視点から、日本国内で唯一全巻がそろっている「平家物語絵巻」(総延長940 メートル)を対象として、超高精細デジタル化とその展示を企
画した。関西大学は、これまでも大阪画壇の作品を通じて、天満およびその周辺地区を焦点とした結節型ネットワークの形成事業を行ってきているが、今回デジタル化した「平家物語絵巻・第十一巻・上」で描かれている屋島の戦いのスタートが渡辺の津(のちの八軒屋浜、現在の大阪
市北区・天満橋近辺)および福島であることもあり、各種展示からこのコンテンツが大阪内外のさまざまな人々を結びつける効果をもつことが明らかになっている。大学と美術館ばかりでなく、高校、企業、公益法人、商店街などがこのデジタル化された文化遺産をめぐってつながり、過去
の大阪の物語を通じてあらたなネットワークが形成されていくことを観察することができた。また、大阪から岡山へ、岡山から大阪への興味も高まってきており、結束型ばかりではなく、結節型のネットワーキングへの展開の高い可能性が確認された。
なにわ大阪研究センターに期待されているハブ形成機能を、地域内部の内向きのネットワーク形成(= 結束型ネットワーキング)にとどめるのではなく、大阪周辺地域までを含めたネットワーク形成(結節型ネットワーキング)へと
展開できるかどうかを、実践的に検討するというのが本プロジェクトの課題である。今回の研究でフィールドとして設定したのは、文人画をめぐって、江戸時代中期に大阪との文化交流が歴史的に確認されている岡山県である。そのなかで、岡山市・林原美術館には大阪と深いつな
がりをもつ浦上玉堂の作品など、文人画が多数収蔵されている。今回は、技術的なチャレンジの視点と、文人画以外での大阪の物語の掘り起しの視点から、日本国内で唯一全巻がそろっている「平家物語絵巻」(総延長940 メートル)を対象として、超高精細デジタル化とその展示を企
画した。関西大学は、これまでも大阪画壇の作品を通じて、天満およびその周辺地区を焦点とした結節型ネットワークの形成事業を行ってきているが、今回デジタル化した「平家物語絵巻・第十一巻・上」で描かれている屋島の戦いのスタートが渡辺の津(のちの八軒屋浜、現在の大阪
市北区・天満橋近辺)および福島であることもあり、各種展示からこのコンテンツが大阪内外のさまざまな人々を結びつける効果をもつことが明らかになっている。大学と美術館ばかりでなく、高校、企業、公益法人、商店街などがこのデジタル化された文化遺産をめぐってつながり、過去
の大阪の物語を通じてあらたなネットワークが形成されていくことを観察することができた。また、大阪から岡山へ、岡山から大阪への興味も高まってきており、結束型ばかりではなく、結節型のネットワーキングへの展開の高い可能性が確認された。
|
| 研究分担者 | 内田 慶市 外国語学部・教授 中谷 伸生 文学部・教授 与謝野 有紀 社会学部・教授 研谷 紀夫 総合情報学部・准教授 浅利 尚民 林原美術館学芸課・課長 |
| 研究期間 | 2年間 |
研究成果概要
平成27年12月に京都で行われた世界工学会議において、プロジェクトの成果として平家物語絵巻の超高精細画像を展示した。また、平成28年3月12日~14日には、グランフロント大阪にて、多摩美術大学との共催でデジタル展示を実施した。
また、平成27 年度には新たに、浦上春琴「玉堂寿像」・浦上玉堂「松風萬樹」・西山芳園「花鳥大横物」・池大雅「春山精霽靄」・森狙仙「虎」の5点を高精細デジタル化した。これらの画像を用いて、3月5日に堺市で講演会を行った。また、3 月5日から4 月3 日まで、林原美術館の企画展にてデジタル展示を行った。
本プロジェクトは、なにわ大阪研究活動を、大阪における地域内部の内向きのネットワーキング(=結束型ネットワーキング)にとどめるのではなく、大阪周辺地域までを含めたネットワーキング(=結節型ネットワーキング)へと展開し、なにわ大阪研究拠点のハブ形成を実践的に試みようとするものであった。
2016年度には、2015年度の活動においてデジタル化を行った林原美術館(岡山市)所蔵の文化財資料、および関西大学図書館所蔵作品の画像を用いて、結束型・結節型ネットワークの形成事業を展開した。
(関西国際空港における「大阪の歴史・文化魅力体験プロジェクト(2016年10月)」、デジタル画像を用いた講演「文人ネットワークの中心地としての天満(講師:与謝野有紀、2016年11月」、「天満から始まる『つながり』の物語(与謝野有紀、2017年2月)」など)を行った。これらの実践活動により、デジタル化された文化財資料コンテンツが、人々の地域への愛着を醸成するだけでなく、地域内外のさまざまな人々を結びつける効果をもつことが改めて明らかとなった。
文化財資料によるネットワーキングの成果の一つとして、2016年度に実現した本プロジェクトと大阪北浜の料亭「花外楼(天保元年創業)」の間の研究協力があげられる。
花外楼は、明治8年、日本の立憲体制の礎となる大阪会議の舞台となった老舗料亭であり、歴史的にも貴重な資料が非常に多く保管されている。
それらの資料のうち、大阪で活躍した画家菅楯彦の作品を中心に、絵画20点について高精細デジタル化を行った。
デジタル化した資料は、2017年4月~5月になにわ大阪研究センターの「関西大学のなにわ大阪研究」展で展示されるほか、2017年7月に、グランフロント大阪にて、大坂画壇研究の研究者による解説とともに公開する予定である。
また、その際には、花外楼女将による大阪の歴史と文化についての講演を開催し、幅広い社会層の交流の場を提供する。
この研究成果の骨子は、通常はアクセスすることが困難と考えられ、さらに、実際に資料を得ることが難しいという声のある大阪を代表する伝統ある高級料亭の絵画資料を、当該料亭、大学、そして地域の三者にとって利益のあるようなポジティブネットワークを形成することでデジタル化し、公開できた点である。
この成果は、社会科学的な理論的背景を持って行われているが、さらに、学内の人文、社会、情報系の行動を推進によってなされている。
この研究から、社会運動論の理論の一つである資源動員論の視点が、地域活性化に必要であることを示唆されており、理論的にも大きな成果がえられたものと考えている。