- HOME >
- 在学生・修了生の声
在学生・修了生の声
研究科一覧
法学研究科

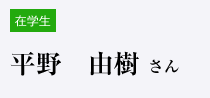
-
法学研究科 法学・政治学専攻
高度職業人養成コース
博士課程前期課程 2022年4月入学
(入試種別:一般入学試験)
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 研究テーマと概要
-
『在留資格のない外国人の人権保障とマクリーン判決の再定位――人権保障におけるグローバル化の可能性を踏まえて――』
- 概要:
- 本研究の実施の背景には、2021年3月に名古屋入管に収容されていたスリランカ人女性が十分な医療を受けられずに死亡した事件が発生したことで、国内における在留外国人の不安定な地位が注目されたことが挙げられます。現在の入管法の根幹となっているのは、昭和53年10月4日のマクリーン判決であり、「外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、右のような外国人在留制度の枠内で与えられているに過ぎないものとするのが相当であって、在留の許否を決する国の裁量を拘束するまでの保障、すなわち、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為在留期間の更新の際に消極的な事情として斟酌されないことまでの保障が与えられているものと解することはできない」と示したことは、「外国人の人権」という問題に大きな影響を与えています。国際人権法の発展などを踏まえマクリーン判決も現代の視点で見直されるべきではないだろうかと考えました。第1章において、外国人の人権論の出発点として、マクリーン判決の内容を再検討しながら、憲法学からの判決の評価を取り上げ、続く第2章において、外国人の人権保障に消極的な学説二つを取り上げ、その内容の検討を批判的に行いました。そして、第3章において、マクリーン判決以降、国際人権法の発展による人権保障のグローバル化をめぐる議論を取り上げ、外国人の人権保障についての新たな可能性を探り、最後に、第4章において、外国人の人権保障に積極的な傾向のある近年の下級審判例を取り上げ、マクリーン事件判決と外国人の人権保障の今後の展望を述べております。
- ー 時間割
-
博士課程前期課程 1年次 秋学期
1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 月 民法研究2
(財産法2)
講義特論研究
(政策法務)
講義火 総合演習
(政策研究)公共経済学研究
講義水 民法研究4
(家族法)
講義木 金 総合演習
(政策法務)土
- ー 奨学支援制度の利用にかかる経験談、よかった点
-
2年次の春学期から、関西大学給付奨学金・教育助成基金奨学金を頂いて通学しておりました。
1年次は奨学金制度の事を詳しく知らず利用していませんでしたが、同じ研究科の友人が利用していたことで豊富な奨学金制度があることを知りました。奨学金を頂いたことで、研究や試験勉強・課題に打ち込むことができましたので、利用してよかったと思います。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
- 大学4年次にゼミで憲法問題のディベートを行っていた際に憲法問題の面白さに気づき、専門的に研究を行いたいと思い、大学院進学を考えました。在籍していた大学には法学部の大学院が無く外部の大学院を受験する必要がありました。大学在籍時から公務員をめざして勉強しておりましたので、高度職業人養成コース政策法務コースのある本学を選び受験しました。
- ー 指導教員名とその教員を選んだ理由や教員とのエピソード等
-
- 指導教員名:
- 髙作 正博先生
関西大学大学院での2年間、指導教員として研究や修士論文に関する指導を丁寧に行っていただき、無事書き上げることができました。また、ご多忙の中、大学の設備や利用方法、公務員試験の対策、就職活動の面接練習や相談といった進路に関することなど、学生生活の面でも親身にサポートしていただきました。大変感謝しております。
- ー 修了後の進路希望
- 公務員をめざしており、大学院2年次に公務員試験を受験しました。市役所から内定を頂きましたので、4月から市役所の一般行政職で従事する予定です。政策法務や立案、公共経済学など大学院での学びを生かしていけたらと思っております。
- ー 関西大学大学院法学研究科に進学を考えている方へのメッセージ
- 関西大学大学院は図書館も広く資料が豊富にあり、自習室など研究のための学習環境が整っているところが魅力だと思います。また、内部進学生だけでなく外部の大学からの一般入学の学生や留学生、社会人学生の方々も多く在籍していますので、プライベートだけでなく学問を通じて議論することで交流できることも良いところだと思います。

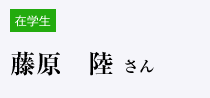
-
法学研究科 法学・政治学専攻
博士課程前期課程 2022年4月入学
(入試種別:学内進学試験)
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 研究テーマと概要
-
『行政評価はなぜ使われないのか(仮題)』
- 概要:
- 行政評価が使われていない理由や自治体にとって何が障害になっているのかを研究していきたいです。
- ー 時間割
-
博士課程前期課程 1年次 秋学期
1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 月 特論研究
(政策法務)火 総合演習
(政策研究)水 行政学研究 木 金 総合演習
(政策法務)土
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
-
公務員をめざしており、高度専門職業人養成コースを通して、学部時代に学んだことをより深く学びたいと思い進学を決めました。
学部時代から、勉強に打ち込みやすい研究室や図書館等を利用しており、学習環境が整っていたことや指導していただきたい教員がいたことから、本学大学院を選びました。
- ー 大学院進学のための受験対策や事前準備
- 学内進学試験で法学研究科に進学したため、試験方法は出願時に提出した志望理由書と研究計画書を中心にした口頭試問でした。そのため、口頭試問に向けて、志望理由書と研究計画書についての質問を想定したり、自分が大学院でどのような研究をしたいのか考え、口頭試問に臨みました。
- ー 修了後の進路希望
- 学部時代から、人々の暮らしを支えられる仕事ができ、地域に根ざした公共性の高い地方公務員になりたいと考えていました。そのため、指導教授の石橋先生のアドバイスを受けて、大学院1年次生に公務員試験を受験しました。地元の市役所に内定をいただいたので、2年次では、市役所で従事しながら修士論文を執筆予定です。
- ー 関西大学大学院法学研究科の魅力
-
法学研究科には、外国人留学生や社会人の学生の方など、国籍や年齢層もさまざまで、多様なバックグラウンドを持った人たちが多く在籍しています。また、公務員・税理士・司法書士・民間企業など修了後にめざす進路もさまざまなので、毎日刺激を受けながら生活することができるのが魅力です。
また、高度専門職業人養成コースには、所期の教育効果を上げるため、専門的な職業能力や資格の取得に資する科目を用意されていて、自分自身の目的や関心に応じた幅広い履修が可能な点も魅力です。
- ー 関西大学大学院法学研究科に進学を考えている方へのメッセージ
-
法学研究科には、外国人留学生や社会人の学生の方など、国籍や年齢層もさまざまで、多様なバックグラウンドを持った人たちとの出会いがあります。そういった人たちと積極的に関わることで、今までの価値観を大きく変える良い経験をすることができると思います。
また、図書館や研究室など、研究を進めるにあたっての環境が充実しているため、自分がやりたい研究に打ち込みやすいと思います。
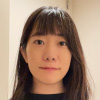
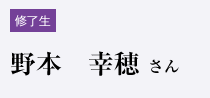
-
法学研究科 法学・政治学専攻
博士課程前期課程 2012年4月入学
(入試種別:学内進学試験)- 勤務先名:
- 株式会社宝島社 編集
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 学位論文題名と概要
-
『日本における「におい商標」導入をめぐる考察―国際比較を通して―』
- 概要:
- 我が国では未導入であり、保護されていない「新しいタイプの商標」。この中でも特に、「におい商標」について我が国での導入をめぐる議論、そして、「におい商標」を導入している各国の状況や判例を踏まえ、我が国において「におい商標」保護を導入するにあたっての重要性とその課題について検討しました。今日の企業のグローバル化における、言語を超えたブランドメッセージの発信手段の1つとして活用の可能性と重要性がますます高まっている「におい」を、どのように保護すべきか。国内外における「におい商標」保護の動向や課題、知的財産諸法における「におい」保護の可能性の検討等も踏まえ、我が国においても「におい商標」は導入すべきであると結論づけたものです。
- ー 現在の仕事において大学院での研究や学修が生かされている場面や、学部卒業で就職をしている方との違いを実感する場面
- 弊社の場合かなり特殊かもしれませんが、著者や権利元への交渉、グッズの作成、権利元への監修依頼、原稿作成など編集の仕事は多岐にわたります。著者や権利元との出版契約、著作物使用許諾、意匠や商標の確認・許諾といった業務も書面作成を行うこともあります。学部で学んだ知識でも十分かもしれませんが、法律に関する文章をたくさん読んできたので、契約書等をみることは苦ではなく、書面づくりや確認がスムーズです。また、出版、ものづくりという、キャラクターやブランドを扱う慎重さが求められる現場で、知的財産権を保護、侵害しないように注意すべきことをさまざまな角度から考えることができたとき、学びが生かせているのではないかと感じます。内容構成を考え、資料を集め、一冊にまとめる……という業務では、修士論文の経験を通し、情報の取捨選択、仕上げる根気強さなども培われたのではと感じます。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
-
私が大学院に進学した理由は2つあります。
ひとつは、就職先にこのまま就職して良いのかという不安です。就職活動にかなり苦戦し、無事獲得した内定先は、めざしていた業界でもなく、自分の学んだ分野とは全く関係のない業界・職種でした。一生懸命勉強とも向き合ってきたこの4年間は何だったのだろうか、と4回生にしてふと不安になりました。もうひとつの理由は、漠然とした「学びたい」という気持ちからでした。丁度そのころ面白そうと受けた「知的財産法」の授業に非常に興味を持ち、もっといろいろなことを見ておきたい、学びたいという気持ちが湧き、大学院への進学を決めました。
- ー 指導教員名とその教員を選んだ理由や教員とのエピソード等
-
- 指導教員名:
- 葛原 力三先生
- 山名 美加先生
もともと、刑法を中心に学んでおり、ゼミも葛原先生のゼミに入っていたため、山名先生とは試験の後にはじめてお話をさせていただきました。
大学院では知的財産法を学びたいというお話をさせていただいたのですが、山名先生がその年海外に行かれていらっしゃらない……ということが判明し、入学早々すごく悩んだのを覚えています。お忙しい中、私が安心して学べるよう親身にお話を聞いてくださり、いらっしゃらない間の一年間はメールでのやりとりで非常に細かくサポートいただきました。お戻りになってからは、学部生のゼミに参加させてくださったり、セミナーなどのお手伝いもさせていただき、勉強という意味での学びはもちろんですが、人とのつながり、人の意見を聞き考える学びなど、一年とは思えない非常にたくさんの学びの機会をいただきました。就職活動と修士論文の両立もかなりハードな作業でしたが、的確にアドバイスいただき、無事に書きあげることができました。山名先生が不在にされている間、葛原先生にも引き続きサポートいただき、非常に安心して学生生活を送ることができました。大変感謝しております。
- ー 現在の就職先・職業を選んだ理由
- 知的財産法を学ぶにつれ、もともと興味のあったメディアやエンタメといった分野により強く関心を持ちました。そして研究を進めるうちに、さまざまな事象、人の思いを伝え、時に流行をつくる「出版物」というものに興味を持つようになりました。さまざまなことを知るたび「こんなに面白いのに食わず嫌いしているなんてもったいない」と思うことがしばしばあり「そんな人がつい食わず嫌いしてしまうようなことを人に伝える仕事」がしたいと思い、出版業界をめざしました。いまでこそ一般的になりましたが、グッズが付いている本、キャラクターやブランド垣根をこえたグッズ製作をしている発想の自由度の高さに惹かれたのが弊社です。当時テレビ、雑誌、ラジオなどクロスメディア展開というようなことが流行り始めた時代でもあり、ここなら自分が学んだ知識を生かしながら新しいことができるのでは、と思い入社しました。
- ー 関西大学大学院法学研究科の魅力
- 膨大な資料・データが揃う図書館、24時間365日使える研究室、といった学修環境が整っているのはもちろん、親身になってくださる先生方がいらっしゃるアットホームさが魅力だと思います。研究室には集中することができる環境もありますし、フリースペースではみんなで和気あいあいとできる場所もあります。誰かしらいらっしゃるので、研究のことはもちろん、進路について相談することもできます。いろんな目線の話や意見を聞くことができるのも楽しいです。指導教員にもよるかもしれませんが、学部生との関わりもあり、学部時代とはまたちがった学びができる環境です。
- ー 関西大学大学院法学研究科に進学を考えている方へのメッセージ
- 大学院というと少し身構えてしまう方もいるかもしれません。進学をされる理由はさまざまあるかと思いますが、「学びたい」という気持ちに対して先生方は本当に一人ひとり、親身になってくださいます。授業なども学部と比べ少人数で、自ら学ぶ姿勢が求められ、修士論文など大変なことももちろんあります。でも大丈夫です。先生方はきちんとこたえてくださいますし、乗り越えた先、きっと自信につながると思います。安心して学んでください。

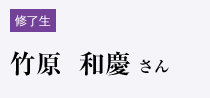
-
法学研究科 法学・政治学専攻
博士課程前期課程 2018年4月入学
(入試種別:学内進学試験)- 勤務先名:
- 県庁 一般事務職
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 学位論文題名と概要
-
『SDGsを媒介とした企業とNGOの協働の展開 ‐CSR活動を軸として‐』
- 概要:
-
議論の中心は、何が企業とNGOが協働するために必要なのかについてです。その鍵となるのが、国際連合で採択されたSDGs(持続可能な開発目標)だと考えました。
実際に、企業へSDGsについて聴き取り調査を行い、また、企業とNGOによって行われているCSR活動との視点からNGOの役割を考えていきます。
そして、このようなSDGsの取り組みを通じて企業とNGOの関係性が開かれたものになっていくと考えました。
- ー 現在の仕事において大学院での研究や学修が生かされている場面や、学部卒業で就職をしている方との違いを実感する場面
-
現在の担当業務において、大学院での研究が直接生かされている場面は少ないです。しかし、研究を行う過程で身についた、さまざまな角度から物事を捉え、情報を収集し、活用していく力は、仕事を行う上で役立ちました。
例えば、現在、保健所で働いております。新型コロナウイルス感染症に関する国からの通知に対して、市や住民の方へ分かりやすく説明する際、過去の通知との違いや要点を的確に伝えるように努めています。このような、専門以外の新しい知識を身につけ、活用していく力の基盤は、大学院時代の研究活動によって培われたものと実感しています。
- ー TA・RA制度の利用にかかる経験談、よかった点
-
2年次の春・秋学期にTA制度を利用させていただきました。
具体的な活動は、4~5人程度のグループの司会役を務めました。授業の性質上、英語を使うので、グループ内の議論が進まない場合、話題を提供して口火を切る役割を担っていました。
TA制度を利用してよかった点は、周りを取りまとめる力がついた点です。学生の反応を見ながら、どのようにしたら議論に加わりやすくなるのかを考える機会が多かったです。
- ー 奨学支援制度の利用にかかる経験談、よかった点
-
2年間、給付奨学金制度を利用させていただきました。
給付金の用途については、研究に必要な書籍の購入、調査や発表のために必要な交通費や資料のコピー代等です。奨学金が2年間継続して支給されるので、計画的に使用することができて良かったです。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
-
卒業論文の内容を、新しい視点から深めていきたいと考え、大学院に進学することを決めました。
給付奨学金制度や研究室、図書館等、学習環境が充実していたことや指導していただきたい教員がいたことから、本学大学院を選びました。
- ー 現在の就職先・職業を選んだ理由
-
インターンシップへ参加し、防災関連の仕事を体験しました。防災の専門家や消防防災航空隊の隊員との講習を通じて、南海トラフ地震・津波に関する応急対応シナリオの作成等の専門的知識の重要性や自治体職員の社会的意義を実感しました。
住民の安全・安心を守る基盤と関わりのある業務が多いこともあり、決めました。
- ー 関西大学大学院法学研究科に進学を考えている方へのメッセージ
-
法学研究科は、社会人学生や留学生も多く在籍しているので、研究室の利用方法から世間話まで、どのようなことでも気さくに話すことが出来ます。
研究について不安な点があっても、先生方からアドバイスをいただくことで、解消されます。
ただし、その前提として自分で何が理解出来ていないのか、どのような方向に進んでいくのかということを明らかにしておく必要があります。大学院で自分は何を学びたいのか、どのようなことに挑戦するのかといったことを考えておくと、有意義な時間を過ごすことが出来ると思います。
文学研究科

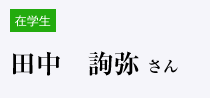
-
文学研究科 総合人文学専攻
博士課程後期課程 2022年4月入学
(入試種別:一般入学試験)- 勤務先名:
- 国家公務員研究職
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 研究テーマと概要
-
『囲繞施設の変遷からみた中世・近世の城下町構造と社会構造の研究』
- 概要:
- 日本の中世・近世における城郭と城下町を囲んでいた囲郭施設(惣構(そうがまえ))について、囲郭施設を構成する土塁や堀の平面プラン・構造を考古学的観点から分析し、当時の城下町・社会構造を明らかにすることを目的としています。
- ー 時間割
-
博士課程後期課程 2年次 秋学期
1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 月 考古学
特殊研究B講義火 水 木 金 土 考古学演習2B
- ー 現在の仕事において大学院での研究や学修が生かされている場面や、学部卒業で就職をしている方との違いを実感する場面
- 私は現在、国家公務員の研究職として働いています。国家公務員の研究職とは自身の専門と関連のある省庁に勤務して調査研究をおこなう職を指し、私の場合は所属官庁に保管されている出土品や墳墓に関する考古学的な調査研究をおこなっています。調査研究の対象には、私が大学院で研究対象とした城郭だけでなく、古墳時代から近代までさまざまな時代の遺構・遺物も含まれるため、幅広く知識を身につけ、業務に活かす必要があります。大学院の時に明日香村で携わった発掘調査の経験や関西大学博物館での学びが生かされていると感じます。また、考古資料だけでなく古文書や公文書を扱うため、いわゆる崩し字などを解読する必要がありますが、大学院にて学んだ古文書に関する知識や古墳に関する古文書を解読した経験が生かされています。埋蔵文化財行政では大学院卒で就職される方がほとんどで、研究能力や調査研究の計画能力・経験値を踏まえても学部卒では柔軟に対応できない場合が多いです。また、専門性が求められるため、同じ大学院卒でも修士課程卒より博士課程卒の方が重宝されます。世界遺産など国際的な場においては、博士号を持っているかで、専門性の有無を判断されます。なお、私が就職した国家公務員研究職は大学院修士号取得相当の能力を有していないと応募できません。
- ー 出願に先立って志望の指導教員へどのような相談をしたか、相談してよかった点
- 私は、博士課程前期課程1年の冬(12月から1月ごろ)に相談しました。一般的に翌年度には就職活動をして修士卒で働かれる方が多い中、後期課程に進学すると安定した収入がないわけですので、金銭的な面を含めて研究に集中できる環境をいかに作り出せるか考えていました。指導教員からは、日本学術振興会特別研究員(DC1)に応募することをすすめられ、関西大学の研究支援・社会連携グループに相談しながら申請書を作成しました。9月には日本学術振興会特別研究員(DC1)の内定をいただき、金銭面での不安無く受験することができました。
- ー 奨学支援制度の利用にかかる経験談、よかった点
- 大学院入学試験の成績で関西大学大学院特別給付奨学金をいただいたため、金銭面での不安が無い状態で学業、調査研究に集中できています。調査研究には、交通費や宿泊費が必要となりますが、計画的に運用し、充実した研究をおこなえています。
- ー お仕事との両立の工夫等について
-
両立に向けて、まず、大きな目標と時期を定め、それに向けた小目標を時期ごとに計画しました。つづいて、一年間の仕事内容、繁忙期などの把握や、先輩職員に両立の仕方を伺うなどして、無理なく両立できるように予定を立てていきました。
結果として平日は、夜は早めに寝て体力を回復し、出退勤の移動時間に先行研究を読み、その内容を翌朝に整理しています。土日は朝から夜まで国会図書館に詰めたり、全国の事例を踏査したりしています。
一年を通すと、4~9月の仕事は文書作成業務が多いので、研究では先行研究や事例の収集(インプット)を中心におこない、業務で長期出張の多い10月~3月は論文作成(アウトプット)をおこなうようにして、業務と研究で異なる作業となるよう心がけています。
- ー 普段、どのような研究活動(手法)を行われているか、またその「おもしろさ」「難しさ」について
-
現代における日本の都市・社会構造は、中世・近世から多くの影響を受けており、都市の約7割が中世・近世城下町をもとに発展し、現代の社会構造は中世・近世の社会構造の継承と脱却によって成立しています。したがって、現代日本の都市・社会構造を理解する上で、中世・近世の城下町と社会構造に関する研究は重要な位置を占めます。中世・近世の城下町は、城郭などの中心施設、武家屋敷・町人地といった居住域、それらを囲む囲郭施設“惣構”から構成されており、惣構の研究は、城下町を権力者の視点から復元することを可能とし、中世・近世の政治・社会構造の解明に繋がります。
従来の研究では、惣構の定義が定まらなかったことで研究が深化せず、惣構の分類がなかったことで、個別事例の研究に比べ全国の事例を比較した研究は行われてきませんでした。
そこで、私の研究では、惣構の定義を定めるとともに独自の観点から惣構を類型化することで、城下町像の構築と惣構の再評価を行いました。詳細な調査方法・内容としては、報告書をもとに惣構の土塁や堀の規模を復元した後、それらを陰影起伏図に重ね合わせ、現地踏査による調査成果を踏まえて惣構を分類しました。その後、分類の成果を分布図などに示し、他の時代・地域の分布図と比較することで、異なる時代の事例との共通点や相違点を明らかにしています。
この研究では、考古学だけでなく、文献史学、歴史地理学、城郭研究、都市史学といった研究を把握し、総合的に取り組んでいます。多様な分野の研究方法を知ることができる面白さがある一方、全ての分野に精通し一定の研究水準に達している必要があるという難しさもあります。
- ー 大学院進学のための受験対策や事前準備
- 修士論文の提出と口頭試問があった関係で、本格的に大学院の受験対策ができたのは、受験日一週間前からですが、博士課程後期課程に進学すると決めてからすぐに、試験内容を確認し、博士課程前期課程2年に進むころには過去問などをもとに入試の情報を収集し、試験内容の傾向と対策を考えていました。受験科目の英語については、当時、考古学の研究が生活の中心だったので、息抜きとして英語の勉強をしていました。修士論文を作成しているときも、疲れたときや研究に集中できない時は英語の文法や単語の問題を解いていました。
- ー 関西大学大学院文学研究科に進学を考えている方へのメッセージ
-
大学院博士課程後期課程の3年は一瞬で過ぎてしまいます。しかし、対象分野の研究はわずか3年でも大きく進展します。そのため、時間を大切にし、この3年の間に進展し続ける研究をきちんと把握し、さらにこれを超えていく研究をおこなうことが目標となります。
博士課程後期課程に進学を考えた際は、すぐに将来設計をしてください。将来設計については細かい部分は変わってもぶれない信念を持つことが大切です。なんとなく進学するのではなく、明確な目的を持って進学することで、充実した3年間を送ることができると思います。
私の場合は、最終目標や就職希望先を定め、それに向けて行うべきこと(どのような経験が必要か、いつどのような論文を作成・雑誌に投稿するか、研究費のお金のためにどのようなことをするか(博物館でのアルバイトをするのか、日本学術振興会特別研究員(DC1)に応募するのか)、いつの段階でどのような能力(崩し字を読めるなど)を身につけている必要があるかなど)を逆算して、紙に書き出しました。これを玄関のドアなど目にするところに張ることで、気負わずとも普段から意識するようになりました。
健康に最大限気をつけつつ、一分一秒を無駄にしないよう綿密に計画を立て、実行し、研究を楽しみましょう(もちろん、休憩や睡眠、気分転換に充てる時間も十分にとりましょう)。

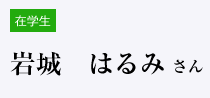
- 文学研究科 総合人文学専攻
教育文化学専修
博士課程前期課程 2022年4月入学
(入試種別:社会人入学試験)
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 研究テーマと概要
-
『乳児期の子育てにおける父親の困難と支援上の課題』
- 概要:
- 男性の子育てが推奨される現代、子育てに関わりたいと考える当事者も年々増えています。しかし「ケア」が必要となる乳児期の子育ては未だ女性に偏っており、この時期の子育て支援にもジェンダーギャップが見られます。男性向けの子育て支援はどうあるべきか。乳児をもつ父親が直面する困難から、その必要とする支援について明らかにします。
- ー 時間割
-
博士課程前期課程 1年次 秋学期
1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 月 教育文化学研究
演習1Bコミュニティ
教育学研究火 教科学習
デザイン研究学校
イノベーション研究教育社会学研究 水 人権教育研究 木 金 土
- ー 出願に先立って志望の指導教員へどのような相談をしたか、相談してよかった点
- 自身の研究したいテーマを伝えた上で当該研究室を希望して問題ないかどうかの相談と、出願の際に提出しなければならない研究計画書についても相談に乗っていただきました。学部時代とは異なる専攻分野であることに加え、そもそも卒業論文を書いてから20年弱も経っていたため、研究の目的や意義について計画書の形式に書き上げること自体一苦労でしたが、アドバイスをいただいたことで無事に完成させることができました。相談に乗っていただいたことで安心して出願することができました。
- ー お仕事との両立の工夫等について
- 私は子育てに関わる仕事をしているため、実は研究と仕事が一繋がりになっています。仕事の中での気付きが研究に影響を与えたり、研究での気付きを仕事に生かすことができたりしてとても面白いです。修士1年目は週の半分くらいは通学したため、仕事を残りの日に固めたり、午前は仕事をして午後は通学したりと時間のやりくりは工夫をしました。実際に学生生活が始まるまでは不安もありドキドキしていましたが、やってみると案外大変さはなく、良いリズムで生活できたと思います。
- ー 出身学部と所属研究科の専門分野が異なっている際に、特にどのような点に注意して受験準備を進めたか
- 学部時代とは異なる分野を希望するにあたり、大学院は「一から教えてもらう」ところではなく「研究する」ところであるということを前提に、ある程度の基礎知識は理解した上で入学しなければと、社会学や教育社会学を中心にさまざまな本を読んで勉強しました。学部時代は数学を専攻していたため、文系の学術書を読むのに最初はかなり苦労した記憶があります。言い回しや使用する単語の種類・数など、分野特有の表現に慣れていけるよう意識しながら文献を読みました。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
- 仕事で子育て支援に関わる中で、子育てに関するさまざまな社会問題の根底にはジェンダーの問題が深く結びついていると感じるようになりました。子育て支援と女性支援が混同されがちなこと、そして自身の活動もその一端を担ってしまっているかもしれないことに気づき、大学院で改めて学び、研究したいと思うようになりました。とりわけ男性の子育てについて研究したいと思っていたところ、仕事でご一緒した方から「岩城さんのやりたい研究なら絶対、関大の多賀先生!」とおすすめしていただき、自宅からの通学も可能でしたのですぐに関西大学に心を決めました。
- ー 指導教員名とその教員を選んだ理由や教員とのエピソード等
-
- 指導教員名:
- 多賀 太先生
男性の子育てについて研究したいと思っていたところ、仕事でご一緒した方から「それなら絶対、関大の多賀先生!」とおすすめしていただき、すぐに検索しました。「この分野に興味がありながら何故私は今まで多賀先生を知らなかったのだろう…」と後悔するほど、まさに私が研究したい内容の書籍や論文を数多く執筆されており、ワクワクしながらそれらに目を通したのを覚えています。出願前の相談(面談)では「いよいよご本人とお話しできるのか」とちょっとした緊張が走ったほどです(笑)

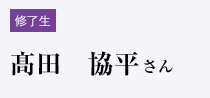
-
文学研究科 総合人文学専攻
地理学専修
博士課程前期課程 2021年4月入学
(入試種別:一般入学試験)- 勤務先名:
- 国土交通省国土地理院
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 学位論文題名と概要
-
『段丘・丘陵の盛土地における液状化の土地条件-地形・地質・法令に着目して-』
- 概要:
- ニュータウンなどの段丘・丘陵の人工改変地でこれまで記録された液状化に関して、その発生条件を地形・地質からモデル化し、現行法令の問題点を指摘しました。
- ー 現在の仕事において大学院での研究や学修が生かされている場面や、学部卒業で就職をしている方との違いを実感する場面
-
現在は1年間の研修を受けています。研修では、地図を作成するため現地調査に行って報告書をまとめることが多くあります。このような時、大学院で学んできた地形・地質に関するフィールドワークの手法、その結果を文章化する経験が役立っていると感じています。
学部卒業で就職をしている方との違いは文章力だと感じています。修士課程では2年間しっかり修士論文の執筆に時間が使えるので、結果をただまとめるだけではなく、読み手に分かりやすい論理的な文章を書く力が養われました。
- ー 出願に先立って志望の指導教員へどのような相談をしたか、相談してよかった点
- 私は他大学出身なので、入試に関する情報や地理学専修の雰囲気について相談しました。また、大学院では学部と異なる研究テーマを希望していたので、そのような場合でも受け入れていただけるかについても相談しました。私が入試を受けた年はコロナ禍でしたのでオンラインでの相談となりましたが、黒木先生に優しく丁寧に教えていただき、お人柄も知ることができたので、不安なく入試に臨むことができました。
- ー TA・RA制度の利用にかかる経験談、よかった点
- 私は、「地理情報システムb」、「地理学・地域環境学調査研究法b」のTAを担当しました。どちらも実習の授業で、学生が行う課題作成のサポートを行っていました。学生から質問を受けた際、分からないこともありましたが、その度に分からないことを自分で調べたり、先生に聞くなどしたため、働きながらも勉強することができ、充実した時間になりました。また、学生と話す機会が多かったので、知り合いが増えたのもよかったです。
- ー 奨学支援制度の利用にかかる経験談、よかった点
- 私は関西大学大学院給付奨学金を利用しました。私の研究の調査地は北海道、宮城県、新潟県と遠方で旅費が多く必要だったため、奨学金をいただけたことはとてもありがたかったです。
- ー 現在の就職先・職業を選んだ理由
- 私は幼少期から地理が好きで、地理に関する職場で真っ先に思いついたのが日本の全ての地図の基礎となる地図を整備している国土地理院でした。国土地理院では防災・減災のための地理空間情報の整備や普及にも力を入れており、大学院時代の地理学と災害に関する学びが最も生かせ、多くの人々の役に立てる場所ではないかと思い、志望しました。
- ー 関西大学大学院文学研究科の魅力
-
関西大学大学院は研究する環境がとても整っていると感じます。文学研究科では専修ごとに大学院生専用の部屋があり、24時間利用することができます。授業は、関西大学以外の先生のものも多くあり、さまざまな分野が学べます。図書館は蔵書が多く、他のキャンパスの書籍も取り寄せることができるのでとても便利です。
先生方や事務職員の方もとても優しく、就職活動などで困ったことがあれば気軽に相談でき、安心して学生生活を送ることができました。

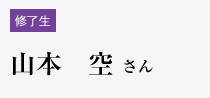
-
文学研究科 総合人文学専攻
国文学専修
博士課程後期課程 2015年4月入学
(入試種別:一般入学試験)- 勤務先名:
- 近畿大学工業高等専門学校・
総合システム工学科(国語)講師
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 学位論文題名と概要
-
『対称詞の談話機能に関する対照方言学的研究』
- 概要:
- 対称詞とは「あなた」「おまえ」等の二人称代名詞や、(佐藤さんに対して)「佐藤さん」、(社長に対して)「社長」、(父に対して)「お父さん」など、話の相手を指す言葉の総称です。日本語では誰に対して話しているかが明らかである場合は「お母さん醤油取って」を「醤油取って」という風に対称詞を省略することが一般的です。しかし中には対称詞を多用する地域もあり、使用に地域差があります。本研究では沖縄を除く全国46地点の方言談話資料を用いて対称詞使用の傾向を分析し、西日本に対称詞を多用する地点が多いこと、多用されているのは文中に係り先がない対称詞(例:「今は あんた みんな スマホが使えるから 便利だよね。」)であることを明らかにしました。さらに主要地点に関してはどのような場面(例:怒っている場面、謝っている場面など)で対称詞を使用するかを分析し、使用量だけでなく使用できる場面や人物に対しても地域差があることを明らかにしました。それらの結果をもとに、東日本(東北)から西日本(九州)に移動するごとに対称詞の使用量が多くなり、使用可能な場面や人物も増えるという分布のグラデーションがあることを明らかにしました。
- ー 現在の仕事において大学院での研究や学修が生かされている場面や、学部卒業で就職をしている方との違いを実感する場面
-
高等専門学校(高専)は中学卒業後5年間(専攻科に進学した場合は7年間)、技術者になるための専門的な知識を学ぶ高等教育機関です。そのため学生の年齢層は高校相当~大学相当と幅広く、国語科の教員は低学年には高校国語相当の授業、高学年には大学のリーディング・ライティング相当の授業を実施する必要があります。
私は国語国文学専修(国語学)でしたが、関西大学大学院では幅広い分野の先生方がいらっしゃり、他ゼミとの交流も多かったため、自分の専門分野に限らず国語国文に関するさまざまな知識を得ることができました。特に専門の国語学に関しては、異なるご専門を持つ先生方が3名いらっしゃり、国語学(日本語学)を基礎からしっかりと教えてくださいました。学部で学んだことをさらに深め、学部では間に合わなかった学びも得られることは、大学院の大きな魅力であり、国語の教員としての力を大きく伸ばすことができると思います。また、方言が専門であるため、在学中は多くの地域に方言調査に赴きました。さまざまな言語文化、地域文化に触れ、多くの方々とお話をさせていただく中で、方言の知識はもちろん、コミュニケーション能力を培うこともできました。対称詞は地域によって使われる形式や使われ方が大きく異なり、コミュニケーション方法にも関わっています。このことに気づくことができたのも、調査の機会をくださった先生方や協力してくださった方々のおかげです。
関西大学大学院で学びを得たことは、国語に関する幅広いことを教え、さまざまな人々と関わる今の仕事に大いに役立っています。研究者として、教員としての基礎をしっかりと固めることができたと思っています。
- ー 出願に先立って志望の指導教員へどのような相談をしたか、相談してよかった点
-
私の出身大学は他大学で、博士課程前期課程から関西大学にお世話になりました。博士課程前期課程の入試の際は、大学4年生の夏に大学院の入試説明会に参加しました。そこで指導を希望する先生に直接連絡を取ることと、関西大学の国語国文学専修が主催する学会(関西大学国文学会)への出席を勧めていただきました。メールでアポイントメントを取って実際に先生にお会いし、関西大学国文学会で先輩方、先生方のご発表を拝聴して、関西大学大学院のレベルの高さを感じました。相談というよりは意思表明に近い形で、自分がいまどのような卒業論文を書いているか、大学院で何をしたいか等だったと思います。
博士課程後期課程進学の際は進路に悩んだ時期があり、進学を半ばあきらめ、就職活動にかじを切ろうかという気持ちがありました。その中で、指導教員の先生には励ましのお言葉で背中を押していただき、博士課程後期課程進学への決心がつきました。
- ー TA・RA制度の利用にかかる経験談、よかった点
- 院生のうちから講義のお手伝いができるため、日々受けている講義がどのように運営されているのかを学ぶことができました。教員、研究者をめざす身として大変ありがたかったです。また、学内でアルバイトができるので研究に融通が利いたことも大変助かりました。
- ー 奨学支援制度の利用にかかる経験談、よかった点
- さまざまな奨学金がある中で、給付であるという点が魅力的でした。奨学金をいただけたおかげで、研究にも身が入ったと思います。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
- とにかく方言が好きで、方言をもっと専門的に学びたいという思いが大学院進学の動機でした。そのため、進学先は方言がご専門の先生がいらっしゃる大学院に絞りました。その中で関西大学大学院は方言がご専門の先生を含めた3名の国語学の先生がいらっしゃったので進学を希望しました。また、学部時代に図書館司書教諭の資格を取得したかったのですが、他の講義と重なって取れませんでした。それを取得できることも進学希望の理由でした。
- ー 関西大学大学院文学研究科の魅力
- 充実した図書館があり、研究に打ち込める大学院棟があり、素晴らしい先生方がいらっしゃいます。そのため多くの学生が集まり、励まし合いながらお互いを高め合える環境が関西大学大学院文学研究科にはあります。私もそうでしたが、高校や大学の非常勤講師やTAなどの仕事をしながら研究に励む院生も多く、仕事との両立も可能です。「学びたい」という意欲があれば、大きく力を伸ばすことができると思います。
経済学研究科

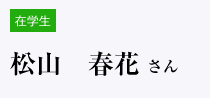
-
経済学研究科 高度専門職業人養成コース
博士課程前期課程 2024年4月入学
(入試種別:学内進学試験〔早期卒業〕)
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 研究テーマと概要
-
『インボイス制度が企業に与える影響』
- 概要:
- 未定
- ー 時間割
-
博士課程前期課程 1年次 春学期
1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 月 データ分析・
政策評価入門
講義租税法研究1
講義財政学研究1
講義火 経済学研究演習1
演習公共経済学研究1
講義水 租税政策研究1
講義木 租税論研究1
講義金 土
- ー 出願に先立って志望の指導教員へどのような相談をしたか、相談してよかった点
- 内部進学だったため、入学試験までに何をすればいいか、入学した際にどのようなところが学部と違うのか、過去に研究室にいた先輩たちがどのような研究をしていたのかを教えていただきました。教授の研究室にいた先輩の研究テーマを知れたのがとてもよかったです。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
- 税理士をめざそうと思い、進学しました。本学を選んだ理由は早期卒業制度があり、5年で学部と大学院(博士課程前期課程)を卒業できるからです。
- ー 指導教員名とその教員を選んだ理由や教員とのエピソード等
-
- 指導教員名:
- 橋本 恭之先生
- ー 大学院進学のための受験対策や事前準備
- 学内進学だったため、入学試験は口頭試問のみでした。そのため、自分の研究計画書を何度も見直し、さまざまな質問を想定し、それに対する答えを考えておくようにしました。また、学部のゼミで取り組んだ研究についても復習し、説明できるよう準備をして試験に挑みました。
- ー 修了後の進路希望
- 修了後は税理士になりたいと考えています。

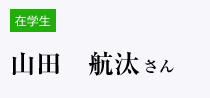
-
経済学研究科 経済学専攻
博士課程後期課程 2021年4月入学
(入試種別:一般入学試験)
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 研究テーマと概要
-
『貧困の世代間連鎖の解消について』
- 概要:
- 貧困が世代間で連鎖している状態を解消する方法として、教育政策をあげ、どのような政策をすると連鎖の解消に効果があると言えるのか、経済学の理論と実証の両面から研究を行っています。
- ー 時間割
-
博士課程後期課程 3年次 秋学期
1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 月 D経済成長論
特殊研究火 水 木 金 土
- ー 出願に先立って志望の指導教員へどのような相談をしたか、相談してよかった点
-
夏休み期間(8月下旬)に志望の指導教員と直接お会いしました。自分の研究したい内容を伝え、研究内容と分析手法が指導教員のそれと離れすぎていないかを確認しました。
対面での相談する機会を持つことで、指導教員とのコミュニケーションをより円滑にとることができました。
- ー TA・RA制度の利用にかかる経験談、よかった点
- 経済学部だけでなく、政策創造学部のTA(ティーチング・アシスタント)も担当してきました。私は将来、大学教員になりたいと考えているため、学部生の講義で先生方が学生へどのように接しているのかを間近で見られる貴重な機会となりました。
- ー 出身学部と所属研究科の専門分野が異なっている際に、特にどのような点に注意して受験準備を進めたか
- まずは、過去問題の分析を徹底しました。どのような問題が出る傾向にあるのか、問題数はどれくらいかなどを確認し、想定される問題についての勉強を行いました。
- ー 普段、どのような研究活動(手法)を行われているか、またその「おもしろさ」「難しさ」について
- 貧困問題の解消を研究テーマとして、経済成長論と教育経済学、地域経済学など複数の分野を横断して研究を行っています。自分でアンケート調査をしているため、データ分析の結果がどのようなものになったとしても、新しい発見になることが「おもしろさ」であり、調査までの課程がかなり長く、不確定要素も多いことが「難しい」点です。
- ー 関西大学大学院経済学研究科の魅力
- 経済学研究科の魅力は、先生方との距離感が近いことにあると思います。博士後期課程に所属している院生の数は他の大学院よりも少ないため、多くの先生とより濃いコミュニケーションをとれることが魅力です。

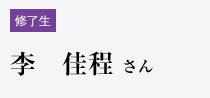
-
経済学研究科 経済学専攻
博士課程前期課程 2018年4月入学
(入試種別:外国人留学生入学試験)- 勤務先名:
- 花王(中国)投資有限会社
CSR担当
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 学位論文題名と概要
-
『中国農村間の所得格差-都市近郊農村と内陸農村の比較に基づいて-』
- 概要:
- 中国における農村地域間格差が形成される要因を分析し、政府による格差是正政策を検討します。小論では主に中国で東西に分布するおおむね同緯度で植生が似ている三つの県(鎮)の農村の状況に基づいて比較による分析を行います。加えて村レベルの具体例を、実地調査を踏まえて、所得格差の要因をより細かくあるいは多面的に検討し、格差の実態、形成する要因および政府から格差を是正する政策について研究します。
- ー 現在の仕事において大学院での研究や学修が生かされている場面や、学部卒業で就職をしている方との違いを実感する場面
- 大学院の研究テーマは中国農村間の所得格差で、中国農村に対して、実地調査したり、格差の形成要因を研究したり、中国農村の実態を把握しました。現職は企業社会責任活動を担当して、農村格差はまた中国社会の問題の一つなので、大学院の研究成果を利用して、中国農村問題を緩和できる企業プロジェクトを行って、企業イメージを向上できるように活躍しています。また、学部卒業で就職をしている方と違うところとしては、やはり問題を考える方法と思います。学部卒業の方より、多くの角度から問題を考え、単一の観点を信じるのではなく、さまざまな考え方を参考した上で、問題の本質を検討して解決方法を策定します。
- ー 出願に先立って志望の指導教員へどのような相談をしたか、相談してよかった点
- 大学院入学試験に合格する前に、半年間、外国人研究生として指導教員のもとで勉強しました。先生との相談と専門知識の勉強を通じて、中国農村や格差の問題に対して、興味をもちました。そして、先生からのたくさんのアドバイスの中で新たな視点を得ることができ、研究計画書も「中国農村間の所得格差」に変更しました。
- ー 出身学部と所属研究科の専門分野が異なっている際に、特にどのような点に注意して受験準備を進めたか
- 学部の専門は金融学で、大学院で経済学に変えました。経済学は金融学より国際関係、歴史や政策などに注目していますので、基礎的な経済学理論はもちろん、日常的に国際の変化、国間の関係などグローバルの情報を把握した上で、自分で考えることを意識したほうがいいと思います。
- ー 指導教員名とその教員を選んだ理由や教員とのエピソード等
-
- 指導教員名:
- 北波 道子先生
私は北波道子先生のもとで勉強しました。北波先生は長年的に東アジア経済圏を研究していますので、NIES、中国経済に対して独自の考え方を持っています。私は中国経済の研究を希望していたため、北波先生を指導教授として志望しました。また、論文で実地調査やインタビューが多いため、一年生の際に先生と同行で中国農村の実地調査を行いました。当地の農民のお話しから、内陸地域の農村状況を把握して、先生からも研究論文に対して意義あるアドバイスをいただきました。
- ー 大学院進学のための受験対策や事前準備
- 基礎的知識はもちろん、国際関係や社会問題に対して日常的に注目する必要があると思います。また、志望する指導教員の研究方向や主な課題を研究したり、できれば先生の授業を聴講したりすることはお勧めです。最後に、情報収集の能力は重要です。たくさんの文献の中で必要な情報を入手することおよびさまざまな観点に参考して、全面的に問題を分析する能力は大学院に進学する前に、準備すべきことだと思います。
- ー 現在の就職先・職業を選んだ理由
- 大学院で中国経済について勉強して、中国の社会問題、特に格差問題に対して興味をもちました。いま会社のCSR活動を担当していますので、企業社会責任をアピールしながら、寄付活動や教育支援などを通じて、中国農村問題や東西格差問題緩和していきたいと思います。また、社会問題に対する考え方を利用して、企業独自のCSR活動を提案・改善できるようにしました。

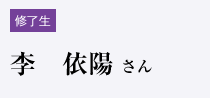
-
経済学研究科 経済学専攻
博士課程前期課程 2018年4月入学
(入試種別:外国人留学生入学試験)- 勤務先名:
- 総合職
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 学位論文題名と概要
-
『日本におけるドラッグストア業態の生成と発展』
- 概要:
- 本論文では、小売業態研究の一環として、日本におけるドラッグストアを取り上げ、その成立経緯や成長過程を明らかにすることを第一の研究目的とし、多様なフォーマットを提示しているドラッグストアの今日的変化について明らかにすることを第二の目的としました。ドラッグストアについては、できるかぎりフォーマットの異なる企業事例を取り上げて考察を進めました。
- ー 現在の仕事において大学院での研究や学修が生かされている場面や、学部卒業で就職をしている方との違いを実感する場面
-
物事を表面的にとらえることに留まらず、本質を見抜ける思考力が養われたと思います。
また、コミュニケーション能力も向上したと思います。そして、大学院の2年間で得られた「論理的な説明や説得力」、「理解力」が活用できていると感じています。
- ー 出願に先立って志望の指導教員へどのような相談をしたか、相談してよかった点
-
日本語学部出身のため、経済学に関する基礎知識や関連知識を大学院に入学する前に身に付けたいと思い、はじめは外国人研究生として経済学研究科に進学しました。当時はまだ中国にいたため、対面できず、メールでやり取りをしました。主に研究内容と今後の進学準備について相談させていただきました。先生のお返事はいつも丁寧かつ迅速なため、メールだけでもコミュニケーションをうまく取れました。
最初は新しい分野に関する勉強・研究がうまくいくかを心配しましたが、先生との相談で不安が解消でき、自信をもって試験に臨むことができました。
- ー 指導教員名とその教員を選んだ理由や教員とのエピソード等
-
- 指導教員名:
- 佐々木 保幸先生
経済学に興味を持ったきっかけがドラッグストア業態のため、小売業に関する専門知識を勉強したいと思い、流通経済学の専門家である佐々木保幸先生に連絡させていただきました。
これまでは、先生の大学院生・研究生と一緒にご飯に行ったり、合宿に行ったりしました。とても楽しく大学院生活を送りました。
就職活動の時も先生からサポートをいただき、学業と就職活動を両立することができました。
卒業後もよく先生と連絡を取り、アドバイスをたくさんいただきました。
佐々木先生には本当に感謝しております。
- ー 大学院進学のための受験対策や事前準備
-
私は外国人研究生として半年ほど(1学期)先生のもとで勉強していたため、不明点は直接伺うことができました。さらに、大学院生と一緒に授業を受けていたため、流通経済学以外の知識も身に付けられました。
また、図書館などの利用もできたため、とても勉強しやすい環境でした。
- ー 現在の就職先・職業を選んだ理由
- 日本の小売業のイノベーションに力を入れたいため、現職を志望しました。
または多様な価値観・文化を持つ人々と一緒に仕事をしたいため、外資系企業への入社を決めました。
- ー 関西大学大学院経済学研究科に進学を考えている方へのメッセージ
- 関西大学大学院での生活を一文字にすると、やはり「光」だと思います。親切で優しい先生と出会い、同じ志をもつ仲間と出会い、素敵な大学院生活を送りました。
また、学部生と比べると、研究室及び図書館の利用はより優遇されるため、研究に最適な環境ではないかと思います。
経済学研究科に少しでも興味をもつようになったら、ぜひ進学を検討してみてください!
商学研究科

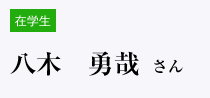
-
商学研究科 商学専攻
博士課程前期課程 2023年4月入学
(入試種別:学内進学試験)
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 研究テーマと概要
-
『年末調整制度の在り方の再検討』
- 概要:
- 年末調整制度は昭和22年(1947年)の導入以来その制度は在り方が代わらないまま続いています。しかし、当時とは比べものにならないくらい我々の生活は進化しています。私は、年末調整制度の今後のあるべき姿を研究していきたいと思います。
- ー 時間割
-
博士課程前期課程 1年次 秋学期
1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 月 現代ファイナンス・
会計研究租税法研究2 火 租税論研究2 租税論研究2 水 会計学 木 金融法研究2 金 土
- ー 出願に先立って志望の指導教員へどのような相談をしたか、相談してよかった点
- まず一番はじめにお会いした際に指導教員の元に入らせていただく許可を得ていましたので、相談内容は基本的に大学院の入試についてでした。どんな内容の勉強をどのレベルまで持って行けばよいのかを相談させて頂きました。優しくおおらかに接してくださり、大学院入試へのやる気が沸き、相談させていただき良かったなと思います。
- ー 大学院進学のための受験対策や事前準備
- 大学院進学のための受験対策は、参考資料に書かれたものを自分の中で完璧になるまでに反復して取り組むことだと思います。自分自身大学院進学を決めたのが1月半ばで2月の入試まで時間がありませんでした。その中でも自分の決めた参考資料だけをとりあえず必死にやった結果、特待生になることができました。これ!と決めたものを頑張ってください。
- ー 修了後の進路希望
- 修了後の進路は、東京の税理士事務所で働こうと思っています。自分自身、20代で税理士として独立するというのが一つの目標であるので、一通り税理士として力をつけるという意味で、中小や零細企業の中で業務を行いたいと考えています。どこの企業に入ろうともやるのは自分なので、自分の夢に向かって突き進んでいこうと思います。
- ー 現在の就職先・職業を選んだ理由
- 私が税理士を志した理由は父親が税理士をしていて、無意識に税理士というものに興味があったからです。しかし、実際の仕事を知らない状況でしたので、税理士事務所でアルバイトを探し、働かせて頂くことになりました。そこで仕事を知り、魅力や大変さも知った上で、この仕事をしたいと思うようになりました。
- ー 関西大学大学院商学研究科の魅力
-
関西大学大学院商学研究科の魅力は、一昨年からできたTASプログラムだと思います。そこは税理士を養成するために作られたプログラムで、周りが全員税理士をめざしており、これまでの大学生活とは違い、刺激を得られる環境があり、そこに良さを見いだせます。
また、留学生の方も多いので、そういった方とも交流があり非常に楽しいです。

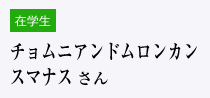
-
商学研究科 商学専攻
博士課程前期課程 2023年4月入学
(入試種別:外国人留学生入学試験)
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 研究テーマと概要
-
『グリーンマーケティングにおける消費者コンフィデンスの影響』
- 概要:
- グリーンマーケティングでの広告などは消費者の懐疑心を及ぼす、本研究はメタ認知における、消費者の自信(コンフィデンス)での影響を調べたいです。
- ー 時間割
-
博士課程前期課程 1年次 秋学期
1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 月 新興市場
経済研究Ⅱ
講義消費者
行動論研究Ⅱ
講義火 水 現代流通・
国際ビジネス研究
(グローバル・リテイリング)
講義現代流通・
国際ビジネス研究
(グローバル・リテイリング)
講義木 研究方法論(定量)
講義金 合同演習
(グローバル・リテイリング)合同演習
(グローバル・リテイリング)/ 日本語アカデミック・
ライティングⅠ
講義土
- ー 出願に先立って志望の指導教員へどのような相談をしたか、相談してよかった点
- 私は大学院に出願する前に、商学研究科の岸谷和広教授にメールを通じて相談させていただきました。相談内容は商学研究科のプログラムの詳細、そして特定の奨学金を受け取っていることによる、普段と少し異なった出願手続きについてでした。いずれも相談してよかったです。
- ー 奨学支援制度の利用にかかる経験談、よかった点
- 国費奨学金を受け取っています。日本に入国前から母国の日本大使館に書類を出願し、面接なども受けました。2022年4月から奨学金を受け取り、コロナ禍ではありますが、航空券などのサポートはよかったです。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
- 大学院に進学した理由は、大学のみの専門知識は不足であると感じたからです。希望のキャリアに就くためにも、より高度な知識、積み重ねた経験が必要と思いました。また、関西大学商学研究科のグローバル・リテイリング・プログラムは希望の分野と一致し、入学を志望しました。
- ー 大学院進学のための受験対策や事前準備
- 大学院入試の準備は主に過去問題を使って練習すること、そして指導教員から専門科目の指導を受けることです。そのほかには、テキストでの学習、そして漢字の学習でした。
- ー 修了後の進路希望
- 大学院の修了後の進路は、博士課程後期課程に進むか、日本で就職するかを考えています。また、就職する場合には日本のメーカー企業、BtoB企業、もしくはコンサルティング関係企業に就職したいと考えています。

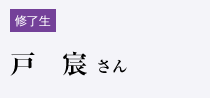
-
商学研究科 商学専攻
博士課程前期課程 2022年4月入学
(入試種別:外国人留学生入学試験)
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 学位論文題名と概要
-
『日本企業の実体的裁量行動』
- 概要:
- 本論文は、機会主義的な利益調整行動に注目し、日本企業は損失回避、減益回避および経営者予想利益達成のために利益調整の方法である実体的裁量行動をどのように行われているか、また、それと会計的裁量行動はどのように使い分けているのかを明らかにすることができました。また、このような利益調整行動は将来業績にどのような影響を及ぼすのかを明らかにしました。
- ー 現在の仕事において大学院での研究や学修が生かされている場面や、学部卒業で就職をしている方との違いを実感する場面
- 利益調整行動とは一般に認められる会計原則の範囲内で利益を調整する行動であり、情報提供機能を促進するための効率的選択と情報提供機能を損なう機会主義的な行動の2種類があります。近年では、機会主義的な行動に関する利益調整行動の研究が主流となっています。このうち、利益ベンチマークの達成のために、会計的裁量行動と実体的裁量行動の影響要因に関する研究も盛んであります。しかしながら、これらの研究では、会計的裁量行動、あるいは実体的裁量行動のどちらの影響要因のみを注目して研究しており、両方法の間に代替関係に関する研究が多くありません。私は博士後期課程において、日本の四半期における会計的裁量行動と実体的裁量行動との代替関係および抑制関係をメインとして、研究を展開しています。
- ー 奨学支援制度の利用にかかる経験談、よかった点
- 私は博士後期課程から関西大学大学院特別給付奨学金をいただいています。博士後期課程は授業回数が少ないが、研究に必要な時間は多いので、アルバイトする暇があまりなく、研究に必要なテキストや学術書は給付型奨学金を使って購入しています。留学生の自分にとって、奨学金制度は非常に重要だと思っています。
- ー 指導教員名とその教員を選んだ理由や教員とのエピソード等
-
- 指導教員名:
- 乙政 正太先生
大学院進学を決意した頃、私は財務会計の実証系の研究の、確実なデータに基づいて結論を導き出すという点に惹かれました。また、粉飾結果とは異なる利益マネジメントという行為に興味を持ち始め、財務諸表のデータを使用する際に、計算式に基づき指標の算出が必要ということが分かりました。そこで財務諸表分析が専門の乙政先生と出会い、先生のもとで勉強させていただくことになりました。
- ー 大学院進学のための受験対策や事前準備
-
私は指導教員を決めてから受験準備を始めましたので、関西大学の入試情報に入試用の参考図書があって、それを参考にしながら過去問を解き筆記試験の準備をしました。
また、面接の準備では、自分の研究計画書を踏まえ、面接での想定問答を準備し、事前に何度もリハーサルしました。
- ー 普段、どのような研究活動(手法)を行われているか、またその「おもしろさ」「難しさ」について
- 私は修士段階から、定量系の研究をしており、修士論文では主に回帰分析を用いた研究でしたが、現在では利益マネジメントの疑われる企業の特定の際に、ヒストグラムや折れ線グラフを使ったりもします。どちらでも統計知識が必要な研究手法で、最初は苦労しました。しかし、その意味が分かれば分かるほど、得られた結論の説得力の強さを感じることができます。
- ー 関西大学大学院商学研究科の魅力
- 関西大学の会計分野に実証分析分野の先生は多いため、私が論文を読む、あるいは実証分析を行う際に、何か自分の力で解決できないことがあれば、先生のお力をお借りすることができることが関西大学大学院商学研究科の魅力だと思います。

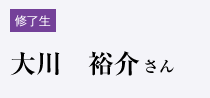
-
商学研究科 商学専攻
博士課程後期課程 2019年4月入学
(入試種別:一般入学試験)- 勤務先名:
- 大阪経済大学 経営学部 専任講師
/公認会計士
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 学位論文題名と概要
-
『地方自治体における財政規律の維持に向けた公会計情報の活用可能性』
- 概要:
- 近年、地方公会計の導入が進められていますが、地方公会計の考え方やその財務書類から得られる情報が、財政規律を中心とした地方自治体の運営にどのように貢献できるかを、定性、定量両方の手法により研究します。
- ー 現在の仕事において大学院での研究や学修が生かされている場面や、学部卒業で就職をしている方との違いを実感する場面
-
現在は大阪経済大学において専任講師をさせていただいていますが、現在、大学において新たに教職に就くためには、博士号の取得はほぼ必須の条件ともいえる状況です。
また、公認会計士としての業務も継続していますが、博士課程における経験により身に付けた論理構成力、文章力など、論文を作成するための基本的な技能は、例えばクライアント向けの報告書を作成するときなどには非常に役に立つものと感じています。さらに、博士号を有すること自体が、クライアントからの信頼を得る際に大きな効果を発揮するという実感も得られています。
- ー 出願に先立って志望の指導教員へどのような相談をしたか、相談してよかった点
- 私は、公務員として予算編成や決算等に関わる業務に従事した後、公認会計⼠となって主に地⽅⾃治体向けのコンサルティング業務に従事してきましたが、それと並⾏し、専⾨領域である「公会計」(政府・地⽅⾃治体の会計)について、⾃⼰流での論⽂の執筆などを⾏っていました。また、指導教員も公認会計⼠でいらっしゃいますので、出願前から公認会計⼠協会等の場で時々お会いし、いろいろお話をさせて頂いていました。その中で、公認会計⼠としての業務経験と、これまでに執筆した論⽂等の実績があれば、前期課程からではなく、個別の⼊学資格審査を受けることで、後期課程からの⼊学の可能性もあるとのお話を頂きました。また、資格審査に先⽴って、実績となりえる論⽂等の基準なども教えて頂いたことなどから、無事に受験資格を認めて頂くことができました。
- ー TA・RA制度の利用にかかる経験談、よかった点
-
1年次に、「M研究⽅法論(定量)講義」を受講させていただき、以前から⾝に付けなくてはと考えていた統計学について、ようやく教科書を最後まで読破することができました。さらに、統計ソフトを⽤いた分析⼿法も学ばせていただき、それを⽤いた論⽂も執筆していました。
それを受けて2年次には、同じ講義においてTA(ティーチング・アシスタント)を務めさせていただき、他の学⽣への指導補助や、提出された課題を⾒てそれに対してコメントをするなどの経験をさせて頂いています。このような経験により、⾃分⾃⾝の知識や技能もより深まっていくのを実感できましたし、その成果は博士論文にも反映できたと思っています。
- ー お仕事との両立の工夫等について
- 在学中は、公認会計⼠としての個⼈事務所を営みながら研究活動を⾏っていますが、会計⼠としての業務量は限定的に抑え、研究活動の時間を確保していました。また、指導教員には講義・演習の時間も配慮して頂き、通学しやすい環境を整えて頂けました。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
- 以前から、公認会計⼠としての私の専⾨領域である「公会計」(政府・地⽅⾃治体の会計)について、⾃⼰流での論⽂の執筆などを⾏っていました。また、はるか以前になりますが、就職する前には研究者としての道に進みたいとの希望を持っていたこともありました。そのような状況で、私の専⾨領域に⽐較的近い分野を専⾨とされる指導教員にお声がけを頂いたことにより、⼀念発起して⼤学院への進学を決めたものです。ですので、志望先は指導教員のいらっしゃる本学以外は考えられませんでした。
- ー 大学院進学のための受験対策や事前準備
- ⼤学院進学のための準備としては、まずは⼊学試験の対策が必要となります。専⾨科⽬については、⾃分の専⾨分野の知識を深めていくしかありません。英語に関しては、かなり厳しいものと考えるべきですが、結局はたくさんの英語の論⽂を読みこなすことが重要と思います。特に、⾃分の専⾨分野にかかる論⽂を多読しておけば、⼊学後の研究活動にも⾮常に役に⽴つと考えられます。
社会学研究科

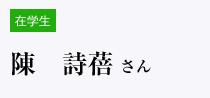
-
社会学研究科 社会学専攻
博士課程前期課程 2023年4月入学
(入試種別:一般入学試験)
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 研究テーマと概要
-
『少年犯罪の再犯防止のための効果的な支援のあり方〜少年院出院者へのインタビュー調査から〜』
- 概要:
- 非行少年の再犯率が減少していないという現状から何が彼らの再犯をもたらしているのかについて実際に少年院出院者にインタビュー調査を行い、どのようなことが彼らの再犯防止要因となっているのかを明らかにすることです。
- ー 時間割
-
博士課程前期課程 1年次 秋学期
1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 月 国際社会学研究 火 社会学特殊研究
(若者論研究)現代社会論研究 社会福祉学研究 水 合同演習1b 合同演習1b 木 専門文献研究 家族社会学研究 金 土
- ー 出願に先立って志望の指導教員へどのような相談をしたか、相談してよかった点
- 相談させていただいたことは受験勉強のことや先生の研究室で自分のしたい研究ができるのかということです。実際に入学して自分のしたい研究と先生の研究が一致していなくてはならないので相談をしたのはとても大事だと思いますし、受験では研究計画書を提出しないといけなかったですが書き方などについてもアドバイスをくださったので安心できました。
- ー 出身学部と所属研究科の専門分野が異なっている際に、特にどのような点に注意して受験準備を進めたか
- 私は出身学部が法学部だったので社会学、社会福祉学に関する専門用語はほとんど知りませんでした。そのため受験に向けての勉強ではとにかく社会福祉用語集を読み、専門用語を理解するようにしていました。それと同時に面接では自分はどのような研究がしたいのか、なぜそのような研究がしたいのかなど聞かれるのでその辺りも答えられるように準備していました。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
- 大学院進学を決めたのは大学1年生の後半ぐらいの時で、きっかけは法学部の導入演習という授業の先生から大学院についての話を聞いたことでした。大学院は大学のゼミとは違い自分の専門についてもっと掘り下げて研究ができるということで、その時すでに少年犯罪の再犯防止について気になっていたこともあったため大学院で研究しようと決めました。
- ー 普段、どのような研究活動(手法)を行われているか、またその「おもしろさ」「難しさ」について
- 普段は論文を探し、先行研究として利用できそうな箇所があればそこをピックアップして研究計画書に組み込む作業や、私の調査方法としては少年院出院者に対するインタビュー調査なので調査対象施設となる施設に出向き、実際に彼らにインタビューをしています。インタビューをした後は録音させていただいたものを文字起こしし、トランスクリプトとしてまとめたりしています。
- ー 関西大学大学院社会学研究科の魅力
- 社会学研究科の魅力は自分の専門分野だけでなく社会学という幅広い分野においての知識が得られること、そして合同演習という研究報告会の授業が1ヶ月に1回あり、そこでは社会学研究科全員の先生方が自分の研究状況を見てくださり、指摘してくださるのでさまざまな方向から自分の研究について考えることができるというところです。

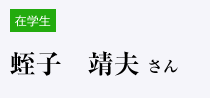
-
社会学研究科
マス・コミュニケーション学専攻
(2024年度からメディア専攻に名称変更)
博士課程前期課程 2022年4月入学
(2024年3月修了)
(入試種別:社会人入学試験)
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 研究テーマと概要
-
『メディア産業の構造変容から見た地上波テレビ・ネットワーク成立に関する考察〜インターネット社会が与えた民放ローカルテレビ局へのビジネス的影響〜』
- 概要:
- インターネット、動画配信社会が与えた地域民放テレビへの影響を地上波テレビのビジネス構造に焦点をあてどのような構造変容を迫られているか、要因を分析し放送現場へ与えている現状と今後の展望を考察する。
- ー 時間割
-
博士課程前期課程 1年次 秋学期
1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 月 火 放送メディア研究 メディア産業研究 水 広告研究 合同演習1b 合同演習1b 木 メディア技術研究 国際
ジャーナリズム研究演習B
メディア産業研究金 土
- ー 出願に先立って志望の指導教員へどのような相談をしたか、相談してよかった点
- 出願前に、コンテンツ論かメディア論なのか、漠然としていた研究テーマの方向性を相談することができた。テレビの実務を経験している社会人学生だからできる現場のメディア状況、作り手や送り手、受け手に通じる研究テーマは何か、論文を書くことだけが大学院進学の目的でなく、地域放送メディアと社会に役立つ研究をすることが目的であることを共有できたことが良かった。また中国人留学生が多く、ジェンダー研究の希望者が多い、また平日昼の授業では社会人院生が極めて少ない等の現状を事前に伺えたことで大学院進学のイメージギャップに戸惑うことがなかった点も良かった。
- ー お仕事との両立の工夫等について
- 覚悟はしていたが、時間・年齢・体力的に仕事との両立は非常に厳しい。夜間、土曜日授業演習のある経営学系の社会人大学院コースと異なり、平日昼間の履修しかできないため、履修科目も仕事に合わせて選ぶことになる。早朝一番に出社し、前日当日のメール連絡チェックをしてから大学院朝1限目の授業を週3日必ず取り、勤務先と往復して午後からの授業出席、また勤務先に戻り終電まで勤務。金曜夜から自室に籠もって土日は翌週の課題レポート作成、自身の論文テーマ研究と睡眠時間との闘いになる。夏期・冬季休暇中に勤務先の仕事をシフトさせるなど年間の計画性を持つことが最も重要だ。ただ同じ専攻で他に社会人学生がおらず仕事との両立を相談したり一緒に頑張れる存在がいれば、あるいは他大学院・他学部の社会人学生の話を聞く機会があれば、少し気持ちが楽になれるのでないか、と思えた。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
- 在京の大学(学部生)時代にジャーナリズム専攻から在阪テレビ局に入社し、35年以上コンテンツ制作現場に従事するキャリアの中で学生の頃からメディアビジネスの資本の論理とジャーナリズムが両立するのか、問題意識があり現場を離れた段階で民放テレビ研究やテレビ局で担当していたスポーツジャーナリズムとメディア研究を現場からの視点でやってみたいと考えていた。関西大学大学院は、メディア研究の領域が広く本来アカデミアとなじみにくい産業論の研究もあり、指導教授も在籍されていたため。もう一つは、社会人学生として研究と仕事と両立させたいために、物理的に勤務先から30分以内で通学、帰社できるという理由が大きかった。
- ー 指導教員名とその教員を選んだ理由や教員とのエピソード等
-
- 指導教員名:
- 三浦 文夫先生
大学院進学説明会で当初、研究テーマとして考えていたスポーツジャーナリズムと地域放送メディア論を担当されていた教授が退官されることを知り、その説明会でテレビメディア産業論に関心があるなら、ということで三浦教授の研究を紹介して頂いた。三浦先生が大手広告会社出身で、テレビビジネスの実務家であったことから、メディアの現場経験を通じて地域民放ビジネスの構造と役割を体系化し、テレビ放送開始70年を迎えた区切りの年に、構造変容を迫られているこれからのテレビの将来像について研究できるのでないか、と考えた。三浦教授は、メディア産業をクリエイティブ、ポリシー、マーケティング、テクノロジーの4つの領域から研究されていること、アカデミアのメディア研究では見落とされている現場の実務家に通じる研究である点に共感し、テレビ研究のテーマ設定も含めて三浦先生のご指導を得たいと考えた。
- ー 大学院進学のための受験対策や事前準備
- 指導教員の先生と連絡を取らせて頂いた際に、受験対策や事前準備のヒントを頂いた。社会人で準備に時間が限られていることがあり、筆記試験の比重が高いこと、基本的な社会学用語が説明できるように準備しておくこと、社会学用語は非常に範囲が広いので万遍なく習得するのは難しいが、入試の過去問に絞って関連用語を広げていく形で学習した。具体的には、社会学用語を自分の志望動機に合わせる形でメディア論、ジャーナリズム論、コミュニケーション論、ネット社会等テーマを整理し、テーマ毎に用語参考書籍やネット論文で用語ノートを作成し、テスト形式でレポート用紙に書いて回答、隙間時間に自作ノートと答え合わせする勉強方法を行った。

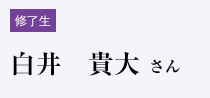
-
社会学研究科
マス・コミュニケーション学専攻
博士課程前期課程 2019年4月入学
(2024年度からメディア専攻に名称変更)
(入試種別:学内進学試験)- 勤務先名:
- 富士通株式会社
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 学位論文題名と概要
-
『済州島人にとってのメディア』
- 概要:
- 鶴橋にあるコリアタウンは、韓国人が多く居住しているが、原点をたどると済州島出身の人が多いです。なぜ済州島人が多く住むコミュニティが出来上がったのか、船というメディアに注目しコリアタウンの成立史を紐解く研究をしておりました。
- ー 現在の仕事において大学院での研究や学修が生かされている場面や、学部卒業で就職をしている方との違いを実感する場面
-
事象から原因を求めるアプローチです。
研究では、事象から直接原因を見つけ、さらに仮説を立てながら根本原因を探し出すというアプローチ方法が主でした。これは今の仕事にもそのまま生かされています。
システムを作る過程で不具合は必ず生じます。ただ起きた原因の求め方でシステムの品質は大きく変わります。
例えばAからBの接続で不具合が見つかるとします。Aの接続方法が悪かったのが直接原因です。ただ、Bの接続様式が変更されていたことがAの担当に伝わっていなかったとします。するとBのコミュニケーションが根本原因となります。Bのコミュニケーションに対策を取ります。もしAを修正するだけであれば、その先もBに関する不具合が多く見つかっていた可能性があり、システムの品質を担保することができなくなります。
研究もシステムも同様に、事象から直接原因、根本原因を求めることが必要とされるため、大学院でここを培った点は今でも役に立っています。
- ー 出願に先立って志望の指導教員へどのような相談をしたか、相談してよかった点
-
指導教員とは、大学院に進学した後の過ごし方や、その後の進路について相談していました。
学部の頃と比較し、どのような授業や研究の場があるのか、どのような大学のサービスを受けられるのか、また修士課程修了後の進路について、研究室に所属されている先輩方も交えながら相談し、進学後の不安な点を解消することが出来ました。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
-
学びの内容に大きな関心があり、もっと深く学びたいと思ったためです。
私は学内進学でしたが、大学の頃から授業の内容一つ一つのメディアの捉え方に大きな関心を寄せていました。例えば、普段何となく見ているテレビやCMの中に込められた意味を知るとメディアの見方が大きく変わります。メディアに対する考えをもっと深く学びたいと思いました。
卒業研究においても、自分の研究に対して、学生、先生同士で意見を交わすことで、相乗効果的に論文の質が上がることを感じました。大学院に進学し、もっと質の高い研究に取り組みたいという思いが強くなりました。
- ー 大学院進学のための受験対策や事前準備
-
大学院の入試は一問一答のような知識だけでなく、知識を用いて文章にする力も求められます。また範囲もさまざまで、幅広く深く頭にインプットしておくことが求められます。
対策として、まずメディアに関する文献を熟読しました。文献に関する言葉が出てくると、それを説明出来るくらいまでです。その後、過去問題を用いて、出題される知識・用語に対して自分の言葉にして書くトレーニングを行っておりました。
- ー 普段、どのような研究活動(手法)を行われているか、またその「おもしろさ」「難しさ」について
-
歴史など事象に対して仮説を立てて、新聞や文献などから説を立証していくというのが主でした。また新聞や文献の内容からさらに仮説・立証を繰り返し、深掘りを続けていました。
図書館を何となく歩き何となく手に取った文献からアイデアが広がった時、特に面白さを感じました。関係ないと思っていた点と自分の研究という点が繋がる瞬間です。
文献を探すのに苦労した時も多々ありました。韓国に関する文献は多くありますが、済州島に関する文献と言うと一気に減ります。そこについては難しさを感じましたが、取り組んでいる人が少ないかもしれないと、やりがいにも繋がりました。
- ー 関西大学大学院社会学研究科の魅力
-
マス・コミュニケーション学研究科には幅広さがあります。
多様なメディアを研究されている学生や先生がいるため、それぞれのメガネを通した考え方を知ることができ、自分にない考え方を養ってくれます。また学生には国内外問わずさまざまなところの出身の方々がおり、出身が違うだけで意見の幅広さが増し、多くの知見を手に入れることができます。
学生と先生の距離の近さも魅力です。例えば、所属研究室でない先生の授業で、私の研究に関する授業があり、招待していただくことがありました。授業の後研究内容にも踏み込んださまざまな議論をする時間もいただき貴重な時間を得られました。

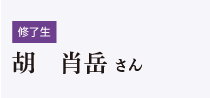
-
社会学研究科 社会システムデザイン専攻
博士課程前期課程 2016年4月入学
(入試種別:外国人留学生入試)- 職種:
- 総合職
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 学位論文題名と概要
-
『日中企業における賃金管理の比較分析―職能給・職務給を中心に』
- 概要:
- 本論文は、日本と中国の基本給体系を比較しながら、それぞれの基本給管理の特徴や実態を確認した上で、現在の中国賃金システムの課題及び、今後の方向性を検討したものです。
- ー 現在の仕事において大学院での研究や学修が生かされている場面や、学部卒業で就職をしている方との違いを実感する場面
- 学部卒業で就職をしている方との違いは、物事においての「考える力」だと感じています。学部時代は主に知識を勉強しましたが、博士課程前期課程在籍時は問題を発見し、知識を用いて解決することに努力しました。これも社会人になってからさまざまなプロジェクトに参加する際、絶対に欠かせないスキルの1つです。
- ー 普段、どのような研究活動(手法)を行われているか、またその「おもしろさ」「難しさ」について
- 自分の研究課題に熱心に取り組みました。より説得力のある論文を完成させるために、大量の文献を調べ、理論研究を組み立てると同時に、実態を把握するために地道な事例研究にも多くの時間を割きました。多くの方からご質問やご意見をいただき、考え方の多様さ、深く考えることの重要さ、研究の壁に何度ぶつかっても挫けずに乗り越えることの大切さを感じながら、自由に思考する充実した歳月を送ることができました。
- ー 出願に先立って志望の指導教員へどのような相談をしたか、相談してよかった点
- まず自分が関心を持っている研究科の教授へメールで連絡しました。教授から返答をいただき、この研究科で学ぶことができる知識および、進学するにはどのような準備が必要かを詳しく説明していただきました。当時迷っていた私にとって入試に対する不安や迷いが軽減され、非常に貴重な機会となりました。
- ー 奨学支援制度の利用にかかる経験談、よかった点
-
関西大学大学院は十分に学生の学費及び生活を配慮し、奨学金制度に大きな支援を与えていると感じております。
博士課程の2年次に入ると、国際部と指導教員の推薦をいただいて、無事文部科学省留学生奨励金を獲得しました。そのおかげで自分の研究課題に熱心に取り組むことができました。
- ー 出身学部と所属研究科の専門分野が異なっている際に、特にどのような点に注意して受験準備を進めたか
-
異なる専攻を学ぶ時に重要なことは、本当にその分野に興味があるか確認しなければなりません。そして、自分の将来キャリアに役立つかどうかを考える必要もあると思います。
「千里の道も一歩から」ということわざのように、ゼロから出発し、まず研究生として、専門基礎知識をきちんと学んだ上で、入学試験に挑戦しました。
- ー 関西大学大学院社会学研究科の魅力
- 社会学研究科では、自らの研究課題に熱心に取り組みました。ゼロから出発し、自身で決めた目標へ突き進んでいった2年間はあっという間でしたが、学問の面白さや厳しさ、考える力の多様さや重要さ、研究の壁に何度もぶつかっても挫けずに乗り 越えることの大切さを感じながら、自由に思考する豊かな歳月を送ることができ、私の人生において大変有意義なものとなりました。
総合情報学研究科

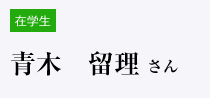
-
総合情報学研究科 社会情報学専攻
博士課程前期課程 2022年4月入学
博士課程後期課程 2024年4月入学
(入試種別:学内進学試験)
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 研究テーマと概要
-
『ポスター作成におけるアイディアスケッチにICT機器を導入した際のイメージ生成と意識』
- 概要:
- 本研究は、ポスター制作におけるアイディアスケッチをイラストソフトで描いた際のイメージ生成と意識を明らかにし、また、ICT機器の活用方法とその意識を探索的に探ることを目的としている。実践を行った後、中学生4名を対象にインタビュー調査を行った。その結果、{イメージ生成}{画像検索の活用と意識}{タブレット活用と意識}の3つの概念が抽出され、概念間の関係からイメージ生成の過程と、活用時の課題が明らかとなった。
- ー 時間割
-
博士課程前期課程 2年次 春学期
1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 月 火 (学部ゼミ) 情報通信技術(ICT)
と新しい教育情報通信技術(ICT)
と新しい教育水 論文指導 木 (コミュニケーションと行為TA) 金 土
- ー 出願に先立って志望の指導教員へどのような相談をしたか、相談してよかった点
- 博士課程前期課程進学にあたって、受け入れの可否を尋ねました。その際、進学に際してどのように勉強を進めていくべきかについて、助言をいただきました。本格的に研究者の道に進むということもあり、不安でいっぱいでしたが、励ましの言葉をいただくことができ、自信を持って進学を決意することができました。
- ー TA・RA制度の利用にかかる経験談、よかった点
- 私の入った授業は、コミュニケーションが多い授業でした。TAという学生に近い立場だったため、身近に感じてもらえるようにと工夫することが楽しかったです。TAをしてよかったと思う点は、授業する側(手伝う側)として授業を捉えることができたことです。授業を受ける側とする側では見える景色が大きく違います。大学の授業をする先生と同じ視点で授業を見られたことは、今後、本格的にアカデミアの世界へ入っていく自分にとって大きなメリットだったと思います。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
-
前期課程進学を選んだ理由は、研究が楽しいからというとても単純なものです。最初に研究の楽しさに気がついたのは、学部の卒業研究でした。試行錯誤の末結果が見えることは、パズルが完成していくような面白さがあります。その魅力に惹かれたことが、私が前期課程に進学し、さらに後期課程まで進んだ根本的な理由です。
本学を選んだ理由は、自分の興味関心と通ずるものが多かったからです。また、尊敬できる先生方に指導をしていただけるという素晴らしい環境に魅力を感じました。
前期課程進学時は、後期課程への進学に魅力を感じながらもアカデミアに骨を埋める覚悟がありませんでした。しかし、進学後、研究をすることの更なる楽しさに気が付きました。後期課程に進学すること、そして進学した後に進む路は甘くないと知っているつもりです。それでも楽しく研究を続けたいと思っている自分の気持ちに素直に従おうと思います。
- ー 指導教員名とその教員を選んだ理由や教員とのエピソード等
-
- 指導教員名:
- 黒上 晴夫先生
私の担当教員は黒上晴夫先生です。
私は、学部のゼミ時代から、黒上先生に担当教員をしていただいています。先生は、研究を愛していて、若い研究者を育てることに熱心で、そして、学生思いです。我々学生に、いろいろなチャンスをくださいます。先生のもとで学んでいると視野が広がりますし、何よりとても楽しいです。先生のもとで行った卒業研究にて、研究の魅力に気がつきました。前期過程では、もっと広いアカデミックな世界を見せてもらいました。研究することに楽しさを見出せるようになったのは、先生のおかげだと確信しています。研究者という点だけでなく、人として本当に尊敬できる方に師事したいと強く思い、黒上先生のもとで研究を続けているわけです。学生から愛される先生、それが黒上先生です。学生みんなで黒上先生の背中を見ながら勉強することが楽しくて仕方ありません。
- ー 関西大学大学院総合情報学研究科に進学を考えている方へのメッセージ
- 大学院は大学よりも深い世界です。底が見えない沼のようだと、仲間で冗談を言い合うほどです。沼にはまってもがくことは多いですが、ありがたいことに相談しあえる仲間がいます。縦の繋がりがあり、横の繋がりがあり、決して孤独ではありません。めざすところは違えど、決して一人ではない環境が整っているのが我が研究科だと思います。そんな環境で、研究への魅力を知り、学ぶことができる機会があることは、幸せなことだと思います。関西大学大学院総合情報学研究科に進学を考えている皆様、ゴールの違う前人未到の地をめざして、仲間と学ぶことは素晴らしいことです。私は、博士課程前期課程に進学してよかったと思っています。とても魅力的な2年間でした。

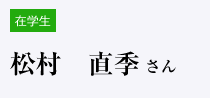
-
総合情報学研究科 総合情報学専攻
博士課程後期課程 2024年4月入学
(入試種別:一般入学試験)
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 研究テーマと概要
-
『RPGにおける擬似対面対話における発話積極性評価と外国語学習支援』
- 概要:
- 本研究は、外国語発話に自信のもてない学習者の発話積極性を向上させることを目的とします。近年注目を集めるゲーミフィケーションやコミュニカティブ・アプローチに着目し、RPGにおけるゲームキャラクタとのインタラクションに発話積極性評価を取り入れます。学習者の発話失敗を恐れず主体的で友好的な発話態度の度合いに応じてゲームキャラクタも応答表現を変化させます。これにより、ゲーム内で会話の成功体験を楽しく積むことが期待できます。
- ー 時間割
-
博士課程後期課程 1年次 秋学期
1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 月 火 水 仮想コミュニケーション
メディア科学特殊研究
演習1木 専門演習TA 卒業研究TA 金 土
- ー TA・RA制度の利用にかかる経験談、よかった点
-
博士前期課程に在籍中から、専門演習、卒業研究のTAを継続的に行ってきました。
学部生との交流においては、研究の中で獲得してきた知識を活用しサポートする中で「どのように言えば伝わるか」「どうすれば研究の視野が広がるか」について考えさせられることが多く非常に勉強になりました。学部生との交流は、自分にとって新たな気付きを多くもたらしてくれて、刺激的で非常に良かったです。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
- 博士前期課程では、米澤教授のご指導のもと、ユーザの発話韻律やジェスチャから発話積極性を数値化するシステムを実装し、その妥当性について検証を行ってきました。しかし、博士前期課程の卒業段階において、発話積極性評価システムはまだ拡張の余地があり、技術の応用に関して議論できる内容が豊富に残されていました。特に、近年注目を集めるメタバース空間において、発話積極性の強化にとどまらず国際交流を視野に入れた発話態度の学習ができる可能性についてさらに深堀りしたいと思い、本学の大学院博士後期課程への進学を決意しました。
- ー 指導教員名とその教員を選んだ理由や教員とのエピソード等
-
- 指導教員名:
- 米澤 朋子先生
米澤教授には私が学部生の頃からご指導いただいています。かつて研究内容に思い悩み、方向性が定まらず思うように進捗が出ない時期がありました。そんな私を先生は優しく諭し、疑問点や懸念点を丁寧に解決しつつ、研究が面白く納得感のある内容になるよう導いてくださいました。また、論文発表やコンテストに挑戦する機会をくださり、私の背中をいつも優しく押してくださいました。このように、米澤教授のご指導のもとこれまで研究成果を積み上げ、有意義な大学生活を送ることが出来ています。米澤教授と共に、これからも研究を継続していきたいと思っています。
- ー 修了後の進路希望
- ゲームを活用した実践的学びの可能性を追求し、教育・コミュニケーション・ゲームの分野において有意義な知見を多く残せるよう研究活動を継続しつつ、ご指導いただいた先生方や諸先輩方の教えを生かし、大学で教員として勤めることを希望しています。
- ー 普段、どのような研究活動(手法)を行われているか、またその「おもしろさ」「難しさ」について
- 先行研究の調査に基づき提案システムを新規実装し、綿密な実験計画のもと検証を行い、その結果を研究成果として論文にまとめます。このプロセスにおける全ての段階がスムーズに行くとは限らず試行錯誤の連続です。特に、システム実装では自分が触れたことのない新技術を導入するケースが多く、実装しつつ勉強する必要があります。また、私の場合、自分の研究を進行させつつ、自分の研究テーマを展開できる仲間として学部生や修士の人たちに研究協力も行っています。このため、研究生活は多忙です。一方で、科学的な観点から効果の期待できるシステムを自分の手で作り上げ検証し、論文として形にしていく点が面白く、非常にやりがいを感じます。

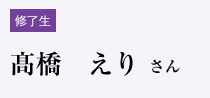
-
総合情報学研究科 社会情報学専攻
博士課程前期課程 2021年4月入学
(入試種別:学内進学試験)- 進学先名:
- 関西大学大学院
総合情報学研究科
総合情報学専攻
博士課程後期課程
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 学位論文題名と概要
-
『自転車放置行動の経済分析』
- 概要:
- 行政による放置自転車政策が自転車ユーザーの放置行動に与える影響について, 自転車ユーザーの変数と行政の政策変数を設定して放置自転車政策にかける予算と, 撤去した自転車に対する罰金の観点からモデル分析を行いました。行政が放置自転車対策にかける予算を増やすと, 放置自転車の撤去確率が上昇し, 放置自転車が及ぼす環境ダメージを減らすことができます。また, 放置自転車に対する罰金を増やすと, 放置確率を減少させ環境ダメージは減ることが分かりました。
- ー 現在の研究内容について教えてください。
- 現在、関西大学大学院総合情報学研究科博士課程後期課程に在学し、前期課程と同じ指導教員のもとで引き続き研究活動を行っています。
- ー 出願に先立って志望の指導教員へどのような相談をしたか、相談してよかった点
- 私は学部生のときに博士課程後期課程まで進学することを決めて、指導教員の先生に今後の進路について相談したところ、その時の自分に足りない知識やスキルを的確にアドバイスして頂きました。身近に研究者の人がいなかったので、将来の自分が全く想像できていませんでしたが、先生の研究者としての話や、なぜこの道に進んだのかいろいろお話をきいて、将来の目標と、まず今の自分がすべきことが明確になりました。
- ー TA・RA制度の利用にかかる経験談、よかった点
- 担当したのはPython実習のTAです。私自身もPythonのスキルをもっと向上させたいという気持ちもあって、応募しました。担当の先生が快く受け入れてくださり、TAに決定したときはうれしかったです。授業の予習をしたり、授業を通して学生のつまずくポイントが分かってきてプログラミングの能力を向上できました。それだけでなく、大学の授業を先生でも学部生でもない立場から俯瞰的にみることができて、毎回の授業の構成や評価方法もとても参考になりました。また先生や他のチューターの質問対応を見てどのようにすれば分かりやすく教えることができるかも学ぶことができ、教える立場としてもとてもよい経験になりました。
- ー 指導教員名とその教員を選んだ理由や教員とのエピソード等
-
- 指導教員名:
- 大堀 秀一先生
学部生のときにたまたま興味があり履修した先生の国際経済学の授業で、グローバルな視点をもつ必要があることに気づきました。先生のゼミでは環境経済学について学び、はじめて論文を読んだり協力して調査をしたり発表したりして、そのときのグループワークやインゼミでの研究・発表・議論の経験が今の研究生活にも生かされています。研究テーマも具体的でなく経済学の知識も全くない状態でしたが研究者の道に進むためのたくさんの助言を頂いて、論文投稿や学会発表までできるようになりました。今は先生のご指導のもと、交通のシェアリングエコノミーが人々や環境に与える影響について研究しており、社会課題の解決に貢献する自立した研究者になれるように日々頑張っています。
- ー 関西大学大学院総合情報学研究科の魅力
- 私は毎日同じ場所に通うのがあまり好きではなくて、これまで学校は時間ギリギリに登校して授業して部活が終わったらすぐ帰っていましたが、総合情報学研究科は学部生からもう7年以上楽しく通っているのでとても勉強しやすい環境だと思います。経済学関連の本も高槻キャンパス図書館になければオンラインシステムを使って他のキャンパスからすぐに取り寄せてもらえて、不自由なく書籍を利用することができます。院生棟も広くて情報端末が揃っていて、ほかの院生も毎日来て遅くまで研究しているので、お互いにモチベーションをあげて集中して研究活動を続けられています。
- ー 関西大学大学院総合情報学研究科に進学を考えている方へのメッセージ
- 他のキャンパスも授業などで訪れたことがありますが、私はこの総合情報学研究科がある高槻キャンパスが一番気に入っています。自然豊かですばらしい研究設備が整っており、異分野を専攻する院生との交流も活発なので、集中して楽しく研究活動に取り組めると思います。

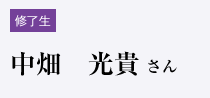
-
総合情報学研究科 知識情報学専攻
博士課程後期課程 2021年4月入学
(入試種別:一般入学試験)- 勤務先名:
- 株式会社野村総合研究所
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 学位論文題名と概要
-
『深層学習を用いた動画像による車両の交通量調査技術に関する研究』
- 概要:
- 我が国では、自動車交通の実態を把握するために交通量調査が実施されています。交通量調査は、調査員が目視にて車両を確認し、通過台数を計数する方法が一般的ですが、調査員の確保が難しく深刻な問題になっています。そこで、私の本研究では、調査地点にカメラを設置し、そのカメラで撮影した映像をAIで解析することで、交通量を自動算出する技術を開発しました。そして、実証実験を通じて、実務の交通量調査に対して適用できることを明らかにしました。
- ー 現在の仕事において大学院での研究や学修が生かされている場面や、学部卒業で就職をしている方との違いを実感する場面
- 現在、私はデータサイエンティストとして民間企業で働いています。業務内容としては、統計学・機械学習・AIを活用して顧客の抱える課題を解決することが主となります。業務の流れとしては、まず論文・既存サービス調査をした上で、最適な手法・技術を選定します。次に、その技術を実装・適用することで問題を解決できるか試行します。そして、目的が達成されるまでトライアンドエラーを繰り返します。これは、大学院での研究と同一の流れであり、大学院で学んだことのすべてが生きていると日々実感しています。
- ー TA・RA制度の利用にかかる経験談、よかった点
- 私は、プログラミング実習のTAを担当していました。TA制度を利用することには、大きく分けて二つの利点があると考えています。一つ目は、学内でアルバイトができることです。大学院生は、研究活動中心の生活になるため、平日にアルバイトをすることが難しい場合もあるかもしれません。しかし、TA制度では授業や研究のすきま時間を利用して働くことができるため、金銭面的に非常に助かりました。二つ目は、話す力・教える力が身につくことです。TAは、授業進行のサポートや授業内容に対する学生の疑問点を解消することが主な業務であり、人と話す機会が多々あります。私は、TAを始めた当初はうまく教えることができないこともありましたが、さまざまな学生を教えていく中で、伝わりやすい説明の仕方や順序を学びました。社会人になると、人に説明する機会はよくあるので、TAで学んだことが生きていると実感しています。
- ー 奨学支援制度の利用にかかる経験談、よかった点
- 在学中は、関西大学独自奨学金と日本学生支援機構の二種類の奨学金を利用していました。私は、研究活動が中心の大学院生活を過ごしていたため、奨学金を利用することでアルバイトをせずとも学費や生活費を賄うことができ大変助かりました。私は、大学院に進学することは自己投資だと考えており、自分の就職したい企業・なりたい職種を実現するための一番の方法だと考えています。自分の夢を実現するためには、それ相応の努力が必要であり、大学院に進学するのであれば奨学金を十分に活用し、学業に専念することも一案だと思います。
- ー 普段、どのような研究活動(手法)を行われているか、またその「おもしろさ」「難しさ」について
- 私は、上述したとおり、AIを用いて動画像を解析することで、交通量調査を自動化する技術を開発していました。私は、研究の一番の面白さは、「まだ誰もしていない・誰も達成していないことを自分が成し遂げること」だと考えています。私の研究活動では、実務の交通量調査で求められる精度を達成するために、何週間、何カ月と試行錯誤を繰り返したのですが、なかなか精度向上できず大変苦労しました。日常生活において、何か分からないことがあればインターネットで調べれば簡単に解決できますが、研究とは誰も取り組んでいないことに挑戦することであり、答えは調べてもでてきません。そのため、失敗原因をしっかり考察し、次のアプローチを考えて試行錯誤を繰り返す必要があり、いろいろな角度から思考して答えを導き出すのが非常に面白かったです。そして最終的にはその成果を論文として発表し、評価されたときの達成感は今でも忘れられません。
- ー 現在の就職先・職業を選んだ理由
- 研究活動で学んだことをフル活用できるとともに、最新の情報技術に触れることが好きなので、私にぴったりの仕事だと思ったからです。具体的には、データサイエンティストは、AIなどの最新技術を活用して顧客の課題を解決することが主な業務であるため、研究活動で培った問題解決能力、プログラミング力、技術力などを存分に発揮できます。また、ブロックチェーンや生成AIのような最新技術にも触れることができ、それらの技術を駆使して顧客に価値を提供できるやりがいのある仕事です。
- ー 関西大学大学院総合情報学研究科に進学を考えている方へのメッセージ
- 大学院に進学すると決めたのなら全力で大学院生活を送ってほしいと思います。あなたが大学院生活を送っている間に、一足早く社会人になった友人とのギャップに苦しむこともあるかもしれません。しかし、大学院に進学すると決めたのなら、目の前の目標に向かって努力してください。そうすれば、大学院を卒業する時には見違えるほど成長していると思います。関西大学大学院総合情報学研究科は、文理問わずさまざまな授業・研究が展開されており、自分の学びたいことを存分に学ぶことができる環境が整っています。充実した大学院ライフを過ごせることを祈っています。
理工学研究科

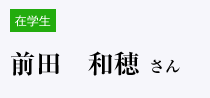
-
理工学研究科 化学生命工学専攻
博士課程前期課程 2022年4月入学
(入試種別:学内進学試験)
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 研究テーマと概要
-
『循環型架橋ポリマーの創出』
- 概要:
- 環境や生体に優しいポリマー材料の獲得をめざし、外部環境に応じて可逆的に結合点が変化する構造を組み込んだ架橋ポリマーの合成について検討しています。このポリマーは分解と再生を繰り返す循環性に優れた材料や生体内でオンデマンドに分解する医用材料などへの応用が期待されます。
- ー 時間割
-
博士課程前期課程 1年次 秋学期
1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 月 火 バイオ
インスパイアード
化学特論水 応用コロイド
化学特論木 金 知的財産論 生体材料
化学特論土 化学・物質工学
ゼミナールⅡ
- ー TA・RA制度の利用にかかる経験談、よかった点
- 私は、TA制度を利用して、週1回、3限分の実験TAをしていました。一般的なアルバイトとは異なり、学部生の実験補助が仕事内容だったので、自分の専門分野を生かしてアルバイトできるだけでなく、気をつけて実験するポイントなどを学ぶことは初心に帰って自分自身にも役に立ちました。自身の研究にも生かせるポイントがたくさんあったのが良いところだと思います。また、学部生とコミュニケーションをとる際に研究室配属の相談や将来についての質問を受けました。自分の体験談や進路について学部生に新たな選択肢を与えられた時が力になれたと実感でき、嬉しかったです。
- ー 指導教員名とその教員を選んだ理由や教員とのエピソード等
-
- 指導教員名:
- 岩﨑 泰彦先生
研究室生活を送る中で、岩﨑先生の生徒に学びの多い生活を送ってほしいという考えが伝わってきます。エピソードの一つとして、研究を通した海外交流が挙げられます。私は、留学生のメンターとして活動しました。先生と留学生の研究について英語で話し合ったことが印象的です。留学生との交流の機会を与えていただき、とても感謝しています。この経験を通して、海外で研究をするという選択肢が新たに増えました。
- ー 普段、どのような研究活動(手法)を行われているか、またその「おもしろさ」「難しさ」について
- 私は医療分野で必要とされているマテリアルを生体に倣って設計し、開発しています。今実際に問題となっていることを解決するためのマテリアルデザインを考えて研究を進め、人体に近い条件下での挙動を確認することでその材料の有用性を調べたりしています。実際の臨床現場で用いられる材料を開発するのはとても難しいですが、世間への貢献や医療材料の進歩への第一歩になることを想像すると喜びを感じます。
- ー 修了後の進路希望
- 私の修了後の進路は、関西大学の博士課程後期課程への進学です。企業への就職では叶えられないと考えた、専門性の高い課題発見力や問題解決能力を博士課程後期課程で培っていきたいと思い、進学を決断しました。学部からの3年間で感じた研究の面白さや達成感が私の研究に対する原動力になっていると思います。専門分野の研究に貢献し、新しい知見で世の中の役に立てるような研究をしたいと考えています。
- ー 関西大学大学院理工学研究科に進学を考えている方へのメッセージ
- 関西大学大学院理工学研究科ではアドバンストインターンシップや海外実習など学外での研修や経験を積む機会があることが強みだと考えています。研究を通していろいろな経験ができるので、いろいろな観点から物事を捉えられるようになり、自己分析力が培われると思います。ぜひたくさんのことに挑戦するために進学してみてください。自分の知らない一面に気づけると思います。

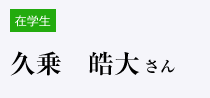
-
理工学研究科 総合理工学専攻
博士課程後期課程 2023年4月入学
(入試種別:学内進学試験)
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 研究テーマと概要
-
『論理構築のための因果関係理解支援システム』
- 概要:
- 正しい論理構築のために知識の因果関係を理解することを支援するシステムを提案しました。因果関係理解支援システムは、因果関係を理解することは2つの事象間の関係が説明可能であることと捉え、原因に当たる活動と結果にあたる状態の因果関係の活動を分析させることで説明させることを支援します。システムは導出したサブ活動系列の候補の妥当性を判定する妥当性判定機能、ユーザの行き詰まりの状態を推定し、操作を推薦する分析操作推薦機能を保持します。
- ー 時間割
-
博士課程後期課程 1年次 春学期
1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 月 電気電子情報工学
ゼミナール5火 水 木 金 土
- ー TA・RA制度の利用にかかる経験談、よかった点
- 私は博士課程前期課程・後期課程の両課程でTAを経験しました。研究活動のために大学に来る頻度が多いため、大学でアルバイトができるのは助かりました。また、TAを経験したことは奨学金の返還免除申請や就職活動においてアピールポイントになるのでその点も良かったと思います。現在博士課程後期課程でRAもしています。RAをすることで学費相当のお金をいただいているおかげで大学に通うことができているので非常にありがたいです。
- ー 奨学支援制度の利用にかかる経験談、よかった点
- 私は博士課程前期課程では日本学生支援機構の奨学金と関西大学の給付金をいただいていました。私の場合、学生支援機構の奨学金と関西大学の給付金を合わせると学費の8割ほどになったのでアルバイトは最小限にとどめることができました。そのおかげで研究活動に集中することができました。また、大学院でいただける日本学生支援機構の奨学金は返還免除制度があり、論文執筆や学会発表を精力的に行うことで奨学金の返還を半額、もしくは全額免除していただけます。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
- 博士課程前期課程に進学した理由は自分の経験では就職活動の際に周りの人と差をつけられないと考えたからです。就職活動では自分の能力をアピールすることが求められますが、その能力がどういった成果につながったかを伝えなければどれだけ能力があっても意味がありません。学部生の頃は成果を生み出すことなどしてこなかったので自分の能力をアピールできないと考えました。なので、何らかの成果を生み出す期間を設けるために進学しました。進学してからは成果として、アプリケーションの開発なども行いましたが、研究活動の楽しさに触れ、研究活動を続けていきたいと思ったので最終的には就職せずに博士課程後期課程に進学しました。
- ー 修了後の進路希望
- 博士課程後期課程進学後は大学教員になりたいと考えています。私は自分の研究分野である学習支援システム分野の研究活動を続けたいと考えています。研究者になるだけなら大学教員以外にも企業の研究者になるという選択肢も考えられますが、学習支援システムの分野で研究・開発を行っている企業はあまり存在しません。なので大学で研究を続けたいと考えています。また、学習支援システムの研究分野をより多くの人に知ってもらうことも必要なので、大学教員になり研究室を持つことはその近道になると思っています。
- ー 普段、どのような研究活動(手法)を行われているか、またその「おもしろさ」「難しさ」について
- 私の研究分野は人の学習やトレーニングをコンピュータによってどのように支援できるかを明らかにすることが目的です。そのためにはまず、対象としている学習活動がどのようなプロセスで行われているのか、獲得させたい知識やスキルはどのような物なのかを明らかにする必要があります。なので、既存の研究や自分達の経験に基づいて仮説を立て、仮説に基づいて学習やトレーニングの支援をするシステムを設計します。人の知識や思考といった目に見えないものに仮説によって形を与えられることや、アルゴリズムによる単純な応答しかできないコンピュータに工夫を施すことによって柔軟に振る舞っているように見せられることに面白さがあります。

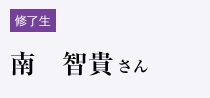
-
理工学研究科 環境都市工学専攻
博士課程前期課程 2019年4月入学
(入試種別:学内進学試験)- 勤務先名:
- 三菱ケミカルエンジニアリング株式会社
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 学位論文題名と概要
-
『火炎法による光触媒ナノ粒子の酸素欠損制御』
- 概要:
- 光を当てると酸化還元反応を示す物質を光触媒と呼び、水分解で水素を得る研究などが進められています。本研究では、炎を用いて分子中の酸素を欠損させた光触媒ナノ粒子を生成し、触媒の反応効率を向上させることを目的としました。
- ー 現在の仕事において大学院での研究や学修が生かされている場面や、学部卒業で就職をしている方との違いを実感する場面
- 仕事において、過去の施工実績から改善点を洗い出しコスト面や工期も考慮しつつ、具体的に何を採用し実行するのか議論する場面があります。そういったプロセスは、研究において事象から原因を考えて検討し、次は改善のためにどういった変更を行うのかという考え方に似ていて、分野や対象が異なっていても学んだ考え方を生かせていると感じています。
- ー 現在の就職先・職業を選んだ理由
- 私は学部時代に学んだ化学工学を生かすと共に、多岐にわたる分野の方々と関わりたいと感じていたため、プラントエンジニアリング業界を志望しました。その中でも、自らの専門性を持ちつつも多分野と協力できる「一専多能」というスローガンに共感し、入社を決めました。大学の授業で学んだことを実際の業務で生かせる場面があり、大いに役立っていると感じています。(※場面=具体的にはポンプの設計など)
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
- 大学院進学か就職か悩んだ時期もありましたが、4年次生時の特別研究であった光触媒を通じて環境問題に取り組むことに魅力を感じ、進学し研究を続けることを決意しました。また、進学することで専攻分野への理解を深めると共に、多分野の研究内容にも興味を広げて見聞を深めることで、就職時に視野が広がると考えたことも理由の一つです。
- ー 指導教員名とその教員を選んだ理由や教員とのエピソード等
-
- 指導教員名:
- 岡田 芳樹先生
学部の講義を通じて、岡田先生は原理原則を重視し、事象に対してその理由を積極的に生徒に考えさせる方だと感じました。私はその姿勢に惹かれて、担当されている研究室を希望しました。研究室では実験のアドバイスと共に、私たちに自分なりの考え方を持って社会に出ることを、熱意をもって伝えてくださいました。社会に出た今でもその言葉が生きていると感じています。
- ー 関西大学大学院理工学研究科の魅力
-
理工学研究科は、私の所属した環境都市工学や電子・情報、建築、機械・電気など多岐にわたる分野が集まっています。その広さから自分が学びたい分野や取り組みたい研究を見つけることができる点が大きな魅力です。
また、関西地域の電機・機械メーカーとパートナーシップを持ち、技術開発の共同研究を行っている研究室もあり、そういったプロジェクトで自身の知見を深めることができることも魅力だと感じています。
- ー 関西大学大学院理工学研究科に進学を考えている方へのメッセージ
- 大学院は勉学、研究活動、就職活動と忙しいですが、だからこそ自分の視野を広げられる良い機会だと感じました。必ずしも一人で取り組むのではなく、同期や教授陣、キャリアセンターの方々などに声をかけて頼ってみるのも良いと思います。私の在学中と同じように、心強いアドバイスをいただけると思います。大学院での日々が将来の糧になるよう、楽しんでください。
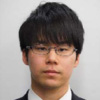
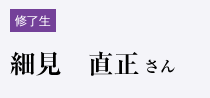
-
理工学研究科 システム理工学専攻
物理・応用物理学分野
博士課程前期課程 2016年4月入学
(入試種別:学内進学試験)- 勤務先名:
- 株式会社島津製作所・
医療機器開発
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 学位論文題名と概要
-
『固体燃料ロケットモータのX線画像解析』
- 概要:
- 宇宙航空産業の成長発展と高度化に向けて固体燃料ロケットの低コスト化/信頼性向上が課題となっており、新たな混合器による製造プロセスが検討されています。製造プロセスにおいて重要なパラメータは捏和操作による構成物質の分散状態や混合度を測定することです。本研究ではX線CT画像から得られる画素値のヒストグラムを用いることで撮影領域における構成物質の分散状態の推定及び、混合度の定量化手法を検討しました。
- ー 現在の仕事において大学院での研究や学修が生かされている場面や、学部卒業で就職をしている方との違いを実感する場面
- 4年次及び博士課程前期課程で研究活動に取り組むことで身に付いた問題解決の思考プロセスや知識を自分に落とし込む⽅法は、就職後の業務でも活かせています。これらは研究テーマに取り組むことで身に付けられたものと考えており、学部卒業で就職をしている⽅との違いだと考えています。
- ー 奨学支援制度の利用にかかる経験談、よかった点
-
日本学生支援機構大学院 第一種奨学金を利用しました。
大学院進学を考えるにあたり、金銭的な心配がありましたが、奨学金制度により不安を解消でき、進学を決意できました。また、本奨学金では在学中の業績を認められた場合に一部の返済が免除されるため、研究活動等に対するモチベーションを高めることができました。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
-
大学院進学の理由は2つあります。
1つ目は、4年次に取り組んでいた研究テーマに取り組み専門的な知識を身につけたいと思ったからです。2つ目は、4年次に就職活動をした際に、自分が志望する領域の企業で働く⽅から、⼤学院での経験が役に⽴っていると伺ったためです。また、理由の2つ目は、他の項目でも記載している通り、⼤学院での経験を就職後の業務でも活かせているため、⼤学院進学は良い選択だったと考えています。
- ー 指導教員名とその教員を選んだ理由や教員とのエピソード等
-
- 指導教員名:
- 山口 聡一朗先生
山口先生を指導教員として希望した理由は、学部在学時にも指導いただいており、博士課程前期課程においても継続して指導いただきたかったからです。山口先生は自らの研究分野に限らずさまざまな領域でチャレンジされている(医療装置開発から宇宙工学などに取り組まれている)ため、在学中は、1つの研究テーマに限らずさまざまな研究テーマを経験できました。
また、研究活動以外でも就職活動に対しても熱心に相談・サポートいただきました。
- ー 現在の就職先・職業を選んだ理由
-
就職先を選んだのは、インターンシップに参加したことがきっかけです。
⻑期のインターンシップに参加できたため、その会社で実際に働いている⽅と⼀緒に仕事することができ、その会社の雰囲気(働き⽅や仕事に対する姿勢)を体感することができました。そこで体感した雰囲気が自分に合っていると考えたため、現在の就職先を希望しました。
- ー 関西大学大学院理工学研究科に進学を考えている方へのメッセージ
- 私は、研究テーマに取り組むことで得られた経験や問題解決のための思考プロセス、専門分野の⼈と交流することで成⻑できたと感じています。就職後の業務においては、博⼠課程前期課程で学んだ専門的な知識をそのまま活⽤できる機会はあまりないですが、身に付けた思考プロセスは活かせています。そのため、⼤学院では、自分の興味がある研究テーマについてとことん没頭し、学部⽣活だけでは経験できない、⼀⽣の糧となる⼤学院⽣活をぜひ楽しんでください。
外国語教育学研究科

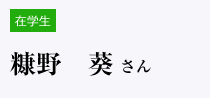
-
外国語教育学研究科
外国語教育学専攻・3年コース
博士課程前期課程 2023年4月入学
(入試種別:一般入学試験)
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 研究テーマと概要
-
題名:『「主体的・対話的で深い学び」を支援するICTとデジタル教科書の効果的な利用』
- 概要:
- 中学校英語科の授業において「主体的・対話的で深い学び」を支援するためのICTやデジタル教科書の効果的な利用を目的に研究を行っています。GIGAスクール構想によって1人1台端末が実現した現在、生徒がより自ら学んでいくために教師は何を行うべきなのかを明らかにし、学習者用・教師用のハンドブックを作成したいと考えています。
- ー 時間割
-
博士課程前期課程 1年次 春学期
1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 月 英語科
教育法(二)英語科
教育法(三)異文化
コミュニケーション
概論火 文化と
コミュニケーションAcademic Listening and Speaking a ことばの世界
(英語)前期課程
演習1a水 木 英語科
教育法外国語教材
開発1外国語教育
メディア論金 エリア
スタディーズ
(英米)外国語音声
教育論
(英語)土
- ー 出身学部と所属研究科の専門分野が異なっている際に、特にどのような点に注意して受験準備を進めたか
- 英語に触れる機会を増やした点と、研究計画書を書く際には外国語教育学の先生に確認をしていただいた点です。出身学部は、志望する研究科と比べて英語に触れる機会が少なかったため、自ら各検定や試験に挑戦する機会を増やし、大学のゼミの先生に英語を学ぶ機会を設けていただきました。また、外国語教育学の分野でわからないことがあった場合、調べるだけにとどめずに当該分野の先生に質問をしてしっかりと確認をすることを意識して、受験準備を進めました。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
- 将来、中学校の英語教員になりたいと考えています。そのため、英語を教えることに関するより深い知識や高いレベルの実践力を身につけるために大学院進学を決めました。本学を選んだ理由としては、理論から実践までしっかりと学ぶことができる授業構成と、多様な背景を持つ院生が集まる環境に魅力を感じたためです。
- ー 修了後の進路希望
- 子どもたちの充実した学びを目的に、公立中学校の英語科の教員として働きたいと考えています。現在、学部の授業も受けており、高校の英語科教員の免許も取得する予定なので(小中の免許は取得済み)、小中高連携を意識して教育現場に携わりたいと考えています。
- ー 指導教員名とその教員を選んだ理由や教員とのエピソード等
-
- 指導教員名:
- 池田 真生子先生
池田先生は学習方略や自己調整学習を研究されており、高等学校検定教科書の編纂など教材開発にも関わられており、私の研究テーマと重なる部分が多くあります。そのため、先生から非常に多くのご助言をいただいており、研究を進めることができています。また、研究以外のことでも、先生は親身になって相談に乗ってくださり、そのおかげで大学院での学びをより充実させることができていると感じています。
- ー 関西大学大学院外国語教育学研究科の魅力
- 研究の最前線でご活躍されている先生から教われる点はもちろんですが、それ以外にも私は、多様な背景を持つ院生が集まっている点に魅力を感じています。年齢も国籍もこれまでの経験も全く異なっていますが、お互いを尊重する雰囲気に居心地の良さを感じています。また、学年や研究分野を問わずに関わりが生まれるので、さまざまな学びや刺激を受けることができる環境がとても魅力的です。

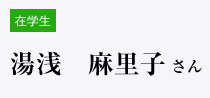
-
外国語教育学研究科 外国語教育学専攻
博士課程後期課程 2022年4月入学
(入試種別:社会人入学試験)- 勤務先名:
- 関西大学・非常勤講師
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 研究テーマと概要
-
『機械翻訳を英語学習ツールとするために-大学生の気づきを高める研究』
- 概要:
- 機械翻訳(MT)の教育的利用がテーマです。学習方略、自己調整学習などの理論的枠組みをもとに、MTを用いた英作活動を通して、ことばへの気づき(メタ言語知識)や産物、自己効力感などの心理的要因がどのように変化するのかを明らかにしたいと思います。
- ー 時間割
-
博士課程後期課程 1年次 春学期
1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 月 火 後期課程演習1a 水 木 応用研究法2 金 土
- ー 奨学支援制度の利用にかかる経験談、よかった点
- 関西大学大学院特別給付奨学金をいただいています。経済的にも負担が軽減されて、とても感謝しています。
- ー お仕事との両立の工夫等について
- 後期課程に進学する際に、仕事量を減らしました。現在は授業日と研究日とを区別して、研究に集中することができています。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
- 当初は英会話学校などで教えていましたが、応用言語学の理論を学びたいという思いから、英国の大学院でTESOL(英語教授法)を修了しました。その後、複数の大学で英語を教えていましたが、現場で直面するさまざまな課題を解決したいと思い、再び大学院の扉を叩きました。「私は “practitioner” (教育の実践者)で、研究には不向きだ」と思っていましたが、今は研究がすごく楽しいです。現場の視点を研究に生かし、そして今度は研究の成果を現場に還元できるよう、日々、努力しています。
- ー 指導教員名とその教員を選んだ理由や教員とのエピソード等
-
- 指導教員名:
- 竹内 理先生
前期課程から引き続き、竹内先生のもとで研究を続けています。私の研究には、動機づけ、学習方略、自己調整学習、CALLなど、竹内先生のご研究の蓄積が土台になっています。いつも的確な助言や研究のヒントをいただいています。ゼミでは幅広いテーマを扱っているため、ゼミの仲間からも刺激を受けることができ、視野が広がりとても勉強になります。
- ー 関西大学大学院外国語教育学研究科の魅力
- 英語教育研究の第一線でご活躍されている先生方のもとで学べることは、最大の魅力です。研究科には現役教員の方もたくさん在籍されており、現場の声が参考になります。全ての研究の基礎となる統計については、基礎から最先端まで学ぶことができます。研究者をめざす方はもちろん、教育現場で課題解決を模索されている方にとっても、理想的な環境だと思います。

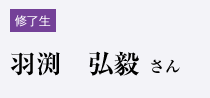
-
外国語教育学研究科 外国語教育学専攻
博士課程前期課程 2019年4月入学
(入試種別:社会人入学試験)- 勤務先名:
- 西宮市立甲陽園小学校 教諭
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 学位論文題名と概要
-
『小学校外国語教育における 「学習評価ハンドブック」の開発と評価』
- 概要:
- 普段の業務が多忙化する中で、学習評価についてじっくり学ぶことができない先生方に評価に関する事柄を図解することで、 短時間で学習評価について学ぶことができるようなハンドブックを作成しました。
- ー 現在の仕事において大学院での研究や学修が生かされている場面や、学部卒業で就職をしている方との違いを実感する場面
-
【授業公開】
市内の先生だけではなく、大学生や大学院生など将来教員をめざす方々にも授業を見ていただく機会が増えました。
https://www.manabinoba.com/tsurezure/author/_167/
【講師依頼】
大学院での研究を生かして、勤務している自治体だけではなく、全国でのレポート発表や学会発表、講師などを依頼されることが多くなりました。
【研究の成果発表】
さまざまなところで研究成果を発表し、現場への還元をめざしています。
https://www.manabinoba.com/ideas/020788.html
- ー 出願に先立って志望の指導教員へどのような相談をしたか、相談してよかった点
-
自分が研究したいことをレポートにまとめ、そのファイルをメールで送信しました。
指導教員(竹内理先生)より、研究の流行も含めて「このような視点もあるのでは?」というご助言をいただきました。自分の研究への新しい視点を見つけることもできました。それをもとに、自分の研究したいことは何かについて再考したり、レポートを改善したりして、院試に向けて準備をしました。
- ー お仕事との両立の工夫等について
-
仕事が終わってから、通学するのは大変でした。教員をしながらの取り組みだったので、6限目始業に間に合わないこともありました。課題に取り組んだり、研究を進めたりする時間は限られているので、通勤(通学)時間を有効に使うことを心がけました。かなり忙しいスケジュールでしたが、「忙しさを言い訳にしない」と決め、見通しを持って何事も取り組むようにしました。
リモートでの授業が始まり、仕事だけではなく、家庭との両立ができるようになりました。余談ですが、子どもたちがオンライン授業に登場するというトラブルも多々ありましたが、子どもたちにとっては父親と一緒に学ぶ楽しさを感じられたようです。
- ー 長期履修学生制度利用にかかる経験談、よかった点
-
3年かけて無理なく単位を取得することができました。また仕事の両立をめざすため、6・7限で連続しないような余裕のある時間割をつくることができました。
仕事の関係上、夜(6・7限目)の授業しか受講することができないので、仕事が休みである土曜日の授業も受講しました。
最後の一年はゼミと自分の興味のある授業をいくつか取るだけで修了することができ、自分の研究を集中して取り組めました。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
-
進学前にいろいろな研究発表や授業公開をしていました。その中で、現場の先生たちが外国語教育に関して困っている実情があることに気づきました。大学院に進学し、「現場の先生を助ける」という目標を定めました。自分なりに研究を進めていくうちに専門家としての確かな力をつけたいという思いも抱くようになりました。
兵庫県の小学校教員として勤務していたので、通学時間がかかることも含めて、どの大学院を選ぶか迷うこともありました。しかし、「外国語教育学」という点であればやはりこの大学院の研究科しかない!と進学を決意しました。
- ー 関西大学大学院外国語教育学研究科に進学を考えている方へのメッセージ
-
外国語教育学研究科には豪華な先生たちが勢揃いしています。さまざまなエキスパートの講義を受けることで自分の研究を深化させることができました。
また、同志には色々な専門や得意分野がある人がいました。その方々との議論を繰り返す中で、自分にはない視点に気づくことができました。修了後もつながりが生まれ、困った時は頼ることができ、研究のことや授業づくりについて相談しています。
もちろん、働きながら通学することは大変です。ただ、忙しさや大変さを言い訳にしてしまうとせっかくのチャンスをつかむこともできません。何事もチャンスだと思って、前向きに取り組んでみてはいかがでしょうか?

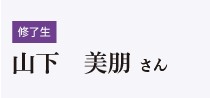
-
外国語教育学研究科 外国語教育学専攻
博士課程後期課程 2012年9月入学
(入試種別:一般入学試験)- 勤務先名:
- 立命館大学 生命科学部 教授
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 学位論文題名と概要
-
『An Analysis of Rhetorical Features and Logical Anomalies in the EFL Argumentative Essays Written by Japanese University Students』
- 概要:
- 日本人大学生の書いた日英の作文を比較して、英語に見られる論理的逸脱が日本語の発想によるものかを分析しました。日本語の作文に特徴的な読み手に推測させるなどの論理的な流れを妨げる傾向が、英文に負の転移をしていることが明らかになりました。パラグラフ・ライティングの指導の徹底と高大連携のアカデミック・ライティングの指導を強調しました。
- ー 現在の仕事において大学院での研究や学修が生かされている場面や、学部卒業で就職をしている方との違いを実感する場面
- 大学院での学びが今の私の仕事の原点となりました。博士後期課程で研究した英文ライティングの研究を今でも続けていますし、現在所属している大学でもライティング指導を任されています。2017年度から所属学部にライティングセンターSAPP(Support for Academic Projects and Papers)を運営しています。SAPPでは理系学部の特徴を生かし、大学院生が学部生の研究テーマを英語の論文にする支援を行っています。現在SAPPは、年間160名の来室のあるセンターになりました。また本年度、科学研究費を獲得し、博士論文で結んだ高大連携のライティング指導に携わり、高校でのライティング指導も行っています。全て関西大学の博士課程での学び、研究が今の仕事につながっていると言っても過言ではありません。
- ー 出願に先立って志望の指導教員へどのような相談をしたか、相談してよかった点
- 研究科に入学する際に、指導頂いた先生に相談に行きました。大量のライティングデータを分析する際のデータ構築の方法や、研究の進め方などについても丁寧にご教示くださいました。また一緒に分析しようと仰ってとても心強かったのを覚えています。
- ー 大学院進学のための受験対策や事前準備
- 大学院進学を考える際に、まず自分の関心のある研究分野(私の場合は英語ライティング指導)の先行文献や書籍などを読み、自分が望む研究ができる先生や大学院の情報を収集することから始めました。その上で直接先生にメールをして詳しいお話を聞くなど十分に納得したうえで進学を決めました。入学試験の情報は修了生を探してどのような試験であるのかを知り、面接で聞かれることなどを準備して臨みました。情報収集と準備に時間をかけることが大切だと思います。
- ー 普段、どのような研究活動(手法)を行われているか、またその「おもしろさ」「難しさ」について
- 私の関心は常にライティング、とりわけ論理的に書くことです。もともとはなぜ日本人はうまく英語で書くことができないのだろうかという疑問への答えを見つけたいと思い博士論文のテーマとしました。博士論文は、「書いたもの」が対象だったのですが、現在は「書き手」つまり「人」に関心が移っています。なぜそのようなものを書くのか、どういう指導をすれば書き手は変わっていくのだろうか、と心理面にまで研究の対象を広げています。書いたものを通して人を見ることができるのでとても面白いですし、ライティング指導や研究を通して学生が成長する姿を追うことができるので教師冥利につきます。
- ー 現在の就職先・職業を選んだ理由
- 現在は大学で専任教員として働いていますが、まさかこのような職位に就くとは思っていませんでした。英語を教える仕事を続けては来ましたが、修士時代の2011年にオーストラリアの大学院で一年間勉強したことがきっかけとなり、帰国後に大学で非常勤講師として英語を教え始めました。年齢的にも遅いスタートだったと思います。好きなライティングの指導や研究ができればとそれだけを思って環境を選んできただけですので、現在大学で教えている自分は縁のおかげだと思っています。
- ー 関西大学大学院外国語教育学研究科に進学を考えている方へのメッセージ
- 関西大学外国語教育学研究科で私は多くを学びました。素晴らしい先生方から、自分では得られない言語学や言語教育の実践的な知識を学ぶことができます。私は博士課程後期課程の指導教員であった竹内理先生から研究の進め方や論文の書き方を学びました。先生のご指導が無ければ、博士課程を終えることは出来ませんでしたし、今の私も無かったと思います。博士課程の研究は時間がかかりますが、そこにじっくり付き合ってくださる先生方がおられるので安心して進学を考えてほしいと思います。
心理学研究科

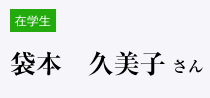
-
心理学研究科 心理学専攻
博士課程前期課程 2022年4月入学
(入試種別:学内進学試験)
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 研究テーマと概要
-
『祈りのメカニズムについて』
- 概要:
-
祈りは精神的健康と関係するが、そのメカニズムは解明されていません。
そこで、祈りの重要な構成要素である祈りの言葉に着目し、調査や生理指標を用いてメカニズムを明らかにします。
- ー 時間割
-
博士課程前期課程 1年次 秋学期
1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 月 英語論文の書き方 健康・人格心理学
特殊講義心理学セミナー1B 火 水 発達・教育心理学
特殊講義木 現代心理学の
学際的問題B研究チュートリアル
セミナー1A
(心理と言語学)金 認知・生理心理学
特殊講義上級心理学実習
(心理実験)上級心理学実習
(心理実験)土
- ー 出願に先立って志望の指導教員へどのような相談をしたか、相談してよかった点
-
進学後の研究について重点的に相談しました。
・研究内容について指導を受けることが可能か
・研究テーマの妥当性について
上記の点を中心に相談したことで、進学までに研究計画を精緻化させることや事前に取り組むべきことが明確になりました。また、大学3年次から連絡を取らせていただいていたため、研究室の雰囲気を知ることもでき進学後のイメージがつきやすくなりました。
- ー 出身学部と所属研究科の専門分野が異なっている際に、特にどのような点に注意して受験準備を進めたか
-
特に注意した点は「心理学全般の基礎知識を身につける」と「異なる専門分野でなければならない理由を明確にする」の2点です。
筆記試験はありませんでしたが、専門分野ではなかったため基礎知識を身につけることから取り組みました。例えば、志望の指導教員や心理学部の友人に聞いて主要な教科書・資料はすべて目を通して対策しました。院では、英語の読解力が必須になるため心理学専用の英単語テキストを熟読し、教科書は英語でも読むなど工夫して理解を深めることに努めました。
また、志望動機と達成したいことに関して、なぜ出身学部ではなく所属研究科でなければならないのかという側面から明確に説明できるよう整理しました。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
- 大学院進学を決めた理由は、学部では抱いていた疑問を解決できず、その疑問について研究することで分野や社会に貢献したいと考えたからです。本学を選んだ理由は、他大学と比較しても学業に必要な施設設備やサポートが非常に充実しているため研究に集中できる環境であると確信したからです。また、本学の心理学研究科であれば、心理学の中でもさまざまな分野の先生方がいらっしゃるため多角的な考察力を通して研究を深化させることができると考え、本研究科への進学を決めました。
- ー 大学院進学のための受験対策や事前準備
- 特に、研究計画の作成に注力して対策および準備を行いました。具体的には、研究分野の歴史について「誰よりも自分が理解している」状態を目指し先行研究を整理しました。そこから問題と目的を明確にし、方法や先行研究と自分自身の研究との違いや独創性など細部まで精緻化することを心掛けて準備しました。
- ー 関西大学大学院心理学研究科の魅力
-
本研究科は、先生と院生・院生同士ともに一方向の学びではなく相互の学びができるため、さまざまな課題に対する創造的な解決力を培えることが強みであると感じています。研究を通して、社会で必要とされる能力を身につけることもできるため、その後のキャリア選択の幅が広がります。研究に関することはもちろん、キャリアなど研究以外のことも相談しやすい環境であるため、不安を解消しながらのびのびと研究に専念することができます。
少しでも進学を考えている方はぜひ早めに志望する(気になる)研究室に連絡されることをお勧めします!

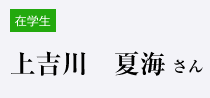
-
心理学研究科 心理臨床学専攻
博士課程前期課程 2022年4月入学
(入試種別:学内進学試験)
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 研究テーマと概要
-
『感覚処理感受性傾向と仕事におけるストレス、および満足度との関連』
- 概要:
- 感覚処理感受性傾向の高い人の職場でのストレスの感じ方の特徴や、仕事に対する満足度、ワークモチベーションとの関連を調査することを通じて、HSPが持つ特徴に特化した心理的支援や、働きやすい職場環境作りを行うための一助となればよいと考えています。
- ー 時間割
-
博士課程前期課程 1年次 秋学期
1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 月 火 心の健康教育に関する理論と実践 心理臨床学研究
演習2家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践 水 心理実践実習Ⅱ 心理実践実習Ⅱ 木 福祉分野に関する理論と支援の展開 金 司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 CSPPセミナーA 土 産業・労働分野に関する理論と支援の展開
- ー 奨学支援制度の利用にかかる経験談、よかった点
- 学部時代から一人暮らしをしているため、大学院への進学を決めた時は、経済面に不安がありました。しかし、奨学金という大学からの援助のおかげで、アルバイトのことをあまり気にせずに、授業や実習に多くの時間を割くことができています。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
- 公認心理師資格取得のために、本大学院に進学しました。また、学部での授業を担当してくださった、さまざまな分野で心理職としてご活躍されている先生方のもとで、より専門性の高い知識と技術を取得したいと思い、学内進学をしました。そして、将来現場で働くことを見据えたカウンセリングや心理検査の方法について、実践的に学ぶことができる授業がある事も決め手のひとつでした。
- ー 大学院進学のための受験対策や事前準備
- 入学試験は面接のみでしたが、それで全てが決まると思うと不安だったので、事前準備を入念に行い、面接に望みました。具体的には、志望動機や大学院でやりたい研究について改めて考え、自分の言葉で伝えることができるよう何度も練習しました。また、卒業論文について簡潔にまとめたり、興味がある分野に関する文献を読んで、それについて話すことができるように準備をしました。
- ー 修了後の進路希望
- 将来は、公認心理師として産業・労働分野で働きたいと思っています。授業で身につけた知識や、実習で身につけた傾聴する力と見立てる力を活用し、復職支援やストレスマネジメント教育、ストレスチェックの実施などを通じて、働く人のサポートをしたいと考えています。
- ー 関西大学大学院心理学研究科に進学を考えている方へのメッセージ
- 心理学研究科では、各領域についての知識を身につける講義中心の授業から、ロールプレイ、プログラムの実施などを中心とした実践的な授業まで、幅広い専門性に特化した授業を受講することができます。また、自分自身や他者についての理解を深める授業などを通してさまざまな視点から学びを深め、心理職として働くための準備をすることができます。先生方も全力でサポートしてくださいますし、相談に乗ってくれる仲間や先輩方もいるため、公認心理師をめざすにはぴったりの環境だと感じています。

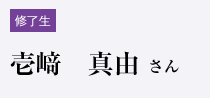
-
心理学研究科 心理学専攻
博士課程前期課程 2020年4月入学
(入試種別:学内進学試験)- 職種:
- 薬事・品質管理
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 研究テーマと概要
-
『虚偽記憶と認知能力の個人差との関連について-DRMパラダイムと誤情報課題を用いた検討-』
- 概要:
- 虚偽記憶とは、経験していない過去の出来事を実際に体験したと思い込むことや想像しただけの出来事を実際に経験した出来事として思い出す現象です。虚偽記憶が流動性知能やワーキングメモリなどの認知的能力の個人差とどのように関連しているかを検討するための研究です。
- ー 現在の仕事において大学院での研究や学修が生かされている場面や、学部卒業で就職をしている方との違いを実感する場面
- 現在の仕事は医療機器の品質管理や薬事に関する仕事を行っています。品質管理業務では、薬機法に基づいた文書を作成し、品質向上や改善のための仕組みを考えています。薬事業務では、製品を医療機器として販売するために必要な厚生労働省の認可を取得するため、信頼性・妥当性を重視しながら申請資料作成を行っています。文章の作成や長い文章を読み解く、信頼性や妥当性を担保できているかどうかの裏付けを含めたすべての面で大学院時代の研究活動を生かすことができています。
- ー 出願に先立って志望の指導教員へどのような相談をしたか、相談してよかった点
- 私は、関西大学社会学部心理学専攻出身で、大学院でも学部時と同じ関口先生に指導していただきました。関口先生に相談する前に同ゼミの先輩に相談し、大学院での授業の様子やプライベートを含めた時間の使い方、最重要事項の研究や修士論文については何度も質問をさせていただきました。先生には、私が大学院に進学するとしたらどのような研究テーマで研究活動を行いたいかを伝え、研究をどのように展開していけば修士論文を執筆することができるのかを相談させていただきました。相談してよかった点は、進学後の自分が想像できるようになったことです。またそれが大学院進学の決め手になり、綿密な研究計画を立てることができ、よい大学院生活のスタートを切ることができました。
- ー 奨学支援制度の利用にかかる経験談、よかった点
- 学部時代及び大学院時代は、関西大学給付奨学金と財団の奨学金制度を利用していました。選考前には、将来のビジョンや考え方を基に、研究活動や課外活動を含めた学生生活を送っているのかをよく考えていました。奨学金制度の最大のメリットは、さまざまな大学の大学生や大学院生と交流することができ、良い刺激を受けながら勉学に励むことができる点です。さまざまな縁をいただけたことを大変感謝しております。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
- 大学院進学は、卒業論文の研究結果が仮説通りであったことが大きな決め手でした。また、計画、実験参加者の募集、実験、分析など、授業ではグループで行っていたものを全て一人で行う楽しさと達成感があり、もっと研究してみたい、学びたいと思いました。関西大学に決めた理由は、指導教員の先生が記憶の専門の先生であること、また学部時代に教えていただいていた先生の授業を大学院でも受講でき、指導していただけることも本学に決めた理由でした。
- ー 現在の就職先・職業を選んだ理由
- 現在の職業を選択した理由は、文章の作成や解読また科学的な視点で物事を見る力を生かすことができると考えたからです。関西大学の心理学専攻では、学部時代にも十分にこれらのことを学ぶことは可能です。しかし、大学院ではより専門的な日本語論文に加え、英語論文の読み書き、考察することが必要な授業があり、修士論文を執筆するためにはこれらのことが大変重要です。大学院で培うことのできる能力は、どのような職業にも生かすことができると思います。
- ー 関西大学大学院心理学研究科に進学を考えている方へのメッセージ
-
私は大学院進学をお勧めします。よく質問されることは、「文系の大学院は就職に不利になりますか」です。私は不利になるとは思いません。大切なのは、何を学び研究したいかという志と、そして実際に行動したのかです。大学院生活は、自分の興味を深める場でもあり、興味を広げる場でもあります。2年間という短い時間ではありますが、自分の武器になる強みをたくさん吸収できる時間でもあります。就職という一点にとらわれず、長い人生というスパンで捉え、今しかない時間を最大限に生かして多くを学ぶことが重要だと考えます。このことは、社会人になってより一層実感します。
関西大学には、親身になってくれる先生や職員の方々、そして多くの先輩や仲間がいます。不安なことがあればいつでも周りの大人や先輩に相談してください!

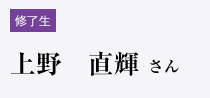
-
心理学研究科 心理臨床学専攻
博士課程前期課程 2020年4月入学
(入試種別:学内進学試験)- 進学先名:
- 関西大学大学院心理学研究科
心理学専攻博士課程後期課程
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 学位論文題名と概要
-
『過剰適応の新たな分類の検討──各因子間の関連及び、 「感覚処理感受性」「自己決定欲求」との関連から──』
- 概要:
- 過剰適応という心理学的概念について、これまで見過ごされてきた過剰適応の一型を見出すため、適応とは異なる側面からその特徴を検討しました。
- ー 現在の仕事において大学院での研究や学修が生かされている場面や、学部卒業で就職をしている方との違いを実感する場面
- 前期課程での学修は、現在の研究と心理臨床活動を両立するということに生かされていると思います。前期課程の当時は心理臨床活動(実習)を中心に学びを深め、実践することに重きを置きながら調査研究も進めるという形でした。現在では研究にもより精力的に力を注ぐ余裕が生まれており、心理臨床活動と調査研究という異なる活動の両立を可能にしています。また、その両方で得た感覚や知見を相互に生かすことにもつながっています。大学院での学びはやはり物事を突き詰める能力を磨くという点に強みがあると感じます。ここで得た突き詰める力は研究者になるかどうかに関わらずあらゆる業種、場面において生かされていると思います。
- ー 奨学支援制度の利用にかかる経験談、よかった点
- 奨学支援制度を利用させていただき、金銭的だけでなく心理的にも安心して研究に邁進することができました。特にこのコロナ禍において、調査を行うにあたっても外部委託を行う必要がありましたが、制度を活用しながら十分な調査ができたと思います。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
- やはり公認心理師の資格取得が大きな目的としてありました。その中でも本学を選んだのは、学部時代からお世話になっていた先生方に引き続きご指導いただけるところが決め手です。
- ー 大学院進学のための受験対策や事前準備
- 公認心理師国家試験の予行演習だと思って、臨床心理学を中心に心理学の基礎を再度しっかりと勉強しました。暗記をするというよりもどういった仕組みなのか、どういった概念なのかなどを説明できるようにすることを意識していました。
- ー 現在の就職先・職業を選んだ理由
- 実習などの心理臨床活動を軸にする中で、研究の楽しさにも触れる機会が多くあり、まだまだ研究を続けたいと思うようになりました。ここではすでに後期課程に進んでおられた先輩方の存在が大きく影響しています。それぞれ異なる分野の研究ではありますが、互いに刺激となって時に助け合うことが研究の原動力になっています。また、研究と心理臨床活動の両立について最初はとても不安でしたが、多くの先生方に支えていただき両立の道を決心することができました。
- ー 関西大学大学院心理学研究科の魅力
- さまざまな分野の先生や学生がいることは心理学研究科の大きな魅力だと思います。特に心理臨床学専攻においては、先生によって専門とされるフィールドが異なり、理論や技法を幅広く学ぶことができました。また、先生方との距離感が近く、実習や研究だけでなく就職や進路についてもご指導いただきました。
社会安全研究科

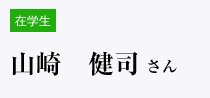
-
社会安全研究科 防災・減災専攻
博士課程前期課程 2023年4月入学
(入試種別:社会人入学試験)
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 研究テーマと概要
-
『日本のハンセン病政策、ハンセン病問題に関する研究』
- 概要:
- ハンセン病問題をテーマに研究しています。全国のハンセン病療養所を訪問し、ハンセン病問題の現状を調査しています。ハンセン病問題から考えられる現代社会への教訓を考察しています。
- ー 時間割
-
博士課程前期課程 1年次 秋学期
1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 月 社会減災政策論 リスクコミュニケーション
特論火 安全の思想 公衆衛生学特論 水 木 金 専攻演習1B 土
- ー TA・RA制度の利用にかかる経験談、よかった点
- TA制度は、アルバイトとして大学の授業の一部補助をする制度です。大学内での仕事であり、学生の事情に配慮して頂けることがメリットです。例えば、TAの時間と学会発表が重なる日がありました。大学のオフィス、補助に入る授業の先生に事情を相談することで、その日はTAを欠勤させて頂きました。
- ー 奨学支援制度の利用にかかる経験談、よかった点
- 奨学金制度利用に関して何度か大学職員の方に相談し、制度利用のための申請方法を教えて頂きました。奨学金制度を利用することで、研究活動に集中できる時間を多く確保できています。大学院生としての貴重な時間を、勉学に有効に使えていると感じます。
- ー 出身学部と所属研究科の専門分野が異なっている際に、特にどのような点に注意して受験準備を進めたか
- 私は出身学部が医療系でした。社会安全研究科を受験するにあたって、「社会安全学入門:理論・政策・実践」(関西大学社会安全学部編集)を参考に受験対策をしました。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
- 新型コロナウイルス感染症が流行した際に、医療施設での感染者への対応だけでなく、社会の中での感染者への偏見や差別、経済対策など種々の問題が同時に起こったことに驚きました。「公衆衛生上の危機」という言葉がメディアで使用されているのを見て、公衆衛生について研究してみたいと思いました。医療分野以外にも、さまざまな学問領域の先生がいる学科で学びたいと思い、本研究科を志望しました。
- ー 関西大学大学院社会安全研究科に進学を考えている方へのメッセージ
- 受験と大学院への入学は、これまでの生活に変化が生じ、不安が生じる時もあると思います。大学説明会に参加し、社会安全研究科の先生から直接話を聞くと、イメージが湧くと思います。ぜひ、勇気を持って一歩踏み出して下さい。

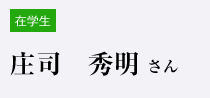
-
社会安全研究科 防災・減災専攻
博士課程後期課程 2022年4月入学
(入試種別:社会人入学試験)
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 研究テーマと概要
-
『中央官庁における組織編制と危機管理体制の研究』
- 概要:
- 行政は国民や住民に対する非常時対応の責任があります。日本の事態対処・危機管理の中核を担う官庁に焦点を当てながら、これまでの変遷をもとに内閣補佐機構全体から分析を行っています。
- ー 時間割
-
博士課程後期課程 2年次 秋学期
1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 月 火 専攻演習4B
(危機対応に関する行政学・公共政策学・政治学研究)水 木 金 土
- ー 出願に先立って志望の指導教員へどのような相談をしたか、相談してよかった点
- 私は、防衛実務、医療実務を経験しており、行政が担う危機管理体制に問題関心がありました。そこで、政治学・行政学・公共政策学を専門領域とし、消防行政をベースに危機管理行政研究をされていた永田先生に相談しました。何度かメール、ビデオ会議、対面型式でのやり取りの後、左記専門領域における親和性の高さを確認することができたことから、研究計画の相談へと進んで行きました。2020年度博士課程前期課程から指導を受けています。入学前の段階から時間をお取りいただき、安心して研究をはじめることができ、今では博士課程へと進むことができています。
- ー 奨学支援制度の利用にかかる経験談、よかった点
- 奨学金制度の種別は『大学院給付奨金』です。私は社会人入試で入学しましたが、博士課程の3年間は研究を最優先にしています。奨学金制度は経済的助けとなっており、研究に専念できています。奨学金は、研究に必要な書籍の購入、資料の複写及び調査等に充てています。
- ー 出身学部と所属研究科の専門分野が異なってい際に、特にどのような点に注意して受験準備を進めたか
- 私の出身学科は、理工学系と医療系でした。そのため、社会安全学の学術的教養はもっていません。そこで、指導教員の助言を受け『社会安全学入門』(関西大学社会安全学部編)をもとに受験の準備をしました。この書籍は、入学後の研究にとっても必要な教養になりますので、今でも大切な1冊になっています。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
- 私は、防災・減災、危機管理、医療・健康危機管理、防衛・軍事・安全保障、行政、組織論を研究のキーワードにしており、『人命』を中心的価値においています。本研究科は社会安全を学問領域とし、各種専門領域を幅広く扱っています。そのため、私は研究の場として本学を選びました。ゆくゆくは「犠牲の最少化」に向けた仕組みづくりをめざしています。努力の方向性は「創造的なやりくり」です。制度論・組織論や科学技術などの識見をもとに各種資源を最適化していくことになります。博士課程後期課程での学びにより、ようやく研究者としての視座が身に付いてきたと感じています。社会安全と言ってもたいへん範囲は広いです。さまざまな教員の教えをいただきながら、そして、学外にも研究の場を求めながら、学際的な研究を続けていきたいと思っています。
- ー 関西大学大学院社会安全研究科の魅力
- 社会安全研究科は、「さまざまな災害の最小化」に向けて多様な学問分野を総合する『社会安全学』を高度化した、「安全・安心な社会」実現の難題に取り組む先進的な教育研究機関です。河田センター長を始めとして、たいへん多くの実績を築かれ、数々の社会的貢献をされている教員が多数在籍しています。本当にとてもすばらしい環境です。社会安全という専門性に関心のある方にとっては、たいへん充実した研究環境があるという意味で、本研究科はとても魅力的な学びの場になるのではないでしょうか。

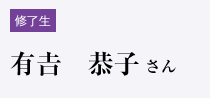
-
社会安全研究科 防災・減災専攻
博士課程後期課程 2020年4月入学
(入試種別:一般入学試験)- 勤務先名:
- 吹田市役所 総務部危機管理室
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 学位論文題名と概要
-
『日本における避難所管理・運営に関する研究』
- 概要:
- 日本の避難所環境については、阪神・淡路大震災時の国際検証で「非人間的な環境」と指摘されて以降、法律改正や各種ガイドラインの策定等対処的方法が考案されていますが、根本的な解決に至っておらず、特に生活環境において課題が存在し続けています。本研究は、これら課題の発生構造を解明し、日本の避難所空間の管理・運営計画のありかたを追求することを目標とし、①現在の避難所空間の問題を整理し、②避難所空間の設定や管理運営の歴史的な経緯を明らかにし、③自治体における避難所空間の管理・運営計画の実態を明らかにし、④現在の避難所空間課題の発生構造と対応・改善手法を検証し、⑤新たな避難所空間の管理・運営計画のありかたを提案するものです。
- ー 現在の仕事において大学院での研究や学修が生かされている場面や、学部卒業で就職をしている方との違いを実感する場面
-
私は行政の危機管理部局で働いています。危機管理部局は、防災・防犯など市民生活の安全をお守りするための施策の推進を担う部署ですが、防災防犯だけではなく、暑熱や食中毒など市民生活の危機に関するあらゆる事象にアンテナをたてて、各部署がタイムリーに適切な対応を進めているか進捗確認する必要があります。
私は大学院で、知見豊富な教授陣から、避難所、公衆衛生、災害対策本部運営ならびに防災行政法務を専門的に深く学ばせていただいたおかげで、市の危機管理業務遂行力の向上のみならず政府の委員会で広く安全に関わる施策を提案できる機会をいただけるレベルの知識とネットワークを得る事ができました。
- ー お仕事との両立の工夫等について
- 学業と仕事の両立について工夫したのは、「スケジュール管理」と「巻き込み力」です。手帳に、学業は赤、仕事は黒、プライベートは青の字で書き、一色に偏らないようにし、授業が減る時期でも先行研究論文を読む予定や、出せたら・・くらいの一般論文提出の〆切等、書かなくてもよさそうなことでも書いて進捗管理をしたことで、遅れず研究が進捗しました。巻き込み力は結果としての色が濃いと思うのですが、課題のレポートやプレゼンテーションを職場で発表してアドバイスをもらったり、研究の楽しさを伝えているうちに、上司や同僚から「応援したろ」という積極的な後押しをもらえるようになりました。職場の理解と応援というのはこんなにも心強いのだと実感しました。
- ー 指導教員名とその教員を選んだ理由や教員とのエピソード等
-
- 指導教員名:
- 越山 健治先生
そして合格後ではありますが、18年ぶりに出席した高校の同窓会で、越山先生にお会いして・・・実は先生と私は高校の同級生同士だったことが判明しました。師匠の越山先生は、隣のクラスのコッシーだった訳で・・同世代だからこその雑談時に時々、同級生のノリになるのも楽しいです。
- ー 普段、どのような研究活動(手法)を行われているか、またその「おもしろさ」「難しさ」について
- 私は基礎自治体の行政職として働いており、今は危機管理室で業務をしています。大学院入学後に危機管理から異動して別業務に従事したこともありますが自治体業務に安全に関係しない部署はありません。どこにいても安全に関する課題に直面します。今までだったら先進自治体に習って改善をはかるしかなかった問題でも、今は研究対象として課題の背景をさぐり、縁のある先生に相談しながら先行研究調査やデータ分析をして、課題の発生原因や、解決手法を明らかにしていくプロセス自体、とても面白いです。一方で、それが明らかになっても、現実社会ではさまざまな事情により解決できないこともあり、難しいなと感じるところです。
- ー 関西大学大学院社会安全研究科に進学を考えている方へのメッセージ
-
関西大学大学院社会安全研究科を進学の選択肢に入れているなら、ぜひ一度、高槻ミューズキャンパスに足を運び、院生室訪問や教授陣と面談することをお勧めします。まずハード面が素晴らしいです。夜や土日も安全で清潔に、院生同士も程よい距離感での研究環境が確認できます。また、教員同士のコミュニケーションの活発さも高槻ミューズの特徴だと思います。●●なら△△先生に聞いてみたら?とお勧めされることも多く、多種多様な専門教員がいる環境、連携の大らかさは学びを深めやすいと感じました。それと指導教官によるかもしれませんが、学会参加や被災地学習に挑戦させていただく環境も整っており、面倒見がよいというレベルをこえて、ともかくさまざまな経験ができる機会の選択肢が多く示されるので、しっかり応えて学びを深めよう!という気が湧いてきます。
何よりオススメしたいポイントは、卒業後にも緩やかに繋がりがあり、相談したら事務局も教授陣も在学時と同じくらいの手厚さで相談にのってくれて、高槻ミューズキャンパスには、研究に関する「実家」みたいな雰囲気があることです。大学の学部を卒業した後とは全く違いますし,他大学の研究科卒業生から聞く話とも違い,高槻ミューズキャンパスの特徴かなと思います。
- ー 出身学部と所属研究科の専門分野が異なっている際に、特にどのような点に注意して受験準備を進めたか
-
相反することに見えますが、自分の入学の目的や研究したいことを明確に絞ると同時に,研究したい事の周辺間口を広げることに注意をして準備をしました。
例えば、入学した暁には、どんな分野の何を研究して何を明らかにしていきたいかを明確に答えられるように先行研究論文を読み、自分が研究したいことはまだ明らかになっていないということを確認しておきました。また、間口を広げるために「社会安全学入門」を読み、目次と索引に出てくる語については概要を理解し、自分が研究したいことに絡めて自分の考えを説明できるように,準備しました。

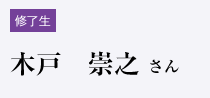
-
社会安全研究科 防災・減災専攻
博士課程前期課程 2014年4月入学
(入試種別:社会人入学試験)- 勤務先名:
- (株)エー・ビー・シー リブラ
(朝日放送テレビ報道局より出向)
ABCテレビ「おはよう朝日です」気象情報担当デスク
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 学位論文題名と概要
-
『データ放送を用いた「ピンポイント避難情報」の基盤構築に関する研究』
- 概要:
- テレビの避難情報伝達は多くの問題を抱えています。「データ放送の強制表示機能」を使えば、合理的できめ細やかな情報伝達を実現できる可能性を示し、そのためにどういう情報基盤の整備が必要かを確認しました。
- ー 現在の仕事において大学院での研究や学修が生かされている場面や、学部卒業で就職をしている方との違いを実感する場面
-
修士論文にまとめた研究をもとに、職場では「災害情報のエリア限定強制表示」の仕組みを国内の放送局で初めて導入し、総務省「電波の日」近畿総合通信局長表彰を受けました。系列局のみならず、他系列にも拡がりを見せており、実務にフィードバックできたと感じています。
ジャーナリストとしてキャリアを積み重ねると、専門分野を深め体系的に学ぶ必要が出てきます。社会安全研究科には、取材対象としても、アドバイザーとしても頼りになる、錚々たる先生方が揃っています。今後の仕事に力強い援軍を得た気持ちです。
- ー 出願に先立って志望の指導教員へどのような相談をしたか、相談してよかった点
- 私は当時、報道記者の仕事をしていました。上司の理解があり、神戸の「人と防災未来センター」で1年間社外研修をさせていただけることになったのですが、そのセンター長が、社会安全研究科の河田恵昭教授(当時)でしたので、「同時に大学院で学びたい」と相談しました。また学生(大阪市大商学部)時代から面識があった安部誠司教授にもご連絡したところ、「専門分野に関する本を少なくとも一冊読んで試験に臨むように」とのご指導をいただき、そのようにさせていただきました。
- ー 奨学支援制度の利用にかかる経験談、よかった点
- 社会人大学院学生給付奨学金を2年次に活用させていただきました。この制度は収入があっても出願でき、学業成績だけでなく社会人業績も採否の判断に加えていただけるとのことでした。私のこれまでのキャリアの、どの点を評価いただけたかはわかりませんが、2人の子どもの教育費など、出費をやりくりしながらの大学院進学でしたので、家計を管理する妻は「とても助かる」と喜んでいました。
- ー お仕事との両立の工夫等について
- 「人と防災未来センター」での社外研修は記者の仕事との兼務でした。記者として約120日を会社で、研究員として約120日をセンターで勤務しましたが、幸いシフトで動く遊軍記者だったので、勤務担当デスクと相談して会社での勤務を土日祝日中心にすることで、平日60日の通学可能日を確保することができました。台風襲来など災害担当記者として稼働する日は欠席しましたが、先生方にご理解いただけて助かりました。2年次は登校がゼミの日のみとなり、シフト調整と代休で対応しました。
- ー 普段、どのような研究活動(手法)を行われているか、またその「おもしろさ」「難しさ」について
- 勤務先での日常の業務では、やるべきことや、やりたいことを前にさまざまな壁にぶつかります。社会人大学院生はその「ニーズ」を研究課題にできる強みがあります。研究のためのデータも(秘匿すべき情報はもちろんありますが)入手しやすいですし、ベースになる知識や考え方を一から調べる手間も少なく済むなど、研究は進めやすいと思います。一方で組織の中には、業務の傍らで大学院に行くことについてネガティブな印象を抱く人もいます。上司や同僚に理解をしてもらえるように腐心しました。
- ー 関西大学大学院社会安全研究科に進学を考えている方へのメッセージ
- 会社組織における中高年の「働き甲斐」や「活かし方」が課題になりはじめた時代に、40歳代前半で大学院に行く機会をいただけたことは、本当に幸運でした。職場で仕事をしているだけでは手に入らない強い「武器」と、わかりやすい「看板」を手に入れることができたと思っています。防災や安全は、どんな企業・組織にも必要な概念です。むしろ、組織のことを大切に考える人にこそ、勇気と信念を持って社会安全研究科の門をたたいていただきたいです。
東アジア文化研究科

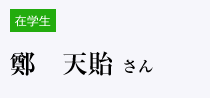
-
東アジア文化研究科 文化交渉学専攻
博士課程後期課程 2022年9月入学
(入試種別:外国人留学生入学試験)
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 研究テーマと概要
-
『日本における宋代書法の受容――五山禅林書道と江戸の唐様をめぐって(予定)』
- 概要:
- 鎌倉時代から室町前期(すなわち五山全盛期)と江戸時代、宋代書法の東伝がどのような影響を与えたのか、また宋代書法の受容に対してどのような偏向を持っていたのか、文化交渉の視点から考察したいと考えています。
- ー 時間割
-
博士課程後期課程 2年次 春学期
1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 月 火 水 木 文化交渉学研究
(東アジアの思想と構造)
演習1A金 土
- ー 出身学部と所属研究科の専門分野が異なっている際に、特にどのような点に注意して受験準備を進めたか
- 関西大学大学院東アジア文化研究科は、勉強の意欲を持つ学生に平等な機会を与えてくれます。しかし、異分野出身の学生は、受験準備を進める際に、同一専攻の学生よりもっと努力しなければならないという覚悟を持つべきです。私自身の場合、早くから歴史や芸術などに興味があり、大学では関連する専攻を選ばなかったためか人文学(特に歴史文化に関して)への熱意が強まりました。日本語や日本文化に関しても、独学で学び始めました。それは文化交渉学に関心を持っていたからです。異文化間の文化の交流・交渉への興味を確認することが大切と思います。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
-
大学院に進学した理由は、人文学というものをしっかりと学び、専門的知識を習得したいからです。
関西大学を選んだのは、大体4つのポイントがあります。
第一に関西大学図書館に豊富な蔵書があることです。書物は人文学研究の礎であり、関大図書館は優れた条件をそなえています。
第二に東アジア文化研究科には博学な先生が多くいらっしゃることです。入学後三年半の間に、先生方から多くのことを学ばせていただきました。特に指導教授の吾妻先生は、コロナ禍で大変な時期に多くの支援をいただきました。
第三に学生たちに十分な研究条件を用意してくれていることです。四季の景色を満喫できるキャンパスや安価でおいしい学食、また明るい研究室などは私たちを研究に専念させてくれます。
最後に東アジア文化研究科は多数の海外発表の機会をしてくれます。「万巻の書を読み千里の道を行く」――内外での発表を通じて自らの研究力を高めるだけではなく、実際に異文化を認識しつつ人文学の魅力を感じられます。学生支援のため、学会発表のための書籍購入や外国への往復航空券の補助なども出ます。
- ー 大学院進学のための受験対策や事前準備
- 東アジア文化研究科の入試は、筆記試験と口頭試問があります。入試準備の中で最も重要なのは研究計画書でしょう。まず興味ある領域で未解決の問題点を探し出し、次に先行研究の成果に基づいて自分の研究方法と内容を確認します。また文化交渉学の研究については、外国語(日本語や英語、漢文など)も必要な能力です。研究計画と外国語の両方を準備しておくべきです。
- ー 普段、どのような研究活動(手法)を行われているか、またその「おもしろさ」「難しさ」について
- 私の場合、文献資料を用いて研究を行います。それらを通して新しい知識の習得や発見があり研究の「おもしろさ」を感じることができます。しかし、論文を書くことは大変で、多くの時間をかけて自分の見解を筋道立ててまとめるのは容易ではなく、それが研究の「難しさ」です。
- ー 関西大学大学院東アジア文化研究科に進学を考えている方へのメッセージ
- 東アジア文化研究科は、東アジアを中心に古代から現代までの歴史や、思想、言語、芸術、文学などさまざまな分野の研究を進めています。我々が今生きている現代社会はどのように誕生し、発展してきたか、その文化はどのような歴史や特色、魅力があるのか。こうした問題に興味があり、また人文学を専門的に追究したいのであれば、当研究科はすぐれた学びの場と思います。

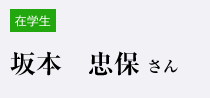
-
東アジア文化研究科 文化交渉学専攻
博士課程前期課程 2021年4月入学
博士課程後期課程 2024年4月入学
(入試種別:一般入学試験)
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 研究テーマと概要
-
『日本統治期台湾の法院通訳・官元未が記す客家語音声の特徴―『台湾警察時報』の音声表記を中心に』
- 概要:
-
日本統治下の台湾では、基本的な政策方針として、台湾人の日本人化を図ろうとする「同化政策」が実施されました。その手段として、台湾人への日本語の教育、普及に力が注がれました。一方で、安定した植民地統治に資するために、警察や教員など、台湾民衆と直接触れる機会の多い職業者に対しては、台湾本土の言語(台湾語、客家語、先住民族の言語)を学ぶことが奨励されました。彼らが学ぶ学習教材として、仮名文字および補助記号を用いた表音システムにより記された辞典、語学雑誌、会話文例集などが数多く刊行されました。台湾で勤務する警察官向けに発行されていた月刊雑誌『台湾警察時報』には語学を専門に紹介するコーナーがあり、ここに連載されていた記事もそのような資料の一つです。このコーナーでは台湾語、客家語、タイヤル語などの記事が警察業務に必要な会話文を中心に紹介されていました。
この『台湾警察時報』誌上で、台北地方法院の法院通訳を務めていた官元未という人物が、1931年から10年間に渡って客家語の記事執筆を担当していました。
本研究では、官元未の人物像、言語観について考察しつつ、官元未の記事に記述された表音システムを整理して、その音声・音韻体系を分析することによって、その客家語の特徴を明らかにしようとしました。
- ー 時間割
-
博士課程後期課程 1年次 春学期
1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 月 火 東アジア
文化資料研究
(言語と表象)A
講義アカデミック外国語
(中国語)(1)A水 木 文化交渉学研究
(東アジアの言語と表象)
演習1Aアカデミック外国語
(中国語)(1)A金 土
- ー お仕事との両立の工夫等について
- 指導教員と相談し、仕事の都合でどうしても講義やゼミを休まなければならない場合があることを予めご了承頂きました。休んだ分は、ゼミの仲間から内容を聞くなどして、次回のゼミに支障のないように努めました。
- ー 出身学部と所属研究科の専門分野が異なっている際に、特にどのような点に注意して受験準備を進めたか
- 学部では他大で農学を専攻していましたが、中国に留学したり、中国で働いていたこともあり、中国語の学習はコンスタントに続けて参りました。そのため、筆記試験はそれなりに自信があり、受験準備としては、過去問を参考に、中国語学に関連する中国語の論文などを読んだりする程度でした。口頭試験では、研究で何を明らかにしたいのかを出来るだけ明確に話すよう心がけました。
- ー 長期履修学生制度利用にかかる経験談、よかった点
- 長期履修制度により比較的ゆとりをもって研究を進めることが出来たので、その分、アウトプット(論文執筆)だけでなく、インプット(学び)に対してもより多くの時間をさくことができました。特に、私は学部での専攻が現在の研究分野と異なるため、論文執筆の上で必要な知識を指導教員である石崎先生からしっかり学ぶ時間を持つことができて、大変よかったと思います。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
-
大学を卒業後、農業や貿易の仕事に携わっていましたが、その傍ら、趣味と実用を兼ねて客家(はっか)語(中国語の方言の一つ)を学んでいました。学習を始めた当時は客家語の教科書が非常に少なかったこともあり、参考のため日本・中国の書店やネット上で目にした客家語に関する本や資料などを収集していました。
それらの資料のうち、近代中国において欧米の宣教師が残した資料や、日本統治時代の台湾において日本語で作成された資料が特に興味深く、それらに目を通しているうちに、解決したい疑問点や、自分なりの発見もあったので、いつか大学院でじっくり研究に取り組みたい、と考えておりました。
実は老後の楽しみにするつもりでしたが、経済的な条件がある程度整ったことと、幸か不幸かコロナ禍のため在宅のまま遠隔で授業に参加できる見通しとなり、仕事と両立しやすくなったため(このメリットは半年程度で無くなりましたが…。)、思い切って大学院進学を決意しました。
関西大学の東アジア文化研究科には、欧米や日本などに残された「周縁」資料から当時の言語の様相や変遷を研究する教授が多くおられるため、上述のような私の関心、研究テーマに対しても有益なご指導を頂くことができるのではないかと思い、本研究科を志望しました。
- ー 関西大学大学院東アジア文化研究科の魅力
- 東アジア文化研究科は、中国をはじめとする各国からの留学生が多く在籍しています。私が修士課程で選択した授業では、自分以外は全員留学生、というケースがほとんどでした。中国語が飛び交う教室に一人いると、むしろ自分の方が留学生であるかのような錯覚に陥ります(笑)。日本人学生は希少なので、留学生から講義や論文について日本語に関する質問を受けることが多く、何かと重宝されます。留学生たちと交流できる機会を多く持つことが出来るのも本研究科の魅力の一つだと思います。

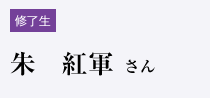
-
東アジア文化研究科 文化交渉学専攻
博士課程後期課程 2018年4月入学
(入試種別:外国人留学生入学試験)- 勤務先名:
- 中国魯東大学 日本語講師
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 学位論文題名と概要
-
『7-9 世紀の山東を中心とする東アジアの文化交渉研究』
- 概要:
- 7-9 世紀の山東を中心とする東アジアの人・モノ(信仰)の交渉から、古代東アジアにおける山東の位置づけを明らかにしようとしたものです。結論として、古代の山東は、中国の窓口としての役割を果たした一地方にとどまらず、独自文化の発信地としての性格をも有する、東アジア文化交渉の一大拠点でありました。
- ー 現在の仕事において大学院での研究や学修が生かされている場面や、学部卒業で就職をしている方との違いを実感する場面
- 東アジア文化研究科では、歴史、思想、宗教、言語といった多岐にわたる知識を勉強することができ、現在の研究に大変役に立っています。現在、大学教員として働いていますが、大学院生時代にお世話になった先生方々から引き続きアドバイスをいただいて、とてもありがたいです。東アジア文化研究科では抱いた興味関心をさらに深めていくこともでき、ひとつのテーマについても多角的に考えていくことができます。これは現在の勤務先での担当講義や学生指導にも生かされているとしみじみと感じています。
- ー 出願に先立って志望の指導教員へどのような相談をしたか、相談してよかった点
- 指導教授は篠原啓方先生です。入学する前に、篠原啓方教授の論著を拝読し、とてもまじめな先生だと思って、先生に連絡を取りました。メールでやりとりし、一回面談しました。先生からは、関西大学および東アジア文化研究科の現状や、私の研究に関する中国・日本・韓国の資料や研究の現状について詳しく分析していただきました。
- ー 奨学支援制度の利用にかかる経験談、よかった点
- 関西大学大学院給付奨学金により年額25万円の給付を受給しました。また、毎年、学会での研究発表に対する補助費、往復航空運賃の半額を補助してもらいました。日本国外での学会にも積極的に参加することにより学術的な刺激を得られる機会がありました。それから、各種の研究助成を申請する前に、研究支援・社会連携グループから文章の論述や日本語の文法を校正していただいたおかげで、笹川科学研究助成を受けたこともあります。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
- 日本の歴史研究の理論と方法を身につけるため、日本の大学院に進学することにしました。研究科の研究対象が東アジアと広域であり、なおかつ、思想、歴史、言語などの分野を専門領域とする教員、学生が在籍しているため、多分野の研究を学び複眼的な研究視野を養えると考えました。
- ー 普段、どのような研究活動(手法)を行われているか、またその「おもしろさ」「難しさ」について
-
歴史史料の輪読を通して、内容についてさらに明確になります。研究に関連する中国・韓国・日本の史書や文学作品、地方志、金石文などを探して読みます。それから、中国東部沿岸や日本・韓国への調査も研究方法の一環になります。
古代史の研究資料は限りがあり、史料の精読やこれまで注目されてこなかった資料の発見などは難しいです。でも、フィールドワークを通して、意外な発見を見つけることは面白いです。
- ー 関西大学大学院東アジア文化研究科に進学を考えている方へのメッセージ
- 東アジア文化研究科では、国籍にかかわらず、さまざまな学生が文化交渉学の方法を使って研究しています。本大学院には、言語・文学・思想・宗教・歴史などの分野の先生が在籍されており、研究する環境が整えられています。または、中国、韓国、ヨーロッパの大学と連携し、年に数回国際院生フォーラムを開催するため、学会で発表する機会も多いです。研究者をめざす学生にとって、学際的研究視野を養う稀な環境なので、ここで自分の目標をめざして夢をかなえてください。

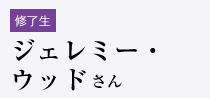
-
東アジア文化研究科 文化交渉学専攻
博士課程前期課程 2014年4月入学
博士課程後期課程 2016年4月入学
(入試種別:外国人留学生入学試験)- 勤務先名:
- 天理大学 国際学部 講師
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 学位論文題名と概要
-
『泊園書院の『中庸』研究について(前期課程)・近世期日本における『近思録』の受容と解釈史(後期課程)』
- 概要:
-
泊園書院の『中庸』研究について:近世・近代大阪に存在した漢学塾、泊園書院における『中庸』の研究や解釈の特色について考察したものです。
近世期日本における『近思録』の受容と解釈史:江戸時代における道学の入門書として知られる『近思録』の受容過程や各儒者とその学派の解釈の特色について考察したものです。
- ー 現在の仕事において大学院での研究や学修が生かされている場面や、学部卒業で就職をしている方との違いを実感する場面
- 現在の仕事は大学教員で、大学院で学んだ研究方法や論文作成技術等のアカデミック・スキルは日々生かされています。
- ー 出願に先立って志望の指導教員へどのような相談をしたか、相談してよかった点
- 指導していただきたかった東アジア文化研究科の吾妻重二教授に、出願前何度かメールで研究課題の内容を相談させていただき、毎回とても丁寧に詳しくアドバイス等お返事をしてくださったので、自分の中で研究テーマがより明確になっていき、出願の際にははっきりとした研究課題が出来上がっていました。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
-
日本儒教思想史の研究者になりたかったため、大学院進学を決めました。
関西大学大学院東アジア文化研究科を選んだ理由として、第一に儒教研究の権威である吾妻先生に指導していただきたかったことが大きいです。
第二に、自分の専門分野だけでなく、幅広く東アジアの歴史・言語・思想等についても学ぶことができるので選びました。
- ー 指導教員名とその教員を選んだ理由や教員とのエピソード等
-
- 指導教員名:
- 吾妻 重二先生
吾妻先生は儒教思想史、特に朱子学研究の第一人者であるため、自分の研究テーマである泊園書院の『中庸』研究や近世日本における『近思録』の解釈史を指導していただきたかったため選びました。
エピソードとしては、吾妻先生は研究の指導だけでなく、研究テーマに関わるイベントにもよく一緒に連れて下さいました。大阪の道明寺天満宮で釈奠という孔子を祀る祭祀が実施された際に私や他の指導生を一緒に連れていってくださったことをよく覚えています。
- ー 関西大学大学院東アジア文化研究科の魅力
- 関西大学大学院東アジア文化研究科の最大の魅力は、自分の専門分野だけでなく、歴史・言語・思想等東アジアの文化全般を、各分野の第一人者の先生から学ぶことができるということです。さらに、泊園文庫や内藤文庫があり、関西大学にしかない漢籍や和本などの東アジア関連資料が非常に豊富なので、東アジアについて研究をするには極めて恵まれた環境であることです。
- ー 関西大学大学院東アジア文化研究科に進学を考えている方へのメッセージ
- 東アジア文化研究科では、上記のように恵まれた環境であることや、ゼミや授業もほとんど少人数で、色々な国の留学生もたくさんいるので国際的な雰囲気で学ぶことができます。東アジアの文化について研究しようと思っている方は是非関西大学大学院東アジア文化研究科を検討してください。
ガバナンス研究科

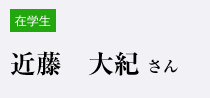
-
ガバナンス研究科 ガバナンス専攻
博士課程前期課程 2022年4月入学
(入試種別:学内進学試験)
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 研究テーマと概要
-
『自社株買い課税に関する考察 -米国インフレ抑制法(2022年8月)を中心に-』
- 概要:
- 本研究では、2022年8月に法案として成立した米国インフレ抑制法を中心として、アメリカにおける自社株買い課税の導入に至るまでの議論の整理、さらに導入後の影響についての考察を行うことを予定しています。本研究を通して、現在のアメリカの格差問題の要因の一つである不公平税制を議会、そしてバイデン政権がどのように改善しようとしているのかを明らかにしていければと考えています。
- ー 時間割
-
博士課程前期課程 1年次 秋学期
1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 月 火 貿易政策研究 ガバナンス演習 福祉政策研究 現代行政学研究 水 政策規範研究 木 公共政策研究 金 土
- ー 出願に先立って志望の指導教員へどのような相談をしたか、相談してよかった点
- 学部時代のゼミ担当の先生が河﨑信樹先生であったため、大学院でも引き続き指導教員に河﨑先生を希望しました。先生には大学のゼミ後の時間などに大学院の進学に関して相談をさせていただきました。相談をしたことで、大学院に進学する上での研究内容についてやスケジュール等を入学前から考えることができました。
- ー 奨学支援制度の利用にかかる経験談、よかった点
- 関西大学独自の給付型奨学金をいただいています。大学院に進学する上で学費の心配がありましたが、奨学金を頂くことで経済的な負担が軽減され、研究に集中することができています。
- ー 大学院進学のための受験対策や事前準備
- 学内進学試験でガバナンス研究科に進学したため、試験内容は研究計画書をもとにした口頭試問でした。そのため、研究計画書の内容で質問されそうな箇所をあらかじめ自分で考えて、その質問に対する回答を作るなどの対策を行いました。
- ー 修了後の進路希望
- 博士課程前期課程修了後は博士課程後期課程に進学し、今後も研究を続けていきたいと考えています。
- ー 関西大学大学院ガバナンス研究科の魅力
- ガバナンス研究科は魅力の一つとして、幅広い学問分野を学ぶことができるということがあります。私自身も授業の中で、自分の研究テーマとは離れているように思っていた授業内容であっても、理解を進めるうちに自身の研究テーマとの関わりが見えてくるということが多々ありました。そのため、ガバナンス研究科で学ぶことで一つの視点に捕らわれずに研究を行うことができ、自身の研究にも良い影響があると実感しています。

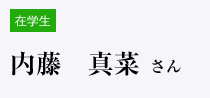
-
ガバナンス研究科 ガバナンス専攻
博士課程後期課程 2023年4月入学
(入試種別:一般入学試験)
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 研究テーマと概要
-
『現代日本の教育政策―教育改革と教育環境の変容―』
- 概要:
- 1955年体制以降の教育政策形成に関与したアクターの特徴、影響力関係を政治学的視点から分析します。そして、教育政策をめぐる政治と社会の相互関係を踏まえ、今日の多様な問題を有する教育環境が形成された要因を明確にします。
- ー 時間割
-
博士課程後期課程 1年次 春学期
1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 月 火 D現代日本政治 Dガバナンス演習 水 木 金 土
- ー 修了後の進路希望
- 修了後は研究者もしくは教育関係の職業に就業したいと考えています。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
- 本研究科を選択した理由は2つあります。第1 に、多様な学問を学べる点に魅力を感じたからです。ガバナンス研究科は幅広い学問を学修することができます。複雑化、多様化している現代社会においては出来事を1つの視点のみならず、多角的視点で考察し、行動する必要性があります。そのため、その力を養い、人びとが笑顔で快適に過ごせる社会の構築に貢献すべく、ガバナンス研究科を選びました。第2に、学部、修士時代にお世話になった小西先生の下で研究したかったからです。学部生時代、小西先生の現代日本政治に対する豊富な知識、懇親丁寧な教育姿勢に惹かれました。自分も小西先生のような存在になりたいと思い、小西先生が在籍するガバナンス研究科への進学を決めました。
- ー 指導教員名とその教員を選んだ理由や教員とのエピソード等
-
- 指導教員名:
- 小西 秀樹先生
学部、修士時代に小西先生のもとで教育政策に関する研究を行っていました。小西先生からの指導は研究活動を進めていく上で有意義な日本政治に関する知識のみならず、論文執筆に必要な文章表現、アイディアなどをご教授頂きました。また、自身の教育政策の研究にも親身に指導してくださりました。小西先生の下で培った知識、経験は約3年近く働いた企業でも役に立ちました。
- ー 普段、どのような研究活動(手法)を行われているか、またその「おもしろさ」「難しさ」について
- 研究においては、教育政策形成に関与したアクターの特徴、影響力関係を分析手法として用いています。面白さとしては、政策形成に関与したアクターの意図、影響力関係が明らかになる点です。教育政策形成には多様なアクターが関与しています。なぜその政策を形成しようとしたか、いかなる働きかけがあったか疑問になる点が多く、その疑問が解消されたときに面白さを感じます。難しさとしては資料収集が大変な点です。現代日本の教育政策は主に教育学からの視点が多く、政治学からの視点から扱った先行研究は少ないです。近年はアクター分析を用いた教育政策の研究が盛んになってきていますが、まだまだ数が少ない印象で、新聞や国会議事録など膨大な1次資料から収集整理、分析を行う必要があります。時間と労力を要する点では大変な作業です。しかし、より良い研究、論文作成をする上では重要な作業なため、それをモチベーションとして日々励んでいます。
- ー 関西大学大学院ガバナンス研究科に進学を考えている方へのメッセージ
- 関西大学大学院ガバナンス研究科は、政治、経済、経営、法律、国際関係など多様な学問を学修できます。複雑化、多様化している現代社会において、私たちは複合的な視点に基づいて考え、行動することが重要です。そのため、ガバナンス研究科で培う多様な知識、思考方法は現代社会で生きる私たちに有意義な学び、視点をもたらしてくれると言っても過言ではありません。また、ガバナンス研究科には多様な経歴を有する社会人や留学生などが在籍しています。こうした方々と交流することは学生にとって良い形で人生の糧になるものだと思います。自身の研究はもちろんのこと、将来に仕事やプライベート面で必要な糧を養いたいと考えている人にとっては、ガバナンス研究科は最適な環境です。是非、ガバナンス研究科への入学をお待ちしています。

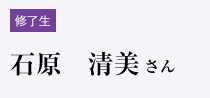
-
ガバナンス研究科 ガバナンス専攻
博士課程前期課程 2020年4月入学
(入試種別:社会人入学試験)- 勤務先名:
- 社会保険労務士事務所 オフィスきよみ
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 学位論文題名と概要
-
『トラック産業における労働時間規制の現状と課題』
- 概要:
-
自動車運転者の働き方改革による時間外労働上限規制は5年間の猶予期間が設けられ、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)と共に2024年に改正が行われましたので、労働環境の改善に繋がる労働時間管理を行わなければなりません。
しかしながら、運送事業者では現状と法律等のギャップが大きく、法を厳守することが困難な事業者が多く見られ、どのようにすれば正しい時間管理ができるのかを考えることとなります。また、厚生労働省賃金統計調査により、自動車運転者の労働時間及び賃金は一般労働者より2割長く2割低いと示され、労働環境の悪化により、人材不足に拍車がかかっております。
トラック運送業は、日本のライフラインを司る必要不可欠な職業であり、その職業に焦点をあて、労働時間を主として、トラック産業における構造的な問題と、人材不足についての原因と対策を考察することとしました。
- ー 現在の仕事において大学院での研究や学修が生かされている場面や、学部卒業で就職をしている方との違いを実感する場面
-
トラック運送業での四半世紀の勤務経験があり、その勤務中に社会保険労務士として資格取得、開業登録し15年以上が経過しました。運送業では現場での業務が重要ですが、まずは労働環境の改善が必要と考えられ、法律等の遵守が最優先となります。
トラック産業における大学院での研究として、法律にかかる経緯や現状の把握、問題の洗い出しを行い修士論文を仕上げました。その論文を基に、運送事業者の方々が時間管理をしなければならない必要性の気づきがあればよいとの思いで書籍を執筆し出版(第一法規株式会社)したところ、トラック協会などの指導書として採用されました。関西大学図書館にも配架しております。また、その出版会社より書籍内容で講演依頼があり、その担当者がガバナンス研究科の修了生(友澤祐太先輩)であったことに驚きを感じました。
大学院終了後には、物流関大会に入会し、そこでの講演を行わせて頂き、社会保険労務士関大会にも入会し、関西大学卒業生の方々より、さまざまなご縁を頂いております。
- ー お仕事との両立の工夫等について
-
入試説明ガイダンスに参加し、社会人学生としての時間が出来るかとの質問もありましたが、自身がやりたいことのひとつであった大学院での研究が叶いましたので優先しました。
入学が決まり、数か月後にコロナ禍によりZoomやオンデマンドでの授業が主となりましたが、あえて教授にお願いし、出来る限り対面出来る講義は出席するように致しました。授業を最優先し、仕事にかかる時間は調整を行いましたので、そんなに負担には感じませんでした。新しい知識を得たことは、今でも役に立っています。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
-
大学院進学につきましては、全国社会保険労務士会連合会特別推薦入学試験を利用し、社会人として受験致しました。基本的な受験以外に個別審査の対象となり追加対応が必要だったので、レポートやそれまでに執筆していた書物のすべてを提出致しました。
最初は3年コースで入学しました。しかし、途中で2年コースに変更しましたので、2年目は単位取得に忙しく通学しましたが、やりがいのある有意義な時間であったことには違いはありませんでした。
また、副指導教員からご指導いただき、「命を削りながら論文を書いている」この言葉を心して研究を続けていきたいと強く思っております。
- ー 指導教員名とその教員を選んだ理由や教員とのエピソード等
-
- 指導教員名:
- 宮下 真一先生
修了式の際は、その修士論文を製本し手渡ししたところ、とても喜んで頂けたように感じました。有難うございました。
- ー 普段、どのような研究活動(手法)を行われているか、またその「おもしろさ」「難しさ」について
-
大学院では、関西大学大学院院生合同学術研究大会があり、ガバナンス研究科として、「自動車運転者の労働時間と現場での実情について」の発表を致しました。参加することに意義があると考えており、大学院に在籍している間にこの行事に参加できたことは、とても良い経験をさせていただいたと思っています。学べることが、こんなにも有難いという実感するひと時でした。
今では、トラック運送業での2024年問題などに関して、登壇する機会が増え、質問などを頂くことにより、資料作成の度に内容がバージョンアップしています。また、それに繋がる研究での管理者研修などで、伝えたい事が伝わったかどうかがわかるのは、伝わった際には相手の行動が変わりますと伝え続けています。
ひとつ一つの経験が今を作っていますので、人生無駄な事はないと思って、どのような事も挑戦しております。
その時の登壇経験も、今に繋がっていると思っております。
- ー 関西大学大学院ガバナンス研究科に進学を考えている方へのメッセージ
-
ガバナンス研究科は2011年4月に設立され、その内容は、公的な問題を発見してその解決策としての政策をデザインし、実現する能力をもつ“高度公共人材”を育成する研究科です。わたしは、ガバナンス研究科修士第60号ですので、60人目だと思います。
このガバナンス研究科の魅力は、自由な研究ができるところです。入学ガイダンスなどに参加して頂き、研究内容の相談をするのが良いと思われます。
また、大学院修士課程では、次の段階の博士課程も見越して入学時に研究内容を模索するのも良いでしょう。大学院博士課程は生半可な気持ちでは研究できないと教授より指導を受けております。しかし、諦めた時点で止まってしまいます。なにごとも、出来ないと考えずに行ってみてください。戸を叩けば道は開かれます。
新しい世界への挑戦、お待ち申し上げております。

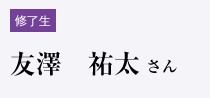
-
ガバナンス研究科 ガバナンス専攻
博士課程前期課程 2017年4月入学
(入試種別:学内進学試験)- 勤務先名:
- 第一法規株式会社
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 研究テーマ
-
『日韓関係と議員外交 -日韓議員連盟の分析-』
- 概要:
- 日韓関係が摩擦に陥った際、日韓議員連盟が関係改善のために、どのような影響力を及ぼしたのか(もしくは影響を及ぼせなかったのか)を分析しました。自民党内の政策決定過程の変化が、日韓議員連盟の国内調整力に影響を及ぼしていたことを仮説とし、「第一次・第二次歴史教科書問題」「日韓経済協力交渉」を事例として分析しました。その結果、選挙制度改革により自民党の政策決定過程が族議員から官邸主導に移行したことに伴い、議員の影響力が弱まった結果、日韓議員連盟の影響力も衰退したことを指摘しました。
- ー 現在の仕事において大学院での研究や学修が生かされている場面や、学部卒業で就職をしている方との違いを実感する場面
-
現在、企業法務担当者向けのマーケティング業務を担当し、WEBセミナーの企画・運営・登壇(弁護士や企業法務実務家とのパネルディスカッションなど)をしています。「企業法務」はガバナンスの側面もあり、政治だけではなく、組織論や統治など、ガバナンス研究科で得た横断的な知識が、セミナーに登壇する際の話の切り口やテーマ設定にもなります。
同時に、政治と法律の繋がりは表裏一体と言えます。法律は社会のインフラであり、法律を審議するのは国会の場となります。まさに大学院時代に学んだ政治過程論の知識が、法律の立法過程・改正内容を把握する際、実務に生きる場面が多々あります。
また、ガバナンス研究科の大学院生は、幅広いバックグラウンドを持った大学院生が在籍しているのも特長です、実は私のチームのメンバーがセミナー登壇を依頼した社会保険労務士の先生が、実はガバナンス研究科を修了された後輩だった(石原清美先生)というエピソードもあります。
- ー 出願に先立って志望の指導教員へどのような相談をしたか、相談してよかった点
- 学部3年次から大学院進学を意識しており、早期から大学院の相談を学部ゼミの指導教員である小西秀樹先生にしていました。小西先生は大学院受験のことだけでなく、院生になったときのことを見据え、合格後の研究生活などに関してもさまざまなアドバイスをしてくださいました。私自身も、先生のアドバイスを受け、4年次に大学院授業科目の先取り履修制度を利用し、入学前から大学院の講義への理解を深めました。
- ー TA・RA制度の利用にかかる経験談、よかった点
- ティーチング・アシスタント(TA)制度を用いて、政策創造学部の講義アシスタントをしておりました。1年次の学生が受講する講義でしたが、大学院生目線で聞くと、学部のときに聞いた同じ講義とは異なる好奇心、知見、視座を得ることができ、研究のヒントとなった講義もあります。収入も得ることができ、かつ講義内容も聞けるため一石二鳥です。
- ー 奨学支援制度の利用にかかる経験談、よかった点
- 奨学金制度を利用することで、研究費や生活費の工面に役立てました。関西大学大学院の給付型奨学金は返済不要の制度のため、将来の返済を気兼ねすることなく研究に勤しむことが可能な有意義な制度であると考えています。もし、関西大学の学部から本大学院に進学する予定がある学生の方がいましたら、関西大学大学院入学前予約採用型給付奨学金制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
- 母が私の子育てをしながら大学院で研究していたこともあり、幼少期から自然と大学院への進学を意識しており、大学院は私にとって憧れの場所でもありました。そのなかでガバナンス研究科を選択した理由は、小西先生がガバナンス研究科の指導教員であると同時に、私のテーマが日韓関係であったことがあげられます。アジアを専門とする先生が多数在籍しており、アジアという同じバックグラウンドを持つ日本、韓国を他アジア諸国と比較、分析することで、日韓関係を複眼的な視点で研究できると考えたからです。
- ー 普段、どのような研究活動(手法)を行われているか、またその「おもしろさ」「難しさ」について
-
研究の特徴として、文献調査に加えて「エリートインタビュー」を行ったことがあげられます。日韓議員連盟という非公式アクターを研究しているため、資料の収集などが思うようにいかない時もありました。文献のみに依拠するわけにはいかず、日韓議員連盟の元役員/元閣僚であった国会議員へのエリートインタビューを行い、その場でしか聞くことができない証言や事実などを得ることができました。
また、常に仮説を転がし、それをどのように論証すべきか意識をし続け、論文の枠組みを組み立てていました。
人間健康研究科

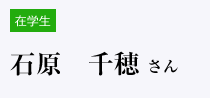
-
人間健康研究科 人間健康専攻
博士課程前期課程 2021年4月入学
(入試種別:学内進学試験)
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 研究テーマと概要
-
『テニス選手におけるイップスの発症率と完全主義との関連について』
- 概要:
- イップスとは「スポーツ中の熟練した運動行動において細かいコントロールを行う過程で起こる不随意運動からなる長期的運動障がい」と定義されており、野球やゴルフ、テニスといったさまざまなスポーツにおいて症状が確認されています。しかし、テニスにおけるイップスについての研究は少なく原因や対処法についても明らかではありません。そこで本研究では調査①として、テニス経験 5 年以上の 262 名を対象にした質問紙調査そして調査②として、テニス経験5年以上かつイップスを経験したことのある2名を対象としたインタビュー調査を実施し、テニス選手におけるイップスの実情、完全主義との関連を明らかにすることを目的としました。
- ー 時間割
-
博士課程前期課程 2年次 秋学期
1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 月 健康トレーニング
研究人間健康
演習(1)B健康マネジメント
研究火 地域連携
課題実習1水 身体運動学研究 健康心理学研究 木 スポーツ
教育学研究金 健康調査
研究法2土
- ー 出願に先立って志望の指導教員へどのような相談をしたか、相談してよかった点
- 学部時代からゼミでお世話になっていて、出願に先立ちたくさん相談させていただきました。大学院での研究テーマや研究スケジュール、修了後についてもいろいろとアドバイスをいただきました。相談を重ねることで、自分のやりたいことが見えてきて最終的に大学院への進学を決心することができました。
- ー TA・RA制度の利用にかかる経験談、よかった点
- 私はこれまでに、4年次の時にオンラインでの「スタディスキルゼミ(PC)」、「スポーツ統計学」、そして大学院に進学後、対面での「スタディスキルゼミ(PC)」、「トレーニング実習Ⅰ、Ⅱ」の授業においてTAを経験しました。TAとして授業に参加し、1年次や2年次の学生との交流でコミュニケーションをとることの大切さや、広い視野を持つこと、またどのようにすればわかりやすく伝えることができるかなどたくさんのことを学ぶことができました。
- ー 奨学支援制度の利用にかかる経験談、よかった点
- 私は関西大学大学院給付奨学金を受給しました。奨学金をいただけたことで自分自身の研究やその他の資格の勉強などに余裕を持って取り組むことができました。奨学金にはさまざまな種類があります。自分の条件にあったものに申し込むため、事前に各奨学金概要の把握や申請準備が必要になると思います。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
- 大学院進学の大きなきっかけは卒業時のコロナが流行し始めた環境です。当時、卒業後に留学を考えていたため就職は考えておらず、その中でコロナウイルスが流行り海外への渡航が厳しい状況となりました。そこで指導教官の先生に相談し、大学院でスポーツや自分のしたい研究について理解を深め、コロナウイルスが落ち着いてから留学に行くことを決めました。
- ー 大学院進学のための受験対策や事前準備
- 私は学内進学試験を受験し、筆記試験は英語のみだったので、ひたすら英語の長文読解問題を繰り返し解き、過去の問題にも本番の試験と同じ状況で取り組みました。長文読解は読むスピードが早ければ早いほど設問の回答にも余裕を持つことができるので、英語の長い文章に目や頭を慣らしておくことは大事だと感じました。また、英語の辞書を使うことがあまりなかったので長文読解の練習をしながら、わからない単語があればすぐに辞書で調べるようにしていました。

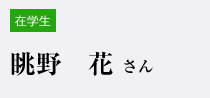
-
人間健康研究科 人間健康専攻
博士課程後期課程 2022年4月入学
(入試種別:一般入学試験)
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 研究テーマと概要
-
『視覚障害者に対するダンス・表現運動の指導のために』
- 概要:
-
視覚に障害がある児童は視覚的模倣(目で見て真似ること)が困難なため、運動指導には特別な工夫を要しますが、現在の学習指導要領には視覚障害児に向けた具体的な指導方法・教材は示されていません。体育の必修種目の中でも、ダンスや表現運動は視覚障害児にとって特にイメージが湧きにくく、難しいと感じられる種目です。
そこで、本研究では、視覚障害児の運動の機会を保障し、運動機能を向上させることを目的としています。視覚障害児が通う学校で行われている運動指導の実態を調査・把握し、視覚障害児の特性を生かしたダンス・表現運動の教材を実践と検証を重ねながら開発していきます。
- ー 時間割
-
博士課程後期課程 2年次 秋学期
1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 月 人間健康特殊演習
Ⅳ(社会福祉政策)火 水 木 金 土
- ー TA・RA制度の利用にかかる経験談、よかった点
-
私はこれまで、人間健康学部の「ダンス」や「身体表現Ⅰ、Ⅱ」などの実技科目、「起業に学ぶ『考動力』入門」という千里山キャンパスからの配信の授業のTAを経験しました。TAは授業の受講生にとって、“指導者より少し身近で、友人より少し頼りになる”ような存在であると考えています。授業中は広い視野を持って、授業についてきていなかったり、1人で悩んでいたり学生にいち早く気づき、声をかけています。また、学生について何か気になることがあった場合は、授業後に指導者へ報告するようにしています。
特に実技科目では受講生との交流も多く、受講生の変化を見ることができました。「ダンス」や「身体表現」は慣れていない学生にとっては恥ずかしくハードルが高く感じる場合がありますが、肯定的で安心できる場づくりが学生の表現を引き出すうえでとても大切であることを学びました。私も学生を指導する立場になったときは、まずは受講生一人ひとりに関心を持ち、安心して表現ができる場を創りたいと感じ、TAを経験したことで指導者としての具体的な目標を持つことができました。
- ー 奨学支援制度の利用にかかる経験談、よかった点
-
私は関西大学大学院特別給付奨学金を利用しています。この奨学金は返済不要の奨学金です。学費は自分で支払っていますが、生活と研究活動を両立するためにも、給付奨学金をいただけることはとても有難いです。
関西大学大学院特別給付奨学金にはいくつかの種類があり、学内進学試験で入学する場合は入学前に申し込みをするものもあるので、進学を考えている方は確認してみてください。
- ー 修了後の進路希望
-
現在私は大学や専門学校で「体育」や「身体表現」、「社会福祉」や「社会的養護」の授業の非常勤講師、関西大学ではTAやライティング・チューターとして学生の指導に関わっています。また、「ダンス・ミーツ・ラボラトリー」という団体を立ち上げ、講師として福祉施設でダンスの指導したり、教員向けにダンス教材を開発・配信したりしています。
この経験を活かし、将来は大学で学生に教示しながらも、地域の障害児・者や高齢者と身体表現する場を持ち、参加者の心身の健康や生きがいづくりに貢献する研究者をめざしています。
- ー 普段、どのような研究活動(手法)を行われているか、またその「おもしろさ」「難しさ」について
-
現在、視覚障害児・者の運動に関する研究は、歩く・走るなどの基本的な運動、ブラインドマラソンやサウンドテニスのような“盲スポーツ”についての研究はありますが、ダンスや身体表現を扱うものは非常に少なく、また、知的障害児・者や聴覚障害児・者を対象としたダンスや身体表現の活動事例はあっても、視覚障害児・者に向けたものはほとんど見られません。そのため、現在私が研究している「視覚障害児のダンス・身体表現」は非常に先行研究が少ないテーマです。
自身の研究テーマに少しでも関連する研究からヒントを探したり、資料から把握できないことは視覚障害当事者やその保護者、指導者や支援者にインタビューしたりすることで実態を把握しています。散在した情報を収集することは大変ではありますが、先駆的な研究ができていることがやりがいとなり、研究の面白さを感じています。
- ー 関西大学大学院人間健康研究科の魅力
- 人間健康研究科には、スポーツ科学や体育科教育学、社会福祉政策や文化人類学などさまざまな専門分野の先生方がいらっしゃいます。そのため、研究報告会などでは幅広い視点からアドバイスをいただくことができ、自身の研究の可能性を広げることができます。また、堺キャンパスには人間健康学部・研究科しかないため、先生方や事務室の職員の方々とも密にお話しできる機会が多く、とてもアットホームな雰囲気であることも一つの魅力です。

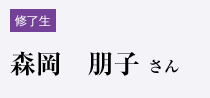
-
人間健康研究科 人間健康専攻
博士課程前期課程 2016年4月入学
(入試種別:社会人入学試験)- 勤務先名:
- (看護系)
看護系大学准教授 & 和ねっとDSD研究所
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 学位論文題名と概要
-
『認知症の人の地域支援体制構築に向けたプログラムの評価
‐認知症地域支援業務を推進する要因と認知症ライフサポート研修効果検証‐』- 概要:
- 認知症支援体制構築に向けた実践現場の取組みについて、プログラム評価の観点で検討することを試みました。認知症地域支援業務を推進する要因として、レジリエンス、燃え尽き、ネットワークに着目し、質問紙調査を行いました。また、国が勧める認知症ライフサポート研修の効果検証を行うため認知症支援意識尺度を開発し、研修事前・事後意識の変化を検証し、認知症ライフサポート研修は、認知症の人への支援体制を構築するためのプログラムとして有効であることを明らかにしました。
- ー 現在の仕事において大学院での研究や学修が生かされている場面や、学部卒業で就職をしている方との違いを実感する場面
-
現在、私は3つの肩書きで活動しています。主には看護系大学准教授(2022年4月~)、和ねっとDementia Social Design研究所(関西大学大学院時代に起業)、大阪市立大学大学院博士後期課程学生(2021年4月~)です。3つの肩書きで活動できている原点は関西大学大学院で培いました。
関西大学大学院時代は、自分が望む学びたいことを自由に勉強させていただきました。人間健康研究科では、ディスカッションを通じて、複合的な視点で「人間」「健幸」「福祉」を考える力を養うことができました。また商学部などの他学部の講義も受けさせていただき、企業の立場での考え方、視点なども学ばせていただきました。
これらの経験は、自分自身の視野を広げ、柔軟に物事を捉えることができるようになる土壌になったと思います。
自分が感じた素朴な疑問に対し根拠を持って論証し書き上げていくという関西大学大学院で経験したプロセスは、私にとって大きな財産となりました。今でも論文を書くときには、当時指導してくださった黒田研二先生の声が頭の中で聞こえてきて私を導いてくれています。
- ー 出願に先立って志望の指導教員へどのような相談をしたか、相談してよかった点
-
関西大学大学院に入学するまで、私は大阪市社会福祉協議会で長年勤めていました。黒田研二先生とは仕事を通じて共同研究をさせていただくことがあり、「知」のシャワーをたくさん浴びてスキルアップした自分を実感していました。
私の母親がアルツハイマー型認知症と上顎洞癌を患い、在宅で看取る経験をしたことをきっかけに、人生でやり残したことがないように、大学院で学び直しをして後進の育成に残りの人生を費やしたいと決心をしました。
黒田研二先生に連絡し、私の決心と研究のテーマについて相談をしました。何度かメールでやりとりをさせていただき研究計画書を書きました。もし事前に黒田先生から指導を受けていなかったら、私は自分が気付かないまま突き進んでいたかと思うと相談して本当に良かったと思います。
- ー 奨学支援制度の利用にかかる経験談、よかった点
- 関西大学大学院の入試説明会で給付型奨学金があることを知りました。学業に専念するために仕事を辞めたところだったので、制度を利用するために黒田研二先生に相談して推薦書(正式名称を忘れてしまいました)を書いていただきました。その結果、給付型奨学金を受給できるようになり、学問の道は何歳になってもどんな状況でも開かれているのだと実感しました。給付金を受給するには必ず年に何回か報告しないといけません。私は年度の終わりの報告期日を逃してしまうという失態をしました。せっかくの奨学金を自らのミスで受給できなくなり、自分への戒めのために2年目は敢えて申請せずに、卒業後に自立して収入が得られるように、さらに努力を重ねて自己研鑽することを選びました。
- ー お仕事との両立の工夫等について
-
学業に専念するために長年勤めた会社を思い切って退職しましたが、社会人として大学に入学してからも、研修講師として全国を飛び回って活動していました。和ねっとDementia Social Design研究所は、関西大学大学院に入学して2年目に立ち上げました。きっかけは、それまでは肩書きを聞かれて「女子大生」と喜んで話していたのですが、研修先から「女子大生では決済するときに困る」と聞いたことをきっかけに、和ねっとDSD研究を立ち上げ、所長の肩書きで活動しました。
大学院の授業を優先するために、仕事をする曜日や時間帯をかなり調整しました。また、新幹線や飛行機の移動時間を利用して勉強をしていました。宿泊先ではパソコンやテキストを参照し、レポートを書いたり研究の案を考えたりしていました。
- ー 出身学部と所属研究科の専門分野が異なっている際に、特にどのような点に注意して受験準備を進めたか
- これまでに看護学と社会福祉学の学位を得ていましたので、出身学部と所属研究分野は異なりますが、受験勉強そのもので困るという感覚はありませんでした。ただ、過去問題から出題されている傾向と、最新の統計データを分析して勉強するようにしていました。問に対して明確に答えられるように自分の考えを文章化し、論理的思考となっているかどうかチェックするなど、自分なりに考えたトレーニングをして受験に備えていました。
- ー 指導教員名とその教員を選んだ理由や教員とのエピソード等
-
- 指導教員名:
- 黒田 研二先生
指導教員は黒田研二先生です。
黒田先生は精神科医でありながら公衆衛生、社会福祉、行政や制度に精通しておられ、その知識と経験の豊富さ、多角的な視点に触れると、学問の奥深さとともに楽しさを学ぶことができました。黒田先生とは大学院入学前の在職中に共同研究者のメンバーと一緒に韓国に渡り、韓国の研究者と交流し施設訪問したことがあります。大学院入学後も韓国で行われた国際ソーシャルワーク学会に他の院生とご一緒させていただきました。私にとっては人生の分岐点となったような貴重な経験でした。黒田先生は海外からみた日本を感じとることを考えさせてくださり、視野を広げる大切さを教えてくれました。

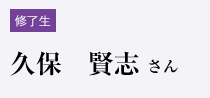
-
人間健康研究科 人間健康専攻
博士課程後期課程 2017年4月入学
(入試種別:社会人入学試験)- 勤務先名:
- 日本大学 スポーツ科学部
競技スポーツ学科
准教授
※掲載内容は、原稿作成時のものです。
- ー 学位論文題名と概要
-
『高校スポーツにおける教育とビジネスの葛藤
―組織と指導者に着目して―
Conflict between Education and Business in High School Sports
― Focusing on organization and the leader —』- 概要:
-
本研究は、従来の日本の高校スポーツの文化・組織的側面から、教育とビジネスがなぜ葛藤状況になるのか分析し、高校スポーツの課題解決に向けて、新たな視座を提供することを目的としました。
その結果、高体連組織がビジネスを積極的に取り入れようとすれば、教育がビジネスの介入を和らげる役割を果たし、対立を回避しようとする働きが生じることが分かりました。
これらの葛藤を解決する方法として、組織の二重構造の解消や教育目的を相互理解したパートナーシップ契約の提案などを行いました。
- ー 現在の仕事において大学院での研究や学修が生かされている場面や、学部卒業で就職をしている方との違いを実感する場面
-
大学院で学修中はスポーツのイベントマネジメントに携わる実務家でしたが、博士号を取得した翌年に大学教員へと転身しました。
大学院では、リサーチクエスチョンの立て方や分析枠組みの考え方、理にかなったエビデンスの提示方法など研究の基礎を徹底的に叩き込んでいただいたことが今に活きています。
- ー 出願に先立って志望の指導教員へどのような相談をしたか、相談してよかった点
-
博士課程前期課程を修了後、博士課程後期課程進学へ強い想いを抱いていましたが関西圏内で自身の研究とマッチする大学院(指導教員)が見つからず諦めかけていました。
そんな折、社会人にも博士課程後期課程の門戸を開いた本学の人間健康研究科を知りました。いてもたってもいられず、研究計画と進学への想いを当時の指導教官であった杉本厚夫先生(現在はご退官)にお伝えしました。
杉本先生からはすぐにメールでお返事をいただきました。返信本文に「この研究計画なら大丈夫です」との文字を見た時は、まだ何も決まっていないにも関わらずガッツポーズしたことを覚えています。その後、実際にお会いし、お人柄に触れ、この先生の下で学びたい!と、さらに意欲が高まりました。
- ー お仕事との両立の工夫等について
-
仕事と大学院の両立は想像を絶するチャレンジでした。特に博士論文提出前は日中仕事、帰宅後や休日は論文執筆と3ヶ月ほどまともに寝た記憶がありません。
工夫というより、疲れなどで体調を崩すと結果的に時間をロスしてしまいますので、追い込み期間以外は睡眠時間を十分に取り毎日3食を欠かさないなど、当たり前の健康管理方法を徹底していました。そして、極力、その日に出来ることをコツコツと進めるよう心がけました。それでも最終学年はやることが山積みでした。
- ー 大学院進学の理由および本学を選んだ理由
-
前職は新聞社で全国高校駅伝や選抜高校野球、黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会、びわ湖毎日マラソン、甲子園ボウル(アメリカンフットボール大学選手権決勝)などのスポーツイベントのマネジメントに関する仕事に就いていました。
特に高校スポーツとの関わりが深かったことから、各種競技がメディアやスポンサーなどと共にコンテンツ作りに取り組み、ある面ビジネス化の様相を呈していることを肌で感じていました。一方で、現状の日本の高校スポーツ組織や文化では、学生スポーツがプロスポーツに近いビジネスとなっている米国のように、高度な発展をとげることが出来ないのではないかといった疑問も持っていました。
このような現場での課題を学術的に解明したいと考えたことが進学を決めた理由の一つでした。
そして、この課題を解決に導く研究環境が関西大学大学院にはあると感じました。なかでも杉本厚夫先生や西山哲郎先生、森仁志先生といったスポーツ社会学、文化社会学、教育学、文化人類学などに精通されている専門家の存在は大きかったです。
- ー 普段、どのような研究活動(手法)を行われているか、またその「おもしろさ」「難しさ」について
-
私の専門はスポーツ産業学(社会学や経営学も含む)になります。入学当時は、定量調査を主とした研究をしていました。
しかし、ご指導いただいた先生方から定性調査で研究課題にアプローチする方法を学びました。特に専門家へのインタビュー調査は新鮮で自身の研究課題の分析にフィットしていると感じました。このような手法を学べたことで、現在はスポーツ産業の組織に関する諸課題を質的研究方法で解明することを主軸としています。
- ー 現在の就職先・職業を選んだ理由
-
スポーツの専門家として生きていきたいと考えたからです。
専門家とは国語辞典で「特定の分野を専門に研究・担当し、それに精通している人。エキスパート」を意味します。前職のキャリアでも専門家と呼ばれたかもしれませんが、あくまで仕事の一環でスポーツマネジメントに携わっていただけでした。やはりそれでは専門家としては成り立たないと思い、大学院で学修して本当の意味での専門家(大学教員)になろうとしたことがきっかけです。
もちろんアカデミックポストの獲得は非常に難しく、狭き門だということも理解していました。しかし、自身の特徴(キャリアやバックグラウンド)を生かしたうえで研究者としての質を高めれば必ずたどり着くことが出来ると信じていました。
