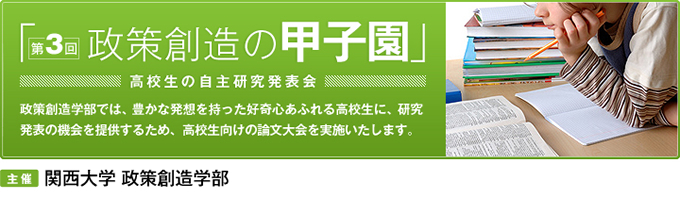
最優秀賞 1名
最優秀賞石川 桃子 (北海道登別明日中等教育学校 2年)
私は将来結婚をして子供を産みたいかと聞かれたら悩んでしまう。日本は現在急速に少子高齢化が進んでいる。自分も少しは国に貢献するために子供を産みたいという気持ちもある。しかし生涯働き続けたいと思うと子供を産んだ後、安心して働けるほどの環境が今の日本にあるだろうか。
現在日本では、働きたいのに安心して働ける環境が整っていなく働けない女性や、子供を産みたいのに仕事やその他の理由のために子供を産めないという女性が多い。なぜだろうか。一つ目の原因に待機児童があげられる。待機児童とは保育所入所申請を出しているにもかかわらず、希望する保育所が満員である等の理由で保育所に入所できない状態の児童のことで都心を中心に存在している。平成22年の厚生労働省の調査では待機児童数は48,356となっていて年々増加していっている。子供を預けることができなければ安心して働けるはずもない。また二つ目の原因として、出産した後職場に戻りやすい環境がないということがあげられる。女性が出産後職場復帰するためには家族や職場の助けが必要不可欠だ。家族、特に夫が家事や育児に非協力的だと女性は働くことができないし、仮に復職しても職場でも家でも働かなければならなくては休まる場もないだろう。また職場の助けがなければ女性はブランク等で復職しにくくなってしまうし、復職した後も大きなストレスを抱えてしまう。また三つ目の原因としては経済的不安があげられる。子供一人が完全に自立するまで育てるには5,000万円かかると言われている。不景気が続いていて、目の前の未来さえも見えない現状で無責任に子供を生むことはできないという訳である。
では、これらを解決するためにはどうすれば良いだろうか。一つ目の待機児童の問題を解決するためには保育サービスを充実させることだ。待機児童の問題は保育所の数や収容人数が足りないために起こっている。まずは保育所の数を増やす。また、長時間の保育や夜間保育もできるよう保育サービスを充実させるべきだと思う。長時間の保育や夜間保育ができれば女性は安心して働くことができるし、夜勤もできるようになり復職しやすくなるだろう。二つ目の子供を育てやすい環境にないという問題を解決するにはまず家族の協力が必要だ。家事や育児は女性だけが負担するものではない。夫婦間で助けあうことが大切だ。互いにワークライフバランスがとれるように協力していかなければならないだろう。また職場のサポートも重要だ。日本のある会社では育児中は一度パートに転換するという制度がある。育児中はパートとして働き、子供に手がかからなくなったら正社員に戻る権利があるという制度だ。この制度ではあまり長い期間ブランクがあかない。また、正社員になってしまうと勤務の途中で会社を抜けにくくなってしまうがパートだとその心配はない。そして子供が大きくなるまで共に充分な時間を過ごすことができる。また福祉大国と言われているスウェーデンで行われている「育児休業制度」では出産予定日の2ヶ月前から8歳になるまで合計480日間の休業が認められている。この休業は男女ともにとることができる。育児休業中の給与保障は約80パーセントで日本よりも高い。この制度ならば女性も男性も休みを気兼ねなくとることができ、育児しやすくなるだろう。三つ目の経済的な不安を解決するためには国のサポートが必要であると思う。日本の育児への手当てには所得制限などの条件がある。しかし子供を育てる大変さに所得の多寡は関係あるだろうか。スウェーデンでは手当ての支給に条件はなく、どんな条件に生まれたとしても子供が最低限の生活が送れるように保障されている。子育てに経済的な問題はつき物だ。しかし、多くは自分たちで解決することができないことでもある。経済的な問題で出産を断念する人も多い。このような人たちを助けるためにも国全体でサポートしていかなければならないと思う。
日本での少子高齢化は大きな問題だ。このまま進んでいったら日本は破滅へ向かっていくだろう。年金制度等も崩壊してしまうかもしれない。これらを防ぐためには女性が子供を生みやすい、生みたいと思える環境を作らないとならない。そのためには家族や職場、地域、国で協力しなくてはならないだろう。子供を生んだ人たちだけで子供を育てるのではなく次世代の日本を背負う子供たちは国全体で協力して育てるべきだ。職場では復職しやすい環境を整える必要がある。また、地域では子育て中の家庭の苦労を少しでも軽減できるようサポートしていく必要がある。国は経済的な不安を軽減できるように、手当てを支給したり安心して子育てできるように保育サービスを充実させていかなければいけない。そして国民一人一人が子供は個人で育てるのではなく国が育てると考えることが最も重要だと思う。
優秀賞 2名
優秀賞重松 優輝 (百合学院高等学校 2年)
現在日本が抱える大きな社会問題の一つに少子高齢化が挙げられる。その内容は読んで字のごとく高齢者人口が増加し、年少人口が減少しているという人口のバランスが上手くとれなくなっている状態だ。そこから派生して年金、介護、医療と様々な分野に影響を与えている。私はこの高齢化社会と高齢者のこれからの在り方に着目して今の日本社会がそして未来の日本がより良く発展していくためにはどうすればいいのか考えていきたいと思う。
日本の高齢者人口の割合は約23パーセント。つまり約4人に1人が65歳以上の高齢者だということになる。その中で私が注目したいのは介護を必要とせず、自分の力で衣食住を成立させており、心身共に健康である「元気高齢者」である。高齢者と言うと、腰は曲がり杖をつき、白髪でといった「おじいちゃん」「おばあちゃん」と呼ぶにふさわしいイメージを持つ人が多いだろう。
だが日常生活の中で考えてみるとどうだろうか。近所に住む話好きな60代後半のおばちゃんも商店街の八百屋の70代のおじさんも学校の校長先生も年齢だけを聞けばみんな高齢者だ。でもその一人一人はとても元気でピンピンしている。そういう「元気高齢者」が元気なままで自分でできることや今の身体能力、生活能力をできるだけキープしていくこと、それが現代社会における介護の大原則である。私もこの原則に沿って考えてみたい。まず高齢者の今ある能力を維持していくためには、日常生活の中で頭と身体を使うことが必要である。そのために少し若者より時間はかかるとしても、家事や買い物など自分の生活に関わることを自力で行うのが最もポピュラーな訓練だが、そんなことは普通になんなくできてしまうという高齢者も医療の進歩や生活用品の発達により増えてきている。もう高齢者の行動範囲は家の中や周辺地域だけにとどまらない。第二の人生を歩むためのフィールドを社会全体として考え、用意していかなくてはならないと思う。例えばリカレント教育や定年時期の引き上げ、就労年齢を上限していない企業の登場などが現在行われている。しかし私はそれだけではまだ不十分だと感じている。高齢者が老人大学で学んでも卒業後の「進路」があまり用意されていないし、企業に関しても高齢者の雇用は極めて少ない。つまり急激な高齢化に社会が追いついていないのだ。そこで私がこれからの高齢化社会に向けて提案したいのはまず、人手不足が問題となっている保育や介護の現場で高齢者に労働の機会を与えることである。最近「育ジイ」や「育バア」という造語も注目を集めているが、子育ての第一線から退いた彼らには育児に関して豊富な知識と経験がある。それらを活かした高齢者の社会復帰は十分可能だと思う。勿論実際に保育所などで子どもに直接触れるのだから必要があれば保育士の資格を取得してもらうが、資格取得の高齢者のための講座を開講し、使用するテキストの字は通常のものよりも大きくはっきりとした色で表すなど工夫をする。そして保育所とデイケアやデイサービスの施設を合体させ、レクリエーション活動など子どもたちと利用者が触れ合い、互いに刺激し合える場をつくる。そうすることで、高齢者には子どもの世話をするという役割ができ、第二の人生が活気に溢れたものとなる。また核家族化が進む現代に生きる子どもたちにとっては、高齢者との関わりによって、思いやりや他者を敬う心を学び、コミュニケーションの向上が期待される。この子どもたち×高齢者プロジェクトは双方に大きなメリットがあり、これまでを支えてきた世代からこれからを担っていく世代への生きるバトンとなるのだ。
私がこのことについて考えるきっかけとなったのは、自分のひいおばあちゃんがつぶやいた「私も何か役に立ちたい。」そんな一言だった。長年家族を支え、家庭を守ってきた人、何十年もの間働き続け自分の身を削ってきた人、高齢者と呼ばれる人々はそういう人たちだ。今までずっと大きな責任を持ち、多くの役割を果たし、日本をここまで育ててくれた人たちだ。そんな人たちから定年や子どもたちの自立によって急にその役目を奪ってしまっては、体や頭、心が一気に衰えてしまうのは想像に難くない。若い人たちでも目的や役割を持たずに生きることはとても辛い。人が生きていくためには誰かに必要とされていることが不可欠なのだ。ただ食べて、寝て、排泄して、息をしているだけ、それでは生きているとは言えないと私は考えている。生きるということには「活きる」も含まれているのだ。誰かと支え合って、社会とつながって、活き活きと生きる。それこそがこれからの社会が理想としていくべき未来ではないだろうか。
全ての人に役割を与え、できる人ができる時にできることをする。高齢者も一人の社会の担い手であり、彼らにしかできない役割がこの国のすき間にはたくさんある。受け身ではなく能動的に高齢者が生きている世界、その一歩として彼らに育児と教育のリーダーになってもらいたい。
優秀賞山上 ひかる (済美平成中等教育学校 1年)
<第I章>
私は、中学1年生までガールスカウトをしていた。その活動の一環として、毎年アフリカのマリ共和国に、自分達で作った支援米とピースパックという筆記用具セットを送るボランティア事業があり、そのとき、世界の飢餓や、アフリカ・アジアでの内戦や欧米による支配について調べる機会があった。また、父から東南アジアに位置するカンボジアという国で1970~80年代にかけて大規模な虐殺があったことを教えてもらった。
虐殺や戦争には多大な犠牲が伴う。家屋が壊れ、政治は乱れ、そして何よりも多くの人命が失われる。そのような悲惨なことはなぜ起こるのか。そして、その後の復興はどうやって行なっていけばいいのか。それらを、カンボジアでの虐殺を例にあげて考え、今後私達が実現しなければならない世界平和のために、何を学び、それをどう生かせばいいのかを明らかにしたい。
<第II章>
まず考えなければならないのは、なぜ戦闘が起きるのかということだ。
カンボジアでの虐殺を行なった中心人物はポル・ポト(本名サロト・サル)である。この虐殺が起きた理由は諸説あるが、私は中でもポル・ポト派にみられるアンチカルチャーに原因があるのではないかと思う。
アンチカルチャーとは、伝統文化に対する反文化のことだ。アンチカルチャー自体は必ずしも悪いものではない。これによって文化や国が進展することもある。しかし、カンボジアの場合、ポル・ポト派はこれに固執し過ぎた。結果、ポル・ポト派の中には反文化があり、民衆の中には伝統文化がある状態になり、自分達の考えに従わない人々を肉体的に抹殺しようとしたのだ。
1、教育の充実
それでは、このような戦闘を起こさないためには、どうすればいいのだろうか。私は、一番重要なのは教育だと思う。ポル・ポト時代、カンボジアでは多くの知識人が殺された。反目を恐れたからだ。そして、それはそのまま、知識の深さがポル・ポトの政策を妨げることになるということを証明している。また、アンチカルチャーというのは、限られた狭い自分の世界で生きていると起こりやすい。だから、広い視点を持つということが反文化への固執を防ぐ重要な意識ではないだろうか。そして、広い視点を持つには、やはり教育が必要だ。
しかしながら今、カンボジアを含め、教育が十分に施されていない国はたくさんあり、また、学校自体が少ないために、家の近くに学校がなく、勉強したくてもできない子がたくさんいる国もある。
それをどうすれば解決できるのか。まずやるべきことは、「教育者を教育する」ことだろう。先ほど述べたように、カンボジアでは虐殺の際、多くの知識人が殺されたので、子供をちゃんと教育できるほどの教養を持った人が少ない。それはカンボジアのように戦闘が起こった国のみならず、いわゆる発展途上国では知識人は少ない。だから、教育者の育成には、やはり外国の助けが要る。しかし、いつまでも外国に頼っていては、国が自立できないので、外国からの教育なしでも自国でちゃんと教育できるように、教育者をきちんと育てることが第一だと思う。ただし、それができない今、十分な数の教育者が育つまでは、やはりまわりの国が協力しなければならない。
2、国の制度
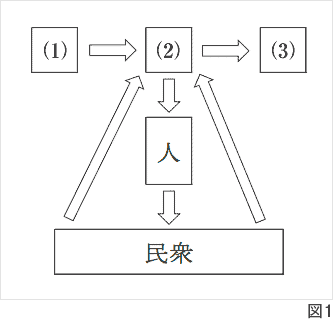 また、国の制度も改める必要があるだろう。そもそもなぜ虐殺を止められなかったのか。ポル・ポト派の人間の中には、一人もこの虐殺を異常だと思う人はいなかったのだろうか。私はそうは思わない。その行動をおかしいと思っていた人が絶対にいたはずだ。しかし、その人たちは異常行為をやめさせるための行動をおこすことはできなかった。その理由は、幹部に反対すれば自分も殺されかねないと考えたからだと思う。集団的な恐怖感に襲われるわけだ。では、どうすれば下の立場の者も上の立場の人に意見を出せるだろうか。私は、そのための制度を考えてみた。
まず、(2)に位置するような人・組織をつくる。これは、誰にも考えを左右されず、独立しており、公正・中立で理性ある判断ができる立場にあるべきで、民衆による選挙などで選ばれる。またこれは、慢心し、独裁が始まらないうちに、定期的に交代する。図中の「人」は基本的には、日本の総理大臣のように国の中心となって政治をするが、どんな場合も(2)の決定には従わなければならず、「人」の判断・行為が異常だと感じた場合は、民衆が(2)に意見できる。(図1)
また、国の制度も改める必要があるだろう。そもそもなぜ虐殺を止められなかったのか。ポル・ポト派の人間の中には、一人もこの虐殺を異常だと思う人はいなかったのだろうか。私はそうは思わない。その行動をおかしいと思っていた人が絶対にいたはずだ。しかし、その人たちは異常行為をやめさせるための行動をおこすことはできなかった。その理由は、幹部に反対すれば自分も殺されかねないと考えたからだと思う。集団的な恐怖感に襲われるわけだ。では、どうすれば下の立場の者も上の立場の人に意見を出せるだろうか。私は、そのための制度を考えてみた。
まず、(2)に位置するような人・組織をつくる。これは、誰にも考えを左右されず、独立しており、公正・中立で理性ある判断ができる立場にあるべきで、民衆による選挙などで選ばれる。またこれは、慢心し、独裁が始まらないうちに、定期的に交代する。図中の「人」は基本的には、日本の総理大臣のように国の中心となって政治をするが、どんな場合も(2)の決定には従わなければならず、「人」の判断・行為が異常だと感じた場合は、民衆が(2)に意見できる。(図1)
ところで、よくよく比べてみると、これは私たちの住む日本も採用している民主主義国家の制度である。日本はこの制度の下、第二次世界大戦以降、他国と戦火を交えることなく民主的で平和な国としてやってきている。だから民主主義国家の制度を採用すれば独裁者が生まれ以前の悲劇が起こることもないのではなかろうか。
<第III章>
1、日本のことについて
いままでカンボジアについて考えてきたが、こうした問題は私たちの住む日本とも、実は無関係ではない。選挙の投票率が低くなっているのもその一つだ。投票率が下がっているということは、それだけ政治に無関心になっているということだ。しかしこれから日本の将来を作り上げていく私たちが、国のことに関心を持たずに知らん顔していては、日本は今以上に発展することなくどんどん衰退していくだろう。あるいは、ポル・ポトのような危険分子が入りこむ余地を与えてしまう可能性もある。私も含め現代の若者たちは、もっと政府や政治などに関して積極的になるべきなのだ。
また、教育についても同様のことが言える。今日本では、国民は教育を受けられるのが当たり前になっているため、教育を受けられるありがたさを感じられなくなって、学生たち自身が教育をないがしろにしてしまっているのだ。しかし、先程も述べたように教育は平和な国づくりの第一歩だ。だから、せっかく恵まれた環境の中で生きているのなら、そうでない人々のことも考えて、学生である我々はまず勉強に励まなければならないと思う。
2、私たちにできること
貧しい国に生まれ、そのために苦しい生活を強いられている人々のために私たちができることを二つ考えてみた。一つ目は、支援だ。例えば、ピースパックというものがある。鉛筆やノートなどを少しずつ一つの袋に入れた、筆記用具セットのことだ。これを貧しい国に送ったり、直接お金を送ることなら、私たちのような子供にもできるのではないだろうか。
また、今、私がしていることもそうだ。この論文を書くことによって貧しい国や発展途上国の現在の事情を少しでも知ってもらおうとしている。これも、世界を平和にするための活動の一つだ。支援をしようとしても、どこの国が、今どんな状況なのかを知らなければどうにもできないので、少しでも現状を知っている人は、それを教えることも一つの支援だと思う。
この世界の全ての国々が、永遠に中立を保ち、この世から戦争がなくなることはないと思う。しかし、少しでも戦争のない平和な国が増え、一人でも「今自分は幸せだ」と思っている人が増えるように、一人一人が行動をおこすことは、地球に住む私たちの義務ではないだろうか。
この論文を書いて、自分はなんと恵まれている環境の中で生きてこられたのかと私は身にしみて感じた。だから、これからもっと世界の様々な国のことに興味を持ち、同じ地球という星に住む仲間の一人としての義務を果たしていきたいと思う。
