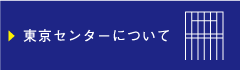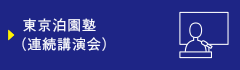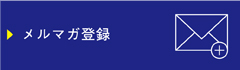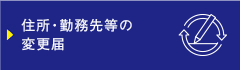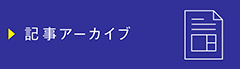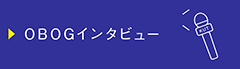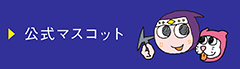公開講座・セミナー
公開講座・セミナー
関西大学では、広く地域社会に生涯学習の機会を
提供することを目的として、様々な公開講座を開設しています。
東京センターで実施の講座は次のとおりです。皆さまのご参加を心よりお待ちしています。
現在受付中の講座
現在受付中の講座はありません。
過去の公開講座
主催:関西大学・南海電気鉄道株式会社・総本山金剛峯寺 平成28年9月3日(土) 13:00~16:00 |
|
|---|---|
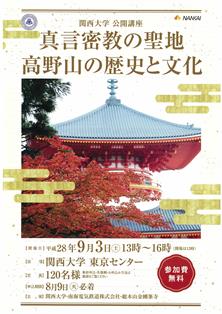 真言密教の聖地 高野山の歴史と文化
◆登壇者プロフィール◆ ◯長谷 洋一 (はせ よういち) 関西大学文学部教授。昭和35年生まれ。博士(文学)。昭和60年関西大学文学部哲学科(美学美術史専修)を卒業。堺市教育委員会社会教育課、堺市博物館文芸課などを経て平成16年関西大学文学部助教授に着任。平成18年より現職。著書に『日本仏像史』(共著)美術出版社 など。 ◯添田 隆昭 (そえだ りゅうしょう) 金剛峯寺下・蓮華定院住職。昭和22年生まれ。権大僧正。昭和47年京都大学卒業後、昭和50年高野山大学大学院博士課程修了。総本山金剛峯寺企画室課長、高野山専修学院能化、高野山勧学財団理事などを歴任し、平成25年総本山金剛峯寺宗務総長に就任、現在に至る。著書に「大師はいまだおわしますか」高野山出版社。 |
|
| 講座チラシ (詳細はこちら) |
|
河出書房新社・中央公論新社創業130周年 平成28年10月21日(金) 18:40~21:00 |
|
|---|---|
 「出版から考える戦後日本」
◆登壇者プロフィール◆ ![120[色修正]大澤写真.jpg](https://www.kansai-u.ac.jp/tokyo/120%5B%E8%89%B2%E4%BF%AE%E6%AD%A3%5D%E5%A4%A7%E6%BE%A4%E5%86%99%E7%9C%9F.jpg)
◯大澤 聡 (おおさわ さとし) 1978年生まれ。批評家/メディア研究者。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。日本学術振興会特別研究員を経て、現在、近畿大学文芸学部准教授。博士(学術)。各種媒体にジャーナリズムや文芸に関する論考を発表。著書に『批評メディア論 戦前期日本の論壇と文壇』(岩波書店)、『1980年代』(共著、河出書房新社)など。最近では『文学』5・6月号(岩波書店)の特集「文壇のアルケオロジー」の責任編集をつとめた。 ![[リサイズ]片山杜秀氏写真.jpg](https://www.kansai-u.ac.jp/tokyo/%5B%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%5D%E7%89%87%E5%B1%B1%E6%9D%9C%E7%A7%80%E6%B0%8F%E5%86%99%E7%9C%9F.jpg)
◯片山 杜秀 (かたやま もりひで) 1963年生まれ。評論家/思想史研究者。慶應義塾大学大学院法学研究科博士課程単位修得退学。文学、歴史、芸術など幅広い分野にわたる論文、エッセイやコラムを執筆。現在、慶應義塾大学法学部教授。著書に『近代日本の右翼思想』(講談社選書メチエ)、『音盤考現学』 『音盤博物誌』(アルテスパブリッシング、両書で吉田秀和賞とサントリー学芸賞受賞)、 『未完のファシズム』(新潮選書、司馬遼太郎賞受賞)など。 ![[リサイズ]竹内洋先生写真.jpg](https://www.kansai-u.ac.jp/tokyo/%5B%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%5D%E7%AB%B9%E5%86%85%E6%B4%8B%E5%85%88%E7%94%9F%E5%86%99%E7%9C%9F.jpg)
◯竹内 洋 (たけうち よう) 1942年生まれ。歴史社会学/教育社会学。京都大学大学院教育学研究科博士課程単位取得退学。教育学博士(京都大学)。京都大学大学院教育学研究科教授、関西大学文学部教授、同人間健康学部教授を歴任。現在、関西大学東京センター長、関西大学名誉教授・京都大学名誉教授。社会批評、エッセイ、書評を執筆。著書に『日本のメリトクラシー』(東京大学出版会、第39回日経・経済図書文化賞受賞)『革新幻想の戦後史』(中央公論新社、第13回読売・吉野作造賞受賞)『教養主義の没落』(中公新書)など。 |
|
| 講座チラシ (詳細はこちら) |
|
平成27年11月14日(土) 13時00分~15時30分 平成27年度 関西大学・堺市 連携公開講座 |
|
|---|---|
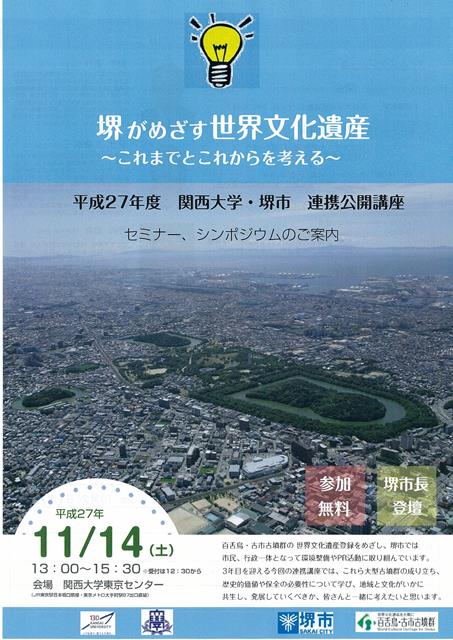 ----------------------------------------------------------
|
|
| 講座チラシ (詳細はこちら) |
|
全4回 特別連続セミナー(5/23,6/6,6/20,6/27) |
|
|---|---|
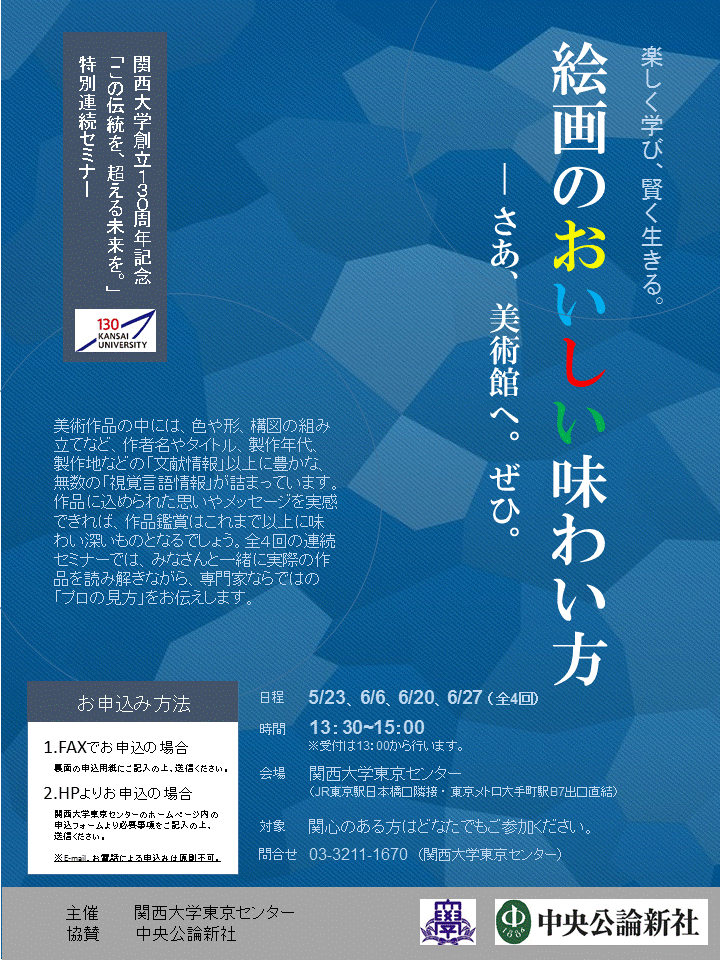
|
|
| 講座チラシ (詳細はこちら) |
|
平成27年2月10日(火) 18時30分~20時30分 ビジネスパーソン養成講座 |
|
|---|---|
 関西大学 商学部教授 陶山 計介
アベノミクスによる景気回復や賃上げ、円安、株価上昇も都市部の大企業がその恩恵を受けるだけで、GDPもマイナス成長と生活者や地方の中小企業にまで波及していません。他方、グローバル競争やICT革命の進展のなかで企業はますます厳しい経営課題やマーケティングに直面しています。そうしたなかで、現在好調と言われるトヨタ、ユニクロ、アマゾン、PBなど"勝ち組"に共通している要因は何か、今後の成長戦略を支えるブランド戦略の理論と現実に迫っていきます。 |
|
| 講座チラシ (詳細はこちら) |
|
平成27年1月24日(土) 13時30分~16時30分 道頓堀フォーラム in 東京 |
|
|---|---|
 ◆講演
|
|
| 講座チラシ (詳細はこちら) |
|
| 講座の様子 | |
平成26年11月15日(土) 関西大学×堺市 連携公開講座 |
|
|---|---|
 長谷 洋一関西大学 文学部 教授 【受付終了】 定員に達しましたので、受付を終了いたします。 5世紀は巨大古墳の時代とされます。それまで奈良に築かれた巨大な前方後円墳は河内・和泉に集中して築かれるようになります。また副葬品などの内容も大きく変化します。このことは当時の東アジア情勢と深く関係しています。巨大古墳の変遷をみながら、古代日本と東アジアの関係について考えたいと思います。 |
|
| 講座チラシ (詳細はこちら) |
|
| 講座の様子 | |
平成26年11月1日(土) 関西大学×堺市 連携公開講座 |
|
|---|---|
 白神 典之堺市文化観光局 博物館学芸課長 【受付終了】 定員に達しましたので、受付を終了いたします。 わが国最大の仁徳天皇陵古墳については、天皇陵であるがゆえに資料はほとんどないと思われがちでしょう。しかしながら、これまでに様々な機会に少しずつではありますが資料が蓄積されてきています。今回はそれらに加えて、古墳築造以後にも焦点を当てて様々な「わかっていること、考えられること」についてお話しします。 |
|
| 講座チラシ (詳細はこちら) |
|
| 講座の様子 | |
平成26年10月18日(土) 関西大学×堺市 連携公開講座 |
|
|---|---|
 徳田 誠志宮内庁書陵部陵墓課 首席研究官 【受付終了】 定員に達しましたので、受付を終了いたします。 百舌鳥・古市古墳群を世界文化遺産に登録しようという活動が正念場を迎えております。そこで大切なことは登録がゴールではなく、未来に向けてこの資産をどのように保護し、活用していくかということです。そのために関西大学と堺市が連携して何ができるのか、何をなすべきかということを、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。 |
|
| 講座チラシ (詳細はこちら) |
|
| 講座の様子 | |
平成26年1月25日(土) 特別講演会 『関西大学のエジプト調査10年の歩み』 |
|
|---|---|
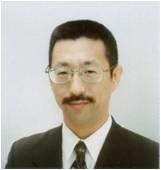 吹田 浩関西大学文学部教授、関西大学国際文化財・文化研究センター所長 関西大学は、2003年にサッカラで古代壁画の修復のための研究を始めました。日本・エジプト合同マスタバ・イドゥート調査ミッションとして、日本とエジプトが対等な関係で調査することをモットーにしています。エジプトの遺跡管理当局、カイロ大学考古学部、遺跡所在地のサッカラ村のいずれとも良好な関係にあり、これが、エジプト学、異文化研究、さらに化学分析、抗菌抗黴化学、建築土 木工学など文理融合型の多様な研究を行う基盤になっています。また、サッカラ村と遺跡とのかかわりをも研究対象にしており、国際的にもこれほど多様な研究を行っている調査隊はありません。 |
|
| 講座の様子 | |
平成25年11月16日(土) 関西大学×堺市 連携公開講座 第3回「茶会記からみた利休茶 -茶道具をもとに-」 |
|
|---|---|
 長谷 洋一関西大学 文学部教授 茶聖・千利休の茶は、堺の津田宗及が記した『天王寺屋会記』や今井宗久『今井宗久茶湯日記抜書』などの茶会記によって知ることができます。茶会記には参加者のほか使われた茶道具などがこまかく記録されています。茶会記にみる茶道具の移り変わりを追いながら利休が命を賭けて求めた「美」について考えてみたいと思います。 |
|
| 講座の様子 | |
平成25年11月9日(土) 関西大学×堺市 連携公開講座 第2回「堺の利休 -わび茶と黄金の日々-」 |
|
|---|---|
 吉田 豊堺市立博物館 学芸課長 堺で生まれ育った利休であるが、簡単な手紙類を除いて彼自身が語った資料はほとんどなく、堺のまちとの関係を示す資料も皆無に近い。イエズス会を代表する宣教師ザビエルが、日本の金銀の大部分が集まるところと言った堺のまちで、なぜ対照的ともいえるわび茶が大成されたのか。その謎に迫りたい。 |
|
| 講座の様子 | |
平成25年10月26日(土) 関西大学×堺市 連携公開講座 第1回「茶の湯 信長・秀吉と利休(与四郎・宗易)」 |
|
|---|---|
 鈴木 宗卓表千家 茶道家 名物道具を「名物狩り」と称して茶道具を悦しみ、部下たちに「茶の湯」の関心を高めさせた信長。「鑑賞の茶」から「茶の湯」そのものに入り込んだ秀吉。そして、天下人となった秀吉がお茶頭筆頭として重用した利休。「茶の湯」を政に利用し、これまでとは異なる空間に変化させた彼らは、現代に続く「茶の湯」の基を作ったのでした。本講では、映画『利休にたずねよ』の撮影現場の裏側や、使用した茶器の紹介も交えながら、分かりやすく解説します。 |
|
| 講座の様子 | |