学校インターンシップについて
学校インターンシップとは
通常、インターンシップというと、企業や行政における就業体験をイメージするかもしれません。関西大学ではその学校版-教職志望者にも学校現場を知る機会があるべきではないか-という考えのもと、2003年度より学校インターンシップを進めてきました。
当初は教職志望者のために始められた学校インターンシップですが、実際に現場で研修を積んだ学生は、自分よりも年少の子どもたちと接することで、「大人」としての自覚と責任を身につけて大学に戻ってきます。
大学生が学校現場を体験することは、教職志望者だけではなく全ての学生にとって「人間性を成長させる」大学教育なのではないかという発見のもと、学校インターンシップは教職志望者に限らず、そうでない学生にも幅広く門戸を開いて実施している就業体験プログラムです。
学校インターンシップ概要
目的
学生(大学院生)が学校・園の日常的な教育活動、課外活動などを幅広く実地体験させていただくことを通して、自己の適性を把握する機会を持ち、人間的成長や社会意識の向上を目指します。
研修生
本学学部生、本学大学院生(意欲と動機が明確で、誠実に取り組むことのできる者を選考します)
※原則として、学年・学部・教職志望の有無など特定の条件は設けておりません。
研修期間
本学では学校インターンシップを大学教育のなかに位置づけて単位認定をしています。このため具体的な研修日程は、派遣が決定した学生と受入学校・園の間で授業に支障のない範囲で設定することとなります。
単位認定を行うため、研修時間は36時間以上で設定いただく必要があります。
| 実施期間 | 8月上旬~12月中旬の間 |
|---|---|
| 短期連続型モデル | 8月上旬~9月中旬の間の6日間など |
| 長期型モデル | 9月下旬~12月中旬の間、毎週特定曜日1日など |
業務
受入学校・園で設定いただきます。
〈例〉授業補助、学校行事(運動会・文化祭)の補助、クラブ活動・図書室運営などの補助
費用
インターンシップ期間中の労働の対価は必要ありません。交通費は学生(大学院生)本人が負担いたします(一部大学の補助あり)。
守秘
インターンシップ期間中に知り得た機密事項の取り扱いは、学生(大学院生)から守秘義務に関する「誓約書」を提出させ、大学がとりまとめたうえで派遣先に郵送します。
事故補償
学生(大学院生)は学研災付帯賠償責任保険に加入しこれを適用します。
事前と事後の指導
学生(大学院生)にはマナーや学校現場での心構えに関しての講習や報告会など事前・事後の指導を課します。
学校インターンシップの取組実績
本学の学校インターンシップは、平成17年度 文部科学省「特色ある大学教育支援プログラム」に採択され、平成21年3月まで特色GPプログラムとし運営しました。
特色GPについて
「人間性とキャリア形成を促す学校Internship‐小中高大連携が支える実践型学外教育の大規模展開」が、平成17年度文部科学省「特色ある大学教育支援プログラム(特色GP)」に採択されました。特色GPシンポジウムについてはコチラへ
特色GPとは
文部科学省は、各大学・短期大学・高等専門学校等が実施する教育改革の取組の中から、優れた取組を選び、支援するとともに、その取組について広く社会に情報提供を行うことにより、他の大学等が選ばれた取組を参考にしながら、教育改革に取り組むことを促進し、大学教育改革をすすめています。この「優れた取組」を「Good Practice」と呼んでいます。これは、近年、国際機関の報告書などで「優れた取組」という意味で幅広く使われており、諸外国の大学教育改革でも注目されている言葉です。なお、この言葉を略して、「GP」と呼んでいます。
文部科学省では、その「GP」をキーワードとして、教育方法や教育課程(カリキュラムなど)の工夫改善の取組や、社会からのニーズの強い課題に対応した取組など、大学における学生教育の質の向上を目指す特色のある優れた取組を選び、これらのサポートのためのプログラムとして、「特色ある大学教育支援プログラム」と「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」を実施しています。これらを「GP」にちなんで、それぞれ、「特色GP」、「現代GP」と呼んでいます。 平成20年度からは、特色GPと現代GPを発展的に統合した「質の高い大学教育推進プログラム(教育GP)」を実施しています。
採択されたGPの概要
「人間性とキャリア形成を促す学校Internship‐小中高大連携が支える実践型学外教育の大規模展開」
学校インターンシップとは、大学生が高校、小・中学校等で就業体験を積み、キャリアデザインと人間形成に役立て、受入校にとっては若い力によって学校現場を活性化する取組です。本学では、①学校インターンシップを希望する学生を選考、面接し、受入校とマッチングし、事前の講習を課して学校現場に送り出す。②研修後には事後報告会を開いて、学生、受入校教員とともに取組の成果を検証する。③受入校教員の評価も参照しながら単位認定する。こうしたプロセスで取り組みを行っております。手厚いケアを保ちながら、毎年200人規模の学生を高校や小・中学校など、あらゆる学校現場に送り出している点が本学の特色であります。
学校インターンシップの意義
1.教職志望者のキャリア形成への寄与
〈学生の声〉「知識を現場で生かせたという自信を得た。自分にできることとできないことが自覚できた。今までは教師になりたいという気持ちが強いだけだったが、そのために何をすればよいかが見えてきた」
2.学生の人間的成長、創造的な思考にもとづく行動力の涵養
〈学生の声〉「障がいがあって話すことが難しい子どもでも、自分から働きかけると反応してくれる。子どもたちのように、素直に喜んだり楽しんだりすることを実感して生きていきたい」「指示を待っているだけではだめ。まわりを観察して、自分にできることを工夫して手がけてみた」
3.キャリアデザイン意識の向上 大人への旅
〈学生の声〉「教員になるか、企業に勤めるか、迷っていたが、学校インターンシップで教職志望に気持ちがかたまった」「高校生をみていると、この子達がここまでになるには色々な大人の力を借りてきたのだと思った」「昼休みに用意した『何でも相談室』では、先輩として彼らにとってプラスになるであろう話ができて、とてもうれしく感じた」
教育実習との違い
教育実習は、教科指導を主とします。しかし、教師の仕事は教科指導だけではありません。補習・勉強会、学校行事の運営、部活動指導、進路指導、生徒会活動指導、図書室業務、さまざまな問題を抱える生徒へのケアなど、多岐にわたります。学校インターンシップでは、教師のこうしたさまざまな仕事の補助をすることで、学校現場の実情を理解し、将来像を現実的に思い描くことができます。
企業・行政でのインターンシップとの違い
企業・行政でのインターンシップは、インターンシップ先に勤めている大人の指示にしたがい、社会人として適応する姿勢を培います。学校インターンシップでも、もちろん、受入校の教員の指導にしたがいますが、対象が年少者であり、しかも学校現場の特性から、学生がみずから状況を観察し、理解し、臨機応変な工夫をする必要があります。年少者を援助することで促される大人と しての責任の自覚と、状況に即した創造的な思考にもとづく行動力の向上が、学校インターンシップの効果です。
社会的ニーズ
本学学校インターンシップ事業は、2018年度で16年目を迎えました。過去15年間で2,600名を超える学生を学校現場に派遣しています。近年では年130名近くの本学学生を学校現場へ送りだしています。
なぜこれほどの社会的ニーズがあるのか。その理由には、学校現場の教員の高齢化、少人数指導の推進、ケアを要する生徒の増加といった一般的な理由が挙げられます。しかし、とくに本学の取組に対しては、受入校から、「全学的規模で運営されている」、「大学が選考・面接して信頼できる学生を送り出している」、「事前事後の講習が充実している」等といった面で高い評価をいただいております。
また、本取組を支えているのは、23自治体(2018年3月現在)の教育委員会と本学との間に結ばれた連携協力協定です。
本取組の趣旨をご理解いただき、積極的にご協力いただいている教育委員会・学校のご支援に感謝しております。
〈受入校の声〉「教職を目指している学生諸君に早くから現場を体験していただきたい」「学生の一生懸命な態度は教員にとってもよい刺激となった」「子どもにとって学校内で教師以外の者と接することは、子どもの社会性を伸ばすにも有意義である」
大学教育、小中高大連携・地域連携への問いかけ
当初は予想していなかったことですが、学校インターンシップは世代と世代とをつなぐ場でもあります。現在、少子化と地域コミュニティの崩壊から、若い世代同士がふれあう機会は減っています。学校制度は学年ごとに世代を断ち切り、それぞれの学校のなかに閉じ込めてしまう側面をもちます。学校インターンシップはそうしたジェネレーション・ギャップを解消する機能ももつのではないか。私たちはここに本取組がさらに発展する可能性をみております。
こうしてみると、学校インターンシップは学生の力を介した小中高大連携・ 地域連携なのだとわかります。大学生が高校や小・中学校等に行き、受入校の生徒の成長を助ける。それによって大学生自身も成長する。だからこそ、大学と高校、小・中学校は若い世代を育てる機関として連携する必要がある。ここに私たちは高大連携、小中高大連携の新たな意義を見出しました。高大連携というと、まだまだ入試、出張講義、公開講座等、大学へのアドミッションに関わる事業を連想しがちです。しかし、これに対して関西大学では、高大連携の目標を、次代の知的継承者の育成、在学生への教育効果、社会貢献・地域連携と捉え、社会全体が若い世代を育てるなかで、大学がその一翼を担うものと受け止めております。
本取組が採択された理由
この取組について、特色ある大学教育支援プログラム実施委員会からは、次のような評価をいただきました。
『この取組は、関西大学の「人間関係を大切にし、地域社会に役立つ、行動力あるたくましい人材の育成」を目標に取り組んできた企業インターンシップの経験を生かし、教員志望者の就業支援を目的に、複数の自治体の教育委員会と連携協力に関する協定を結び、教育実習とは異なる「学校インターンシップ」を実現したものであり、非常に優れた取組です。
学校現場を派遣先にするという特殊性に配慮し、事前の市場調査を始めとする木目細かな指導を組織的に行っています。さらに、教職志望者以外の学生にも門戸を広げ、取組を「広義の教養教育」として捉え、「学生の力を活かした小中高大連携」という新たな意義を見出しております。
システムならびに組織性においても優れた取組であると認められます。特に学生が、大人社会の企業や行政のインターンシップと違い、年少者に接することで大人としての責任を自覚し、世代間のつながりを意識させるのに役立つ、教育課程上の工夫と大学と地域社会との連携推進を兼ね備えた事例であり、他の大学等の参考になり得るものと言えます。』
今後の展望
私たちは単なる量の拡大をめざしているものではありません。本取組の質を確保し、さらに向上させる方向で努力したいと考えております。具体的には、本取組が学生のキャリア形成、人間性の向上、大学での学習意欲などに及ぼした成果の追跡調査を進める、事後報告会やシンポジウムを通して、受入校の高校、小・中学校、教育委員会との間でカリキュラム、教育上の達成目標、共有できる問題についてさらなる相互理解と連携を進める、さらには他大学への積極的な情報提供を進めて参ります。
学校インターンシップは学生の人間的成長に資するとはいえ、人間的成長を促す教育に特効薬はありません。事後報告会でこういう感想を述べた学生がいました。「学校インターンシップがきらきらした経験で終わる必要は必ずしもありません」。この言葉は私たちにとっても戒めと励ましとなる言葉であります。現在の大学教育が抱えるさまざまな問題を切り開く糸口として、私たちはこの取組のなかで苦労してみようと思っております。
特色GPシンポジウム
文部科学省の「特色ある大学教育支援プログラム(通称:特色GP)」は、選定された取組の内容等を広く社会に情報提供することにより、今後の高等教育の改善に活用されることを目的としています。本プログラムにおいても、多くの方に知っていただき、大学教育改革推進につなげていただきたく、特色GPシンポジウムを開催し情報提供を行ってきました。
以下に、平成17年度から平成20年度に行われたシンポジウムについて報告いたします。
特色GP第4回公開シンポジウムを開催しました
平成21年1月10日(土)に関西大学千里山キャンパスにて 『文部科学省 特色ある大学教育支援プログラム 「人間性とキャリア形成を促す学校Internship‐小中高大連携が支える実践型学外教育の大規模展開‐(平成17年度選定)」』に関する第4回公開シンポジウムを開催いたしました。
当日は、青森・富山など遠方からの参加者を含め、70名(主に教育関係者〔大学、教育委員会、高等学校、小・中学校など〕)にご来場いただきました。

『学校インターンシップの歩みと展望‐4年間の特色GPを終えて、その成果と今後の課題を検証する‐』をテーマに、特色GP最終年度となる今回のシンポジウムでは、この間、果敢にプログラムに挑戦し大きな成果を獲得した学生諸君からの報告と提案をふまえ、これまで本取組を支え協力していただいた教育現場の先生方、本取組の中心的役割を担ってきた本学の関係者からの応答も交えながら、参加者のみなさんと今までの成果や今後の課題を検証しました。
特に、今年度より学校インターンシップを複数回体験している学生によって結成された「学生懇談会」からの、“学生から見た学校インターンシップ”についてのアンケートの調査結果報告や要望等については参加者からも、実地に即した興味ある内容として高い評価をいただきました。

特色GP第4回公開シンポジウムを開催します
平成21年1月10日(土)に関西大学千里山キャンパスにて『文部科学省 特色ある大学教育支援プログラム 「人間性とキャリア形成を促す学校Internship‐小中高大連携が支える実践型学外教育の大規模展開‐(平成17年度選定)」』に関する第4回公開シンポジウムを開催いたします。
『学校インターンシップの歩みと展望‐4年間の特色GPを終えて、その成果と今後の課題を検証する‐』をテーマに、今回のシンポジウムでは、この間、果敢にプログラムに挑戦し大きな成果を獲得した学生諸君からの報告と提案をふまえ、スタート時より本取組を支え協力していただいた教育現場の先生方、本取組の中心的役割を担ってきた本学の関係者からの応答も交えながら、これまでの経過を辿っていきます。
入場無料・事前予約不要となりますので、どうぞ奮ってご参加ください。
特色GP第3回公開シンポジウムを開催しました
平成20年1月12日(土)に関西大学千里山キャンパスにて『文部科学省 特色ある大学教育支援プログラム 「人間性とキャリア形成を促す学校Internship‐小中高大連携が支える実践型学外教育の大規模展開‐(平成17年度選定)」』に関する第3回公開シンポジウムを開催いたしました。

当日は、鹿児島など遠方からの参加者を含め、約80名(主に教育関係者〔大学、教育委員会、高等学校、小・中学校など〕)に来場いただきました。
『学校インターンシップを通じて若者はどのように育っていくのか‐インターンシップ生の過去・現在・未来‐』をテーマに、今回のシンポジウムでは、学生時代に学校インターンシップを体験した3名の卒業生と、現在参加している2名の在学生から学校インターンシップを通して得たものや感じたことなどを聞き、また卒業生については現在のキャリア(1名はレコード会社勤務、1名は高校教諭、1名は大学非常勤講師)における学校インターンシップの影響力についても伺いました。
これらを踏まえたうえで、コメンテーターからの助言と討論を行うことで今までの成果・課題を検証することができました。

特色GP第3回公開シンポジウムを開催します
平成20年1月12日(土)に関西大学千里山キャンパスにて『文部科学省 特色ある大学教育支援プログラム 「人間性とキャリア形成を促す学校Internship‐小中高大連携が支える実践型学外教育の大規模展開‐(平成17年度選定)」』に関する第3回公開シンポジウムを開催いたします。
『学校インターンシップを通じて若者はどのように育っていくのか‐インターンシップ生の過去・現在・未来‐』をテーマに、今回のシンポジウムでは、学生時代に学校インターンシップを体験した後、教育現場を含め社会で活躍している卒業生や現在参加している在学生から評価や意見を聞き、コメンテーターからの助言と討論を行うことで今までの成果・課題を検証し、今後の取り組みをさらにステップアップさせることを目的に開催します。入場無料・事前予約不要となりますので、どうぞ奮ってご参加ください。

特色GP第2回公開シンポジウムを開催しました
平成17年度特色GP「人間性とキャリア形成を促す学校Internship‐小中高大連携が支える実践型学外教育の大規模展開」の第2回シンポジウム「若い世代をともに育てる組織として‐学生の力を活かした小中高大連携の新たな展開」が平成19年1月15日に開催されました。

東京、山形、名古屋、鹿児島など遠方からの参加者を含め、約80名(主に教育関係者〔大学、教育委員会、高等学校、小・中学校など〕)に来場いただきました。
取組責任者の品川 哲彦(文学部 教授)が本学の特徴を活かした本取組の目標設定と運営方式を説明、学校インターンシップを体験した学生二人の報告の後、中永 健史氏(京都市教育委員会 教員養成支援室長)、丸岡 俊之氏(大阪府教育委員会 教育振興室 高等学校課 主査)、杣 順子氏(寝屋川市教育委員会 学校教育部 教育指導課 指導主事)、鵜飼 昌男氏(神戸市立六甲アイランド高等学校 教諭)によるシンポジウムを行い、本取組の大学生、生徒、学校教員、教育委員会に及ぼす効果が検証され、本取組の課題に関する理解を深めることができました。



本学のような総合大学が教員養成に寄与するとすれば、とくにそれはどういう面でか、また、教員養成の目標は何か、いかなる点で一般の社会人とは異なる特性を要求されるのか等々、本学の本取組にとって、今後も引き続き検討し、検証していくべき課題を見出せた有意義なシンポジウムとなりました。本シンポジウムの具体的な内容は、本取組の2006年度報告書のなかに掲載します。
特色GP第2回公開シンポジウムを開催します
平成19年1月15日(月)に関西大学千里山キャンパスにて『文部科学省 特色ある大学教育支援プログラム 「人間性とキャリア形成を促す学校Internship‐小中高大連携が支える実践型学外教育の大規模展開‐(平成17年度選定)」』に関する第2回公開シンポジウムを開催いたします。
当日は、取組の成果を検証するとともに、大学教育に造詣の深い方々、学校教育に実際に携わっている方々をお招きし、「(1)大学生が小中高の学校現場で活動することでえられる、ジェネレーションギャップの解消、(2)将来、教職を志望する学生に対して、学校現場、教育委員会はどのような期待を寄せているのか、(3)小中高とともに若い世代をともに育てる組織のひとつとして、大学が果たすべき使命」について、教育委員会、学校現場からのご意見、実際に学校インターンシップを体験した学生の報告をまじえたシンポジウムを予定しております。入場無料・事前予約不要となりますので、どうぞ奮ってご参加ください。

特色GP第1回公開シンポジウムを開催しました
平成17年度文部科学省「特色ある大学教育支援プログラム(特色GP)」に採択された本学の学校インターンシップ「人間性とキャリア形成を促す学校Internship‐小中高大連携が支える実践型学外教育の大規模展開‐」の特色GP第1回公開シンポジウムを平成18年2月16日に本学尚文館マルティメディアAV大教室にて開催しました。

本プログラムは、平成17年度には、学校・園から約1,600名の学生受入申込、約300名の学生を派遣するという大規模な実践型学外教育として展開しております。
第1回公開シンポジウムでは、学外有識者、教育委員会、高等学校ならびに大学の教育活動に関わりの深い方々が一堂に会して、この取組の意義と成果を検証し、プログラムの今後の可能性を探ることを目的として開催しました。当日の参加者数は、全国各地から約70名(内訳、学外教育関係者約40名、学内関係者約30名)でした。
河田悌一学長の開会挨拶、プログラム責任者で高大連携運営委員長の品川哲彦(文学部教授)からの基調報告に続き、江原武一氏(立命館大学 大学教育開発・支援センター教授)、大江淳良氏(ユニバーシティ・アクティブ代表取締役)、生田義久氏(京都市教育委員会教育企画監)の各氏によって、このプログラムのもつ意義と可能性(1.大学教育における実践型学外教育のあり方、2.高校、小・中学校、幼稚園等にとっての大学生受け入れの意味、3.教員養成に関わる大学教育における実践教育のあり方)についてシンポジウムを行いました。

学校インターンシップが、”若い世代と若い世代とを繋ぐ機会”として、また”学校・園と大学、地域社会全体で若い世代を育てていく可能性”などについて活発な意見交換があり、貴重で示唆に富むシンポジウムとなりました。
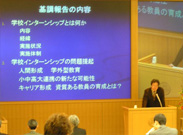
特色GP第1回公開シンポジウムを開催します
平成18年2月16日(木)に関西大学千里山キャンパスにて『文部科学省 特色ある大学教育支援プログラム 「人間性とキャリア形成を促す学校Internship‐小中高大連携が支える実践型学外教育の大規模展開‐(平成17年度選定)」』に関する第1回公開シンポジウムを開催いたします。当日は、取組の成果を検証するとともに、大学教育に造詣の深い方々、学校教育の実際に携わっている方々をお招きし、(1)大学教育における実践型学外教育のもつ意義と可能性、(2)高校、小・中学校、幼稚園等にとっての大学生派遣の意義と可能性、(3)教員養成に関わる大学教育における実践教育のもつ意義と可能性をめぐるシンポジウムを予定しております。どうぞ奮ってご参加ください。


