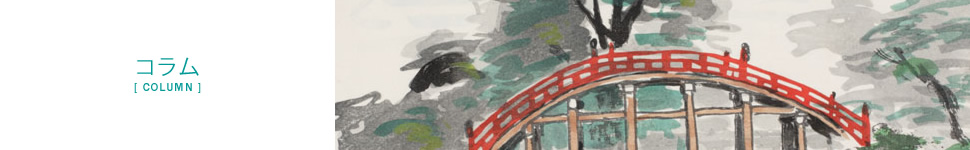第11回 2013/4/24
文化遺産の喪失を考える
松の梢を渡ってくる風がやさしく顔を吹きすぎて行き、潮の香りがいつしか体を包み込んでいくような、のどかな東北の海辺の町に移り住んでいた知り合いのご夫婦はいまだに見つかっていない。
3・11、突如として襲いかかった大津波が家屋敷どころか何もかもを奪い去ってしまった。「痛恨の極み」などと、そんなありきたりな言葉など、人びとの口の端にされることにさえ怒りをおぼえるが、さりとて如何ともしがたい。
町の再生とか復活といったところで、その地域の歴史性とか文化的特性、あるいは生業を根幹に置かなければならないことは言わずもがな、とても構想できるはずもない。幸いというべきか、これまで各市町村はそれぞれ自治体史を発行してきた経緯にあるものの、史料・資料編については道半ばというところ少なくない。そうした史・資料は資料館・博物館が収集、あるいは寄託されている。ところが、そうした資料館・博物館の多くが罹災し、史・資料が壊滅的被害を受けた。文化庁はすぐさま文化財レスキュウ隊を派遣し、国立文化財研究所の保存処理施設などで史・資料の再生化が試みられている。

首里城正殿正面(大正11年鎌倉芳太郎撮影)
文化遺産の散逸のことで、どうしても頭から離れない言葉がある。少し前のことになるが、琉球大学の高良倉吉教授をお招きしてシンポジュームを開いたことがある。高良教授の「第二次世界大戦中の沖縄戦によって、実に多くの人びとの生命が失われたことはいうまでもなく、戦後の米軍の占領期を含めて、沖縄から何が失われたのかがわからない、沖縄にとってこれほど口惜しく、無念なことはない」の発言にとてつもなく大きな衝撃を受けた。
文化遺産の喪失は、ただ単に「もの」が失われたことではない。その地域の人びとの誇りが汚され、無残に投げ散らかされたこと、大げさに過ぎるかもしれないが、民族的心情の打擲(ちょうちゃく)である。あれ以来、何度も足を運んだが、壊滅的被害を受けながらも、罹災地の人びとの顔は「キッ」と正面をにらんでいる。その顔こそが東北に育った私の何よりの支えである。