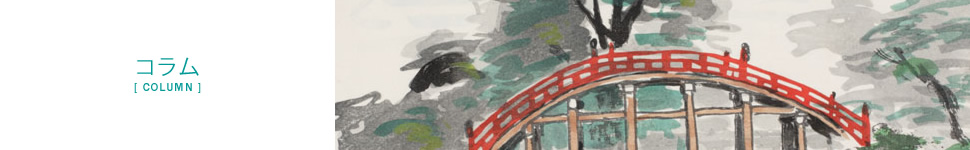第10回 2013/2/14
2011映画、モダニティ、そして織田作之助

織田作之助はよく道頓堀で映画を観ていた
織田作之助は、映画というメディアの特性を鋭く捉えていた作家である。映画には「映画のもつ本来の夢」があると織田はいう。この「映画のもつ本来の夢」とは、すなわち「映画の嘘」のことである。
実物大の数倍の大きさの人間の顔のクローズアップが、果たして正確な写実であろうか。ラムネの玉のような大粒の汗のアップが「汗が流れた」といふ一行以上の如何なる正確な表現であり得ようか。クローズアップといひロングといひ、表現としては嘘だ。しかし、この嘘が魅力なのである(織田作之助「映画と文学」『映画評論』一九四四年九月号、二五頁)。
確かに映画は、三センチの人間の目を三メートルもある巨大な目に変え、二メートルもある大男を突然小さな豆粒サイズに変えることができる。また、北海道の木の上にいた男が、次の瞬間、いきなり沖縄の海にいるといった表現も可能だ。しかも映画は、ほかのメディアにはない強烈なリアリティを見せつけながら、嘘をつく。それこそが映画の得意とする「嘘」の魅力である。
映画の「嘘」にリアリティは必要である。だから織田は、けっして映画のもつ「写実の力」を否定してはいない。むしろ織田が否定するのは、映画の「写実の力」を「盲信」し、「事物が正確にありのまま写されていることを他愛もなく喜んでいる」輩である。自然主義小説のような些末主義的描写に陥り、「糞リアリズム」に終わっている映画なのだ。織田にとって「文学を追いかけまわした」だけの、想像性を欠いた文芸映画は、滑稽以外の何物でもない(おそらく豊田四郎監督の『夫婦善哉』は嫌いだろう)。まさに『可能性の文学』『二流文学論』を書いた男の美学がそこにある。
映画は、従来のメディアにはありえないほどのリアリティとスピードで空間と時間の概念を飛躍させ、刺激に満ちた驚きを与える視覚メディアであった。だから魅力的だったのだ。映画が近代性を象徴するメディアであるといわれるゆえんも、そこにある。織田は、その魅力の核心をとらえていた。実に的を射ているのである。