Re:ORDIST 181
- 特集 1
- 特集 2
特集1 ウェルビーイング すべての命が尊重される未来を目指して
DNA を素材に未来をデザインする
分野を超えて広がる社会実装への挑戦
化学生命工学部 化学・物質工学科 知能分子学研究室 教授 葛谷 明紀
DNA を"生命の設計図"ではなく、"ものづくりの材料"としてとらえる独自の視点から、最先端のナノテクノロジー研究を進めてきた葛谷明紀教授。一本の長いDNA を折り畳み、思い通りの形を作る「DNA オリガミ」技術の世界的なトップランナーの一人として、医療・環境・エンタメといった分野の垣根を越えた応用開発をリードしてきました。
DNA が持つ緻密な設計性と反応性を、どのように活かして社会に役立てていくのか。多彩な分野へと
広がる革新的な挑戦について伺いました。
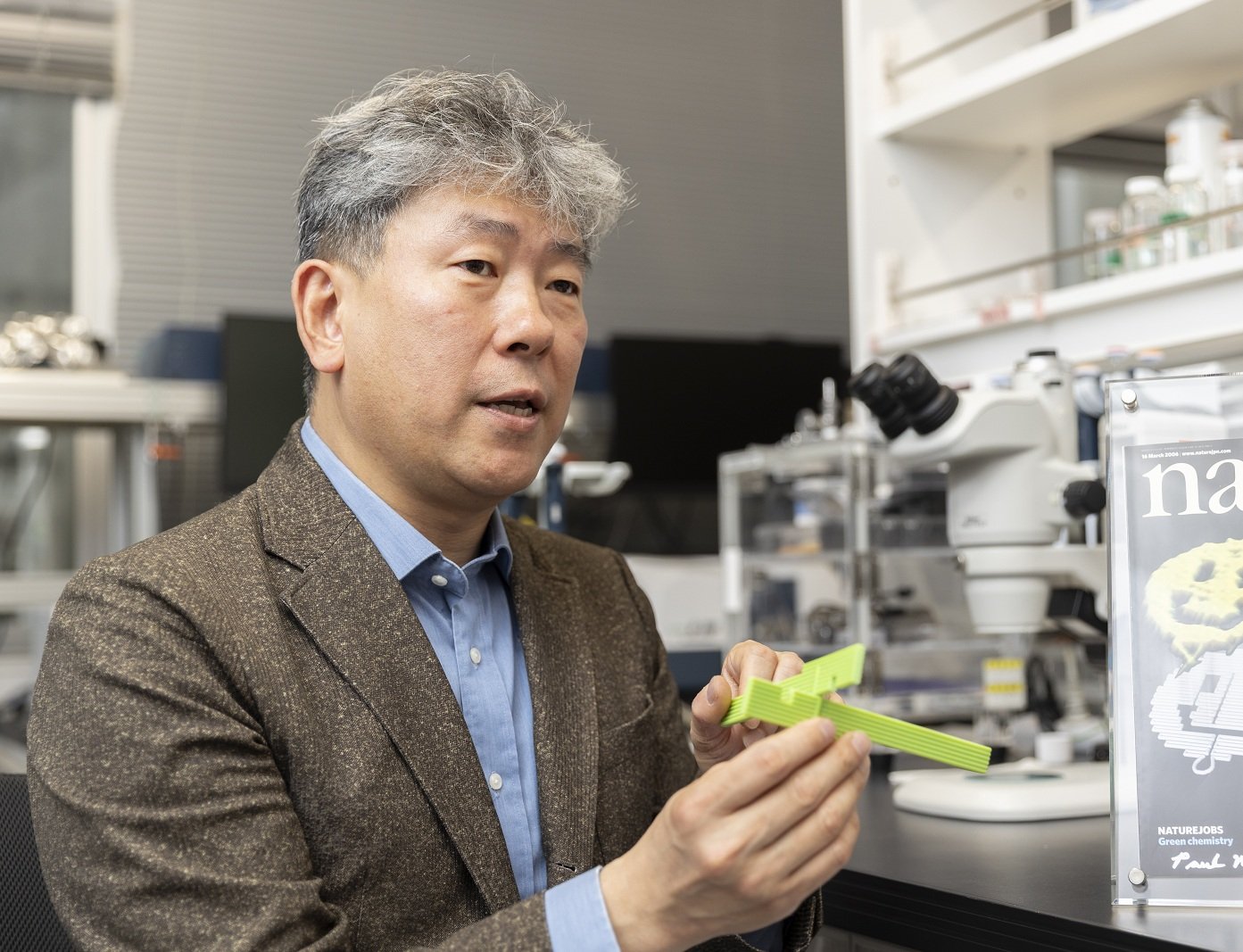
"知能"をもつ分子としてDNAをとらえる新発想
葛谷先生の研究室名には「知能分子」という耳慣れない言葉が使われています。これはどのような意味を持つのでしょうか?
名付ける時に意識したのは、「検索しても一件しか出てこない研究室名にしたい」ということでした。でも、奇をてらったわけではなく、「知能分子」という言葉には、私なりの確かな思いが込められています。
DNA という分子は、私たち人間が指示しなくても、分子同士が正確に反応し、適切な相手と結びつきます。たとえば、アデニン(A)はチミン(T)、グアニン(G)はシトシン(C)といった具合に、必ず決まったペアを組んでいく。そのふるまいが、まるで、"知能"を持っているように感じられて、私はこの分子を「知能分子」と呼びたくなったのです。
反応があまりに精緻で、知能的に見えるということですね。
その通りです。DNA にあらかじめ情報を書き込んでおけば、それに従って自律的に判断して動く。学生たちには、「"知能分子"って書いて、"DNA"と読んでね」と冗談混じりに話すこともあります(笑)。
そうしたDNA の性質を活かして、どのような研究を展開されているのですか?
DNA といえば、一般的には「生命の設計図」や「遺伝情報の担い手」として知られていますよね。ですが、私たちはそれを「ものづくりの材料」としてとらえ、最大限に活用しながら、さまざまな研究開発に取り組んでいます。
具体的には、DNA を人工的に合成し、自然界には存在しない情報を与えることで、新たな構造体や機能を持ったナノスケールの物質を作り出す。こうしたアプローチが、私たちの専門とする「DNA ナノテクノロジー」と呼ばれる分野です。その中でも、中心的な技術として世界中で研究が進められているのが、「DNA オリガミ」です。
動きを持つDNA 構造体を世界に先駆けて開発
葛谷先生は、DNA オリガミの日本における先駆者としても知られています。これは一体どのような技術なのでしょうか?
一本の長いDNA に対して、短いDNA をホッチキスの針のように組み合わせ、折り畳みながら設計図通りの構造体を作っていく手法です。折り紙に例えられていますが、感覚的には、縦糸と横糸で布を織る"織物"に近いかもしれません。
この技術との出会いについて、教えていただけますか。
DNA オリガミは、2006 年にアメリカで初めて報告されたのですが、そのとき私はちょうど留学中でした。現地でニュースを見て、「とんでもない技術が出てきたぞ」と仲間たちと興奮したことを覚えています。
帰国後、すぐに自身の研究テーマに据え、日本でいち早くこの分野に取り組み始めました。当時、世界でもこの研究をしている研究室は3 〜4 か所ほどで、日本では私たちが最初だったと思います。
DNA オリガミでは、具体的にどのような構造が作れるのですか?
平面的な図形から立体構造、さらに"動く構造"まで、さまざまな形を設計することができます。その中でも代表的なのが、私たちが開発した「DNA Pliers(ペンチ)」という構造体です。このDNA ペンチは、中央に蝶番構造を持ち、一点で固定された部分を軸にして、左右の"レバー"がペンチのように開閉する仕組みになっています。特定の分子に反応して動作するよう設計されており、ある分子を検出すると、それを挟み込むように構造が変化します。
従来のDNA オリガミは、「形を作る」ことに主眼が置かれていましたが、私たちはそこに「動き」という新たな要素を加えることに成功しました。しかも、この開閉動作を電子顕微鏡で目に見える形で確認できる点が、ナノ構造として非常に画期的だと高く評価されています。
 ▲ DNA Pliers(ペンチ)の模型
▲ DNA Pliers(ペンチ)の模型
動きを持たせるという発想は、どのようにして生まれたのでしょうか?
当時、世界中の研究者が、DNA で「箱」を作ろうとしていました。私たちもそこに挑戦したのですが、タッチの差で他のチームに先を越されてしまったんです。そこで発想を転換し、「動く構造体」で勝負することにしました。
その結果、世界で初めて動きのあるDNA 構造体を報告することができ、今の応用研究へとつながる重要な土台となりました。
DNA オリガミが社会実装へ高感度・簡便な検査を実現
その技術を、細菌やウイルスを高感度に検出できる「検査キット」に応用されているそうですね。
はい。私が取締役を務めるスタートアップ「Cranebio(クレインバイオ)」では、DNA ペンチを応用した人工酵素「Dozyme 」を搭載した新しい検査キットを開発しています。Dozyme は、特定の分子を検出すると構造が変化し、
酵素活性が発現するよう設計されています。さらに、構造変化によって発光する機能も備えており、その変化をスマートフォンのカメラで読み取ることで、高感度な検出が可能になります。
PCR 検査のような精度が、より簡単に短時間で実現できるようになるのですね。
まさにそうです。専用の装置や熟練した技師は不要なので、どこでも手軽に使えますし、これまで数日かかっていた検査がその場で完結できます。目に見えない分子の動きを、光として直感的に把握できる革新的な検査ツールといえますね。
新しい検査のスタンダードとして、医療だけでなく、さまざまな分野で活用が広がりそうです。
水質検査や食品の衛生管理、さらには災害時の感染症対策など、即時の対応が求められる場面で役立つのではな
いかと期待しています。
また、開発元であるクレインバイオは、大阪・関西万博に設置された「大阪ヘルスケアパビリオン」の展示・出展ゾーンにて、関西大学のリボーンチャレンジ参加企業の一つとして出展しました。その中で、この検査キットも、動くDNA オリガミを活用した世界初の製品化事例として紹介することができました。これまで研究室で育んできた技術が、いよいよ社会実装へと歩み出す、大きな節目となりました。
DNA オリガミは、今や応用のフェーズに入っているのですね。
DNA オリガミは誕生から約20 年が経ち、"何を作るか"よりも、"それをどう使うか"が問われる段階に来ています。DNA を人工的に設計・合成し、それを使って新たな機能を持つ構造体を作り、応用へとつなげる。これらを一貫して担える体制が、私たちの強みだと自負しています。
「人工ホタル」で目指す環境にやさしい次世代ディスプレイ
DNA オリガミの応用として、分子自身が自律的に判断して動く「分子ロボット」の研究にも注力されています。その一つが、生物由来の
仕組みで発光を実現する「人工ホタル」です。これはどのような技術なのでしょうか?
従来のディスプレイや発光技術といえば、電気とLED を使って光を制御するのが一般的でした。でも私たちはそこに、「生体分子だけで光らせる」という発想を取り入れました。
具体的には、DNA 構造体に深海エビ由来の発光タンパク質「NanoLucルシフェラーゼ」を組み込み、そこに発光物質である「フリマジン」を加えることで、化学反応によって光を生み出すシステムを構築しています。
この仕組みでは、DNA が特定の分子を検出すると、それに応答して自ら発光するという一連の動作が、すべて分子レベルで完結します。こうした自律的なふるまいから、私たちはこれを"分子ロボット"と位置付けています。
さらに、私たちが得意とするDNAの精密な設計技術を活かせば、光の色や明るさも自在にコントロールできます。RGB の三原色の発光も実現できるので、将来的には色や輝度を自由に調整できる"電気を使わないディスプレイ"としての応用も視野に入れています。
環境にやさしい、次世代のディスプレイですね。
このシステムは、電子回路ではなく化学エネルギーで駆動し、しかも使用する素材はすべて生体由来なので、最終的には自然に分解されて還る構造になっています。電子部品に比べて製造コストが抑えられる可能性もあり、環境負荷の少ない新しい発光デバイスとしての展開に、大きな可能性を感じています。
具体的には、どのような用途を構想されていますか?
今、最も実用化に近いと考えているのが「スマートコンタクトレンズ」です。たとえば、糖尿病患者の方がこのレンズを装着すると、涙に含まれるグルコース濃度を検出し、その情報を目の中で光として"視覚的に確認できる"という仕組みを想定しています。
このレンズには発光タンパク質が内蔵されており、そこに目薬のようにフリマジンを投与するだけで、化学反応によって光が発生します。つまり、電気を使うことなく、分子の働きだけで体内情報を可視化できる、ウェアラブルな医療デバイスとしての活用を目指しています。
まさしく"未来の医療"ですね。
でもそれだけでなく、発光するコンタクトレンズやアクセサリーは、コスプレやアートの世界にも応用の可能性があるかもしれません。技術って、どこでブレイクするかわかりませんからね。むしろ、エンタメ分野で先に広がって
くれたら面白いなという思いもあります。
人工ホタルは、分子ロボットの製品化第一号になる可能性もあるのでしょうか?
はい。すでにDNA オリガミは、構造を作る技術として製品化を実現していますので、次はこうした"自律的に動作する分子構造体"による製品化第一号を狙っているところです。
医療への実装を加速させる量産可能なDNA 素材とは
一方で、DNA を使ったゼリー状の材料を開発され、薬剤送達システム(DDS)への応用も進めておられるそうですね。
これは、DNA 自体を"薬を運ぶ乗り物"として使うという発想から始めた研究です。従来、薬剤を体内の細胞に届けるには、キャリアと呼ばれる運搬体が不可欠でした。しかし、DNAはもともと生体が"好んで取り込む"素材。つまり、DNA 自体がキャリアとして機能できるという点が、他の材料とは大きく異なります。
中でも、私たちが開発したDNA ヒドロゲルは、DNA の四重鎖構造を使ってゲル化させた新しい材料です。薬剤を包み込んで安定的に保持し、狙った細胞に向けてゆっくりと放出することができる。しかもDNA が原料なので、生体適合性が高く、安全性にも優れています。

▲ 体液を感知して瞬時に固化するヒドロゲル材料( =DNA 四重鎖ゲル)
実用化に向けて、量産性やコスト面はいかがでしょうか?
DNA オリガミは自由度が高く、精密な制御が可能ですが、量産性には課題があります。一方、DNA ヒドロゲルは比較的シンプルな構造で、量産性やコスト面で非常に優れています。私たちは、すでに独自の大量製造技術を確立しています。
「精密に設計された構造物」としてのDNA オリガミと、「生産しやすく安定した素材」としてのDNAヒドロゲル、それぞれ異なる利点を持ちながらも、DNA を軸に医療応用へとつながっているのですね。
DNA オリガミや分子ロボットとは異なるカテゴリーではありますが、DNA ヒドロゲルもまた、広い意味での"ナノバイオデバイス"の一種として、医療やヘルスケアの未来を支える重要な技術だと考えています。
DNA ナノテクノロジーの応用は、今後どのように広がっていくとお考えですか?
医療への応用を本格的に実現するのは、まだ何十年とかかるかもしれません。だからこそ今、私たちが強く意識しているのが、「医療応用だけにこだわらない」という視点です。
この分野はどうしても、医薬品の開発に直結する形で語られがちですが、医療は研究から承認、そして実際に使われるようになるまでに非常に長い時間を要します。そこで重要になるのが、医療だけでなく、「非医療」の応用にも力を入れるという、両輪での推進です。
非医療とは、具体的にどのような分野があるのでしょうか?
たとえば、DNA を使ったバイオセンサーやエネルギー変換素材、化学プロセス制御などは、比較的早い社会実装が見込めます。さらに、そうした周辺分野での実績が、医療応用に対する信頼性や注目度を高める土台にもなってくれます。
加えて、DNA を大量かつ安価に合成する技術が進展すれば、最終的に医薬品のコスト削減にもつながりますし、結果として医療応用への資金的な支援につながる可能性もあるのです。
技術を医療に限定しない姿勢が、結果として医療分野をも加速させるのですね。
DNA ナノテクノロジーは、医療だけでなく、あらゆる社会課題の解決に寄与できる可能性を秘めています。制度の壁や実装のタイミングを見極めながら、まずは"走り出せる領域"から確実に技術を社会に届けていく。そんな戦略的な進め方が、今後ますます重要になると考えています。
「オメガ核酸科学」で切り拓く新たな学術フレームの創出
そして現在、新しい構想の実現に向けて、動き出されているそうですね。
今立ち上げようとしているのが、「オメガ核酸化学」という新たな学術領域です。DNA やRNA は天然に存在する核酸ですが、私たちはこれまで、それを人工的に改造した「XNA(人工核酸)」の開発にも取り組んできました。XNAの各タイプは、これまで世界中でアルファベットを1 つずつ割り当てて命名されてきましたが、研究が進むにつれ、もうアルファベットの8 割が使われてしまった。そこで、私たちはギリシャ文字に目を付けたのです。中でも「オメガ」は最後の文字で、"究極"という意味もある。まだ誰も使っていないということは、自分たちで定義できるということ。そこは新たな分子技術のフレームワークを築く上で、非常に意義深いことだと思っています。
単なる命名ではなく、世界的な研究の潮流の中で、新たな規格やアプローチを提案するということですね。
その通りです。特に日本は、材料科学や分子設計の領域で世界に誇れる強みを持っています。だからこそ欧米とは違うアプローチで、新しい学術領域を世界に向けて発信したいのです。そして若い研究者にも、この面白さを伝え、広く社会とつながる技術として、DNA ナノテクノロジーの分野を育てていきたいと考えています。
そこまでDNA に情熱を注がれている、その原動力はどこにあるのでしょうか?
DNA って、裏切らない分子なんですよ。設計通りにきちんと組み上がるし、再現性も非常に高い。しかもこちらが予想した通りの動きを見せてくれる。構造をデザインする側にとって、これほどありがたい素材はありません。
それに、ペアの組み合わせのルールが厳密なので、設計の自由度が高いんです。つまり、自分のアイデアをかなりの精度で形にできる。だからこそ飽きることなく、ずっと夢中でいられるんだと思います。まあ、自他ともに認めるDNA オタクですね(笑)。
まさに、これまでの研究人生を、DNAととも歩んでこられたのですね。
ええ、たぶんこのままDNA の研究ひと筋だと思います。でも、それはまったく後悔のない選択です。DNA は、生き物が40 億年という時間をかけて選び抜いてきた、生命にとって最適な構造を持つ分子です。そんな生命の根幹を成す素材を使って、まったく新しい価値を生み出せることは、研究者として本当に幸せなことだと思っています。
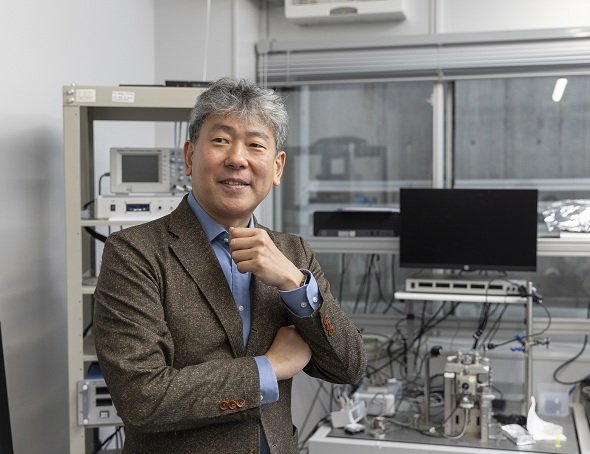
<プロフィール>
茨城県つくば市出身。卒業研究以来、DNA 等の核酸を機能材料ととらえ、有用な分子デバイスの構築に取り組む。
趣味は映画鑑賞。健康のため、水泳とジョギングも継続中。最近なぜか通訳案内士(英語)の資格を取得。
特集2 ウェルビーイング すべての命が尊重される未来を目指して
セミの羽がもつナノ構造を模した材料で
薬剤に頼らない抗菌・殺菌を実現
システム理工学部 機械工学科 ナノ機構物理工学研究室 教授 伊藤 健
動植物の構造や機能を模倣し、社会に役立つ技術や製品への応用をめざす「バイオミメティクス」。
なかでもセミの羽が持つ微細な突起「ナノスパイク」構造を模して、薬剤を使わない抗菌・殺菌材の開発に取り組んでいるのが伊藤健教授です。持続可能な未来社会の実現を期待させる、バイオミメティクスの研究について伺いました。
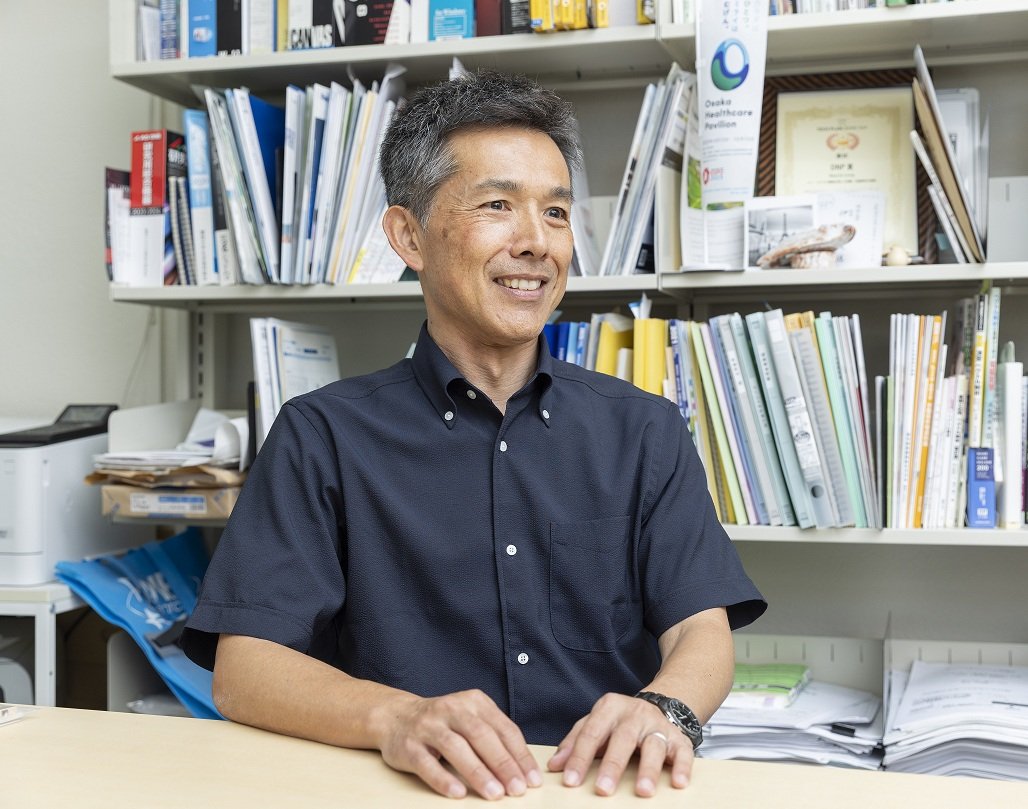
バイオメティクスに感じた可能性と疑念から研究を開始
バイオミメティクスに興味を持たれたきっかけを教えてください。
幼い頃から昆虫が好きで、単に捕まえて飼うくらいのものでしたが、2010年頃、JST CREST でバイオミメティクスが取り上げられていたのを見て、知らないことが思いのほか多く、「生物の不思議」に面白さを感じ、興味を持ったことがきっかけです。
バイオミメティクスの実用例としては、ハスの葉を模倣した撥水性の高いヨーグルトの蓋や、野生ゴボウの実、いわゆるひっつき虫を模倣した面ファスナーなどが有名です。動植物がそれぞれの環境に適応する構造を身につけていること、さらにはその構造が人間社会に応用できることに驚きを感じました。
前職の神奈川県立産業技術研究所では、個人の研究と外部から依頼される分析などを並行して手がけていたのですが、2015 年、関西大学へ移ってくる際に、大学ならではの自由な研究がしたいとバイオミメティクスをテーマに選びました。
バイオミメティクスを研究するなかで、セミの羽に着目された経緯は?
ナノ機能物理工学研究室に入り、国際的な研究をリサーチするなかで、「セミの羽のナノ構造に殺菌性がある」というオーストラリアの論文を見つけ、研究結果に疑問を抱いたのがきっかけです。そんな簡単に、しかも物理的に細菌が死滅するとは考えにくかったのです。学部生時代や前職でも細菌を扱っていたこともあり、自分でも実験してみようと考えました。
前職の神奈川県立産業技術研究所でも細菌を扱われていたんですか?
産業技術総合研究所では、増殖スピードの速い大腸菌を活用して、利用したいタンパク質を生成するという仕事を手がけていました。タンパク質の遺伝情報を入れた大腸菌を増殖させ、最終的に浸透圧で膨張・破裂させてタンパク質を取り出すのですが、菌を死滅させるのって結構大変なんです。しかし当該研究では、セミの羽に緑膿菌の培養液を垂らすと、表面にある超微細な突起から物理的なダメージによって細菌が死滅したと書かれていて、「そんなに簡単に死なないよな...」と。そこで大学構内で捕まえたクマゼミの羽で試してみたところ、細菌が突起によって変形し、理由はわからないけれど事実として死滅したんです。これを応用すれば、薬剤を使わない抗菌・殺菌材が実現できるかもしれない。そう考え、セミの羽が持つナノスパイク構造を人工的につくって確かめることにしました。

▲クマゼミの羽と電子顕微鏡による観察例
ナノスパイクの構造だけで物理的に殺菌できることを確認
ナノスパイクをどうやって作製されたんですか。
半導体の微細加工がコアである所属研究室の技術を流用しました。遠心力で数百nm の小さな球= コロイドを基板上に並べる「コロイダルリソグラフィ」や、金属を触媒にしてシリコン基板を削る「メタルアシストケミカルエッチング」などを用いて、ナノスパイク構造の作製に成功しました。そして、大腸菌の培養液を垂らしてみたところ、確かに死滅したんです。作製時に使う薬品が洗浄されていなかったのでは...といったネガティブな要素をすべて検査しましたが、やはり構造だけで物理的に死んでいるのは間違いない。そこから細菌数を最大で10 万分の1 にまで減らすことを実証し、2018 年に「ナノスパイク構造による抗菌・殺菌材の作製」に関する特許を出願しました。
ただ、シリコンは材料費が高く、硬くて扱いにくいこともあり、大面積化には不適です。そこでシリコンに比べて非常に安価であり、柔らかくて加工もしやすい樹脂での作製を試みました。金型をつくって転写すれば、大量生産も可能ですからね。
樹脂での作製もうまくいったのでしょうか。
加工自体は割と早い段階でできたのですが、シリコンほどの殺菌効果が得られませんでした。そこで樹脂やナノ構造の形状、表面の物理化学的な性質をチューニングして、殺菌性に与える影響を評価しました。細菌の種類によっても殺菌効果は異なるため、すべてを把握できていませんが、ナノスパイクの硬さが重要であることはわかりました。
もともとは樹脂の突起もシリコンと同じ高さにしていたのですが、柔らかい樹脂は高くなるほど曲がりやすくなり、殺菌効果が薄れてしまったのです。そのため改めて樹脂に合った突起の高さや形状を精査し、殺菌効果を最も発揮できるナノスパイク構造を確認しました。これについても特許を申請しています。

▲クマゼミの羽表面にあるナノ構造を模して作製
抗ウイルス性やバイオフィルムの形成を抑制することも確認
なぜナノスパイク上で菌が死滅するのでしょう?
メカニズムについてはNICT(研究開発法人情報通信研究機構)などと連携し、解明を試みました。遺伝子工学を利用し、生きている間は光を発する大腸菌をつくっていただき、死ぬ過程
を観察していったのです。大腸菌は鞭毛を回転させて動くので、その間、尖ったところにぶつかった衝撃で死ぬのではとこれまでは考えていたのですが今ではストレス由来のアポトーシス(自己死)ではないかと考えています。
ストレスを受けると人間も体調が悪くなりますが、細菌のような単純な生物だと死を招きます。ナノスパイクによって細胞の一部が変形すると、ストレス応答として酸化物質が大量に発生します。これが引き金となって、分裂に必要な膜を溶かす酵素に信号が送られ、アポトーシスのプログラムが活性化し、自らの膜を溶かして死に至ります。ストレスが発生した後にどういう情報で信号が送られているのかはまだわか
りませんが、時系列としてこのプロセスが起こっているのは間違いありません。
ストレス由来とは驚きです。現在、ナノスパイクの研究はどこまで進んでいますか。
多剤耐性緑膿菌やメチシリン耐性黄色ブドウ球菌など、薬剤に耐性を持ち感染症を引き起こす代表的な細菌に対しても効果があることも、大阪大学医学部感染制御学講座との共同研究で確認しています。また、ウイルスやバイオフィルム(細菌を主とする微生物の集合体)を対象にした調査も行っていて、抗ウイルス性を示すことやバイオフィルムの形成を抑えることも確認できています。
実用化されれば、どのようなシーンで役立つのでしょう?
薬剤耐性菌による感染症で亡くなっている人が世界全体で年間約130 万人、日本でも年間約8000 人いるという報告が出ています。こうした耐性菌による感染を防ぐには物理的に殺すことが重要であり、その手段としてナノスパイクはとても有効であると考えます。これまでは強力な化学薬品を使う必要があった箇所や薬品を使えなかった箇所への利用が期待できますからね。
たとえば、医療用のカテーテルを介した感染は、表面にバイオフィルムが形成されることが主な原因とされています。しかし体内に直接挿入する器具であるため、化学的な抗菌・殺菌剤を塗布するのは難しい。そこにナノスパイクを利用すれば、人体に影響のない、半永久的に抗菌・殺菌効果のあるカテーテルも作製可能なわけです。
起業し大阪・関西万博に出展いち早い製品の実用化をめざす
医療現場での実用化が待たれますね。
将来的には医療アクセスの乏しい空間、たとえば災害地の避難所や宇宙空間における制菌にも利用できるのではないかと考えています。
ほかにも公共交通機関のつり革や手すりなどでの感染予防も期待できます。近頃はすでに抗ウイルス・抗菌加工が施されていますけど、薬品の効果は持続性がないので、定期的に再コーティングしなければなりません。構造そのもので予防できれば半永久的なものなので、より安心ですよね。
また、作製コストが下がれば、一般消費者向けの抗菌フィルム、たとえばスマホの保護フィルムなどにも展開できます。スマホの表面には便座の10倍もの細菌がいるとの報告もありますからね。
薬剤を使わずに済むのは安心にもつながりますね。社会実装に向けた取り組みについても教えてください。
この4 月には大学発のベンチャーを立ち上げ、ナノスパイクの技術提供、ライセンシングなどに取り組んでいます。自分たちの会社でオリジナルの製品をつくるのではなく、自社の商品に採用しようという会社とコラボレートしたほうがスピード感もありますし、各社の強みも活かせますからね。
また8 月には、大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」にも出展しました。セミの羽に殺菌抗菌性を持つナノ構造があること、それにインスピレーションを得てつくられたナノスパイクがあることなんて、ほとんどの人はご存じない。この技術を多くの人に知ってもらうことで、生物の不思議に興味を持ってもらえると思いますし、技術の活用先が広がるかもしれません。

▲先生による説明と併せ、実際に触れることができる展示ブース
早く社会に届けたいですね。
ナノスパイクの技術を用いた製品が世の中に一つでも出て、感染症対策になればいいなと思っています。社会実装されていくことが、皆さんの生活を豊かにすることにつながるのではと期待しています。
動植物は最も効率のいい形に自ら進化している。そういった自然の知恵を借りて、より良い形で未来社会に還元していきたいですね。
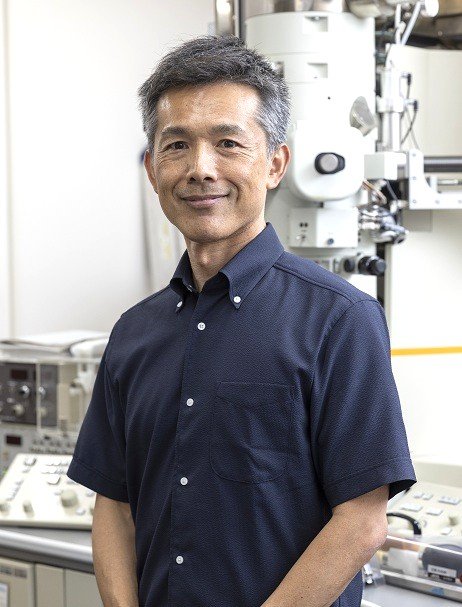
<プロフィール>
神奈川県出身。大阪大学理学部宇宙・地球科学科の第一期生として卒業。
東京大学大学院理学系研究科地球惑星物理学専攻修了。
慶応義塾大学大学院理工学研究科総合デザイン工学専攻 博士。
神奈川県立産業技術総合研究所にて18 年間勤務し、常に先端研究と商品化の狭間で「学の実化」を体感
された。
2015 年4 月に准教授として本学に着任。2018 年より現職。
専門はナノ・マイクロ科学。
