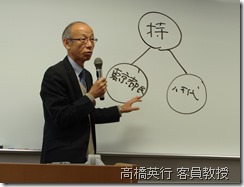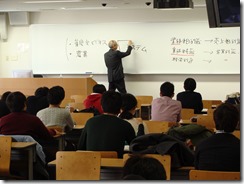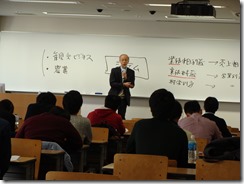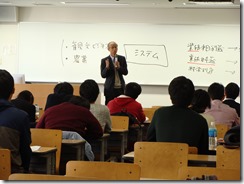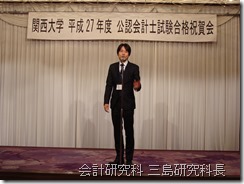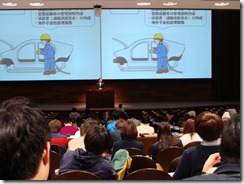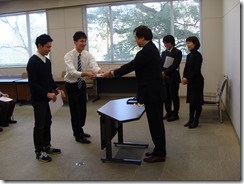« 2015年12月 | メイン | 2016年2月 »
2016年1月29日
関西大学商学部の田村ゼミ3年次生が平成27年度証券ゼミナール大会で優秀賞を受賞しました!
平成27年12月11日(金)〜12日(土)にかけて東京(国立オリンピック記念青少年総合センター)で開催された「平成27年度証券ゼミナール大会」において、関西大学商学部田村ゼミ(3年次:2013年度入学生)の小松班が優秀賞を受賞しました!
優秀賞受賞の小松班メンバー 
(写真左から)石田 さとみさん、小松 千波さん、中山 岳弥さん、藤原 健志さん
全日本証券研究学生連盟が主催する「証券ゼミナール大会」は、金融証券に関する分野を研究する全国の大学生が集まり、予め作成する論文の評価やプレゼンテーション報告、そして昼夜続く2日間の討論を行う大会です。
全日本証券研究学生連盟の発足は昭和26(1951)年、証券ゼミナール大会は昭和55(1980)年から続く歴史ある大会です。日本証券業協会の後援のもとに毎年開催され、昨年度は総勢約700名の学生が参加しています。
今年度田村ゼミは、それぞれが選んだテーマについて春から研究を重ね、4チーム参加しました。その結果、第3テーマ「中小企業における資金調達について」Bブロックにおいて、田村ゼミB小松班が優秀賞を獲得しました!
他のチームも熱心な討論行い、これまでの研究成果を存分に発揮した2日間となりました。
証券ゼミナール大会および証券研究学生連盟の概要 http://shougakuren.jp/
証券ゼミナール大会結果 http://shougakuren.jp/kakoseminar/
2016年1月27日
客員教授講演会〔12月22日 高橋英行氏〕を開催しました!
平成27年12月22日(火)10:40~12:10(第2時限)に、関西大学千里山キャンパス第2学舎2号館C303教室において、関西大学客員教授、大阪銀行協会専務理事の高橋英行氏を講師に迎え、「地方銀行の現状と課題~地方銀行はどう生き残るか」というテーマで商学部主催の客員教授講演会を開催しました。
講演会の要旨は次のとおりです。
****************
最近、新聞各紙に足利銀行と常陽銀行の経営統合が大きく報道された。近年、地方銀行同士の経営統合のニュースをよく耳にする。こうした地方銀行の経営統合が相次ぐ背景を金融当局のレポート(金融庁の金融モニタリング・レポート、日銀の金融システムレポート別冊)をもとに考えてみたい。
足元の地方銀行の収益をみると極めて好調な姿が窺える。しかしながら、中身をよく分析してみると、預金を集め、その資金を貸出す言わば銀行の本業の部分は苦戦している姿が見えてくる。これは貸出金利が預金金利に比べ大きく低下し、いわゆる預貸金利鞘が縮小していることが主因である。預貸金利鞘の縮小を招いているのは、人口減少による地域経済の活力の低下が原因の一つとこれらのレポートは分析している。
本業の苦戦が人口減少によるものとすれば、いわば構造的な問題であり、5~10年後を見据えた中期的な持続可能なビジネスモデルの構築が地方銀行には求められる。この問題に対応するため人口減少の影響の少ない首都圏に出店するケースもみられるが、競争が激しく十分な利益を稼げる状態ではない。
その対応の一つは、それぞれの地方銀行が基盤とする地域にしっかりと根とおろし、地域経済としっかり向き合う方法である。地域の産業・企業の活力向上のためしっかりと金融支援を行うことである。そして、もう一つの方法が業務提携や経営統合である。規模の拡大は経費削減効果があり、また、業務範囲の拡大も期待でき、地方銀行にとっての一つの選択肢であることに間違いはない。
いずれにしろ、地方銀行に求められているのは、人口減少社会を見据えて中期的な持続可能なビジネスモデルを構築することであり、最近の地方銀行の経営統合もこうした大きな流れの中で理解すべきである。
*******************
具体的な事例を取り上げながら、学生にも分かりやすく説明をしていただきました。
講演会に出席した、主に商学部の学生たちは、大変熱心に聴講していました。
☆写真をクリックすると大きく表示されます。
2016年1月23日
関西大学商学部の陶山ゼミ生が第62回日本学生経済ゼミナール大会・プレゼンテーション部門の決勝戦において最優秀賞・優秀賞を受賞しました!
平成27年12月6日(日)に新潟大学で開催された、第62回日本学生経済ゼミナール大会・プレゼンテーション部門の決勝戦において、関西大学商学部から参加した陶山計介ゼミの学生が見事、最優秀賞・優秀賞を受賞しました!
最優秀賞受賞のTeam Private Brand のメンバー  (写真左から) 氏江 知紗さん、山村 優佳さん、井上 拓也さん、西山 句美さん、安定 拓哉さん
(写真左から) 氏江 知紗さん、山村 優佳さん、井上 拓也さん、西山 句美さん、安定 拓哉さん
日本学生経済ゼミナール大会は、日本学生経済ゼミナールという学術団体が中心となり、全国の経済学部・経営学部・商学部の学生を対象として「研究活動の促進」と「他大学の学生との交流」を理念に掲げる学術大会で、60年以上の歴史をもっています。
プレゼンテーション部門は、日頃の研究成果をパワーポイントにまとめ発表技術や内容について競い合うものです。
今大会のプレゼンテーション部門には全国から約100チームが参加、予選を勝ち抜いた13チームによって決勝が行われました。
陶山計介ゼミのTeam Private Brandが「日英PB(プライベート・ブランド) ロイヤルティ構築モデルの国際比較による日本型PB戦略の導出」というテーマのプレゼンテーションが最優秀賞に選ばれました。
発表の内容は、トップバリュやセブンプレミアムに代表されるPBの食品市場に注目し、消費者の継続的な購買に至るためにはどのような要因が重要であるのかを、PB先進国のイギリスと比較することで日本のPB戦略を明らかにしました。
また、Team Buzz (奥田更紗さん、川端由佳子さん、中屋早紀さん、松岡亜依さん、安田雪乃さん、吉田航さん)は第三位となりました。
なお、Team Food Security(石村姫乃さん、植田志織里、篠原梨沙さん、中村真悠さん、高尾侑里さん)も決勝大会に臨みました。
日本学生経済ゼミナールの詳細と決勝大会の最終結果はこちらをご覧ください。
大 会 の 概 要 : http://www.inter-seminar.com/
決勝大会の最終結果 : http://www.inter-seminar.com/images/stories/kesshou-kekka.pdf
☆写真をクリックすると大きく表示されます。
写真・記事提供 : 商学部 陶山 計介教授
2016年1月20日
平成27年度公認会計士試験に31名が合格し、合格祝賀会〔12月19日〕を開催しました!
平成27年度公認会計士試験の合格発表があり、31名の本学学部・会計専門職大学院出身者が合格しました。
商学部からは、3年次2名、4年次8名、合計10名の在学中学生が合格しました!
会計専門職大学院在学中合格者4のうち、2名は商学部を卒業した1年次在学生でした。そのうち1名は3年次で早期卒業し会計専門職大学院への進学者でした。
公認会計士試験合格発表の詳細については、こちらをご覧ください。
公認会計士試験合格者の皆様のこれまでの努力を慰労するとともに今後ますますのご活躍を祈念し、関西大学商学部・専門職大学院・公認会計士関大会 共催による、「公認会計士試験合格祝賀会」が12月19日(土)に開催されました。
当日は合格者20名の他に、法人本部長、副学長、商学部長、会計研究科長、合格者の演習担当教員、校友会副会長、公認会計士関大会関係者の皆様が多数出席し、交流を深めました。
【商学部在学生・卒業生合格者の皆さんと商学部長(写真前列中央)】

☆写真をクリックすると大きく表示されます。
2016年1月18日
商学部公認会計士(CPA)受験支援委員会主催講演会〔12月14日〕を開催しました!
2015年12月14日(月)10:40~12:10(第2時限)に千里山キャンパス第2学舎4号館BIGホール100において、日本公認会計士協会副会長/日本公認会計士協会近畿会会長の高濱滋氏を講師に迎え、「会計人材の魅力と公認会計士」というテーマで講演会を開催し、商学部生を中心に約500名の参加がありました。
講演会ではアニメーションなども活用しながら、会計の役割や公認会計士の仕事についてわかりやすくご説明を頂きました(アニメのご紹介は次のURLを参照)。 http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/jicpa_pr/sp/tenkousei_dvd/
また、スマートフォン対応の公認会計士アドベンチャーゲームアプリ「公認会計士 市松雄大」についての紹介もありました(アプリのご紹介は次のURLを参照)。 http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/jicpa_pr/sp/appli/cpa_ichimatsu/
公認会計士の仕事は甘いものではないが、会計という世界共通のスキルを身に付けることによってグローバルな活躍の場が広がる、女性にとっても資格を活かしながら多様な働き方ができるなど、数年をかけてもトライする価値は十二分にある資格・職業ということです。
また、公認会計士ではなくても、会計を勉強しておくことは、社会人になって大変役に立つ知識であることについても説明していただきました。
11月13日に平成27年度公認会計士試験の合格発表があり、商学部からも3年次生2名、4年次生8名、合計10名の在学者が合格しました。
より多くの商学部生が公認会計士試験にチャレンジし、ビジネスの現場で活躍することを期待したいと思います。
☆写真をクリックすると大きく表示されます。
記事提供 : 商学部 水野一郎教授、岩﨑拓也准教授、岡照二准教授
2016年1月15日
【大学院】関西大学大学院商学研究科専門職コースへ進学を希望する方へ
関西大学大学院商学研究科に進学するにあたって、入学までに最低限理解しておいて欲しいと思われる内容が含まれる、基本的な図書等の一例を下記のとおり紹介します。
進学準備に際して<参考>にしてください
<ご参考>
【経営学】
1 「よくわかる現代経営」編集委員会編(2014)『よくわかる現代経営<第4版>』
ミネルヴァ書房
*商学部マネジメント専修の教員が、各自の教育担当分野の基本についてわかりやすく紹介している本です。
2 井原久光(2008)『テキスト経営学<第3版> 基礎から最新の理論まで』
ミネルヴァ書房
*経営学の基本について幅広く触れられています。
3 伊丹敬之・加護野忠男(2003)『ゼミナール経営学入門<第3版>』
日本経済新聞出版社
*経営学の出題テーマのいくつかについて根本から理解したい時に参考になります。
【経済学】
1 マンキュー,N.G.著/足立 英之訳/石川 城太訳/小川 英治訳/地主 敏樹訳/中馬宏之訳/柳川 隆訳(2013)
『マンキュー経済学Ⅰ ミクロ編(第3版)』東洋経済新報社、第4章~第20章
*基本的なミクロ経済学の教科書なので、精読することを勧めます。
2 マンキュー,N.G.著/足立 英之訳/石川 城太訳/小川 英治訳/地主 敏樹訳/中馬宏之訳/柳川 隆訳(2014)
『マンキュー経済学Ⅱ マクロ編(第3版)』』東洋経済新報社、第5章~第18章
*基本的なマクロ経済学の教科書ですが、最新のトピックスも扱っています。
【会計学】
1 笹倉淳史・水野一郎(2015)『アカウンティング:現代会計入門(5訂版)』同文舘出版
*商学部会計専修の教員が、各自の教育担当分野の基本についてわかりやすく紹介している本です。
2 桜井久勝(2015)『財務会計講義(第16版)』中央経済社
*財務会計の定番となっているテキストで幅広く読まれている基本書です。
3 廣本敏郎・挽文子(2015)『原価計算論(第3版)』中央経済社
*管理会計・原価計算の定番となっているテキストで幅広く読まれている基本書です。
【統計学】
「統計検定」(一般財団法人統計質保証推進協会が実施)の2級、「品質管理検定」(一般財団法人日本規格協会が実施)の2級に準拠のため、これらの出題範囲、レベル等を参照してください。なお、これら検定のいずれかの2級以上の合格者に関しては、専門科目試験が免除されます(詳細については、学生募集要項を参照のこと)。
・統 計 検 定 : http://www.toukei-kentei.jp/
・品質管理検定:http://www.jsa.or.jp/kentei/qc1.html
【税制論】
1 増井良啓(2014)『租税法入門』(有斐閣)
2 中里実・弘中聡浩・渕圭吾・伊藤剛志・吉村政穂編(2015)『租税法概説(第2版)』有斐閣
3 岡村忠生・渡辺徹也・高橋祐介(2013)『ベーシック税法(第7版)』有斐閣アルマ
*1から3は、いずれも税制を法的視点から学ぶための基本書です。
4 増井良啓・宮崎裕子(2015)『国際租税法(第3版)』東京大学出版会
*最新の改正を踏まえた国際課税の基本書です。
以上
2016年1月 8日
第2回商学会懸賞論文の表彰式(12月17日)を行いました。
商学会は、商学部生(個人もしくはグループ)を対象にして「商学に関する論文」(テーマは自由)の募集を6月から始めました。
応募のあった論文は、厳正な審査の結果、優秀な論文に対して表彰状と賞金を授与します。
第2回商学会懸賞論文の募集が11月6日(金)に締め切られ、個人・グループ合計5本の応募があり、商学会に所属される先生方のご協力のもと、論文1本に対して2名の先生に審査して頂きました。
第2回商学会懸賞論文入賞者に対する表彰式を12月17日(水)お昼休みに第2学舎1号館共通会議室において行いました。
当日は、辻准教授の進行により、髙井准教授から審査の講評の説明の後、商学会会長の杉本教授(商学部長・商学研究科長)から賞状および賞金の贈呈がありました。
【 審査結果 】
特賞 該当論文なし
1等:西村 太貴さん 藤井 彩子さん
「現地人材の自律性とパフォーマンスの関係“在タイ日系販売法人への質問票調査を通して”」
2等:辻 龍太郎さん 荒山 由樹さん 田向 美菜さん
「製品の生産または開発が新興国に移った場合に製品イメージの低下量を減らす要因はなにか?:日本人大学生を対象にした調査より」
3等:大岸 翔さん 秋元 遥華さん 川島 里菜さん 筒井 宥次さん
「非技術者との比較から見る技術者の職務満足要因の検討“技術者にとって望ましい施策とは?”」
佳作 該当論文なし
2016年度も商学会懸賞論文の募集をいたしますので、奮ってご応募ください。
☆写真をクリックすると大きく表示されます。
記事提供 : 商学会
2016年1月 7日
【大学院】 商学研究科修了生の植村武史さんが「第11回 税に関する論文」で奨励賞を受賞しました!
本研究科2015年3月修了生の植村武史さんの修士論文「ハイブリッドインスツルメントの所得課税上の問題-レポ取引を中心に-」が、公益財団法人納税協会連合会「第11回 税に関する論文」で奨励賞を受賞しました。
公益財団法人納税協会連合会では、租税等に関する研究の奨励及び研究内容の向上並びに学術研究の助成に寄与すること等を目的として、毎年「税に関する論文」を募集し、優れた論文に賞を贈っています。
詳しくは、公益財団法人納税協会連合会HPをご覧ください。
「第11回「税に関する論文」入選者発表」
http://www.nouzeikyokai.or.jp/yomimono/topics/1512.html
「第11回「税に関する論文」入選者表彰式を開催」
http://www.nouzeikyokai.or.jp/yomimono/topics/1512_2.html
 最前列の右から2番目が植村武史さん〔右から3番目は関西大学名誉教授の村井正先生(選考委員長)〕
最前列の右から2番目が植村武史さん〔右から3番目は関西大学名誉教授の村井正先生(選考委員長)〕
記事提供 : 商学部 辻 美枝 准教授