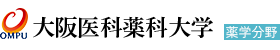活動内容
双方向講義 単位互換・科目開設 実技・実習 × 教育部門
各大学で開設されている科目の中から、医・工・薬学を学ぶ学生が異分野理解を行うため受講を推奨する科目を設定し、遠隔授業(ライブ配信あるいはオンデマンド配信)を取り入れた双方向講義を行っています。学生が修得した他大学の科目は、それぞれの大学で単位互換を行っています。
講義では、専門的な知識を備えていない他分野の学生が聴講することにより、どのような疑問を持ち、知識を習得しているかを測るため毎回授業アンケートを実施し、これを三分野で共有することによるFD活動も行っています。
また、一部の講義では、異分野を学ぶ学生を対象とした実技・実習を実施し、学生達がより深い理解につなぐ取組を行っています。
![[写真]双方向講義 単位互換・科目開設 実技・実習 × 教育部門](../program/img/img-1-1.jpg)
![[写真]双方向講義 単位互換・科目開設 実技・実習 × 教育部門](../program/img/img-1-2.jpg)
対象科目は次のとおりです。
関西大学(工学分野)から
配信する科目
- 生体無機材料
- 微生物学4
- 栄養科学
- バイオメカニクス
- 機能性食品
- 福祉工学概論
大阪医科薬科大学(医学分野)から
配信する科目
- 生命誌
大阪医科薬科大学(薬学分野)から
配信する科目
- 生薬学
- 医工薬連環科学
- 基礎漢方薬学
- 応用放射化学
このうち「医工薬連環科学」は、医学、工学、薬学の学術交流を進め、それぞれの専門分野だけでなく看護や福祉に関するテクノロジーにも精通した優れた人材の育成をめざして開設した科目で、三分野の教員がそれぞれの分野をオムニバス形式で担当しています。また、この授業の教科書である『医工薬連環科学が果たす役割と可能性―高槻家の成長に寄り添う医療』(ライフサイエンス出版)は、ある家族に起きる事象を導入とし、人生と強い連携関係を持つ医工薬看の各分野でのトピックスを題材とする形式で、医療産業を含んだ真のチーム医療のためにどのようなことが話題となっているのかを両大学の学生以外の方にもご理解いただけるようにという思いで作られています。
![[書籍] 医工薬連環科学が果たす役割と可能性](../program/img/img-book.jpg)
研究セミナー 研究発表会 × 研究部門
医工薬連環科学教育研究機構は、設置された2009年当初から、教育プログラムを中心に事業を推進してきました。この10年の活動をベースとして、2019年4月から新たに研究部門をこの医工薬連環科学教育研究機構に設置し研究推進上の大学間連携をより親密にかつ深く実現をする活動をしています。
今まで実施してきた共同研究に向けたそれぞれの研究シーズの探求と披露の場として「研究セミナー」を実施し、主に若手の研究者の交流、研究成果発表の場となる「研究発表会」も開催しています。
医学・工学・薬学・看護学のそれぞれの専門分野を研究面でもうまく融合させ、「医工薬連環科学」分野を切り拓いていき、研究成果を広く社会へ還元していくとともに、若い世代の人材育成にも積極的に携わってまいります。
![[写真] 研究発表会 教育セミナー × 研究部門](../program/img/img-2-1.jpg)
![[写真] 研究発表会 教育セミナー × 研究部門](../program/img/img-2-2.jpg)
初等中等理科教育支援/シンポジウム × 教育部門
大学の第3の使命である社会貢献として本機構では、「医工薬連環科学」分野に特化した連携事業を実施しています。
シンポジウム
各大学が提供している市民講座などに加え、本機構では協働で医・工・薬学分野に関わるテーマに特化した「医工薬連環科学シンポジウム」を年1回実施しています。このシンポジウムは、医療従事者、大学教員、企業関係者等、様々な方を対象としています。
![[写真] シンポジウム](../program/img/img-3-1.jpg)
![[写真] シンポジウム](../program/img/img-3-2.jpg)
小学校への出張講義
初等教育課程において「医工薬連環科学」のみならず広く理科への興味を育てるため、理科実験の体験を中心とする出張講義を高槻市内の小学校で企画しています。
学年教科内容の進行にできるだけリンクした形で実施し、簡単な講義と実験の組合せにより、特別に高価な実験器具などを用いず、理科実験を身近に感じて理解を深化させるような形式で行っています。また、この講義の補助者として、医工薬連環科学教育課程を修得する学生が参加することにより、年代を超えてつながる「縦の知の循環」の形成にも役立っています。
![[写真] 小学校への出張講義](../program/img/img-4-1.jpg)
![[写真] 小学校への出張講義](../program/img/img-4-2.jpg)
自由研究コンテスト
未来の科学の発展のために子どもたちの理科への関心を高めることを目的として毎年高槻市の小・中学生を対象とした「自由研究コンテスト」を実施しています。小学校低学年(1~2年生)には、「未来の生活」をテーマにした作文と絵を、小学校中高学年(3~6年生)・中学生には、それぞれ興味・関心を持ったテーマを題材にして、独自の視点で実験・観察した内容についての自由研究(理科)を募集し、毎回数百点の応募があります。二次審査会では大学生さながらの研究発表がなされています。二次審査会で子供たちの発表を観覧された方々からは、自分の好きなことを探求する力とともに他者に自分が研究したことを表現する力も必要となることを学ぶことができるコンテストであると好評をいただいています。
![[写真] 自由研究コンテスト](../program/img/IMG-5-3.JPG)
![[写真] 自由研究コンテスト](../program/img/img-5-4.JPG)

![[ロゴ] 関西大学](../img/img-ft-site-pict1.jpg)

![[ロゴ] 大阪医科薬科大学](../img/img-ft-site-pict2.jpg)
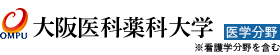
![[ロゴ] 大阪医科薬科大学](../img/img-ft-site-pict3.jpg)