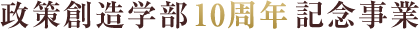学部長と語る!
政策創造学部創立10周年の節目に、学内外でさまざまな活動をしてきた学生2名が学部長の小西教授と対談。
政策創造学部の「これまで」と「これから」について語ります。





中西 智美 さん
国際アジア法政策学科 4年次生
香川/丸亀高校 出身
小西 秀樹 教授
政策創造学部長
髙松 宏幸 さん
政策学科 地域・行政専修 4年次生
三重/名張西高校 出身
中西 智美 さん
1年次に学部独自の海外英語研修制度に参加し、研修先のオーストラリアでホームステイも経験。研修をきっかけに国際交流活動を行う学生団体に所属し、国際学生会議の実行委員を務めました。
髙松 宏幸 さん
所属ゼミで「若年層の投票率向上のための政策」を研究し、学内の政策提言シンポジウムや吹田市主催の選挙啓発イベントで提言。また、アカデミックフェアなど学部イベントの運営にも取り組んでいます。
学部創立10周年を迎えて
- 小西:
- 政策創造学部は今年で創立10周年と比較的新しい学部ですが、だからこそ時代の要請に応えられる学びを展開できるのではないでしょうか。特に、主体的な学びを重視しているところを各所から評価されています。まさに学部名の「創造」にあたる部分で、他大学の政策系学部・学科とは異なる特色だと思います。
- 髙松:
- 学部名の「創造」には自主的な学びという意味が込められているのですね。私が数ある政策系学部からこの学部を選んだのも、自分の考えを発信するなど実践的な学びの機会が多いと感じたからでした。実際入ってみて、授業はもちろん政策提言シンポジウムやアカデミックフェアなど学部独自の取り組みにおいても実践の姿勢が身についています。
- 小西:
- 授業は少人数教育が基本なので、教員や他の学生と意見を交換する機会が多いですよね。自分以外の視点に触れることで新しい発見があったのではないでしょうか。髙松さん、中西さんは4年次生ということで、これまでにさまざまな学問分野に触れ、あるいは交友関係や学内外の活動で多様な経験をしてきたことと思います。その学びや経験をもとに、変化し続ける社会の中で自分自身をどう生かすか、どう活躍するかを考えてほしいですね。
- 中西:
-
違う視点から物事を考えることの大切さや面白さは私も実感しています。中学生の頃にタイの学校と交流した機会があり、文化や歴史が異なると考え方も変わることに気づきました。この体験をきっかけに、幅広い学びの領域に触れて自分の考えを広げたいと思い、この学部をめざしました。

- 小西:
- 実際入ってみて、幅広く考えられるようになったでしょうか。
- 中西:
- 1・2年次にはさまざまな分野の基礎的な内容を学ぶことができ、視野が広がったと感じています。最初はあまり興味を持てなかった科目でも、別の科目の内容とつながって面白くなるといった新しい発見もありました。
- 小西:
- 多様な学問分野についての、一見すると独立しているように思えるそれぞれの授業にも一貫したコンセプトがあります。「グローバルな視野を身につける」ことは本学部における柱のひとつともいえます。多くの授業で日本のことはもちろん、海外、特にアジアの国々の法律や経済、文化や価値観を学んでもらうことを目的にしています。
確立されつつある学部独自の取り組み
- 小西:
- 先ほどのお話にもありましたが、髙松さんは学生主体の取り組みにいくつも参加されていますね。準備段階では苦労も多かったと思いますが、何か得るものはありましたか。
- 髙松:
-
アカデミックフェアには2年次に参加し、昨年度は運営に携わりました。たくさんの人がかかわるため確かに準備は大変でしたが、その分得るものは大きかったと思います。特に、人間関係が広がったことで、より充実した大学生活を送れていますね。また、昨年の12月に開催された政策提言シンポジウムでは、所属するゼミの仲間とともにパネリストとして壇上にあがるという貴重な経験もさせていただきました。

- 小西:
- 政策提言シンポジウムは昨年で4回目と比較的新しいイベントですね。そもそも、10年前の学部創立当時には、1期生、2期生は学部のイベントひとつにしてもゼロから作り上げなければいけませんでした。試行錯誤を繰り返しながら、髙松さんたちの代まで引き継がれてきたのです。そうして培われてきた開拓精神は、海外渡航に挑戦する学生の多さにも表れているように思えます。中西さんは国際アジア法政策学科の所属ですが、海外研修には参加されましたか。
- 中西:
- 私は1年次に、学部独自の海外英語研修制度に参加しました。オーストラリアのアデレード大学での研修は5週間という短い期間でしたが、研修期間中はホームステイだったため、常に英語に触れられました。何よりも大きな収穫だったのは、現地の文化や習慣を肌で感じて、その国の法制度を文化的・歴史的な背景から理解する面白さに気づけたことでした。
- 小西:
- 中西さんは海外で身に付けたことを大学での学びに生かされてきたのですね。それこそが、この学部が国際交流やグローバルな視点を重要と考える理由の一つです。「政策」とは、現状を把握したうえで解決へのプロセスを示すものです。政策を立案するにはさまざまな視点が必要であり、日本とは異なる文化や歴史を持つ海外の視点が大きなヒントをもたらすこともあるのです。
多様な経験がつながって理解が深まる
- 小西:
- 視点を変えるという意味では、学内の学びだけでなく学外の地域とのかかわりから新たな視点を得るということも重視しています。実際に、学生が地域社会のプロジェクトにかかわる、もしくはプロジェクトを提案するということも行っていますね。
- 髙松:
- 私も2年次から、大学周辺地域の自治会の方と一緒にイベントを開催しています。例えば、関大の落語研究会による寄席を開いたり、音楽サークルのコンサートを催したりしました。地域のお祭りでイベントを企画・運営したこともありました。地域の人とともにイベント運営に取り組むことは、とても得難い経験だと感じています。授業でも地域活性化に関する事例を学びますが、実践の場があることでより理解が深まりますし、自分で感じたことを教室での学びに生かすこともできています。
- 中西:
-
髙松さんのお話を聞いて、私も地域行事にとても興味がわきました。私は地域とかかわる活動はしていなかったのですが、よく外国を訪れるようになり、色々な価値観に触れています。海外英語研修をきっかけに所属した学生団体で、国際交流活動のためにこれまで4カ国を訪問しました。現地の学生と交流したことで、より実感をもってその国の文化的背景を理解できるようになりました。海外での経験は、大学で外国の法律を学ぶときにも役立っていると思います。

- 小西:
- お二人がされてきたような、大学や教室の中だけに留まらない学びは政策創造学部がめざす教育の形でもあります。地域や海外へと飛び出してさまざまな経験をされたことで、キャンパスでもより深く学べているのではないでしょうか。
政策創造学部のこれから
- 小西:
- 来年には、中西さんと髙松さんは本学部の8期目の卒業生となるわけですが、めざしている職業や将来の目標はありますか?
- 髙松:
- 民間であれ公務員であれ、地域の活性化に貢献できる仕事に就きたいと考えています。私はもともと、地域活性化の主体は行政だというイメージを持っていましたが、3年次に受講した「地域産業戦略論」で民間企業による事例が取り上げられ、ビジネスの視点から地域活性化について考察できることを知りました。幅広い可能性から、学部で学んできた知識を生かせる場を探していきたいと思っています。
- 中西:
- 私は、国際的に活躍できる仕事ができればと考えています。いずれは海外で働きたいと考えていますが、今は日本国内でもグローバルな考え方が必要な時代だと思います。どこで働くかにかかわらず、国ごとに異なる文化や価値観を大切にしていきたいです。
- 小西:
- 二人とも頼もしいですね。あらゆる可能性に挑戦していってほしいと願っています。現在、まだ卒業生の数は多くありませんが、あなたたちの先輩は国内外で活躍されていますよ。公務員やメーカーをはじめ、NPO、新聞記者など多様な職業に就いています。本学部の教育の特徴がよく示されていますし、学生時代の多様な取り組みの成果だと思っています。
- 中西:
- 私たちも先輩方に続いて、政策創造学部出身として胸を張れるように社会で活躍していきたいです。
- 髙松:
- そして、後輩たちにも政策創造学部らしさを受け継いでいってほしいと思います。
- 小西:
-
こうしてタテのつながりも強くなっていけば素晴らしいですね。とはいえ、学部創立からまだ10年ですので「伝統」ができたというには少し早いかもしれません。これからも引き続き、主体的な学びや多様な学問分野の交わりといった教育を展開していくとともに、国際色や地域とのつながりをより一層強めていきたいですね。次の10年、20年と、年を重ねるごとに学部の「色」を濃くし、学生のみなさんの可能性を広げていけたらと願っています。